ディックが写真を始めたころ(1970年代後半)は、当然ながらフィルムカメラの時代でした。
そして、一眼レフには単焦点レンズの使用が一般的であり、今からはとても信じられないことですが、ズームレンズは日陰者の扱いでした。
当時もズームレンズは出回っていましたが、写真を始めるにあたって、いきなりズームレンズを購入する人はほとんどいなかったと思います。
ディックも最初に一眼レフを購入した時は、ズームレンズを買おうなどどいう発想は全くありませんでした。まずは50mmの単焦点レンズ(標準レンズ)を揃えるというのが一般的で、ディックも当然最初の1本は標準レンズという考えでした。
標準レンズは当時もっとも売れるレンズということもあって、普及版のレンズであれば値段も他のレンズと比べると安い設定でした。値段的にも揃えやすいという状況にありました。
その時代のズームレンズは、今ほど性能が高くないこともあって、特に周辺部分の解像度の劣化や被写体が直線なのにゆがんでしまう(樽型や糸巻型)状況が出やすく、カメラ雑誌やノウハウ本では単焦点レンズとの比較の画像を示して、画質の点から単焦点レンズを使うべきという話がよくされていました。
また、開放f値が暗いため、フィルム感度とのかねあいで(常用感度がISO(当時はASA)100が普通の時代だったので)、撮影対象が限られるという点(暗めのシーンは手持ち撮影が難しい、速度が速いものの撮影が難しいなど)や背景をボカした撮影も単焦点レンズに比べてボケないため限界がある、さらには、レンズ自体が重い(対象の焦点距離の数本分と考えれば、一概にそうとも言い切れないですが)というのもデメリットとされました。
これらの話(前段 性能面、後段 ズームレンズのそもそもの特質)は、当時では、そもそもズームレンズの使用が否定的という考えがベースにあるものの、ズームレンズの弱点としては間違っていないものだと思います。
でも、前者の性能面の話は、デジタルになって、PC上で等倍に拡大して、解像度が甘いとか論じているのと似ている面があります。
そもそもレンズの性能を判断するために作品を見るわけではなく、作品としてその写真がいいかどうかを見るべきであって、拡大した画面の一部を捉えて解像度が問題だとかいうのは、通常の写真の見方からすると違和感を覚えます(そうだとするともっと昔のカメラやフィルムの性能が現在と比べて今ひとつの時代の写真は、すべてダメな写真ということになってしまいます。)。
作品の鑑賞において、ズームレンズの性能のデメリットの面によって、作品の表現に問題をきたすため使えなかったというような例は、通常の撮影の分野では、当時でも少なかったのではないかと推察されます。
今はズームレンズの性能自体よくなり、画質も単焦点レンズと比べてほとんど遜色はありません。そのため、ズームレンズを使ったから、写りに問題があるという議論自体意味のないものになっています。
また、ズームレンズの開放f値が暗いという点も、標準ズーム(24-70mmなど)や望遠ズーム(70-200mmなど)では開放f値が通しで2.8のものもあり、単焦点との差があまりなくなってきています。
スナップであれば、もともと開放f値は暗くてもいいですが、人物のポートレート撮影を行うのであれば、全域f2.8のズームレンズがほしいところです。
ところで、今回の本題につながるところですが、ズームレンズを使うべきではないという主張にはそれらとは別の写真撮影の技術面に関係するものがあります。それは、ズームレンズを使うと写真の上達を阻害するというものです。
これも先ほどのズームレンズの性能の話と相まって、当時、盛んにカメラ雑誌等で書かれていました。また、ズームレンズがメインになった今でも、そのような話をされるプロの方も見受けられます。
ディックが写真を始めたころは、上記のあげた理由(ズームレンズの性能面、ズームレンズのそもそもの特質(単焦点レンズと比べて開放f値が暗い、重い)、上達するための技術面)からズームレンズはよろしくないという風潮が写真界の主流であり、ズームレンズを使っているのは、必要性からあえて使っているプロを除けば、写真を分かっていない素人だというような雰囲気だったので、ディック少年も当然単焦点レンズを使うべしという考えが頭を支配していました。今から思うとズームレンズが性能以上に不当に低い扱いを受けていたと思います。
ちなみに、最初にカメラを買う人が標準レンズの代わりにズームレンズ付きを普通のこととして買うようになったのは、本格的なAF一眼の登場(ミノルタα7000が登場して1985年)の少し前くらいからと記憶しています。
ズームレンズを使うと写真がうまくならないとする理由は何かです。
そもそも撮影スタイルとして問題だという精神論的な面(特に単焦点を専ら使用していたプロからすると、ズームレンズの撮影はそもそもが安易で許しがたいという面もあったようです。)からの話もあったと思います。
それは置いておくとして、ディックの理解では、
ズームレンズを使うと、メインの被写体を相当な大きさに入れて撮影するために、フレーミングを自身が動くのではなく、その場でズーミングして行いやすくなり、そのような撮影をしていると写真が上達しない
というものです。
フレーミングをズーミングして行った場合、どの焦点距離でも同じ写りなら問題ないのですが、実際はそうではなくレンズの焦点距離(画角)によって、写り自体が変わってきます。例えば人物を撮影する際に、広角側で撮るか、望遠側で撮るかで、たとえ写る人物の大きさは同じでも、背景の写りが異なるため写真の出来は大きく変わってきます。
それを無視して、今いる場所からズームして撮ってしまうことがよろしくないということです。
ズームレンズを使用していると、その点が理解できず、安易な撮影になりがちとなるので、そんなことをやっていては写真が上達しないという流れです。
ディックは、ズームレンズを使うと写真の上達を阻害するという説には懐疑的です。
ズームレンズを使っているということのみをもって、画角による写りの違いが理解できず、安易な撮影にいたるということにはならないと考えます。そもそも画角の違いを理解することとズームレンズの使用は直接リンクしていません。
画角の違いは別途理解するば済むことですし、ズームレンズならではのメリットがあり、それを使いこなすことによって、写真は確実に上達すると考えます。
特に問題となるのは、写真を始めたばかりのビギナーの方です。
最初から単焦点レンズを使ったら写真の上達が早いのでしょうか。
ディックは、むしろズームレンズを積極的に使って、自身に興味あるシーンをたくさん撮ることが逆に写真の上達の近道ではないかと考えています。
画角による写りの違いについては、写真をやっていく上では理解した方がよいに決まっていますが、それはカメラを始めた最初である必要はありません。
撮影のバリエーションを豊かにするには、むしろズームレンズの方が適しています。単焦点レンズでは撮影の機会が極めて限定的になりますし、レンズ交換で対応しようと思っても、レンズ交換に頭を悩ましたり、レンズ交換しているうちにシャッターチャンスを逃すなど、初心者の方にはかえって敷居が高いです。
ズームして遠近いろいろな被写体をまず撮ってみる。いろいろなシーンが撮れるという写真の面白さを体験しているうちに、画角とかという話にも自然に興味を持てるのではないでしょうか。その方が自然な流れだと思います。
ズームレンズは、簡単に画角を変えて自由に撮影できることが利点なので、このメリットを活かして撮影すればいいのです。
また、もう少し近づきたいけど物理的に近づけない時もありますが、そうした時もズームレンズなら、きちんとしたフレーミングで撮影できます。
更に、微妙なフレーミングの調整をしたい時に、少し自分を前後することと、それをズームで行うこととで、作品の出来を阻害するようなことは起こりません。
ちなみに、ディックは、一眼(α7系列)では、FE24-240mmf3.5-6.3というレンズをよく使用しています。
開放f値の点はさておいて、広角域24mmからまずまずの望遠域である240mmまで、即座に焦点距離を変えることができ、大変重宝しています。
単焦点レンズだと、広角域のカメラで撮影している時に、望遠域での撮影をしたい場合には、レンズを変えるか、別のレンズを付けたカメラを用意して、カメラをチェンジする必要があります。また、被写体を大きく写したい時に、もう少し近寄りたいけど場所の制約で近寄れない時がままあります。その場合には、望遠側にズームすれば簡単に対応できます。
このように、ズームレンズを使用すると、より撮影の幅が広がるので、汎用的な使用(スナップ撮影が多いですが)ではズームレンズがディックにとって不可欠です。
コンデジでも高級路線では単焦点レンズのものもありますが、ズーム付きでないと撮影の制約が多すぎるため、メインで使用するカメラにはなりえません。もちろんディックも撮影対象によっては単焦点レンズも使用していますが、ディックにおいては、ズームレンズで撮影できる範囲がほとんどです。
ディックも、写真を始めたころにズームレンズを使っていたら、もっと写真を楽しめ、よりスキルも向上したのではないかと思ったりします。


ディック少年も、当時は、ばりばりのズームレンズは否定派でしたが、全く興味がない訳ではありませんでした。当時鉄道写真をメインに撮っていたので、あると便利だろうなとは心の片隅に思っていました。
当時密かに注目していたのが、このタムロン80-210mm f3.8-4 (130A 1981年~87年販売)です。これが出始めのころ、まだ創刊間もなかったカメラ雑誌CAPA(創刊号は 1981年10月号)に、高校の写真部の紹介とともにこのレンズが紹介されていて、このレンズがまぶしく感じたことが今でも思い出されます。
マニュアル時代のタムロンは、マウント部分を交換して(アダプトール2という名称です)、ほとんどのカメラに使用できました。これもタムロンの売りでしたが、そもそもいろいろなメーカーのカメラを同時に使っている人はアマチュアでは少数派だったので、どの程度のメリットがあったかは不明です。ただ、複数のタムロンのレンズを持っていて、このマウントが一つあれば使い回しはできますが、これも面倒そうです。
当時ズームレンズの値段はそこそこしました(このレンズは当時52,000円、これに別売の自分のカメラにあうマウント(5000円)が必要)。ただ、買えるお金が当時あっても、やはり買わなかったでしょうね。
これは後年、ほぼジャンク扱いの値段で購入しました。当時メインの直進式ズーム(ピントリングを前後してズーミングするもの。今はほとんどズームリングが別にある回転式になっています。)で、被写界深度の色とりどりのラインや数字やアルファベットの独特の書体がおしゃれに感じたものです。
これはペンタックス用がついていたので、Eマウントのアダプターをかませてα7Ⅱにつけています。
そして、一眼レフには単焦点レンズの使用が一般的であり、今からはとても信じられないことですが、ズームレンズは日陰者の扱いでした。
当時もズームレンズは出回っていましたが、写真を始めるにあたって、いきなりズームレンズを購入する人はほとんどいなかったと思います。
ディックも最初に一眼レフを購入した時は、ズームレンズを買おうなどどいう発想は全くありませんでした。まずは50mmの単焦点レンズ(標準レンズ)を揃えるというのが一般的で、ディックも当然最初の1本は標準レンズという考えでした。
標準レンズは当時もっとも売れるレンズということもあって、普及版のレンズであれば値段も他のレンズと比べると安い設定でした。値段的にも揃えやすいという状況にありました。
その時代のズームレンズは、今ほど性能が高くないこともあって、特に周辺部分の解像度の劣化や被写体が直線なのにゆがんでしまう(樽型や糸巻型)状況が出やすく、カメラ雑誌やノウハウ本では単焦点レンズとの比較の画像を示して、画質の点から単焦点レンズを使うべきという話がよくされていました。
また、開放f値が暗いため、フィルム感度とのかねあいで(常用感度がISO(当時はASA)100が普通の時代だったので)、撮影対象が限られるという点(暗めのシーンは手持ち撮影が難しい、速度が速いものの撮影が難しいなど)や背景をボカした撮影も単焦点レンズに比べてボケないため限界がある、さらには、レンズ自体が重い(対象の焦点距離の数本分と考えれば、一概にそうとも言い切れないですが)というのもデメリットとされました。
これらの話(前段 性能面、後段 ズームレンズのそもそもの特質)は、当時では、そもそもズームレンズの使用が否定的という考えがベースにあるものの、ズームレンズの弱点としては間違っていないものだと思います。
でも、前者の性能面の話は、デジタルになって、PC上で等倍に拡大して、解像度が甘いとか論じているのと似ている面があります。
そもそもレンズの性能を判断するために作品を見るわけではなく、作品としてその写真がいいかどうかを見るべきであって、拡大した画面の一部を捉えて解像度が問題だとかいうのは、通常の写真の見方からすると違和感を覚えます(そうだとするともっと昔のカメラやフィルムの性能が現在と比べて今ひとつの時代の写真は、すべてダメな写真ということになってしまいます。)。
作品の鑑賞において、ズームレンズの性能のデメリットの面によって、作品の表現に問題をきたすため使えなかったというような例は、通常の撮影の分野では、当時でも少なかったのではないかと推察されます。
今はズームレンズの性能自体よくなり、画質も単焦点レンズと比べてほとんど遜色はありません。そのため、ズームレンズを使ったから、写りに問題があるという議論自体意味のないものになっています。
また、ズームレンズの開放f値が暗いという点も、標準ズーム(24-70mmなど)や望遠ズーム(70-200mmなど)では開放f値が通しで2.8のものもあり、単焦点との差があまりなくなってきています。
スナップであれば、もともと開放f値は暗くてもいいですが、人物のポートレート撮影を行うのであれば、全域f2.8のズームレンズがほしいところです。
ところで、今回の本題につながるところですが、ズームレンズを使うべきではないという主張にはそれらとは別の写真撮影の技術面に関係するものがあります。それは、ズームレンズを使うと写真の上達を阻害するというものです。
これも先ほどのズームレンズの性能の話と相まって、当時、盛んにカメラ雑誌等で書かれていました。また、ズームレンズがメインになった今でも、そのような話をされるプロの方も見受けられます。
ディックが写真を始めたころは、上記のあげた理由(ズームレンズの性能面、ズームレンズのそもそもの特質(単焦点レンズと比べて開放f値が暗い、重い)、上達するための技術面)からズームレンズはよろしくないという風潮が写真界の主流であり、ズームレンズを使っているのは、必要性からあえて使っているプロを除けば、写真を分かっていない素人だというような雰囲気だったので、ディック少年も当然単焦点レンズを使うべしという考えが頭を支配していました。今から思うとズームレンズが性能以上に不当に低い扱いを受けていたと思います。
ちなみに、最初にカメラを買う人が標準レンズの代わりにズームレンズ付きを普通のこととして買うようになったのは、本格的なAF一眼の登場(ミノルタα7000が登場して1985年)の少し前くらいからと記憶しています。
ズームレンズを使うと写真がうまくならないとする理由は何かです。
そもそも撮影スタイルとして問題だという精神論的な面(特に単焦点を専ら使用していたプロからすると、ズームレンズの撮影はそもそもが安易で許しがたいという面もあったようです。)からの話もあったと思います。
それは置いておくとして、ディックの理解では、
ズームレンズを使うと、メインの被写体を相当な大きさに入れて撮影するために、フレーミングを自身が動くのではなく、その場でズーミングして行いやすくなり、そのような撮影をしていると写真が上達しない
というものです。
フレーミングをズーミングして行った場合、どの焦点距離でも同じ写りなら問題ないのですが、実際はそうではなくレンズの焦点距離(画角)によって、写り自体が変わってきます。例えば人物を撮影する際に、広角側で撮るか、望遠側で撮るかで、たとえ写る人物の大きさは同じでも、背景の写りが異なるため写真の出来は大きく変わってきます。
それを無視して、今いる場所からズームして撮ってしまうことがよろしくないということです。
ズームレンズを使用していると、その点が理解できず、安易な撮影になりがちとなるので、そんなことをやっていては写真が上達しないという流れです。
ディックは、ズームレンズを使うと写真の上達を阻害するという説には懐疑的です。
ズームレンズを使っているということのみをもって、画角による写りの違いが理解できず、安易な撮影にいたるということにはならないと考えます。そもそも画角の違いを理解することとズームレンズの使用は直接リンクしていません。
画角の違いは別途理解するば済むことですし、ズームレンズならではのメリットがあり、それを使いこなすことによって、写真は確実に上達すると考えます。
特に問題となるのは、写真を始めたばかりのビギナーの方です。
最初から単焦点レンズを使ったら写真の上達が早いのでしょうか。
ディックは、むしろズームレンズを積極的に使って、自身に興味あるシーンをたくさん撮ることが逆に写真の上達の近道ではないかと考えています。
画角による写りの違いについては、写真をやっていく上では理解した方がよいに決まっていますが、それはカメラを始めた最初である必要はありません。
撮影のバリエーションを豊かにするには、むしろズームレンズの方が適しています。単焦点レンズでは撮影の機会が極めて限定的になりますし、レンズ交換で対応しようと思っても、レンズ交換に頭を悩ましたり、レンズ交換しているうちにシャッターチャンスを逃すなど、初心者の方にはかえって敷居が高いです。
ズームして遠近いろいろな被写体をまず撮ってみる。いろいろなシーンが撮れるという写真の面白さを体験しているうちに、画角とかという話にも自然に興味を持てるのではないでしょうか。その方が自然な流れだと思います。
ズームレンズは、簡単に画角を変えて自由に撮影できることが利点なので、このメリットを活かして撮影すればいいのです。
また、もう少し近づきたいけど物理的に近づけない時もありますが、そうした時もズームレンズなら、きちんとしたフレーミングで撮影できます。
更に、微妙なフレーミングの調整をしたい時に、少し自分を前後することと、それをズームで行うこととで、作品の出来を阻害するようなことは起こりません。
ちなみに、ディックは、一眼(α7系列)では、FE24-240mmf3.5-6.3というレンズをよく使用しています。
開放f値の点はさておいて、広角域24mmからまずまずの望遠域である240mmまで、即座に焦点距離を変えることができ、大変重宝しています。
単焦点レンズだと、広角域のカメラで撮影している時に、望遠域での撮影をしたい場合には、レンズを変えるか、別のレンズを付けたカメラを用意して、カメラをチェンジする必要があります。また、被写体を大きく写したい時に、もう少し近寄りたいけど場所の制約で近寄れない時がままあります。その場合には、望遠側にズームすれば簡単に対応できます。
このように、ズームレンズを使用すると、より撮影の幅が広がるので、汎用的な使用(スナップ撮影が多いですが)ではズームレンズがディックにとって不可欠です。
コンデジでも高級路線では単焦点レンズのものもありますが、ズーム付きでないと撮影の制約が多すぎるため、メインで使用するカメラにはなりえません。もちろんディックも撮影対象によっては単焦点レンズも使用していますが、ディックにおいては、ズームレンズで撮影できる範囲がほとんどです。
ディックも、写真を始めたころにズームレンズを使っていたら、もっと写真を楽しめ、よりスキルも向上したのではないかと思ったりします。


ディック少年も、当時は、ばりばりのズームレンズは否定派でしたが、全く興味がない訳ではありませんでした。当時鉄道写真をメインに撮っていたので、あると便利だろうなとは心の片隅に思っていました。
当時密かに注目していたのが、このタムロン80-210mm f3.8-4 (130A 1981年~87年販売)です。これが出始めのころ、まだ創刊間もなかったカメラ雑誌CAPA(創刊号は 1981年10月号)に、高校の写真部の紹介とともにこのレンズが紹介されていて、このレンズがまぶしく感じたことが今でも思い出されます。
マニュアル時代のタムロンは、マウント部分を交換して(アダプトール2という名称です)、ほとんどのカメラに使用できました。これもタムロンの売りでしたが、そもそもいろいろなメーカーのカメラを同時に使っている人はアマチュアでは少数派だったので、どの程度のメリットがあったかは不明です。ただ、複数のタムロンのレンズを持っていて、このマウントが一つあれば使い回しはできますが、これも面倒そうです。
当時ズームレンズの値段はそこそこしました(このレンズは当時52,000円、これに別売の自分のカメラにあうマウント(5000円)が必要)。ただ、買えるお金が当時あっても、やはり買わなかったでしょうね。
これは後年、ほぼジャンク扱いの値段で購入しました。当時メインの直進式ズーム(ピントリングを前後してズーミングするもの。今はほとんどズームリングが別にある回転式になっています。)で、被写界深度の色とりどりのラインや数字やアルファベットの独特の書体がおしゃれに感じたものです。
これはペンタックス用がついていたので、Eマウントのアダプターをかませてα7Ⅱにつけています。













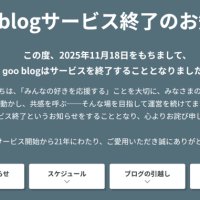













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます