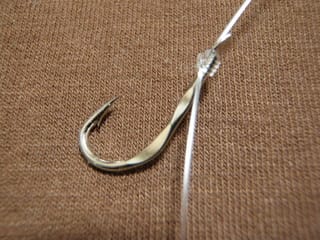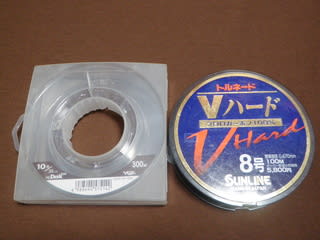出来過ぎだった2023~2024年の白石グリの、春ヒラマサの釣果が一転して、今春以来パッとせず、煮えきらない感のままで釣果が停滞している。
4月の半ばに入ってから、小マサの釣果は主に中浜方面で出ているそうだが、「小マサの数釣りは…?。」なので、いつもならソワソワしながら各船の空き状況を確認しているこの時期であっても、家でどっしり座ったままになっていた。
とは言え、釣りに関わっていないとストレスが溜まるので、以前にクエ釣り用ロッドで紹介した「ロッド・リビルド」で時を過ごしていた。
前回のクエ用に続いて、今回は完全フカセ用の制作に入ったのだが、まずはベースになるロッド探しから入った。
■ベイリア完全フカセ■
以前にも何度か触れたが、完全フカセ専用用ロッドは絶滅して久しい。2大メーカーだと、シマノはリアランサー・シリーズで、ダイワはリーオマスター・シリーズでラストになるが、2本共にHタイプの所有歴がある。内、リーオマスーは手放していて、リアランサーは現在でも8号ハリス装着時に使用中だが、もう少し胴に張りが欲しいと思っていた。
中古市場を色々と物色している内に思いついたのが、リアランサーの一つ前のモデルでベイリア・完全フカセ H300というロッドだった。

●ベイリア・完全フカセ H300●
リアランサーとの相違点は、先径は同じだが、元径が2.6mm太く、重量が35g重い。この差の意味と、年を追うごとに胴にかかるロッドが多くなったシマノ船竿の傾向から、「一つ旧モデルなら、恐らく胴の張りはあるはず。」と予想していた。しかもカラーが赤系でリールとのコーディネートもぴったりである事から、これに的を絞り、幸いにも今春、入手するに至った。因みに中古相場は¥10,000前後で、かなりこなれていた。
入手後に新旧2点を手に取って比較したが、ベイリアは元部のガイドが一つ少なく、リールシートから10cm遠い位置に取り付けられている。これは胴の張りがある証しで、実際の曲げ込みテストでも実証されたので狙い通りだった。

●上=ベイリア、下=リアランサー●
■パーツ選び■
今回はリビルドが前提なので、次いでパーツの購入に入った。交換してグレードアップさせるのはリールシートとバット・エンドなので、ロッド・パーツ販売では大手のイシグロさん他の通販でALPS社のアルミ・リールシート(CAH-17PG)と、AFTCO(アフコ)社のアルミ・ギンバル(#2)を入手した。

●ALPS社のCAHリールシート●

●AFTCO社のアルミ・ギンバル●
バットエンドをギンバル仕様にした理由は、デカアテが装着可能になる事だ。魚が斜め沖から上がって来る完全フカセでは、脇挟みではなく、竿尻を骨盤に当てるのがやりとりの基本なので、ボクの場合は基本的に装着出来る方が有り難いからだ。

●デカアテ●
■リビルド開始■
まずは既存のリールシートグラインダーで割れ目を入れて除去。

●削り過ぎに注意●

●マイナスドライバーでこじる●

●バラバラに●
次いでEVAグリップをカッターで削ぎ落とす。

●極力ブランクスを削らないように●
アルミリールシートは径が太くなるとシート全体が太くなって、ロッドの径とのバランスが悪くなるので、ロッド径に合った17サイズを購入したが、そのままでは内径が合わないので、バットを切断してカーボンパイプで繋ぐ方法を採用した。

●フォアグリップの直前でカット●

●ここにリールシートが入る●
各部の内外径に差があって、そのままではガタが出るので、調整に入る。

●カーボンパイプをtesaテープで嵩上げ●
全てノガタが取れたら、カーボンパイプ部にリールシートを通した後にエポキシ接着剤で固定する。
次いでグリップの制作に入る。バットの経にあった内径のストレート・グリップが発売されているので、それを購入した。

●ジャストエースのEVAグリップ●
成形法は、カッターで荒削りした後にサンドペーパーの240番を使用して、手のひらで回しながら削る。作業は以外に簡単で、1個あたり10分もあれば整形が完了する。
今回はフォアグリップはそのままなので、リールシートの後端部とギンバルの前端部に通すグリップを制作した。

●左がリールシート側、右がギンバル側●
最後に別途購入したアルミ製の飾りリング=ワインディングチェックを入れつつバット部の全てのパーツを通しながらエポキシ接着剤で固定する。

●補強を兼ねたクランプ固定部の飾り巻き●

●ギンバル部●
リールシート直後のグリップは短めにした方が、リールがロッドキーパーの前受部に触れなくなるのでオススメだ。(ノーマル状態では必ずリールが擦れる。)

●リールがロッドキーパーに当たらない長さ●
飾り巻きのスレッドを入れてコーティング剤で固める場合はフィニッシング・モーター等の専用器具が必要になるが、それ以外は基本的にエポキシ接着剤で事足りる。
投資金額は¥7,000ほど。ロッドの金額に迫る額だが、オリジナル(風?)を手に入れた喜びは大きい。

●トータルコーディネート!●
完成したロッドをを眺めつつ、「大マサゲット!」を夢見ているが、それは次回以降の話。果たしてこのロッドを曲げこむヤツに遭遇出来るだろうか?。次回から春のヒラマサチャレンジ・レポートが始まる。