星の音、風の冷気、炎の熱、そして酒 そんな山の夜

岳夜、想話 act.3―side story 「陽はまた昇る」
遭難者が降りた獣道の入口に、目印の石積みを作ると、ビバークの準備に入る。
この尾根は細く場所は限られる。国村の言っていた場所まで歩いた。
きれいに整地して、枯れ木を集めて火を起こす。
空の雲はほとんど吹き払われていた。あわく残る雲の影からは、星がのぞき始めている。
見上げて、楽しげに国村が笑った。
「晴れてきてよかったな、雨や風は辛いからね」
山岳救助の現場では、こんなふうにビバークをする事も珍しくない。
ビバークは、登山やキャンプなどで、緊急的に野営することを指す。
公式には緊急時以外、いかなる山でも焚き火は肯定されていない。けれどこれは緊急時だった。
そんなわけで今は、堂々と焚き火を行える。
「冷たい山の空気で眺めるとさ、焚き火の良さを一番感じられるよ」
国村はこういう事が好きらしく、機嫌良く準備している。
不用意な遭難者には怒っても、ビバークは嬉しそうだった。
もしかして国村は、この為に山岳救助隊員になったのかな。そんな事を英二は思った。
「火は小さく起こして、大きく育てるのが、焚き火のコツなんだ」
慣れた手つきで、国村が火をおこし、上手に火を育てていく。
あらかじめ大量に集めておいた薪を、様子をみながらくべていった。
枯れた秋の山は燃えやすい、付近に相当の注意を払いながら、このまま夜明しをする。
順調に大きくなる火を見つめながら、国村がそうだったと英二を見た。
「あのさ、遠慮なく電話しなよ。待ってるんでしょ」
いつも周太には21時に電話している。今はもう23時前だった。
青梅署を出る前にメールはしたが、心配しているかもしれない。
「悪いな。じゃ、ちょっと」
英二は微笑んで、遠慮なくベルトと繋いだ携帯を開いた。
受信メールが1件入っている。
From :湯原周太
subject:まってる
本 文 :いつでも、待っているから。
短い文章、けれど気持が嬉しい。
周太も当番勤務で、今夜は新宿駅東口交番での夜になる。
今頃は、どうしているのだろう。あの声を聴きたい。
けれど、その前に英二は、吉村医師への短いメールを送った。
やっぱり吉村は、心配してくれていたらしい。すぐに、短文でも温かな返信が届いた。
メールして良かったと英二は微笑んだ。
英二は立ち上がって、新宿方面の空を眺めた。
深夜23時、それでも無数の明りが瞬いている。そのどれか一つに今、あの隣はいる。
発信履歴から通話ボタンを押すと、コール音も無く繋がった。
「待ってた?」
「…ん、待ってた」
待っていて貰えて、嬉しい。嬉しくて英二は微笑んだ。
「すげえ嬉しいよ。待っていてくれて、ありがとうな」
「ん…こっちこそ、うれしい。電話、ありがとう」
答える声に初々しい艶がある、眠たくて無防備になっている所為だろう。
こんな無自覚な艶が、周太にはある。警察学校の時から、英二は見惚れていた。
けれどこの1ヶ月半で更に、きれいになっている。他では絶対に見せないでと、いつも英二は思ってしまう。
今もすこし心配になりながら、英二は訊いた。
「いま、周太、ひとり?」
「…ん、そう…休憩室でね…仮眠とってる」
言葉の合間が、眠たそうで可愛い。
ふっと聞こえる吐息が、一緒の夜を懐かしがらせてくれる。
眠たそうで寝ませてあげたいのに、つい声を聴きたくて、英二は少しだけ話した。
「榧ノ木山って所にいるんだ。雲取山とね、新宿も見える」
「そうなんだ、…なんか、うれしいな」
「どうして、うれしい?」
そっと訊いてみると、眠たげで恥ずかしげな声が、答えてくれた。
「…俺のいるところ、見ていてもらえる、なんか安心…うれしい」
こんなふうに、言ってもらえる事が、嬉しくてならない。
とても小さな事かも知れない、日常的なありふれた会話。けれどこんなに、その日常が嬉しい。
そしてきっと、この日常が遠くなった時は、こんな小さな事が、細かく重たい冷たい傷になる。
それなのに自分は、13年前に周太につけられた、そんな傷を想いやれなかった。
唯ひとり、この隣に立っていたいと願いながら、自分は解っていなかった。
ただ詫びて済ませられるなら、簡単だと思う。けれど自分の想いは、そんなに簡単には済ませられないだろう。
だってこんなにもう、この隣の事ばかり想っている。
「いつも本当は見ていたいよ、周太のこと。小さい事でも一つずつ、ずっと見つめていたい」
「…ん、うれしい。俺も、…見ていたい」
繋いだ電話の向こう、あの隣が微笑んでくれる。きっと、きれいな純粋な笑顔が咲いている。
こんなふうにいつも、周太は純粋でいてくれる。呼吸するごと素直になって、きれいな瞳で応えてくれる。
こんな今が嬉しくて、そっと微笑んで英二は言った。
「3日後は見ているよ、山の上で」
「ん、…うれしいな。楽しみにしてる」
そんなふうに少し話して、周太の寝息を聴いて、英二は携帯を閉じた。
振り返ると、国村も携帯を閉じたところだった。
「国村さんも電話?」
「うん、彼女にね。これさ、食っていいんだよね」
さらっと言って、国村はアーモンドチョコレートの箱を開け始めた。
おうと返事して、はたと英二は止まった。
今、確かに「彼女」と国村は言った。
国村は、文学青年みたいな整った風貌をしている。賢明で洞察力も鋭く、言葉にも行動にも無駄がない。
すぐ人を転がす癖はあるけれど、底抜けの明るさで厭味にならない。
クライマーで警察官の兼業農家で、落着いた思考と高い身体能力の持ち主でもある。
こんなふうに国村は良い奴だ、彼女がいても不思議はない。
でも、国村は冷静沈着な反面、大胆不敵で自由人だ。
この間も、平気でミニパトカーを激走させた。さっきも、遭難者へと風変わりなエールを送っている。
そんな国村は悪戯心が起き上がると、やっかいな知能犯になってしまう。
普通の女の子だと、ついて行き難いだろう。
「国村さんの彼女って、どんなひと?」
微笑んで率直に英二は訊いてみた。
アーモンドチョコレートをごりごり噛みながら、国村は英二を見た。
「うん。幼馴染みでさ、逞しいかな」
「逞しい?」
幼馴染は想定どおりだと英二は思った。
けれど逞しいってなんだろう、考えていると国村は口を開いた。
「美代ん家もさ、農家なんだよ。それでね、梅干しでも味噌でも、何でも自分で作って俺にもくれるんだ」
「へえ、すごいな」
素直に英二は感心した。今時の女の子で、そうした手仕事がこなせる人は少ないだろう。
国村は涼しい顔で、アーモンドチョコレートをまた口に放り込んでいる。
「うん、今時は少ないタイプかもね。でも、美代は美代だからさ」
国村の細い目が、ふっと和やかになった。
「美代は美代だから」そんな言葉から国村の想いが解る。
微笑んで、英二は訊いてみた。
「写真とかないの?」
ごりごり口を動かしながら、国村は携帯をチェーンから外した。
片手で気軽に操作して、はいと英二に差出してくれる。受け取って見て、英二は素直に褒めた。
「へえ、かわいいな」
すこし陽に妬けた、きれいな瞳の女の子が笑っていた。化粧気も少ない、くったくない明るさが可愛い。
同じ年なんだよねと、何でもない事のように国村は教えてくれた。
「家が隣でさ。生まれてすぐにね、保育園から農業高校まで、ずっと一緒だったんだ」
「いいな、そういうの」
「うん。一緒にいるのが当たり前で、自然なんだよね」
ずっと国村は、彼女だけを見ているのだろう。
生まれた時から見つめた相手を、ずっと見つめていける。
当たり前のように自然に、ずっと一緒に生きている。そういうのはきっと、とても幸せだ。
そういう国村がなんだか嬉しくて、英二は微笑んだ。
「なんかさ、国村さんらしいよ」
「だろ、」
焚き火に白い頬を照らしながら、からっと笑って国村は言った。
「だからさ、警察学校に入る時は、寂しかったな」
美代も泣いたけど、俺もちょっと泣いたよ。
そんなふうに、さらっと言って国村は笑った。
泣いている国村が、なんだか想像できない。
国村はどこか浮世離れしていて、天才肌の空気がある。
だからそんなふうに、自分と同じような面があるのは、なんだか嬉しい。
英二は笑った。
「国村さんでも、泣くことあるんだな」
「うん、回数少ないけどね。たまには、あるよ」
からり笑って国村は、また一つ口に放り込んで、ごりごり噛み砕いた。
英二もオレンジ色のパッケージを出して、一粒口に含んだ。この味を好む笑顔と、馴染んだ味がやさしい。
今頃はよく眠っているだろう。仮眠でも周太には、良い夢を見ていてほしい。
焚き火の炎が、ぱちんと爆ぜる。
夜半を過ぎた寒気が山を覆っていく、けれど焚き火の周りは暖かだった。
山の静けさに炎の音が響く。こういう時間は好きだ、英二は安らいだ。
炎に照らされるお互いの顔を見ながら、国村が口を開いた。
「俺の両親ってさ、山で死んだだろ?」
国村の両親は、国内ファイナリストのクライマーだった。
国村が中学校に上がってすぐ、海外の雪山で亡くなったと英二も訊いている。
静かに英二は頷いた。
「…うん、」
ぱちっと炎が小枝に爆ぜる。
静かな夜の空間に、底が明るい落着いた声が、ゆっくり言った。
「祖父と一緒にね、遺体を引取りにさ、ネパールまで行ったんだ。そのときは俺ね、涙が出なかった」
細い目を炎に微笑ませて、国村が話していく。
薪を少し足しながら、そっと英二は国村の話に寄り添っていた。
「マナスルをさ、両親はペアを組んで登った。二人でペアを組むのは珍しかった、俺が生まれてからはね」
「うん、…」
マナスルManaslu 標高8,163m、世界8位の高さを誇り、ヒマラヤ山脈に属している。
何人もの登山家が雪崩で亡くなっていると、英二も読んだ事がある。
いつもの落着いた声で、国村は英二の目を見、細い目は静かに笑った。
「セラック崩壊のブロックにね、飛ばされてさ。二人とも雪と氷に引きこまれた」
セラックとは、氷河に出来た氷塔ブロックをいう。非常に不安定で崩壊すると、氷の塊ブロックが飛ぶ。
セラック崩壊に巻き込まれる事は、こんなふうに死にも繋がる。
高く深い雪山に登るなら、誰もが覚悟する事態。
それでも雪山を目指す、その想いは英二には否定できない。
山ヤを志して出会った雪山の写真、その経験談は、既に英二の心を惹きつけ始めている。
それでもやはり、遺された人間を想うと、英二は悲しかった。
国村はそうして遺された。
焚き火に照らされながら、静かに国村が口を開いた。
「両親は二人一緒に、ロープで結ばれた姿で発見されたよ。互いに固く、アイザイレンしていた」
アイザイレンは、ザイルパートナーとして、互いにザイルを結び合うこと。
国村の両親の、お互いへの想いが、英二の心にも静かに感じられた。
「ほんとにね、仲のいい両親なんだ」
温かな炎の前で、国村は微笑んだ。
国村の細い目の瞳に、ゆっくり炎が光っている。
「俺さ、そのときに思ったんだ。きっと二人一緒で、幸せだったろうなって」
中学生にあがったばかりの、明るい春だったろう。
そこへ急に現われた悲しみを、12歳の国村は静かに見つめていた。
「ずっと俺、涙が出なかった。知らせを受けた時もさ、ネパールで両親と対面した時も、家に戻ってもね」
「うん、…」
そっと英二は頷いた。
そんな英二に微笑んで、きれいに笑って国村は言った。
「そうしたらさ、葬儀の時に田中のじいさんが言ってくれたんだ。
山ヤが山で死ぬだけだ、それが山ヤの本望だ。
だからお前の両親は幸せだよ。そう言われてね、やっと俺、初めて涙が出たんだ」
話してくれる口調は穏やかで、静かだった。
国村の家と田中の家は、遠縁の親戚だった。農家同士で、互いに援け合う。代々そんな付き合いだと聴いている。
田中の孫である秀介も「こうちゃん」と国村には懐いていた。
そんなつきあいの中で、世代を超えた山ヤ同士の、そういう繋がりが結ばれたのだろう。
田中らしく、国村らしい。そんなふうに英二は思えた。
薪が炎に爆ぜる、ぱちりと響く音を聴きながら、英二は国村を見つめていた。
それでさと、微笑んで国村は続けた。
「田中のじいさんね、あの大きな掌と胸でさ、俺を抱きしめて泣かせてくれたんだ。ほんと温かくて嬉しかったよ」
「うん、」
写真家で地元の農家だった田中は、愛した御岳山で眠りについた。
英二の背中で最後を迎えた時も、大きな掌と胸は温かかった。
爆ぜる炎に頬を明るませながら、国村は教えてくれた。
「両親が死んだあとはさ、田中のじいさんが俺を山へ連れて行ってくれたんだ」
「…そうだったのか、」
そうと頷いて、国村は微笑んだ。
「一緒に国内をさ、いろんな山に登った。そうしてね、俺を山ヤに育ててくれたんだよ」
田中が息を引き取った、御岳の氷雨の夜。
呼吸を止めた田中を、駆けつけた国村は必死で蘇生させようとした。
けれど戻らない息に、国村はぽつんと呟いた。
― …俺に、背負わせてくれるかな ―
そして国村は静かに田中を背負って、下山した。
あの時なぜ国村が、田中を背負うことを望んだのか。
その理由がわかったと、英二は思った。
あの時の国村は、色白の顔が余計に、透けるように白く憔悴していた。
けれど国村は、真直ぐ立って田中を背負って、青梅署へと戻った。
あのときの国村は泣いていなかった。
田中の家の手伝いとして立ち会っていた、通夜でも葬儀でも泣いていなかった。
山ヤに育ててくれた田中を、同じ山ヤとして、山の警察官として見送りたい。
きっとそんなふうに、あの時の英二と似た想いで、泣かなかったのだろう。
爆ぜる焚き火を見つめながら、ふっと国村が微笑んだ。
「俺はさ、田中のじいさんみたいに、生まれた場所を見つめられる、山ヤになりたいんだ。
それでさ、両親みたいに、ずっと大切な相手と寄り添ってね、生きて死んでいきたいよ」
そういう生き方は好きだ。英二は微笑んだ。
「ああ。俺もそんなふうに、生きたいって思う」
夜闇に朱色の炎が鮮やかだった。
いつのまにか空は晴れ、星がふるように輝いている。
冷たい風が雲を吹き、夜空を払ったようだった。
山にこだまする静けさに、星の音すら響くほど、空気は鎮まっている。
雲取山の日も、こんなふうに晴れるだろうか。周太にも見せてあげられたらいい。
きれいだなと見上げていると、頬に冷たい物が押し付けられた。
驚いて英二は、笑って振返った。
「冷てぇっ、なんだよ国村、」
驚いて、思わず呼び捨てになった。それを聴いて国村が、楽しそうに笑った。
「いいね、呼び捨て。俺もそうさせてもらうよ、宮田」
山の夜に焚き火の前で、国村は英二に、自分の話をした。
いつものように明るい目のままで、静かに自分の心を開いて話した。
見せてもらった心は、やっぱり良い奴で良い男だった。
こういう奴と対等な友人でいられたら、さぞ楽しいだろう。そう英二は思ってしまう。
そして国村も同じように思っているだろう。
だから口を開いて話して、呼び捨てで呼ぼうと笑ってくれる。
国村は、からりと底抜けに明るい。
冷静沈着だけれど大胆不敵。自由で厳しく、愉快な悪戯心、山への純粋無垢な想い。
そんな国村は英二と同じ、直情的で思ったことしか言えない、行動できない。
そして英二と同じように、大切な隣を見つめて、唯一の居場所にしている。
こういう友人を持てるなら、きっと良いだろう。
きれいに笑って英二は言った。
「じゃあさ国村、先輩だとかの遠慮も、もうしないけど?」
「ああ、いいよ。その方が俺もさ、気楽で助かるよ。ほら、」
言いながら国村は、持っていた缶を渡してくれる。
ありがとうと受取って見て、英二は笑った。
「これ、ビールだろ」
「そうだけど、なに?」
涼しい顔で国村は、さっさとプルリングを引いてしまった。
そして英二を見て、唇の端をあげて笑った。
「ほら、さっさと開けろよ、宮田、」
今、自分達がここにいるのは、遭難救助の任務中の為のはずだった。
任務中に酒を呑んでも、良いものだろうか。
けれど国村は自由人だ、多分言っても無駄だろうな。思いながらも、英二は訊いてみた。
「任務中にさ、いいのかよ?」
「もう0時過ぎている、構わないだろ」
何が悪いんだと涼しい顔で笑っている。
冷静沈着な国村の事だから、こういう大胆不敵な行動でも、どうせ計算があるのだろう。
そういえば国村は、3時間前まで遭難者に怒っていた。
機嫌をとれと後藤にも言われている。仕方ないなと英二もプルリングを引いた。
「はい、乾杯、」
からり笑って国村は、缶をぶつけてくれた。
熱い焚き火の前で、山の冷気によく冷えたビールは、旨かった。
ひとくち英二が呑みこんでから、国村は唇の端をあげた。
「あ、このこと内緒な。宮田も、もう飲んだから共犯だよ」
やっぱりなと英二は思った。
国村は文学青年みたいな繊細な風貌だけれど、酒も強い。
寮でも、晩酌はあたり前だという顔をして、缶を持っている時がある。
今も国村は焚き火を眺め、楽しそうに呑んでいる。
「酒飲んでもさ、救助隊員ならね、誰も酔っぱらわないよ」
奥多摩で山を見つめて育った国村。世田谷で苦労知らずに育った自分。
そんな二人が、同じ山ヤの警察官として、焚き火を囲んで酒を飲んでいる。
こういうのは悪くない、英二は楽しいなと微笑んだ。
けれど生真面目な周太が聴いたら、一体どんな顔をするのだろう?
任務中に酒呑むなんてと、呆れるだろうか。
けれど仕方ない、ここは山。
山には山ヤのルールがあるだろう。
幼い頃から山ヤとして生きる、そういう国村のルールには、初心者の自分は学ぶことしか出来やしない。
こういうのは悪くない、そして不思議にも思う。
自分が生まれ育った、あの高級住宅街。要領良く生きればいい、無難であればいい。そう気楽なフリをしていた。
けれど今、星空の下の山上で、無難を選べない直情的な男同士、こんなふうに酒を呑んでいる。
こういう友人と出会えた、そして今も周太の事を想ってしまう。
全く想定していなかった生き方、けれどこういうのは悪くない。むしろ幸せで、楽しい。
がらりと薪が崩れる音が、夜の底に響く。
傍らの薪を、国村のやり方を見ながらくべていく。
頬撫でる炎の熱と、肚の底を温める酒の熱が、心地良い。
こういうことは、自分は好きなんだな。思って英二は、静かに微笑んだ。
そんなふうに焚き火を眺めていると、からっと笑って国村が口を開いた。
「宮田はさ、男が好きなわけ?それとも、バイってやつ?」
英二は笑ってしまった。
ストレートな率直な物言いが、国村の底抜けな明るさで楽しかった。
朝は「時間違いの話題だからNG」と国村は言っていたが、今は深夜1時を過ぎた。
きっと、深夜の今ならば構わないのだろう。
そうだなと呟いて、英二は訊いた。
「国村はさ、人間なら誰でもいい訳じゃない、美代さんだから、大切なんだろ?」
細い目を和ませて、国村が微笑んだ。
「うん、そうだね。…そうか、宮田も同じなんだな」
やっぱり国村は察しが良い。頷いて英二は続けた。
「俺さ、小さい頃からモテたんだよね。
でも誰も俺の事なんか、ほんとには見てくれなかった。こういう見た目だけ。
あとは、ちょっと優しくて、それなりに頭もよくて運動できて、お洒落で会話が出来る。それだけ」
「それさ、宮田以外が言ったら、厭味になるね」
あははと国村が笑い飛ばしてくれる。
こういう国村の、底抜けな明るさはいい。英二も笑って、続けた。
「それで俺、いつのまにかさ、要領良く生きるようになったんだ。どうせ本当の俺なんか誰も見ない。そう思ってた」
へえ、と国村が笑った。
「今しか知らないと、驚くな」
「だろ?」
囲む炎の光が温かい、頬に火の熱を感じながら、英二は微笑んだ。
「でも、警察学校で周太に出会った。俺たち、寮の部屋が隣同士だったんだ」
ふうんと呟いて、そっと細い目を微笑ませて国村が言った。
「運命?」
「かな、」
国村の相槌は、どこか明るく、穏やかでいて楽しい。
夜に鎮まる山の空気の中で、英二はゆっくり話していった。
「警察官として男として、誇りをもって生きること。生きることの意味。何かの為に全てを掛けても、真剣に立ち向かう事。
そういう全てを教えてくれたのは、周太なんだ。
そして俺は、要領良く生きる事を止められた。こんなふうにさ、素直に生きる事を選べたんだ。だから頑張れた。
だからきっと、周太と出会えていなかったなら俺、ここには居ないんだ」
細い目を和ませて、国村は明るく微笑んだ。
「うん、いいな、そういうの」
頷いて、きれいに笑って、英二は言った。
「生きる目的を与えてくれた人。きれいな生き方で、俺を惹きつけて離さない。
静かに受けとめてくれる、穏やかな繊細な、居心地のいい隣。
どこより大切な、自分だけの居場所。それが俺にとっての周太。あの隣だけが、俺の帰る場所なんだ」
薪をくべながら、国村は微笑んでくれた。
「そういうのってさ、解るね」
真直ぐに見た国村の目は、底抜けに明るく笑って、頷いている。
やっぱり解ってくれるんだな。思って、英二は嬉しかった。
焚き火の熱、山の冷気、鎮まる星空。山に抱かれた夜のなかで、こんなふうに向き合う。
まだ1ヶ月半のつきあい、けれど英二と国村は互いに話せた。
そういう相手として国村は、男同士の話が、からり明るく楽しめる。
薪をまたくべると、ザックから国村がまた缶を取りだした。
今度はこれと渡されて見ると、低アルコール仕様のジントニックだった。
「3時過ぎたからね、アルコール量もさ、減らしていかないと」
そんなこと言いながら、プルリングをひいて英二にも促す。
英二も酒は弱くはない。開けて、また国村と缶をぶつけた。
ごくり喉鳴らして細い目を和ませると、国村は口を開いた。
「朝にさ、藤岡が言っていたこと。あれさ、マジなんだろ?」
周太がどう綺麗になったのか。
英二に訊かれて、藤岡は何気なく言った。
―女の子がさ、初体験で好きな男に抱かれた後。そんな顔に近いよ―
周太は、特別な関係を結んだのは、英二が初めてだった。
それから呼吸するごと周太は、素直に、きれいになっている。
だから藤岡の発言は、確かに本当の事だろう。英二は微笑んだ。
「ほら、運命だから」
きれいに笑って、英二はジントニックを呑んだ。
ふうんと呟く楽しげな国村は、細い目が温かい。温かい目のままで、国村が言った。
「そういう運命の相手って、いいよね」
やっぱり国村は、話して楽しい。
嬉しくて、きれいに英二は笑った。
「ああ、出会えて、幸せだな」
「だね、」
国村も笑った。
きっと国村も、きれいな瞳の明るい笑顔の、幼馴染を想いだしている。
今日は国村とビバーク出来て良かった。そう素直に思える。
ここに来られて本当によかった。
周太の父の合鍵に、救助服越しに触れながら、英二は綺麗に笑った。
夜が明けて、目星をつけた獣道を降った。本人達も登ってきて、合流して尾根まで上がる。
焚き火も出来ずに、ふたりで抱きあって夜を過ごしていたらしい。
すっかり冷え切っている2人に、飴を含ませながら、英二はカイロとレスキューシートで保温を施した。
その横から国村が、笑顔で事情聴取をしていく。
「もう、本当に寒くて大変でした」
「そうですか、おつかれさまでしたね。この道に入ったのは何時でした?」
そうして丁寧に聴取を終えると、国村はがらりと口調を変えて、男に言った。
「ほんと何も解っちゃいないね、ガキ過ぎんだよ。女連れで山に来るならさ、焚き火くらい出来ろよな。
それで彼女と星見てさ、火を囲んで夜明ししたら良いデートになったのに。気が利かない男だな、ねえ?」
英二は笑ってしまった。
こういう国村と一緒にいる、きれいな瞳の明るい笑顔は、きっと幸せだろう。
自分もこんなふうに、周太を幸せに出来たらいい。
きれいに微笑んで、英二は遭難者の男に言った。
「ほんとに、おつかれさまです。でも彼の言っている事は、きっと、あなたにとって大切なヒントですよ」
おどおどした男は、なんだろうと考えこんだ。
そんな英二を、男の隣から彼女は微笑んで見つめている。
それを見ていた国村がぼそっと呟いた。
「…あーあ、もう、」
英二の隣へと立って、国村が呆れたように唇の端を上げた。
「宮田さ、おまえ今ね、無自覚に恋をひとつ終わらせたんじゃない?」
「え、…そうかな?」
そうしている内に、岩崎達が登ってきた。
「お、どうやら無事だな」
笑いながら、持ってきてくれた温かい味噌汁と握飯を渡してくれる。
旨いなと頬張りながら、英二は2通のメールを送信した。
送ってすぐに、2通の受信が戻って英二は微笑んだ。
青梅街道で合流した後藤に、英二はおいでと呼ばれた。
国村の事を聴きたいのだろう、英二は後藤に微笑んだ。
遭難者への国村の言葉を聴いて、後藤は愉快そうに笑った。
「あいつ、やっぱり、山ヤで男だな」
本当にそうだと、英二も思う。
微笑んだ英二に、後藤は訊いてくれた。
「焚き火を囲んで、ふたりで一晩どうしていた?」
そうですねと笑って、英二は答えた。
「お互いを、呼び捨てで呼び合う事に、なりました」
「そうか、うん」
嬉しそうに後藤は破顔して、楽しそうに言ってくれた。
「お前たち、良い山ヤのコンビになれそうだな」
国村は、ファイナリストを嘱望されるクライマーだ。
同年だけれど警察官として4年先輩で、そして良い奴で良い男だ。
それから自分と同じように、大切な人の隣に居場所をもっている。
そういう国村と、まだ1ヶ月半しか経験のない自分を、そう言ってもらえる。
こういうのは、きっと得難い事だろう。英二は、真直ぐに後藤を見た。
「はい、山ヤで友人で、なりたいですね」
素直に嬉しくて、きれいに英二は笑った。
blogramランキング参加中!

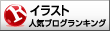
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村

岳夜、想話 act.3―side story 「陽はまた昇る」
遭難者が降りた獣道の入口に、目印の石積みを作ると、ビバークの準備に入る。
この尾根は細く場所は限られる。国村の言っていた場所まで歩いた。
きれいに整地して、枯れ木を集めて火を起こす。
空の雲はほとんど吹き払われていた。あわく残る雲の影からは、星がのぞき始めている。
見上げて、楽しげに国村が笑った。
「晴れてきてよかったな、雨や風は辛いからね」
山岳救助の現場では、こんなふうにビバークをする事も珍しくない。
ビバークは、登山やキャンプなどで、緊急的に野営することを指す。
公式には緊急時以外、いかなる山でも焚き火は肯定されていない。けれどこれは緊急時だった。
そんなわけで今は、堂々と焚き火を行える。
「冷たい山の空気で眺めるとさ、焚き火の良さを一番感じられるよ」
国村はこういう事が好きらしく、機嫌良く準備している。
不用意な遭難者には怒っても、ビバークは嬉しそうだった。
もしかして国村は、この為に山岳救助隊員になったのかな。そんな事を英二は思った。
「火は小さく起こして、大きく育てるのが、焚き火のコツなんだ」
慣れた手つきで、国村が火をおこし、上手に火を育てていく。
あらかじめ大量に集めておいた薪を、様子をみながらくべていった。
枯れた秋の山は燃えやすい、付近に相当の注意を払いながら、このまま夜明しをする。
順調に大きくなる火を見つめながら、国村がそうだったと英二を見た。
「あのさ、遠慮なく電話しなよ。待ってるんでしょ」
いつも周太には21時に電話している。今はもう23時前だった。
青梅署を出る前にメールはしたが、心配しているかもしれない。
「悪いな。じゃ、ちょっと」
英二は微笑んで、遠慮なくベルトと繋いだ携帯を開いた。
受信メールが1件入っている。
From :湯原周太
subject:まってる
本 文 :いつでも、待っているから。
短い文章、けれど気持が嬉しい。
周太も当番勤務で、今夜は新宿駅東口交番での夜になる。
今頃は、どうしているのだろう。あの声を聴きたい。
けれど、その前に英二は、吉村医師への短いメールを送った。
やっぱり吉村は、心配してくれていたらしい。すぐに、短文でも温かな返信が届いた。
メールして良かったと英二は微笑んだ。
英二は立ち上がって、新宿方面の空を眺めた。
深夜23時、それでも無数の明りが瞬いている。そのどれか一つに今、あの隣はいる。
発信履歴から通話ボタンを押すと、コール音も無く繋がった。
「待ってた?」
「…ん、待ってた」
待っていて貰えて、嬉しい。嬉しくて英二は微笑んだ。
「すげえ嬉しいよ。待っていてくれて、ありがとうな」
「ん…こっちこそ、うれしい。電話、ありがとう」
答える声に初々しい艶がある、眠たくて無防備になっている所為だろう。
こんな無自覚な艶が、周太にはある。警察学校の時から、英二は見惚れていた。
けれどこの1ヶ月半で更に、きれいになっている。他では絶対に見せないでと、いつも英二は思ってしまう。
今もすこし心配になりながら、英二は訊いた。
「いま、周太、ひとり?」
「…ん、そう…休憩室でね…仮眠とってる」
言葉の合間が、眠たそうで可愛い。
ふっと聞こえる吐息が、一緒の夜を懐かしがらせてくれる。
眠たそうで寝ませてあげたいのに、つい声を聴きたくて、英二は少しだけ話した。
「榧ノ木山って所にいるんだ。雲取山とね、新宿も見える」
「そうなんだ、…なんか、うれしいな」
「どうして、うれしい?」
そっと訊いてみると、眠たげで恥ずかしげな声が、答えてくれた。
「…俺のいるところ、見ていてもらえる、なんか安心…うれしい」
こんなふうに、言ってもらえる事が、嬉しくてならない。
とても小さな事かも知れない、日常的なありふれた会話。けれどこんなに、その日常が嬉しい。
そしてきっと、この日常が遠くなった時は、こんな小さな事が、細かく重たい冷たい傷になる。
それなのに自分は、13年前に周太につけられた、そんな傷を想いやれなかった。
唯ひとり、この隣に立っていたいと願いながら、自分は解っていなかった。
ただ詫びて済ませられるなら、簡単だと思う。けれど自分の想いは、そんなに簡単には済ませられないだろう。
だってこんなにもう、この隣の事ばかり想っている。
「いつも本当は見ていたいよ、周太のこと。小さい事でも一つずつ、ずっと見つめていたい」
「…ん、うれしい。俺も、…見ていたい」
繋いだ電話の向こう、あの隣が微笑んでくれる。きっと、きれいな純粋な笑顔が咲いている。
こんなふうにいつも、周太は純粋でいてくれる。呼吸するごと素直になって、きれいな瞳で応えてくれる。
こんな今が嬉しくて、そっと微笑んで英二は言った。
「3日後は見ているよ、山の上で」
「ん、…うれしいな。楽しみにしてる」
そんなふうに少し話して、周太の寝息を聴いて、英二は携帯を閉じた。
振り返ると、国村も携帯を閉じたところだった。
「国村さんも電話?」
「うん、彼女にね。これさ、食っていいんだよね」
さらっと言って、国村はアーモンドチョコレートの箱を開け始めた。
おうと返事して、はたと英二は止まった。
今、確かに「彼女」と国村は言った。
国村は、文学青年みたいな整った風貌をしている。賢明で洞察力も鋭く、言葉にも行動にも無駄がない。
すぐ人を転がす癖はあるけれど、底抜けの明るさで厭味にならない。
クライマーで警察官の兼業農家で、落着いた思考と高い身体能力の持ち主でもある。
こんなふうに国村は良い奴だ、彼女がいても不思議はない。
でも、国村は冷静沈着な反面、大胆不敵で自由人だ。
この間も、平気でミニパトカーを激走させた。さっきも、遭難者へと風変わりなエールを送っている。
そんな国村は悪戯心が起き上がると、やっかいな知能犯になってしまう。
普通の女の子だと、ついて行き難いだろう。
「国村さんの彼女って、どんなひと?」
微笑んで率直に英二は訊いてみた。
アーモンドチョコレートをごりごり噛みながら、国村は英二を見た。
「うん。幼馴染みでさ、逞しいかな」
「逞しい?」
幼馴染は想定どおりだと英二は思った。
けれど逞しいってなんだろう、考えていると国村は口を開いた。
「美代ん家もさ、農家なんだよ。それでね、梅干しでも味噌でも、何でも自分で作って俺にもくれるんだ」
「へえ、すごいな」
素直に英二は感心した。今時の女の子で、そうした手仕事がこなせる人は少ないだろう。
国村は涼しい顔で、アーモンドチョコレートをまた口に放り込んでいる。
「うん、今時は少ないタイプかもね。でも、美代は美代だからさ」
国村の細い目が、ふっと和やかになった。
「美代は美代だから」そんな言葉から国村の想いが解る。
微笑んで、英二は訊いてみた。
「写真とかないの?」
ごりごり口を動かしながら、国村は携帯をチェーンから外した。
片手で気軽に操作して、はいと英二に差出してくれる。受け取って見て、英二は素直に褒めた。
「へえ、かわいいな」
すこし陽に妬けた、きれいな瞳の女の子が笑っていた。化粧気も少ない、くったくない明るさが可愛い。
同じ年なんだよねと、何でもない事のように国村は教えてくれた。
「家が隣でさ。生まれてすぐにね、保育園から農業高校まで、ずっと一緒だったんだ」
「いいな、そういうの」
「うん。一緒にいるのが当たり前で、自然なんだよね」
ずっと国村は、彼女だけを見ているのだろう。
生まれた時から見つめた相手を、ずっと見つめていける。
当たり前のように自然に、ずっと一緒に生きている。そういうのはきっと、とても幸せだ。
そういう国村がなんだか嬉しくて、英二は微笑んだ。
「なんかさ、国村さんらしいよ」
「だろ、」
焚き火に白い頬を照らしながら、からっと笑って国村は言った。
「だからさ、警察学校に入る時は、寂しかったな」
美代も泣いたけど、俺もちょっと泣いたよ。
そんなふうに、さらっと言って国村は笑った。
泣いている国村が、なんだか想像できない。
国村はどこか浮世離れしていて、天才肌の空気がある。
だからそんなふうに、自分と同じような面があるのは、なんだか嬉しい。
英二は笑った。
「国村さんでも、泣くことあるんだな」
「うん、回数少ないけどね。たまには、あるよ」
からり笑って国村は、また一つ口に放り込んで、ごりごり噛み砕いた。
英二もオレンジ色のパッケージを出して、一粒口に含んだ。この味を好む笑顔と、馴染んだ味がやさしい。
今頃はよく眠っているだろう。仮眠でも周太には、良い夢を見ていてほしい。
焚き火の炎が、ぱちんと爆ぜる。
夜半を過ぎた寒気が山を覆っていく、けれど焚き火の周りは暖かだった。
山の静けさに炎の音が響く。こういう時間は好きだ、英二は安らいだ。
炎に照らされるお互いの顔を見ながら、国村が口を開いた。
「俺の両親ってさ、山で死んだだろ?」
国村の両親は、国内ファイナリストのクライマーだった。
国村が中学校に上がってすぐ、海外の雪山で亡くなったと英二も訊いている。
静かに英二は頷いた。
「…うん、」
ぱちっと炎が小枝に爆ぜる。
静かな夜の空間に、底が明るい落着いた声が、ゆっくり言った。
「祖父と一緒にね、遺体を引取りにさ、ネパールまで行ったんだ。そのときは俺ね、涙が出なかった」
細い目を炎に微笑ませて、国村が話していく。
薪を少し足しながら、そっと英二は国村の話に寄り添っていた。
「マナスルをさ、両親はペアを組んで登った。二人でペアを組むのは珍しかった、俺が生まれてからはね」
「うん、…」
マナスルManaslu 標高8,163m、世界8位の高さを誇り、ヒマラヤ山脈に属している。
何人もの登山家が雪崩で亡くなっていると、英二も読んだ事がある。
いつもの落着いた声で、国村は英二の目を見、細い目は静かに笑った。
「セラック崩壊のブロックにね、飛ばされてさ。二人とも雪と氷に引きこまれた」
セラックとは、氷河に出来た氷塔ブロックをいう。非常に不安定で崩壊すると、氷の塊ブロックが飛ぶ。
セラック崩壊に巻き込まれる事は、こんなふうに死にも繋がる。
高く深い雪山に登るなら、誰もが覚悟する事態。
それでも雪山を目指す、その想いは英二には否定できない。
山ヤを志して出会った雪山の写真、その経験談は、既に英二の心を惹きつけ始めている。
それでもやはり、遺された人間を想うと、英二は悲しかった。
国村はそうして遺された。
焚き火に照らされながら、静かに国村が口を開いた。
「両親は二人一緒に、ロープで結ばれた姿で発見されたよ。互いに固く、アイザイレンしていた」
アイザイレンは、ザイルパートナーとして、互いにザイルを結び合うこと。
国村の両親の、お互いへの想いが、英二の心にも静かに感じられた。
「ほんとにね、仲のいい両親なんだ」
温かな炎の前で、国村は微笑んだ。
国村の細い目の瞳に、ゆっくり炎が光っている。
「俺さ、そのときに思ったんだ。きっと二人一緒で、幸せだったろうなって」
中学生にあがったばかりの、明るい春だったろう。
そこへ急に現われた悲しみを、12歳の国村は静かに見つめていた。
「ずっと俺、涙が出なかった。知らせを受けた時もさ、ネパールで両親と対面した時も、家に戻ってもね」
「うん、…」
そっと英二は頷いた。
そんな英二に微笑んで、きれいに笑って国村は言った。
「そうしたらさ、葬儀の時に田中のじいさんが言ってくれたんだ。
山ヤが山で死ぬだけだ、それが山ヤの本望だ。
だからお前の両親は幸せだよ。そう言われてね、やっと俺、初めて涙が出たんだ」
話してくれる口調は穏やかで、静かだった。
国村の家と田中の家は、遠縁の親戚だった。農家同士で、互いに援け合う。代々そんな付き合いだと聴いている。
田中の孫である秀介も「こうちゃん」と国村には懐いていた。
そんなつきあいの中で、世代を超えた山ヤ同士の、そういう繋がりが結ばれたのだろう。
田中らしく、国村らしい。そんなふうに英二は思えた。
薪が炎に爆ぜる、ぱちりと響く音を聴きながら、英二は国村を見つめていた。
それでさと、微笑んで国村は続けた。
「田中のじいさんね、あの大きな掌と胸でさ、俺を抱きしめて泣かせてくれたんだ。ほんと温かくて嬉しかったよ」
「うん、」
写真家で地元の農家だった田中は、愛した御岳山で眠りについた。
英二の背中で最後を迎えた時も、大きな掌と胸は温かかった。
爆ぜる炎に頬を明るませながら、国村は教えてくれた。
「両親が死んだあとはさ、田中のじいさんが俺を山へ連れて行ってくれたんだ」
「…そうだったのか、」
そうと頷いて、国村は微笑んだ。
「一緒に国内をさ、いろんな山に登った。そうしてね、俺を山ヤに育ててくれたんだよ」
田中が息を引き取った、御岳の氷雨の夜。
呼吸を止めた田中を、駆けつけた国村は必死で蘇生させようとした。
けれど戻らない息に、国村はぽつんと呟いた。
― …俺に、背負わせてくれるかな ―
そして国村は静かに田中を背負って、下山した。
あの時なぜ国村が、田中を背負うことを望んだのか。
その理由がわかったと、英二は思った。
あの時の国村は、色白の顔が余計に、透けるように白く憔悴していた。
けれど国村は、真直ぐ立って田中を背負って、青梅署へと戻った。
あのときの国村は泣いていなかった。
田中の家の手伝いとして立ち会っていた、通夜でも葬儀でも泣いていなかった。
山ヤに育ててくれた田中を、同じ山ヤとして、山の警察官として見送りたい。
きっとそんなふうに、あの時の英二と似た想いで、泣かなかったのだろう。
爆ぜる焚き火を見つめながら、ふっと国村が微笑んだ。
「俺はさ、田中のじいさんみたいに、生まれた場所を見つめられる、山ヤになりたいんだ。
それでさ、両親みたいに、ずっと大切な相手と寄り添ってね、生きて死んでいきたいよ」
そういう生き方は好きだ。英二は微笑んだ。
「ああ。俺もそんなふうに、生きたいって思う」
夜闇に朱色の炎が鮮やかだった。
いつのまにか空は晴れ、星がふるように輝いている。
冷たい風が雲を吹き、夜空を払ったようだった。
山にこだまする静けさに、星の音すら響くほど、空気は鎮まっている。
雲取山の日も、こんなふうに晴れるだろうか。周太にも見せてあげられたらいい。
きれいだなと見上げていると、頬に冷たい物が押し付けられた。
驚いて英二は、笑って振返った。
「冷てぇっ、なんだよ国村、」
驚いて、思わず呼び捨てになった。それを聴いて国村が、楽しそうに笑った。
「いいね、呼び捨て。俺もそうさせてもらうよ、宮田」
山の夜に焚き火の前で、国村は英二に、自分の話をした。
いつものように明るい目のままで、静かに自分の心を開いて話した。
見せてもらった心は、やっぱり良い奴で良い男だった。
こういう奴と対等な友人でいられたら、さぞ楽しいだろう。そう英二は思ってしまう。
そして国村も同じように思っているだろう。
だから口を開いて話して、呼び捨てで呼ぼうと笑ってくれる。
国村は、からりと底抜けに明るい。
冷静沈着だけれど大胆不敵。自由で厳しく、愉快な悪戯心、山への純粋無垢な想い。
そんな国村は英二と同じ、直情的で思ったことしか言えない、行動できない。
そして英二と同じように、大切な隣を見つめて、唯一の居場所にしている。
こういう友人を持てるなら、きっと良いだろう。
きれいに笑って英二は言った。
「じゃあさ国村、先輩だとかの遠慮も、もうしないけど?」
「ああ、いいよ。その方が俺もさ、気楽で助かるよ。ほら、」
言いながら国村は、持っていた缶を渡してくれる。
ありがとうと受取って見て、英二は笑った。
「これ、ビールだろ」
「そうだけど、なに?」
涼しい顔で国村は、さっさとプルリングを引いてしまった。
そして英二を見て、唇の端をあげて笑った。
「ほら、さっさと開けろよ、宮田、」
今、自分達がここにいるのは、遭難救助の任務中の為のはずだった。
任務中に酒を呑んでも、良いものだろうか。
けれど国村は自由人だ、多分言っても無駄だろうな。思いながらも、英二は訊いてみた。
「任務中にさ、いいのかよ?」
「もう0時過ぎている、構わないだろ」
何が悪いんだと涼しい顔で笑っている。
冷静沈着な国村の事だから、こういう大胆不敵な行動でも、どうせ計算があるのだろう。
そういえば国村は、3時間前まで遭難者に怒っていた。
機嫌をとれと後藤にも言われている。仕方ないなと英二もプルリングを引いた。
「はい、乾杯、」
からり笑って国村は、缶をぶつけてくれた。
熱い焚き火の前で、山の冷気によく冷えたビールは、旨かった。
ひとくち英二が呑みこんでから、国村は唇の端をあげた。
「あ、このこと内緒な。宮田も、もう飲んだから共犯だよ」
やっぱりなと英二は思った。
国村は文学青年みたいな繊細な風貌だけれど、酒も強い。
寮でも、晩酌はあたり前だという顔をして、缶を持っている時がある。
今も国村は焚き火を眺め、楽しそうに呑んでいる。
「酒飲んでもさ、救助隊員ならね、誰も酔っぱらわないよ」
奥多摩で山を見つめて育った国村。世田谷で苦労知らずに育った自分。
そんな二人が、同じ山ヤの警察官として、焚き火を囲んで酒を飲んでいる。
こういうのは悪くない、英二は楽しいなと微笑んだ。
けれど生真面目な周太が聴いたら、一体どんな顔をするのだろう?
任務中に酒呑むなんてと、呆れるだろうか。
けれど仕方ない、ここは山。
山には山ヤのルールがあるだろう。
幼い頃から山ヤとして生きる、そういう国村のルールには、初心者の自分は学ぶことしか出来やしない。
こういうのは悪くない、そして不思議にも思う。
自分が生まれ育った、あの高級住宅街。要領良く生きればいい、無難であればいい。そう気楽なフリをしていた。
けれど今、星空の下の山上で、無難を選べない直情的な男同士、こんなふうに酒を呑んでいる。
こういう友人と出会えた、そして今も周太の事を想ってしまう。
全く想定していなかった生き方、けれどこういうのは悪くない。むしろ幸せで、楽しい。
がらりと薪が崩れる音が、夜の底に響く。
傍らの薪を、国村のやり方を見ながらくべていく。
頬撫でる炎の熱と、肚の底を温める酒の熱が、心地良い。
こういうことは、自分は好きなんだな。思って英二は、静かに微笑んだ。
そんなふうに焚き火を眺めていると、からっと笑って国村が口を開いた。
「宮田はさ、男が好きなわけ?それとも、バイってやつ?」
英二は笑ってしまった。
ストレートな率直な物言いが、国村の底抜けな明るさで楽しかった。
朝は「時間違いの話題だからNG」と国村は言っていたが、今は深夜1時を過ぎた。
きっと、深夜の今ならば構わないのだろう。
そうだなと呟いて、英二は訊いた。
「国村はさ、人間なら誰でもいい訳じゃない、美代さんだから、大切なんだろ?」
細い目を和ませて、国村が微笑んだ。
「うん、そうだね。…そうか、宮田も同じなんだな」
やっぱり国村は察しが良い。頷いて英二は続けた。
「俺さ、小さい頃からモテたんだよね。
でも誰も俺の事なんか、ほんとには見てくれなかった。こういう見た目だけ。
あとは、ちょっと優しくて、それなりに頭もよくて運動できて、お洒落で会話が出来る。それだけ」
「それさ、宮田以外が言ったら、厭味になるね」
あははと国村が笑い飛ばしてくれる。
こういう国村の、底抜けな明るさはいい。英二も笑って、続けた。
「それで俺、いつのまにかさ、要領良く生きるようになったんだ。どうせ本当の俺なんか誰も見ない。そう思ってた」
へえ、と国村が笑った。
「今しか知らないと、驚くな」
「だろ?」
囲む炎の光が温かい、頬に火の熱を感じながら、英二は微笑んだ。
「でも、警察学校で周太に出会った。俺たち、寮の部屋が隣同士だったんだ」
ふうんと呟いて、そっと細い目を微笑ませて国村が言った。
「運命?」
「かな、」
国村の相槌は、どこか明るく、穏やかでいて楽しい。
夜に鎮まる山の空気の中で、英二はゆっくり話していった。
「警察官として男として、誇りをもって生きること。生きることの意味。何かの為に全てを掛けても、真剣に立ち向かう事。
そういう全てを教えてくれたのは、周太なんだ。
そして俺は、要領良く生きる事を止められた。こんなふうにさ、素直に生きる事を選べたんだ。だから頑張れた。
だからきっと、周太と出会えていなかったなら俺、ここには居ないんだ」
細い目を和ませて、国村は明るく微笑んだ。
「うん、いいな、そういうの」
頷いて、きれいに笑って、英二は言った。
「生きる目的を与えてくれた人。きれいな生き方で、俺を惹きつけて離さない。
静かに受けとめてくれる、穏やかな繊細な、居心地のいい隣。
どこより大切な、自分だけの居場所。それが俺にとっての周太。あの隣だけが、俺の帰る場所なんだ」
薪をくべながら、国村は微笑んでくれた。
「そういうのってさ、解るね」
真直ぐに見た国村の目は、底抜けに明るく笑って、頷いている。
やっぱり解ってくれるんだな。思って、英二は嬉しかった。
焚き火の熱、山の冷気、鎮まる星空。山に抱かれた夜のなかで、こんなふうに向き合う。
まだ1ヶ月半のつきあい、けれど英二と国村は互いに話せた。
そういう相手として国村は、男同士の話が、からり明るく楽しめる。
薪をまたくべると、ザックから国村がまた缶を取りだした。
今度はこれと渡されて見ると、低アルコール仕様のジントニックだった。
「3時過ぎたからね、アルコール量もさ、減らしていかないと」
そんなこと言いながら、プルリングをひいて英二にも促す。
英二も酒は弱くはない。開けて、また国村と缶をぶつけた。
ごくり喉鳴らして細い目を和ませると、国村は口を開いた。
「朝にさ、藤岡が言っていたこと。あれさ、マジなんだろ?」
周太がどう綺麗になったのか。
英二に訊かれて、藤岡は何気なく言った。
―女の子がさ、初体験で好きな男に抱かれた後。そんな顔に近いよ―
周太は、特別な関係を結んだのは、英二が初めてだった。
それから呼吸するごと周太は、素直に、きれいになっている。
だから藤岡の発言は、確かに本当の事だろう。英二は微笑んだ。
「ほら、運命だから」
きれいに笑って、英二はジントニックを呑んだ。
ふうんと呟く楽しげな国村は、細い目が温かい。温かい目のままで、国村が言った。
「そういう運命の相手って、いいよね」
やっぱり国村は、話して楽しい。
嬉しくて、きれいに英二は笑った。
「ああ、出会えて、幸せだな」
「だね、」
国村も笑った。
きっと国村も、きれいな瞳の明るい笑顔の、幼馴染を想いだしている。
今日は国村とビバーク出来て良かった。そう素直に思える。
ここに来られて本当によかった。
周太の父の合鍵に、救助服越しに触れながら、英二は綺麗に笑った。
夜が明けて、目星をつけた獣道を降った。本人達も登ってきて、合流して尾根まで上がる。
焚き火も出来ずに、ふたりで抱きあって夜を過ごしていたらしい。
すっかり冷え切っている2人に、飴を含ませながら、英二はカイロとレスキューシートで保温を施した。
その横から国村が、笑顔で事情聴取をしていく。
「もう、本当に寒くて大変でした」
「そうですか、おつかれさまでしたね。この道に入ったのは何時でした?」
そうして丁寧に聴取を終えると、国村はがらりと口調を変えて、男に言った。
「ほんと何も解っちゃいないね、ガキ過ぎんだよ。女連れで山に来るならさ、焚き火くらい出来ろよな。
それで彼女と星見てさ、火を囲んで夜明ししたら良いデートになったのに。気が利かない男だな、ねえ?」
英二は笑ってしまった。
こういう国村と一緒にいる、きれいな瞳の明るい笑顔は、きっと幸せだろう。
自分もこんなふうに、周太を幸せに出来たらいい。
きれいに微笑んで、英二は遭難者の男に言った。
「ほんとに、おつかれさまです。でも彼の言っている事は、きっと、あなたにとって大切なヒントですよ」
おどおどした男は、なんだろうと考えこんだ。
そんな英二を、男の隣から彼女は微笑んで見つめている。
それを見ていた国村がぼそっと呟いた。
「…あーあ、もう、」
英二の隣へと立って、国村が呆れたように唇の端を上げた。
「宮田さ、おまえ今ね、無自覚に恋をひとつ終わらせたんじゃない?」
「え、…そうかな?」
そうしている内に、岩崎達が登ってきた。
「お、どうやら無事だな」
笑いながら、持ってきてくれた温かい味噌汁と握飯を渡してくれる。
旨いなと頬張りながら、英二は2通のメールを送信した。
送ってすぐに、2通の受信が戻って英二は微笑んだ。
青梅街道で合流した後藤に、英二はおいでと呼ばれた。
国村の事を聴きたいのだろう、英二は後藤に微笑んだ。
遭難者への国村の言葉を聴いて、後藤は愉快そうに笑った。
「あいつ、やっぱり、山ヤで男だな」
本当にそうだと、英二も思う。
微笑んだ英二に、後藤は訊いてくれた。
「焚き火を囲んで、ふたりで一晩どうしていた?」
そうですねと笑って、英二は答えた。
「お互いを、呼び捨てで呼び合う事に、なりました」
「そうか、うん」
嬉しそうに後藤は破顔して、楽しそうに言ってくれた。
「お前たち、良い山ヤのコンビになれそうだな」
国村は、ファイナリストを嘱望されるクライマーだ。
同年だけれど警察官として4年先輩で、そして良い奴で良い男だ。
それから自分と同じように、大切な人の隣に居場所をもっている。
そういう国村と、まだ1ヶ月半しか経験のない自分を、そう言ってもらえる。
こういうのは、きっと得難い事だろう。英二は、真直ぐに後藤を見た。
「はい、山ヤで友人で、なりたいですね」
素直に嬉しくて、きれいに英二は笑った。
blogramランキング参加中!


















