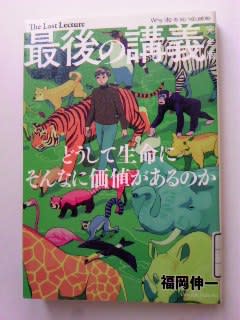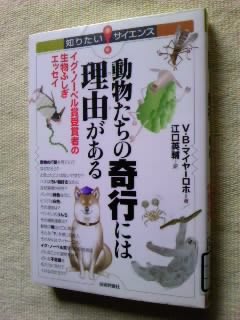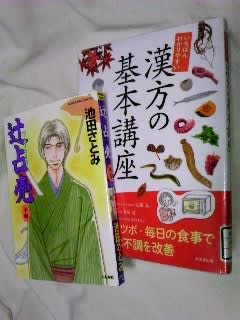6月16日(水)
「あなたの隣の精神疾患」春日武彦(集英社インターナショナル新書 2021年)を読了。
春日武彦の「読解力」はすごい。
すごいっていうか「凄い」。
人間の精神の脆さやグロさやキッチュな様子を解説するために、
症例以外によく文学作品を例に使うけど、
その読み解きが見事で、
ああ、そう読み取るんだ!とはっとさせられることが多いです。
精神科医になるべくしてなったというかんじ。
特に完全に“狂っちゃった”人より、
普通の生活のなかに生きる“ちょっとおかしい人”を受信するアンテナが高性能すぎます。
「あなたの隣の精神疾患」春日武彦(集英社インターナショナル新書 2021年)を読了。
春日武彦の「読解力」はすごい。
すごいっていうか「凄い」。
人間の精神の脆さやグロさやキッチュな様子を解説するために、
症例以外によく文学作品を例に使うけど、
その読み解きが見事で、
ああ、そう読み取るんだ!とはっとさせられることが多いです。
精神科医になるべくしてなったというかんじ。
特に完全に“狂っちゃった”人より、
普通の生活のなかに生きる“ちょっとおかしい人”を受信するアンテナが高性能すぎます。