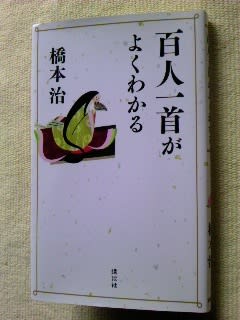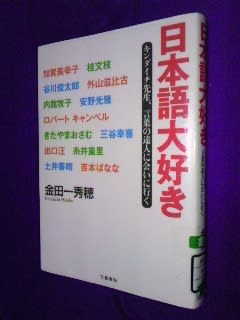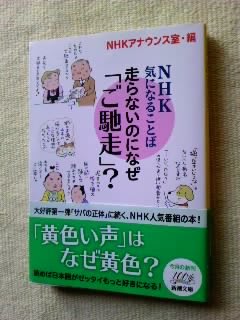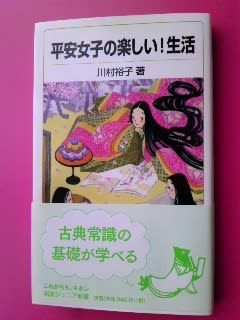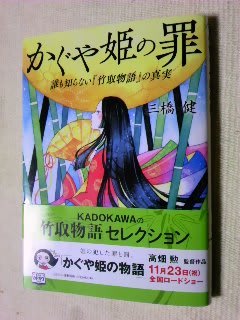《8/4読了 新潮社 2011年刊 【評伝 安部公房】 あべ・ねり》
一人娘の手による安部公房の評伝。
1/3ほど読んだあたりで中断したままになってたんですが、先日の山口果林本があまりにおもしろかったので、その勢いでこっちの残りも読了。
日本人2人めのノーベル文学賞受賞者になるはずだった安部公房の足跡をたどった伝記資料(なんと祖父母の代から話が始まります)としても、安部文学論としても、充実しています。
筆者ねりさんは、娘であると同時に安部公房研究者でもあり、そこらへんのあたたかさとクールさの混ざり加減がこの本の魅力です。
「安部公房全集」各巻の付録に収録された25人のインタビューがまとめられているのもお得なかんじがします。
さらに、未公表の写真がたくさん収められていて、文学者であり父であり夫であった安部公房とその家族の表情もすごくいい。
進化論をめぐっての父娘の口論も微笑ましい。
でも、ここに書かれたこと以上に「書かれなかった2つのこと」が大きな意味を持っています。
ひとつは癌のこと。
安部公房は自らが癌に冒されていることを徹底的に隠しました。
だからこの本には、癌のガの字も出てこない。
彼の死後も遺志を守り、その事実を伏せた娘と、癌だったことのみならずそれを隠した理由まで書いた愛人、その「愛」の違いを思うとなんだかゾクッとします。
もうひとつは山口果林のこと。
ねりさんは、安部夫妻の関係に亀裂が入った理由として、芸術家同士の競争心のようなものと、それによって真知夫人の夫への尊敬が薄れてしまったことをあげています。
もちろん山口果林の存在は黙殺です。
そして、夫婦が決して没交渉なんかではなかったことを強調している。
父母の死後、娘が必死に互いを繋ぎ止め、わたしたちは紛れもない家族だったんだ!と静かに歯を食いしばっているような気がします。
「ふたりの関係が苦痛なものになっても公房は、極貧だった若い時代、認められ、やっと食べられるようになって喜んだ真知を忘れることはなかった。公房は、かつてのように真知に小説の構想を話し、真知は喜んで『カンガルー・ノート』に使われた「一つ積んでは親のため」という賽の河原の歌のテープを故郷の大分から取り寄せた」(217p)
安部公房は1993年1月に亡くなるのですが、前年の暮れには親子3人で食事までしています。
安部本人も苦しんだでしょうが、彼を囲む女3人の苦悩を思うといたたまれない。
この本こそが、山口果林に火をつけ、暴露本を書かせたに違いない!と邪推する次第です。
→
「安部公房とわたし」山口果林
/「安部公房伝」安部ねり