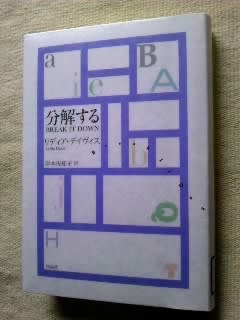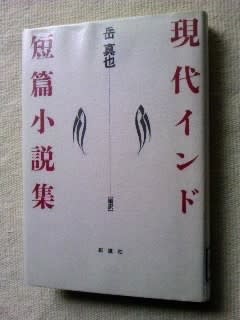4月14日(火)
「コドモノセカイ」(岸本佐知子/編訳 河出書房新社)を読む。
生まれてこの方、いつのまにか時間だけがただ経過したという人間(つまりわたし)が読むと呼吸が苦しくなる作品集でした。
(賞賛です)
子供時代なんて一度でたくさん。
毎日ドキドキしてるし、嫉妬でがんじがらめだし、融通は利かないし、感情や欲求のコントロールは下手だし、後悔ばっかりだし、嘘ついちゃうし、妄想は止まらないし、最悪です。
とにかく苦労が多い。
そういうあれこれを忘れたことにして生きて行きたいのに、つい魔が差してこんな本を読んでしまいました。
ヘトヘトになりました。(賞賛です)
もう二度と子供には戻りたくない。
あと、周知のことではありますが、岸本佐知子は翻訳者としてはもちろんアンソロジストとしても最高です。
「コドモノセカイ」(岸本佐知子/編訳 河出書房新社)を読む。
生まれてこの方、いつのまにか時間だけがただ経過したという人間(つまりわたし)が読むと呼吸が苦しくなる作品集でした。
(賞賛です)
子供時代なんて一度でたくさん。
毎日ドキドキしてるし、嫉妬でがんじがらめだし、融通は利かないし、感情や欲求のコントロールは下手だし、後悔ばっかりだし、嘘ついちゃうし、妄想は止まらないし、最悪です。
とにかく苦労が多い。
そういうあれこれを忘れたことにして生きて行きたいのに、つい魔が差してこんな本を読んでしまいました。
ヘトヘトになりました。(賞賛です)
もう二度と子供には戻りたくない。
あと、周知のことではありますが、岸本佐知子は翻訳者としてはもちろんアンソロジストとしても最高です。
2月21日(金)
ちびちび読んでいた「女嫌いのための小品集」(パトリシア・ハイスミス 河出文庫)を読了。
ちょっと悪ノリに思えるものや珍味も混ざってるので、すこしずつ読むのが正解かも。
あらゆる種類の困った女たちが出てくるこの作品集と、「キャロル」みたいなきめの細かい女同士の恋愛ものを書く人が同一人物ってのがまたときめかせます。
この作品集の容赦ない“女嫌い(misogyny)”っぷりは、山岸凉子に似ている気がします。
違うところは、山岸凉子には“厳格な姉と奔放な妹”ものがいくつもあるけど、ある作品では姉をかばって妹を裁き、また別の作品では妹をしっかり認めるみたいになっていて、そこに作者のタフさや成熟を感じる点です。
慈悲と言ってもいい。
鋭すぎる冷徹さは共通しているけど、
ハイスミスには山岸凉子の“業(ごう)を静かに見つめるまなざし”や“人間を見捨てない心の厚み”のようなものがほとんどなくて、
だから一層厳しくてどうしようもなく孤独なかんじがするのかもしれません。
ちびちび読んでいた「女嫌いのための小品集」(パトリシア・ハイスミス 河出文庫)を読了。
ちょっと悪ノリに思えるものや珍味も混ざってるので、すこしずつ読むのが正解かも。
あらゆる種類の困った女たちが出てくるこの作品集と、「キャロル」みたいなきめの細かい女同士の恋愛ものを書く人が同一人物ってのがまたときめかせます。
この作品集の容赦ない“女嫌い(misogyny)”っぷりは、山岸凉子に似ている気がします。
違うところは、山岸凉子には“厳格な姉と奔放な妹”ものがいくつもあるけど、ある作品では姉をかばって妹を裁き、また別の作品では妹をしっかり認めるみたいになっていて、そこに作者のタフさや成熟を感じる点です。
慈悲と言ってもいい。
鋭すぎる冷徹さは共通しているけど、
ハイスミスには山岸凉子の“業(ごう)を静かに見つめるまなざし”や“人間を見捨てない心の厚み”のようなものがほとんどなくて、
だから一層厳しくてどうしようもなく孤独なかんじがするのかもしれません。
7月26日(火)
リディア・デイヴィス『分解する』(岸本佐知子 訳/作品社)を読み終わる。
おもしろいやつもあれば、ピンと来ないやつもある。
好きだなと思ったのは「私に関するいくつかの好ましくない点」「母親たち」「骨」「母親」「メイド」。
読みやすさでいうと『ほとんど記憶のない女』の方が読みやすい。
ナマッぽさではこっちかな、というかんじ。
リディア・デイヴィス『分解する』(岸本佐知子 訳/作品社)を読み終わる。
おもしろいやつもあれば、ピンと来ないやつもある。
好きだなと思ったのは「私に関するいくつかの好ましくない点」「母親たち」「骨」「母親」「メイド」。
読みやすさでいうと『ほとんど記憶のない女』の方が読みやすい。
ナマッぽさではこっちかな、というかんじ。
5月23日(月)
おもしろくないわけではないが、短編集『10の奇妙な話』(ミック・ジャクソン/東京創元社)にちょっと飽きてくる。
話の転がり方がなんだか恣意的でうっすらと独りよがり、別にこういう展開じゃなくてもいいんじゃないかとも思える。
毎日新聞の書評では「童話の無邪気な怖さ」と褒められていたけど、そこを狙ってそういうコンセプトのもと書かれたような薄っぺらさを感じてしまった。
ひねくれている、と言われれば返す言葉もない。
あと3つ残っているので、ちゃんと読みます。
おもしろくないわけではないが、短編集『10の奇妙な話』(ミック・ジャクソン/東京創元社)にちょっと飽きてくる。
話の転がり方がなんだか恣意的でうっすらと独りよがり、別にこういう展開じゃなくてもいいんじゃないかとも思える。
毎日新聞の書評では「童話の無邪気な怖さ」と褒められていたけど、そこを狙ってそういうコンセプトのもと書かれたような薄っぺらさを感じてしまった。
ひねくれている、と言われれば返す言葉もない。
あと3つ残っているので、ちゃんと読みます。
5月20日(金)
短編集『10の奇妙な話』(ミック・ジャクソン/東京創元社)の始めの3つを読む。
不気味で不条理で妙な笑いを誘う。
何だか喉に引っかかった小骨みたいに心地よくない読後感。
そこがとてもいい。
3つの中では、1番め「ピアース姉妹」が特にいい。
事件が起きる前の、姉妹の日常の描写がおもしろかった。
事件起きなくてもいいと思った。
すべての話にデイヴィッド・ロバーツの絵が挿入されていて、これがあるのとないのとでは全然違うと思う。
ピアース姉妹の挿絵なんて、ムーミンの本文に対するムーミンの絵くらい切り離し不可だ。
短編集『10の奇妙な話』(ミック・ジャクソン/東京創元社)の始めの3つを読む。
不気味で不条理で妙な笑いを誘う。
何だか喉に引っかかった小骨みたいに心地よくない読後感。
そこがとてもいい。
3つの中では、1番め「ピアース姉妹」が特にいい。
事件が起きる前の、姉妹の日常の描写がおもしろかった。
事件起きなくてもいいと思った。
すべての話にデイヴィッド・ロバーツの絵が挿入されていて、これがあるのとないのとでは全然違うと思う。
ピアース姉妹の挿絵なんて、ムーミンの本文に対するムーミンの絵くらい切り離し不可だ。
3月31日(木)
『現代インド短編小説集』(岳真也 編訳/彩流社)を読み終わる。
貧困と身分制度と宗教と、そしてあらゆる種類の笑い。
民話っぽいものから現代ものまで、思ってたよりずっとおもしろかった。満足。
短編それぞれが違う訳者で、ひとつだけ、「ジレンマ」という作品の「話しずらい」とか「飛んでもない」っていう表記が引っかかった。
翻訳って、外国語の力と同じくらい、いや、場合によってはそれ以上に日本語の能力が大事なんだね~、と思ったところで就寝。
『現代インド短編小説集』(岳真也 編訳/彩流社)を読み終わる。
貧困と身分制度と宗教と、そしてあらゆる種類の笑い。
民話っぽいものから現代ものまで、思ってたよりずっとおもしろかった。満足。
短編それぞれが違う訳者で、ひとつだけ、「ジレンマ」という作品の「話しずらい」とか「飛んでもない」っていう表記が引っかかった。
翻訳って、外国語の力と同じくらい、いや、場合によってはそれ以上に日本語の能力が大事なんだね~、と思ったところで就寝。
3月28日(月)
『現代インド短編小説集』(岳真也 編訳/彩流社)の2つめ「落石事故」、3つめ「郵便局員」を読みながら、文学ってのは特殊を書いて普遍を描くもんだということを思い出す。
ふたつとも、60年前の日本を舞台にしても全然違和感ない気がする。
あ、でもラストが違うかな、「そこか!」っていう。
ひとつお願いするなら、話に出てくるお金について、それがどのくらいの価値なのかという註がほしい。
この短編集、期待以上におもしろい。
満足しつつ就寝。
『現代インド短編小説集』(岳真也 編訳/彩流社)の2つめ「落石事故」、3つめ「郵便局員」を読みながら、文学ってのは特殊を書いて普遍を描くもんだということを思い出す。
ふたつとも、60年前の日本を舞台にしても全然違和感ない気がする。
あ、でもラストが違うかな、「そこか!」っていう。
ひとつお願いするなら、話に出てくるお金について、それがどのくらいの価値なのかという註がほしい。
この短編集、期待以上におもしろい。
満足しつつ就寝。
3月27日(日)
珍しくあれこれ用事が重なって、一度も本を手にしないまま夜になった。
寝る前、『現代インド短編小説集』(岳真也 編訳/彩流社)のひとつめ「井戸」を読む。
ある男が井戸を飛び越すというスポーツ(?)を思いつき、その飛びっぷりが周囲の拍手喝采を浴びて全国的な有名人になる。
そんなある日、男は別の男からの挑戦を受ける。
対決を控えた男は練習のため、森にある井戸を訪れた。
すると、そこに自殺志願の見知らぬ男がいて……という話。
すごく深い寓話のようでもあるし、コントとして上演してもおもしろそうだし、落語みたいと言えばそんなかんじ。
いろんな作家の短編が収められたアンソロジーなので、他のも楽しみ。
珍しくあれこれ用事が重なって、一度も本を手にしないまま夜になった。
寝る前、『現代インド短編小説集』(岳真也 編訳/彩流社)のひとつめ「井戸」を読む。
ある男が井戸を飛び越すというスポーツ(?)を思いつき、その飛びっぷりが周囲の拍手喝采を浴びて全国的な有名人になる。
そんなある日、男は別の男からの挑戦を受ける。
対決を控えた男は練習のため、森にある井戸を訪れた。
すると、そこに自殺志願の見知らぬ男がいて……という話。
すごく深い寓話のようでもあるし、コントとして上演してもおもしろそうだし、落語みたいと言えばそんなかんじ。
いろんな作家の短編が収められたアンソロジーなので、他のも楽しみ。
2月13日(土)
よく、テレビのバラエティで、高い鉄棒にどれだけぶらさがっていられるか競うやつがある。
必ず落ちることは決まっているが、スタート時点では余裕しゃくしゃく、だんだん苦しそうになってバタバタしたり苦悶しだしたりして、あー!もうダメだ!って指が滑る瞬間、奇妙な快感がある。
落ちていく人を見ながら、変な開放感を感じる。
シーラッハの短編の面白さってそれに似ているなあと『カールの降誕祭』(フェルディナント・フォン・シーラッハ/東京創元社)を読みながら思う。
ひとつめの「パン屋の主人」も、「サイボルト」も、表題作のカールも、日常という鉄棒にかろうじてぶら下がりながら、あるラインを越えるとダムが決壊するみたいに何もかもがダメになる。
長編『コリーニ事件』『禁忌』もいいけど、シーラッハはやっぱり短編だと思う。
あらすじかと思うほど簡潔な文章と、そこから生まれる皮膚が切れるようなスピード感がたまらない。
それにしても、わたしはなんでこんなにシーラッハの短編が好きなのか。
今のゆる~くて取り立てて不満のない毎日の底がフッと抜けて、日常から滑り落ちる不安があるのかもしれない。あるいは期待?
作品のバッドエンドでそこらへんの疑似体験をしているのか。
そういえば、絶叫マシンは自殺の疑似体験であるといってた人がいたから、そういうことかもしれない。
装画や挿し絵は、『犯罪』『罪悪』の表紙と同じ人だ。
ずっとシーラッハと同じドイツの画家の作品だと思っていたが、タダジュンという日本の人だった。
あまりにも雰囲気がぴったりで気づかなかった。
よく、テレビのバラエティで、高い鉄棒にどれだけぶらさがっていられるか競うやつがある。
必ず落ちることは決まっているが、スタート時点では余裕しゃくしゃく、だんだん苦しそうになってバタバタしたり苦悶しだしたりして、あー!もうダメだ!って指が滑る瞬間、奇妙な快感がある。
落ちていく人を見ながら、変な開放感を感じる。
シーラッハの短編の面白さってそれに似ているなあと『カールの降誕祭』(フェルディナント・フォン・シーラッハ/東京創元社)を読みながら思う。
ひとつめの「パン屋の主人」も、「サイボルト」も、表題作のカールも、日常という鉄棒にかろうじてぶら下がりながら、あるラインを越えるとダムが決壊するみたいに何もかもがダメになる。
長編『コリーニ事件』『禁忌』もいいけど、シーラッハはやっぱり短編だと思う。
あらすじかと思うほど簡潔な文章と、そこから生まれる皮膚が切れるようなスピード感がたまらない。
それにしても、わたしはなんでこんなにシーラッハの短編が好きなのか。
今のゆる~くて取り立てて不満のない毎日の底がフッと抜けて、日常から滑り落ちる不安があるのかもしれない。あるいは期待?
作品のバッドエンドでそこらへんの疑似体験をしているのか。
そういえば、絶叫マシンは自殺の疑似体験であるといってた人がいたから、そういうことかもしれない。
装画や挿し絵は、『犯罪』『罪悪』の表紙と同じ人だ。
ずっとシーラッハと同じドイツの画家の作品だと思っていたが、タダジュンという日本の人だった。
あまりにも雰囲気がぴったりで気づかなかった。
1月24日(日)
『謎のクィン氏』(アガサ・クリスティー/ハヤカワ文庫)の3つめ「道化荘奇聞」を読む。
これ、名探偵クィン氏が事件の謎を解く!わけではなく、カウンセリング方式?というか、3ヵ月前に起きた事件を傍観者サースウェイト氏が語り、クィン氏が聞き役をつとめながら真相へと導いていく、というパターンだ。
クィン氏がサタースウェイトに向かって「わたしはただきっかけをつくるだけ」だと言うとそこにすごい稲妻が光る、という場面があるが、正にそれ。
クィン/サタースウェイトは稲妻/稲 の関係なのかも。
昔の人は田んぼに稲妻の光が刺さることで穂が実ると考えた(だから「稲妻」。「妻」は今の「夫」の意)っていうから。
確かに、この人と話すといろんなことに気づくなあ、という人はいるな、相性の問題もあるな、とか考えながら就寝。
『謎のクィン氏』(アガサ・クリスティー/ハヤカワ文庫)の3つめ「道化荘奇聞」を読む。
これ、名探偵クィン氏が事件の謎を解く!わけではなく、カウンセリング方式?というか、3ヵ月前に起きた事件を傍観者サースウェイト氏が語り、クィン氏が聞き役をつとめながら真相へと導いていく、というパターンだ。
クィン氏がサタースウェイトに向かって「わたしはただきっかけをつくるだけ」だと言うとそこにすごい稲妻が光る、という場面があるが、正にそれ。
クィン/サタースウェイトは稲妻/稲 の関係なのかも。
昔の人は田んぼに稲妻の光が刺さることで穂が実ると考えた(だから「稲妻」。「妻」は今の「夫」の意)っていうから。
確かに、この人と話すといろんなことに気づくなあ、という人はいるな、相性の問題もあるな、とか考えながら就寝。
1月15日(金)
夕方って、燃料が切れるっていうか、おなかがすくし眠くなるし、みんなどうやって乗り切ってるんですかね。
初場所 毎日楽しみでいいんだけど、ちょうど上位戦あたりになると睡魔に勝てないのが目下の悩み。
昼間、短編集ハヤカワ文庫)の「クィン氏登場」を読んだ。
ある男が自殺した10年後、当時その場に居合わせた人たちが集まったところに現れたクィン氏がするするっと謎を解く話。
ヒントは非常に堂々と示され謎解きは鮮やかで、爽快感がたまらない。
絡まったネックレスを辛抱してほどいたときの快感を味わえた。
唯一の難は、ただでさえ外国人の名前が覚えられないのに、短編だから「ええと、リチャード卿って誰だっけ」とかいってるうちに終わってしまうことだ。
夕方って、燃料が切れるっていうか、おなかがすくし眠くなるし、みんなどうやって乗り切ってるんですかね。
初場所 毎日楽しみでいいんだけど、ちょうど上位戦あたりになると睡魔に勝てないのが目下の悩み。
昼間、短編集ハヤカワ文庫)の「クィン氏登場」を読んだ。
ある男が自殺した10年後、当時その場に居合わせた人たちが集まったところに現れたクィン氏がするするっと謎を解く話。
ヒントは非常に堂々と示され謎解きは鮮やかで、爽快感がたまらない。
絡まったネックレスを辛抱してほどいたときの快感を味わえた。
唯一の難は、ただでさえ外国人の名前が覚えられないのに、短編だから「ええと、リチャード卿って誰だっけ」とかいってるうちに終わってしまうことだ。
《☆☆ 羽田詩津子/訳 7/7読了 ハヤカワ文庫 2015年刊 【翻訳小説 エルキュール・ポアロ 】 Agatha Christie(1890~1976)》
なんかこう、事件が箱庭っぽいというか、用意された“推理クイズ”をポアロが解きました、みたいなお手盛り感が否めない。
長いシリーズものだから、たまにはこういうのがあってもしかたないのか。
事件に関わる人物が比較的若いってところにもコクが足りないと感じる原因があるのかもしれません。
わかんないけど。
/「ポアロとグリーンショアの阿房宮」アガサ・クリスティ
なんかこう、事件が箱庭っぽいというか、用意された“推理クイズ”をポアロが解きました、みたいなお手盛り感が否めない。
長いシリーズものだから、たまにはこういうのがあってもしかたないのか。
事件に関わる人物が比較的若いってところにもコクが足りないと感じる原因があるのかもしれません。
わかんないけど。
/「ポアロとグリーンショアの阿房宮」アガサ・クリスティ
《☆☆☆ 10/17読了 沼野恭子/訳 ウラジーミル・リュバロフ/絵 新潮社 2015年刊 【短編集 ロシア】 Людмила Улицкая(1943~)》
収録作品:キャベツの奇跡/蝋でできたカモ/つぶやきおじいさん/釘/幸運なできごと/折り紙の勝利
子供のころのことをよく覚えている人とそうじゃない人がいますよね。
わたしは完全に後者なんですが、具体的なできごとがすっかり消えていても、そのときの不安・恐怖・悲しみ・ドキドキだけはずっと底の方に残っていて、これを読みながら何度もフラッシュバックを起こしました。
行ったこともないソビエトの冬の匂い、見たこともない料理の味、大柄なおばあさんの小言、怖いおじいさん、そんな全てがなぜだか懐かしい。
リュバロフの絵の効果も大きいです。
6編全部よかったけど、特に好きなのは「釘」です。
おじいさんという生き物は口が重く、愛想がなく、そして不器用で、ごつごつしてるくせにやわらかい。
/「子供時代」リュドミラ・ウリツカヤ
収録作品:キャベツの奇跡/蝋でできたカモ/つぶやきおじいさん/釘/幸運なできごと/折り紙の勝利
子供のころのことをよく覚えている人とそうじゃない人がいますよね。
わたしは完全に後者なんですが、具体的なできごとがすっかり消えていても、そのときの不安・恐怖・悲しみ・ドキドキだけはずっと底の方に残っていて、これを読みながら何度もフラッシュバックを起こしました。
行ったこともないソビエトの冬の匂い、見たこともない料理の味、大柄なおばあさんの小言、怖いおじいさん、そんな全てがなぜだか懐かしい。
リュバロフの絵の効果も大きいです。
6編全部よかったけど、特に好きなのは「釘」です。
おじいさんという生き物は口が重く、愛想がなく、そして不器用で、ごつごつしてるくせにやわらかい。
/「子供時代」リュドミラ・ウリツカヤ
《☆☆☆ 3/5読了 羽田詩津子/訳 ハヤカワ文庫(クリスティー文庫3) 【翻訳小説 イギリス】 Agatha Christie(1890~1976)》
海外のドラマやミステリー小説がおもしろいのは、自分の日常との距離と、それでも感じるリアリティとのバランスが絶妙だからだと思います。
「わが友よ、わたしは考えているのではなく、知っているのです」(329p)
灰色の脳細胞を駆使して真実をつきとめるポアロものの中でも評価が高い、一方で、その仕掛けがアンフェアなんではないか、という意見もあるそうで、そこに惹かれて読んでみました。
結論から言えば、読後、アンフェアなんでは?という感想は全く持ちませんでした。
発表時(1926年)ならともかく、90年も経った今なら不公正だと感じる読者の方が少ないんじゃないかと思うんだけど、どうでしょう。
個人的にはむしろ、“この人なら本当のことを隠せる、この人が犯人だったらおもしろいな”という人が犯人だったので、とてもしっくりときました。
そんなトリックより何より、真相が分かった後、終わり方の苦い味がよかった。
このラストの苦味だけで星3つ!です。
子供のころは断然クイーンやブラウン神父派だったのですが、どっぷり中年になるにつれてクリスティ好きになってきました。
/「アクロイド殺し」アガサ・クリスティー
海外のドラマやミステリー小説がおもしろいのは、自分の日常との距離と、それでも感じるリアリティとのバランスが絶妙だからだと思います。
「わが友よ、わたしは考えているのではなく、知っているのです」(329p)
灰色の脳細胞を駆使して真実をつきとめるポアロものの中でも評価が高い、一方で、その仕掛けがアンフェアなんではないか、という意見もあるそうで、そこに惹かれて読んでみました。
結論から言えば、読後、アンフェアなんでは?という感想は全く持ちませんでした。
発表時(1926年)ならともかく、90年も経った今なら不公正だと感じる読者の方が少ないんじゃないかと思うんだけど、どうでしょう。
個人的にはむしろ、“この人なら本当のことを隠せる、この人が犯人だったらおもしろいな”という人が犯人だったので、とてもしっくりときました。
そんなトリックより何より、真相が分かった後、終わり方の苦い味がよかった。
このラストの苦味だけで星3つ!です。
子供のころは断然クイーンやブラウン神父派だったのですが、どっぷり中年になるにつれてクリスティ好きになってきました。
/「アクロイド殺し」アガサ・クリスティー