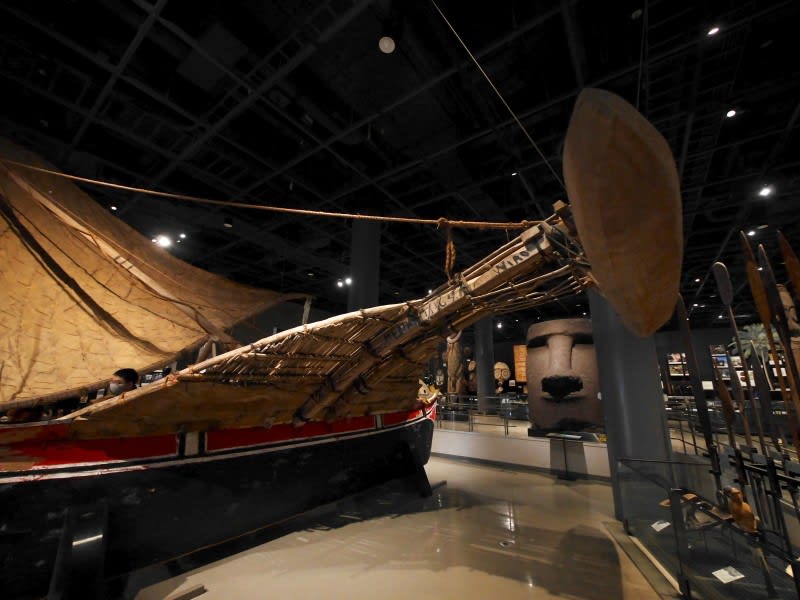雑木林や竹林、池や散策路に、体育館やグランドがある、ちょっと大きな公園でのクモの観察会に参加した。

市の生息調査標本用に採集されたもの・・
冬なのにみつかるのかなぁ・・の心配は無用だった。どうやって見つけるのかなぁ・・も愚問だった。
「さぁ、いきましょうか・・」と、軽いトーンで始まり、少し歩くだけで、次から次へとクモが見つかる。

笹の葉の表面を船形に凹ませた網の中に、ほぼ同色の少し大きなクモを見つけた。

逆光は必須だ・・・

アオオニグモ・・・クモハンドブックの表紙を飾る奴だ!!
初心者の私の為に、一つ一つ名前を教えて頂け、写真を撮らせてくれた。
数時間の観察から、名前を控えたものだけで20種を超えた。
季節柄、亜成体や幼体が多く、その識別を控えなかったので、帰宅後に図鑑やwebで検索すると、写真が合わないものが多数・・・
先生の話は、しっかりと書き留めておくのだった・・

ユノハマサラグモ・・
佐賀県の湯ノ原にちなんでつけた名前の記載違いで「ラ」が「マ」になってしまったと教わる。

カニグモの仲間・・・
横に広いのが、カニグモで、広くないのはエビグモとのこと。
カニグモはカニらしくも見えたけど、大量に見つかったアサヒエビグモをはじめ、図鑑のエビグモは、どれもエビには見えなかった。

ネコハグモと卵のう・・・コンクリート壁面に大量にいた。
こいつの名も、猫とどう繋がっているのか連想できなかった。

ヒラタグモ・・こちらも、同じコンクリート壁面に大量にいた。
「ヒラタ」の由来も謎だ・・

ネコハグモとヒラタグモの網は、コンクリートやガラスの壁面にたくさんあった・・

スネグロオチバヒメグモ・・脛が黒くて、ずばり落ち葉の中にいた!!

アシヨレグモ・・・
名前を聞いただけで、よく見ずに「あっ、本当だ、足がよれてる。」と言ってしまったら、
「えっ、滅多にわからないけど・・・わっ、よくわかる。」と、言われて、慌てて写真に撮った。
確かに第1脚がよれているように見える。

ユウレイグモ・・
それにしても足が長いなぁ・・何のメリットがあるのか知りたい・・

センショウグモ♂・・・触肢が、カニやエビの眼柄(がんぺい)に似てないか・・?
クモを食べるクモだそうで、飼うことができ、餌に与えるクモを間違えると、逆に食べられてしまうらしい。
生きたクモしか食べないけど、毎日バクバク食べたりしないから、そんなに大変じゃないのだとか・・

竹林内に多数張られていた、サガオニグモ幼体の網・・・

網を触ったら、横に逃げてしまった。。
名前のサガが「佐賀県」に由来するのか、聞き逃した。それにしても先生方は、貴重な時間の中で、こんなバカな質問にも、一つ一つ、丁寧かつ的確に答えて下さった。

太い竹の根元近く、日が当たる場所に、コガネグモ幼体がいた・・・
コガネグモの幼体の識別は、困難らしい。

まだ生きていたジョロウグモ♀・・・腹部の大きさから、交尾できずに終わってしまったのでは?とのこと。

笹の葉の裏側・・・水滴がキラキラ光っていたので、「クモの網に水滴がついている」と先生に言ったら、「水滴だけですよ・・」と言われてしまった。
なんで葡萄の房のように、水滴がつくんだ・・? この日一番の謎だった。。

ヤガタアリグモ・・
名前とは関係ないけど、腹が赤いのが特徴で、名古屋市で見つかるアリグモは、ほとんどこの種だとか・・

ヤチグモの仲間♂・・・この日の最大種。朽ち木の中から出てきた。

背面の模様に惹かれた・・

ヤマトゴミグモ・・?

ゴミグモの仲間の体の形は、面白いなぁと思う。

先生方は、クモの他は、ほとんどスルー・・・イシムカデの仲間か?

ハヤシワラジムシの仲間か・・?、こんな色合いのは初めて見た。

サシガメの仲間ではないか? とのこと・・・ナナフシに似ているような気もする。

今回一番の謎の虫・・・足が6本だから昆虫だと思うけど、ヨコバイ等の幼体か? 何なんだろう・・・?
とまぁ、こんな風に、書き出しただけでも、実に充実した時間だった。
来月の発表会の見学もお誘いいただけたので、それまでにクモの基本的な知識を覚えたいぞ・・・
ちなみに前日は、駅伝大会の観戦に20km歩いたけど・・この日の観察会は3時間で1kmも歩かなかった。

レベルの高い競技会に挑戦する知り合いの姿は、有名な選手よりもかっこよく感じた。
以上、本日もご覧いただき、ありがとうございました。