【グローバリズムは人類社会を破壊する。①】☜左クリックで開く
【グローバリズムは人類社会を破壊する。➁】☜左クリックで開く
世界的にみた資源を巡る諸問題
世界資源の賦存・需給の基本構造
第一の特徴
世界資源の賦存・需給の基本構造として、地球資源の賦存および生産の偏在性が著しい。☜化石燃料や鉱物資源埋蔵量や先端技術を以て其れ等を加工生産する生産国が偏在して存在している。
第二の特徴
資源保有国と雖も、其の保有資源の種類に偏在がある。持てる国とも雖も、自給自足可能な国は存在し無い。北側先進国のなかのもてる国々、例えば米露についても資源が豊富ではあるが、消費が供給を上回り、全体としては輸入国となっている。
第三の特徴
世界の資源の需要・消費も亦偏在しており、然も資源賦存に恵まれ無い日本や西欧の先進国が、米・Д・中共と共に、主要消費国と成っている事実である。☜貿易によって初めて可能と成ることは言うまでも無い。
第四の特徴
多くの主要な資源の場合、欧米先進国を母国とする巨大な国際資源企業乃至国際大資本が介在しており、資源保有国に代わって、資源の開発・生産・加工・輸送・販売等の担い手と成って来た事実がある。☜先進諸国の此等のメジャー企業に対して、国際的資本形成で大きく遅れを取って居た資源保有国も、資源ナショナリズムを高揚させ、国際大資本への挑戦を1960年代後半以降大胆に展開して来たが、メジャーの持つ技術力・経営力・資本力・販売力・輸送力等は尚侮り難かった。然し、今日、資源保有国の国々が結束することで、所謂メジャーも此の力を無視出来無い状況に追い込まれて居る。
資源枯渇は差し迫っているのか
人類が、高度成長が常態であり、永遠に持続するといった考え方、および使い捨て・浪費は美徳であるといった価値観や生活態度を根本的に再検討し、地球資源は有限であることを前提に、資源の節約・有効利用こそを美徳として、自然との調和・バランスに努め、真の生きがいなり福祉を追求していくならば、地球資源の物理的な枯渇は差し迫った問題ではなくなり、地球資源余力は今後もなお十分に存在すると、以下の理由から、結論を下せるであろう。
第一に、①通常の論議の対象となる資源埋蔵量は確認埋蔵量⇒現在の技術と価格とを所与として、経済的に引き合って採取可能な資源量に過ぎ無い。➁再生産不可能な鉱物資源☜地球の物理的全資源量と比べて、確認埋蔵量は、何百万分の1から何十億分の1といったオーダーの量⇒今後の技術革新や価格の上昇によって、膨大な埋蔵量の追加が生ずる可能性が大。
第二に、此れ迄、可採年数が大幅に減少した場合、探鉱投資・技術開発等が為されて、可採年数は元の水準に回復して来て居る。
第三に、石油等の化石燃料に関しては、最も枯渇が差し迫っているといわれる石油を観ても、可採年数は現在35年弱であり、究極可採埋蔵量は100年前後、地球資源量は300年近く在るとされている。化石燃料全体の可採年数は、尚最低数百年以上は存在しており、更に既知の原子力や今後の高速増殖炉、核融合、および新・再生エネルギーを含めて考えれば、潜在的には粗無限ともいえる資源余力が存在して居る。☜此れも、先ず、現在の様に現在のような資本主義経済下での企業論理からの効率化の持つ障碍を取り除くことが必要と成る。企業が刹那的な利益で盛衰を決定する経済の仕組みは最早陳腐化した時代に入ったのだ。
第四に、資源の再循環利用(リサイクリング)や廃棄物の再生利用の可能性が大⇒新規の処女資源必要量は減少。枯渇の問題⇒資源価格が上昇し、節約・有効利用は促進、資源間の代替も加速、希少な資源に替わってた、より豊富な資源が利用への志向⇒特定資源の不足は軽減・除去。☜現在の資本主義的観点からは大変非効率に看えるが、極論、非効率こそ人間の尊厳を取り戻せるのでは?
第五に、再生産可能な食糧や農林産原材料について、その物理的限界が一部で重大視されている。☜農業経済学者達は、耕地面積の拡大に依る今後の食糧増産では無く、寧ろ既耕地に於ける生産性の向上、特に東側(北側の生産性の約半分)と南側(北側の約3分の1)とに於ける生産性の向上を重視。北側の既存の技術や方法を、南や東へ移転し適用⇒増産の大きな可能性。☜地球環境や動植物の種の保存からも此れ以上の自然環境の破壊は避けるべきで、人口少減も急務として併せて考えるべき。
第六に、食糧の場合、供給面及び需要・消費面が決定的な重要性を持つ。☜欧米や日本等先進諸国の食れょう事情は粗満足されているものだが、世界の多くの国々には未だに飢餓に苦しむ国も少なく無く、食料需給の不均衡は早急に解決すべき課題である。
第七に、資源の生産コストや価格の長期にわたる動向を分析してみても、短期的には激しい乱高下が生じているが、絶対的及び相対的なコストや価格は、決して上昇して居ず、何方かといえば、低下傾向にある事実が重要。少なくとも、経済学的に判断する限り、資源の物理的枯渇が進んでいると結論することは不可能。[深海博明]☜此の結論付けには大いに異論があるばかりか、此れ迄、筆者が言って来たことと大いに矛盾する。何故ならば、国や地域によって、食料需給に大きな格差があることを無視した発言と成って居る。
※ 次の「国際政治経済関係における資源問題」も、当稿の「世界的にみた資源を巡る諸問題」の課題の一つだが、【グローバリズムは人類社会を破壊する。】の一連のシリーズの重要論稿の一つと成るので次回に譲ることとする。
続 く










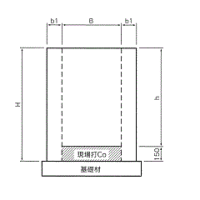









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます