【グローバリズムは人類社会を破壊する。①】☜左クリックで開く
【グローバリズムは人類社会を破壊する。➁】☜左クリックで開く
【グローバリズムは人類社会を破壊する。③】☜左クリックで開く
国際政治経済関係における資源問題[深海博明]
・・・、地球資源枯渇が差し迫った問題でないとすれば、資源問題に関しては手放しの楽観論をもつことができ、資源危機はまったくの虚構であるといえるのであろうか。現段階ないし近い将来において問題や危機が生ずるとすれば、それは、地球資源の物理的な賦存や潜在的可能性を、実際の国際政治経済関係および国内政治経済関係の舞台において現実化し、資源の開発・供給を確保していくことが、かならずしも保証されていないことに主として根ざしている。世界全体さらに各地域・各国・各人の必要に応じて、資源の開発・供給・輸送・分配・利用・消費等が、以下の理由から、円滑に行われない可能性が強く存在している。☜此処での資源の対象は、主に鉱物資源や化石燃料資源等地下埋蔵資源に重点を置かれたものと感じられ、再生天然自然資源、詰まり、「森林や原野、或いは海洋資源等についての差し迫った危機については外されている」と感じざるを得ない。除外された再生天然自然資源については、既に限界に達して居る。此の限界は、「地球のキャパを超えて膨れ上がった人口抑制、乃至人口少減を如何に為すべきか」という解決法に集中すべきである。
第一に、世界資源問題発生の根本的要因は、経済空間と政治空間(統治可能空間)、すなわち経済の実態と政治やその枠組みとの間の矛盾・ギャップが、現段階で一つの極限に到達していることに求められるであろう。
経済の実態面とりわけ資源取引の面では、経済活動は国境を越え、まさに世界的に展開している。世界資源最富裕国といえども、国際交流を完全に断っては、円滑な経済の運営や国民生活の維持が不可能な状況下にある。それに対し、政治面や制度は、依然として基本的に国民国家nation-stateという狭い枠内にとどまっている。
最近高揚している資源ナショナリズムや狭い国益追求による国際的な資源獲得抗争は、過去の植民地支配や従属もその一因となっているが、根本的にはこの矛盾・ギャップに根ざしており、国民国家という政治・枠組みからの、経済の実態面とくに資源問題の国際化の進展に対する反発・反撃であると、みなすこともできるであろう。☜雅に、此処迄の説明でグローバライズの至向への根源的考え方が見えるのだ。此処で説明した考え方は、経済的福利を確保する為には、“安倍晋三「最早、国籍も国境も拘る時代で無い」”ということに成るが、では、安倍晋三の内閣総理大臣の地位は、「日本国首相」では無く、「地球国家の日本“地域”の代表」に過ぎ無い。政治の役割は「人心(内心の自由)」に及ばす「主として経済的福利の確保」にあり、国家は「国民の福利の維持向上にある」という大原則は、ある意味「ナショナリズム」無しには実現され無い。
近い将来において、経済の実態に適合する形で、国民国家が変容し世界国家形成の方向に向かうと安易に期待することは不可能であるし、逆に、経済の実態を国民国家の枠内に押し込み、国際交流を完全に断って、自給自足的な経済運営を目ざすこともできない。したがって、この原因に基づく資源問題発生の可能性は将来も根強く存在しており、漸進的にではあっても、双方が歩み寄り調整しあう方向での解消の努力がなされていかねばならない。☜政治の役割が「主として経済的福利の確保」にあるとするのが真とするならば、著者の此処での説明は上節と矛盾し、言い訳囂しい。
第二に、北側の先進国においては、ある程度福祉国家が現実のものとなり、最低生活の保障や極端な不平等是正といった形での、公正や正義の目標が達成されているが、これを国際的にも拡大し、公正・正義の目標の実現を目ざす動きが、南北問題の解決といった形で高まりつつある。とくに南北間の所得水準・資源消費水準の大きな格差の是正や、資源の生産と消費との格差是正(南側で生産された資源の多くは北側に運ばれてそこで加工・消費されている)を志向する要求が強まり、北側が自らの必要なだけ資源を獲得・消費してよいのかどうかが、再検討されつつある。☜現実には、国家間の不平等是正への努力が、各国国内での格差を著しく拡大させている。如何も、全人類的「資源の有効活用」という美しい「標語」を奇貨とし、怪しいものを感じる。
第三に、主要資源において、南側を中心とする保有国側が手を結んで、輸出国機構や生産国同盟を形成し、生産・供給・輸出の調整や価格の維持・引上げを図る動きが、1960年代後半から強まってきている。二つの石油危機の一因となったOPEC(オペック)(石油輸出国機構)やOAPEC(オアペック)(アラブ石油輸出国機構)の石油戦略は、その代表的なしかも輝かしい成功を収めた事例として、注目されてきた。
しかし1980年代に入ると、原油価格の大幅な引上げは、有効利用・節約や代替エネルギーへの転換やOPEC以外の原油生産の増大を生じさせ、一転して価格は低下・低迷し、供給過剰に苦しむ事態が生じている。市場・需給の条件を無視した行動は、経済が基本的に具備している調整・転換能力によって、手厳しい反撃を受けることが明白となり、中・長期的には、こうした資源カルテルといわれる輸出国機構等に起因する資源危機は、むしろ重視されなくなっている。☜難癖を付ける訳では無いが、自然エネルキー等も、詐欺師の様な拝金主義の曲者に依って、例えば大規模ソーラー設置開発で森林破壊によって人為的に土砂崩壊等の危険を誘引し、再生天然自然資源を破壊してる現状を政治屋は何故か無視してる。
第四に、各国が経済の調整・受容能力をどれだけもっているのかが決定的に重要である。北側で達成されている農業生産性を南側で実現できれば食糧問題は解決される可能性を指摘したが、南側でそれを実現するためには、土地改革、農民の教育や技術指導、資金等の供与、流通制度の改変などの抜本的な息の長い政策措置を実施していくことが不可欠であり、これらなしには潜在的可能性にとどまらざるをえない。☜此れについても、前述で筆者も言われて居たが、アマゾン開発等で行われて居る大規模な自然破壊に依る開発は厳に慎むべきであり、農業生産性の向上は、人口問題絡めて農地拡大を可能な限り抑えて為されるべきである。
第五に、「油断」や「食糧輸入ゼロの日」といった、戦争・紛争の勃発やゲリラ行動や事故等により、生産の減少や輸送・積出し設備の破壊や海上等の輸送ルートの遮断といった形で、日本への資源供給が、一時的ではあるが、突然しかもかなりの期間にわたって途絶したり、大幅に削減されたりする可能性も十分にあろう。☜当面、問題なのは破落戸国家中共や北朝鮮を国際社会は全人類の敵として徹底して排除すべきである。然し、此れを邪魔して居るのが、全人類的資源の最適配分を奇貨としてグローバライズを利用する悪徳国際無国籍企業と其の傀儡の走である小悪党の政治屋共である。
続 く










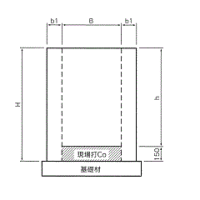









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます