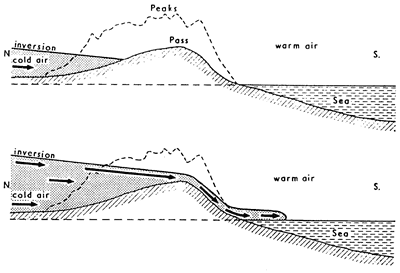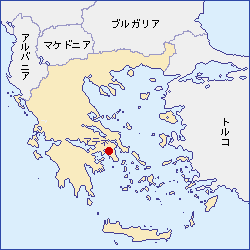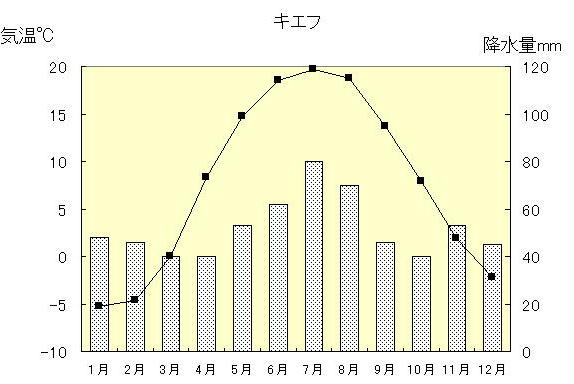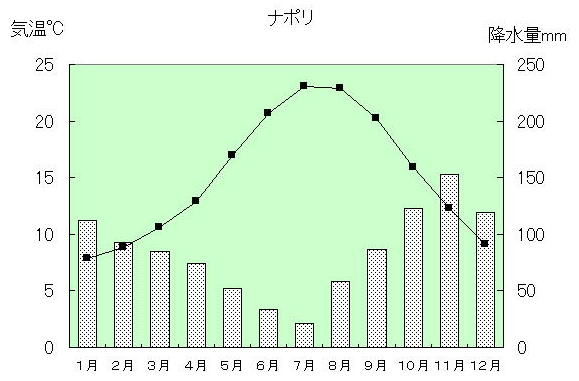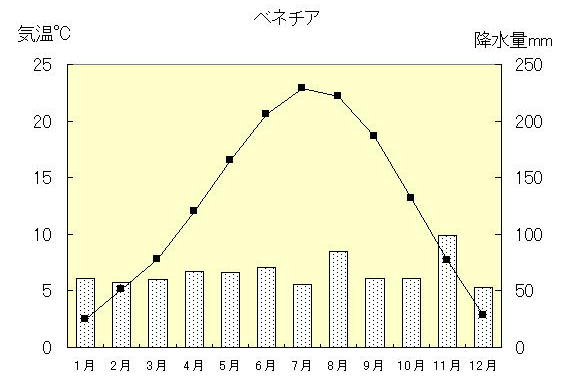聖地サンマリノ
4世紀、ローマ皇帝がキリスト教徒を厳しく迫害した。この時、ローマの敬虔なキリスト教徒マリーノが、現在のサンマリノにキリスト教徒を集め、共同体を建設した。サンマリノはこのような建国神話のある、キリスト教カトリックの聖地である。この建国神話に登場するマリーノの職業は石工である。
1631年にローマ法王により、サンマリノは独立的地位を認められた。1862年にイタリアとの友好善隣条約を結び、近代国家としての主権と独立を確立した。イタリアに軍事・外交をまかせている。また、イタリアとサンマリノとの間では、国境審査はないことになっているが、入国記念スタンプが有料で押される。

中立国サンマリノ
サンマリノはイタリアにまわりを囲まれているにもかかわらず、第1次、第2次世界大戦でも、中立を維持した。第2次大戦中は、ナチスドイツがイタリア半島で戦った数週間だけ戦場になったが、ナチスも連合軍もすぐに退去した。
積極的にイタリアのためには戦わず、大戦中は中立を維持したのであった。
1992年に国連に加盟した。
観光立国サンマリノ
60k㎡の国土に3万人が住む。年間観光客数は300万人である。通貨はイタリアのユーロが流通している。しかし、サンマリノは2ユーロ硬貨の片面に独自デザインした通貨を製造発行している。その発行数が少ないので通貨としては流通せず、マニアと観光客に高値で売られている。
また、切手は高額切手も少数ずつ販売し、次々とデザインを変更して、観光客の土産としている。
聖地サンマリノを訪れる観光客300万人が、通貨と切手を公式価格の何倍もの高値で購入し、サンマリノの財政を潤している。

サンマリノはEUには加盟していないが、通貨はイタリアのユーロ通貨を使う。サンマリノでつくられる2ユーロ通貨は、19世紀のイタリア統一の英雄ガルバルディが描かれている。日本円で300円程度なのだが、発行数が少ない記念硬貨であり、額面の100倍3万円が取引相場になっている。このような通貨や切手の高値誘導政策は、サンマリノの財政収入に大きな役割を果たしている。
4世紀、ローマ皇帝がキリスト教徒を厳しく迫害した。この時、ローマの敬虔なキリスト教徒マリーノが、現在のサンマリノにキリスト教徒を集め、共同体を建設した。サンマリノはこのような建国神話のある、キリスト教カトリックの聖地である。この建国神話に登場するマリーノの職業は石工である。
1631年にローマ法王により、サンマリノは独立的地位を認められた。1862年にイタリアとの友好善隣条約を結び、近代国家としての主権と独立を確立した。イタリアに軍事・外交をまかせている。また、イタリアとサンマリノとの間では、国境審査はないことになっているが、入国記念スタンプが有料で押される。

中立国サンマリノ
サンマリノはイタリアにまわりを囲まれているにもかかわらず、第1次、第2次世界大戦でも、中立を維持した。第2次大戦中は、ナチスドイツがイタリア半島で戦った数週間だけ戦場になったが、ナチスも連合軍もすぐに退去した。
積極的にイタリアのためには戦わず、大戦中は中立を維持したのであった。
1992年に国連に加盟した。
観光立国サンマリノ
60k㎡の国土に3万人が住む。年間観光客数は300万人である。通貨はイタリアのユーロが流通している。しかし、サンマリノは2ユーロ硬貨の片面に独自デザインした通貨を製造発行している。その発行数が少ないので通貨としては流通せず、マニアと観光客に高値で売られている。
また、切手は高額切手も少数ずつ販売し、次々とデザインを変更して、観光客の土産としている。
聖地サンマリノを訪れる観光客300万人が、通貨と切手を公式価格の何倍もの高値で購入し、サンマリノの財政を潤している。

サンマリノはEUには加盟していないが、通貨はイタリアのユーロ通貨を使う。サンマリノでつくられる2ユーロ通貨は、19世紀のイタリア統一の英雄ガルバルディが描かれている。日本円で300円程度なのだが、発行数が少ない記念硬貨であり、額面の100倍3万円が取引相場になっている。このような通貨や切手の高値誘導政策は、サンマリノの財政収入に大きな役割を果たしている。