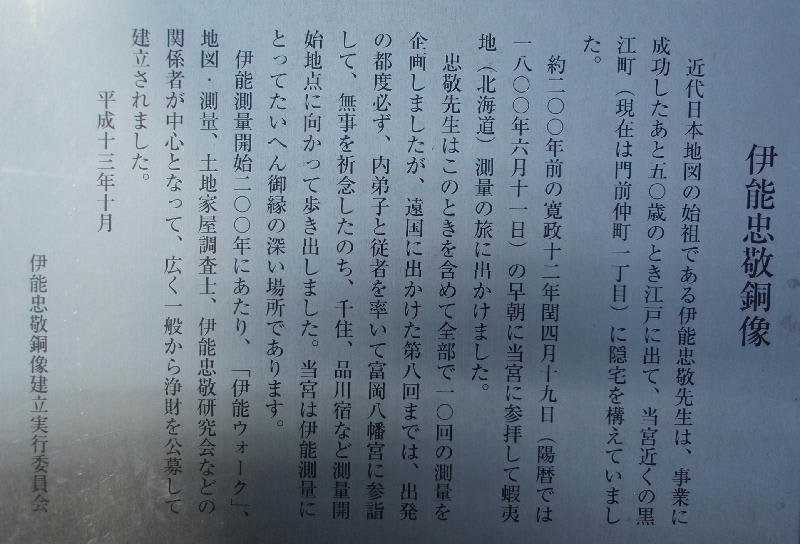三富新田(さんとめしんでん)
隆起扇状地は洪積台地の一つであり、水を得にくいので農業開発が遅れた。1694年に川越藩主柳沢吉保によって開発が始められた。上富新田91戸、中富40戸、下富49戸が入植した。集落は道路道沿いの路村、農地は平均5haの畑地ができた。

典型的新田集落(下富)
一戸当たり5haの畑作農地を開墾所有した。農業用水は深井戸を掘って得たが、大量の水を得ることができず、恒常的に水不足の問題があった。水不足に強い、茶・麦・野菜類が栽培された。

狭山茶
三富新田の茶は狭山茶(さやまちゃ)として、江戸で好まれた。茶は関東ロームの舞い上がるのを防ぐ役割も果たした。住居は路村であり、ケヤキ、ナラ、クヌギなどの屋敷林に囲まれていた。

屋敷森
下富新田集落の中には、ケヤキの巨木に囲まれている農家もある。ナラやクヌギなどもある。季節風を弱める、落葉を肥料にする、木材として利用する。巨木を保存するのか、伐採して苗木と植え替えるのか、景観保護の点から議論がなされている。

防霜ファン
茶栽培を本業とする農家では、茶の霜害を防ぐため、茶畑には防霜ファンを設置している。初夏の新茶取り入れの頃、霜がないように、茶園の冷気と上層に暖気を、ファンでかきまぜるものである。霜害を防ぐ効果が大きく、全国的に普及している。

隆起扇状地は洪積台地の一つであり、水を得にくいので農業開発が遅れた。1694年に川越藩主柳沢吉保によって開発が始められた。上富新田91戸、中富40戸、下富49戸が入植した。集落は道路道沿いの路村、農地は平均5haの畑地ができた。

典型的新田集落(下富)
一戸当たり5haの畑作農地を開墾所有した。農業用水は深井戸を掘って得たが、大量の水を得ることができず、恒常的に水不足の問題があった。水不足に強い、茶・麦・野菜類が栽培された。

狭山茶
三富新田の茶は狭山茶(さやまちゃ)として、江戸で好まれた。茶は関東ロームの舞い上がるのを防ぐ役割も果たした。住居は路村であり、ケヤキ、ナラ、クヌギなどの屋敷林に囲まれていた。

屋敷森
下富新田集落の中には、ケヤキの巨木に囲まれている農家もある。ナラやクヌギなどもある。季節風を弱める、落葉を肥料にする、木材として利用する。巨木を保存するのか、伐採して苗木と植え替えるのか、景観保護の点から議論がなされている。

防霜ファン
茶栽培を本業とする農家では、茶の霜害を防ぐため、茶畑には防霜ファンを設置している。初夏の新茶取り入れの頃、霜がないように、茶園の冷気と上層に暖気を、ファンでかきまぜるものである。霜害を防ぐ効果が大きく、全国的に普及している。