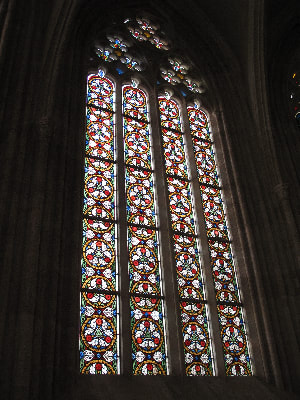6時半起床。いよいよ今日が実質的な最終日。悔い?は残すまい、と張り切って朝食を食べる。
地下鉄6号線と4号線を乗り継いで、世界遺産・シェーンブルン宮殿に向かう。昨日お世話になったツアーのガイドさんから、混雑を避けるなら朝早くかお昼頃がよい、と教えてもらっていたので。
アドバイスの通り、開館直前の宮殿前広場は人もまばらだった。そして朝日を受けたテレジア・イエローの宮殿の美しさに目を瞠る。空は雲ひとつなく、真っ青だ。
美しく整備された庭園も、数人が散歩をしているだけで、とてつもなく広く感じる。
シシィ・チケットを使ってグランド・ツアーを見学する。日本語の音声ガイドを聞きながら見学する。こちらの解説は割と簡素で、さっさと先に進める。後から次々にツアーの団体客に追い越されていくが、ほとんどがインペリアル・ツアーで帰ってしまうので、グランド・ツアーに進むと空いてきた。
こちらは内部の写真撮影が禁止されている。知らずに撮影している人は厳しく注意されていた。「ホーフブルク宮」に対してこちらは夏用の離宮という位置づけだが、各部屋の装飾や調度品はむしろこちらのほうが上、という感じがした。
フランツ・ヨーゼフ1世の書斎(執務室)もあり、そして彼が亡くなった部屋もここにある。もちろんエリザベートゆかりの化粧室も。6歳のモーツァルトがマリア・テレジアの前で演奏した鏡の間は、ミュージカル「モーツァルト!」のなかでも触れられる場所である。
大きな天井画の大ギャラリーは工事中で、半分ほどだけ見ることができる。
グランド・ツアーで見学できるのは、主としてマリア・テレジアにまつわる部屋の数々である。「漆の間」は西洋の文化と東洋の文化とが交差している面白い空間だ。ロココ調の可愛らしいデザインの部屋もある。豪華絢爛なベッドのあるフランツ・ヨーゼフ1世が誕生した部屋も見ることができた。
こちらはミュージアムショップも充実していて、定番のガイドブックや絵はがきの他に、ハプスブルク家の紋章が入ったインク瓶がカッコいいGペンのセットなんてものまで買ってしまった。見学コースを出るころには、入口には長い行列ができていた。
庭園に出る。お天気もいいことだし、歩いてみることにしよう。とりあえず「ネプチューンの泉」を目指して歩き出す。振り返ると真っ白な砂利道の向こうに宮殿がどーんと構えている。
「ネプチューン」の泉の向こう側には「グロリエッテ」が見える。せっかくだからあそこまで上ってみよう。
汗をかきかき上っていくと、視界が大きく広がる。高いところからの眺めはまた格別だ。遠くには「シュテファン寺院」まで望める。
間近で見る「グロリエッテ」もまた遠くから見たときとは趣が異なる。記念「碑」とのことだが、立派な建物である。内部にはカフェが設けられていた。
ここで日がなでれーんとしていたら楽しいだろうが、われわれには時間がない。地下鉄4号線と1号線を乗り継いでプラーターシュテルン駅へ。近郊列車Sバーンの駅もあって、かなり広い。高架下の自由通路を抜けるとすぐに「プラーター公園」である。ミュージカル「モーツァルト!」ではいろいろな物語が展開する。モーツァルトとシカネーダーが遊びに行って、コンスタンツェと再会する場所だ(もちろん史実とは違うのだろうが)。
こちらでのお目当ては大観覧車。ゴンドラは木製で、かなり大きめ。定員は12人とのこと。映画「第三の男」に登場したことで知られる(僕はこの映画は観たことがない)。近寄ってみるとかなり大きい。
チケット(観覧車とリリプットバーンのセット券)を買い、中に入ろうとしたところで記念写真を撮られる。普段なら買わないところだが、せっかくだからここは買ってみることにした。ゴンドラの合成写真だが、表情の演技指導までしてくれるのでなかなかである。
しかしこの観覧車、12人乗りでどのようなタイミングで人を乗せているのかと疑問に思っていた。乗り場で待っていると、目の前をゴンドラが通過していく。なかにはテーブルがあって食事でもできそうなものもある。
ゴンドラは操縦する人がいったん停止させて、そこに乗り込む形になっている。だから回転は一定ではない。結構な速さで回ると思ったら、次のお客さんを乗せるために一時停止するのだ。それにしても木製の古びたゴンドラには何ともいえぬ味わいがある。

上に上がっていくと、これまた素晴らしい景色が広がる。もちろん「シュテファン寺院」はちゃんと見える。
「プラーター公園」は実に広大だ。もともとはハプスブルク家の狩猟場だった土地である。
集合住宅地と思しき一角が見えるが、日本の団地とは全く異なったたたずまいだ。
観覧車でひと回りしたころには、写真ができあがっていた。それを受け取ってからリリプットバーンに乗りに行く。小さなかわいらしいディーゼル機関車がオープン客車を牽引する。まあどこにでもありがちなミニ鉄道だな、と思って乗り込んだ。

ところがいざ走り出してみると、これが実に楽しい。遊園地から出発して、やがて深い緑のなかへと入っていく。


途中駅もちゃんとあって、公園を散策する人が適宜乗降していく。全長は4kmほどだそうで、実に乗りでがあった。今まで乗ったミニ列車のなかでは間違いなくナンバーワンだ。
プラーターシュテルン駅の構内には、市営交通の案内所がある。そちらに市電の模型が売っていたので自分のおみやげに買って帰ることにした。模型は手ごろなものから結構高価なものまでいろいろと揃っている。
地下鉄をカールスプラッツ駅まで乗る。「分離派会館(ゼツェッシオン)」の前を通る。黄金のキャベツと呼ばれるドームが目を引く。
「アン・デア・ウィーン劇場」へ。正面ではなく、脇のパパゲーノ門を見に行く。現在は入口としては使われていないようだが、ちゃんとオペラ「魔笛」のパパゲーノの像がある。

この劇場はシカネーダー設計によるもの。以前はミュージカル「エリザペート」もこちらで上演されていたそうだ。現在はオペラとクラシックコンサートが中心とのこと。
リンクの内側まで歩いて、「カプツィーナー教会」を見学する。それほど大きな建物ではなくて、探すのに手間取った。だがこちらの教会の地下には、ハプスブルク家の人々の棺が安置されている。内臓は昨日見た「シュテファン寺院」に、心臓は「アウグスティナー教会」にそれぞれ収められている。
地上の暑さとはうってかわって、地下室はひんやりとした空気が漂う。マリア・テレジアと夫フランツ1世の棺はひときわ豪華なもの。2人の像が向かい合う形になっている。
フランツ・ヨーゼフ1世(中央)とエリザベート(左側)、ルドルフ(右側)の棺は仲良く並んでいる。ここが「エリザベート」「ルドルフ」の登場人物の人生の終着点である。
出口に近いところには、今年7月に亡くなった、最後の皇太子オットー・フォン・ハプスブルクの棺がある。慣例に従って、遺体はこの棺の中に、心臓はハンガリーの「ノンバンハルマ修道院」に収められているとのことである。
帝政は廃止されても、ハプスブルク家の歴史は脈々と続いている。どのおみやげもの屋さんに行っても、エリザベートの肖像画を使った商品はあるし(これは日本でもよく見かけるが)、フランツ・ヨーゼフ1世の肖像をあしらったものもたくさんある。
(その2)に続く。