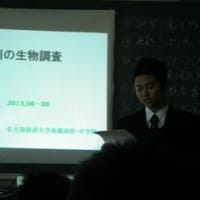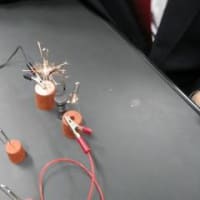6月6日(月)
6月5日(日)に内田先生が自宅の近所の床屋さんに散髪に行ったときの話です。
散髪中にツバメのヒナの話題になりました。
どうやら床屋さんの玄関にツバメの巣があるらしいのです。
その巣の中にヒナは5羽いたらしいのですが、その中の4羽は巣から落ちて死んでしまったそうです。
また、残った1羽も親鳥が世話をしなくなって、動かなくなってしまったらしいのです。
床屋さんから、是非残った1羽のヒナだけでも助けて欲しいと内田先生に申し出がありました。
そこで、内田先生がヒナを観察したところ、体温も低下しているし、とてもきけんな状態だったそうです。
何もしないと死んでしまう生き物を内田先生が見捨てるわけがありません。
さっそく自宅に持ち帰り、応急処置を行いました。

これが、保護したツバメのヒナです。保護してから1日経ちました。
その間に、巣箱を用意して、中に携帯用カイロを入れて温め、色んな物を入れた練り餌を食べさせて、次にドッグフードと練り餌の粉とビタミンとブドウ糖を食べさせたミルワームを食べさせて暗くして様子を見ます。

ようやく、指によじ登れるようになりました。

このように、巣箱の「へり」に止まるのが好きです。

正面から見たツバメです。

横から見たものです。まだ、くちばしは柔らかいし、尾羽(しっぽ)はとても短いです。

これがミルワームです。ゴミムシダマシの幼虫です。

この中にブドウ糖が入っています。

ヨーロッパイエコオロギです。内田先生が買ってきました。

カイコガの幼虫です。いわゆる「カイコ」です。ペットショップでは「シルクワーム」といって売っています。

このような粉の中にミルワームを入れて育ててから鶏の餌にします。

ヒナのエサのやり方です。
ピンセットでくちばしの中にミルワームを無理矢理入れます。

のどの奥まで入れます。

すると、このように呑み込みます。
呑み込まない場合は、くちばしの周りに水をつけます。
すると、鳥は嫌でも水を飲んでしまうので、エサも一緒に呑み込むことになります。
理科部では、このように野鳥を含め、死にそうな野生動物を保護しています。
命の大切さを知るためにも重要なことだと内田先生は言います。
【感想】
・今日、理科部に子どものツバメがやって来ました。思ったよりも小さくて、可愛かったです。【中2】
・今日、ツバメが理科部にやって来て、とても突然のことだったので、びっくりしました。
さわっていいと内田先生が言ってくれたので、さわってみると、とてもフワフワしていて触り心地が良かったです。
これから、このツバメのヒナが成長していくのを見守り続けたいと思っています。【中2】
・理科部の実験室にツバメのヒナがやって来ました。予想よりも小さすぎてびっくりしました。
ヒナに餌をあげることもすぐ近くで見て、内田先生の知識に感動しました。
人間のように噛むのではなく、丸飲みする感じですごかったです。【中1】
・私は、初めてツバメが何を食べるのかを知りました。以前、私の家の近くでツバメの子どもが落ちていました。
そのとき、巣に戻すには身長が足りずにどうしようかと迷っていました。家に持ち帰り、世話をしたのですが、結局、ツバメのエサが何か分からなかったためにツバメのヒナは2日目に死んでしまいました。その時は、プラスチック製のカップの中にティッシュペーパーをひいて、温めてあげたのですが、それだけでは足りなかったのです。
内田先生がやっていたように、もう少しふかふかの巣箱に入れてあげれば良かったのだと思いました。
私が、その時に今の知識があればあの命は助かったかもしれないと思うと、何事も勉強は大切だと思いました。
だからこそ、今度ツバメのヒナが落ちていたら、巣に戻して様子を見ようと思います。
そして、それでも親がエサをあげないようなら、保護をして、今回勉強したように世話をしてあげたいと思います。
鳥の餌やりは大変そうでしたが、今度世話をするときは、助けるためには頑張らないと行けないと思いました。【中2】
・今日は、内田先生のためになるお話がたくさん聞けて良かったです。名古屋経済大学高蔵高校に入学し、さらに理科部に入部して良かったと心から思いました。
そして、ツバメのように小さな生き物も、精一杯生きようとしています。
そのような命の強さを感じる良い経験になりました。【高1】
・ツバメの子どもは、見ているだけなら可愛いけれど、触ることができなかったのが、残念でした。【高1】
・今までに理科部が野鳥を何百羽も助けてきたなんて知らなかったです。
先輩や内田先生から聞く話は初めてでびっくりしました。
私たちは、これからも命を大切にして活動を続けていきたいと思いました。【高2】
・早く成長して、大空を自由に飛び回ってほしい。【高3】
・身近で初めてツバメのヒナを見ました.とてもかわいいのでびっくりしました。
元気にすくすくと成長してくれることを臨みます。【高1】
・内田先生が、理科部に助けたツバメのヒナを持ってきてくれました。
まだ小さくて、私のコブシよりもずっと小さく、自分一人ではえさを食べることも飲み込むことも出来ないようです。
内田先生がえさの食べさせ方と飲ませ方を教えてくれたので、何人かは内田先生と一緒にえさをやっていました。
次回、ツバメのヒナが理科室にやってきた時は、自分でもツバメなどの野鳥の世話が出来るようにしたいです。
内田先生の言っていたように「新しい理科部の一員」として、早く「卒業」出来るように協力していきたいと思いました。
【高2】
6月5日(日)に内田先生が自宅の近所の床屋さんに散髪に行ったときの話です。
散髪中にツバメのヒナの話題になりました。
どうやら床屋さんの玄関にツバメの巣があるらしいのです。
その巣の中にヒナは5羽いたらしいのですが、その中の4羽は巣から落ちて死んでしまったそうです。
また、残った1羽も親鳥が世話をしなくなって、動かなくなってしまったらしいのです。
床屋さんから、是非残った1羽のヒナだけでも助けて欲しいと内田先生に申し出がありました。
そこで、内田先生がヒナを観察したところ、体温も低下しているし、とてもきけんな状態だったそうです。
何もしないと死んでしまう生き物を内田先生が見捨てるわけがありません。
さっそく自宅に持ち帰り、応急処置を行いました。

これが、保護したツバメのヒナです。保護してから1日経ちました。
その間に、巣箱を用意して、中に携帯用カイロを入れて温め、色んな物を入れた練り餌を食べさせて、次にドッグフードと練り餌の粉とビタミンとブドウ糖を食べさせたミルワームを食べさせて暗くして様子を見ます。

ようやく、指によじ登れるようになりました。

このように、巣箱の「へり」に止まるのが好きです。

正面から見たツバメです。

横から見たものです。まだ、くちばしは柔らかいし、尾羽(しっぽ)はとても短いです。

これがミルワームです。ゴミムシダマシの幼虫です。

この中にブドウ糖が入っています。

ヨーロッパイエコオロギです。内田先生が買ってきました。

カイコガの幼虫です。いわゆる「カイコ」です。ペットショップでは「シルクワーム」といって売っています。

このような粉の中にミルワームを入れて育ててから鶏の餌にします。

ヒナのエサのやり方です。
ピンセットでくちばしの中にミルワームを無理矢理入れます。

のどの奥まで入れます。

すると、このように呑み込みます。
呑み込まない場合は、くちばしの周りに水をつけます。
すると、鳥は嫌でも水を飲んでしまうので、エサも一緒に呑み込むことになります。
理科部では、このように野鳥を含め、死にそうな野生動物を保護しています。
命の大切さを知るためにも重要なことだと内田先生は言います。
【感想】
・今日、理科部に子どものツバメがやって来ました。思ったよりも小さくて、可愛かったです。【中2】
・今日、ツバメが理科部にやって来て、とても突然のことだったので、びっくりしました。
さわっていいと内田先生が言ってくれたので、さわってみると、とてもフワフワしていて触り心地が良かったです。
これから、このツバメのヒナが成長していくのを見守り続けたいと思っています。【中2】
・理科部の実験室にツバメのヒナがやって来ました。予想よりも小さすぎてびっくりしました。
ヒナに餌をあげることもすぐ近くで見て、内田先生の知識に感動しました。
人間のように噛むのではなく、丸飲みする感じですごかったです。【中1】
・私は、初めてツバメが何を食べるのかを知りました。以前、私の家の近くでツバメの子どもが落ちていました。
そのとき、巣に戻すには身長が足りずにどうしようかと迷っていました。家に持ち帰り、世話をしたのですが、結局、ツバメのエサが何か分からなかったためにツバメのヒナは2日目に死んでしまいました。その時は、プラスチック製のカップの中にティッシュペーパーをひいて、温めてあげたのですが、それだけでは足りなかったのです。
内田先生がやっていたように、もう少しふかふかの巣箱に入れてあげれば良かったのだと思いました。
私が、その時に今の知識があればあの命は助かったかもしれないと思うと、何事も勉強は大切だと思いました。
だからこそ、今度ツバメのヒナが落ちていたら、巣に戻して様子を見ようと思います。
そして、それでも親がエサをあげないようなら、保護をして、今回勉強したように世話をしてあげたいと思います。
鳥の餌やりは大変そうでしたが、今度世話をするときは、助けるためには頑張らないと行けないと思いました。【中2】
・今日は、内田先生のためになるお話がたくさん聞けて良かったです。名古屋経済大学高蔵高校に入学し、さらに理科部に入部して良かったと心から思いました。
そして、ツバメのように小さな生き物も、精一杯生きようとしています。
そのような命の強さを感じる良い経験になりました。【高1】
・ツバメの子どもは、見ているだけなら可愛いけれど、触ることができなかったのが、残念でした。【高1】
・今までに理科部が野鳥を何百羽も助けてきたなんて知らなかったです。
先輩や内田先生から聞く話は初めてでびっくりしました。
私たちは、これからも命を大切にして活動を続けていきたいと思いました。【高2】
・早く成長して、大空を自由に飛び回ってほしい。【高3】
・身近で初めてツバメのヒナを見ました.とてもかわいいのでびっくりしました。
元気にすくすくと成長してくれることを臨みます。【高1】
・内田先生が、理科部に助けたツバメのヒナを持ってきてくれました。
まだ小さくて、私のコブシよりもずっと小さく、自分一人ではえさを食べることも飲み込むことも出来ないようです。
内田先生がえさの食べさせ方と飲ませ方を教えてくれたので、何人かは内田先生と一緒にえさをやっていました。
次回、ツバメのヒナが理科室にやってきた時は、自分でもツバメなどの野鳥の世話が出来るようにしたいです。
内田先生の言っていたように「新しい理科部の一員」として、早く「卒業」出来るように協力していきたいと思いました。
【高2】