本日(8月21日)は、覚王山・日泰寺の「弘法市」。

今朝8時半頃の様子ですが、参道には簡易店舗が設営され始め、
「弘法市」ならではの賑わいを予感させていました。
日泰寺門前・千躰地蔵堂に祀られる地蔵菩薩。

その左手に載っているのは “ マニ宝珠 ” であります。

“ マニ宝珠 ” の “ マニ ” 自体が、サンスクリット語で「宝珠」。
元々の語形は “ cinta mani(チンター・マニ)” で、
“ チンター ” が「意思」や「願い」を意味したところから、
後世において「如意(にょい)」と訳され、“ マニ宝珠 ” は、
一般的に “ 如意宝珠 ” と呼ばれるようになったと伝わります。
杉浦康平氏の著書「宇宙を叩く」(工作舎)は、
副題が「火炎太鼓・曼荼羅・アジアの響き」。
杉浦先生は、火炎太鼓の外形や仏像の光背等々は、
“ 如意宝珠 ” を模している・・・とされたうえで、
『如意宝珠は、たとえようもない霊力を秘めた不思議珠です。
いずことも見きわめぬところから不意に現れる。
ゆらめく炎を発しています。
宝珠は日・月の光の精だとされ、あるいは月のしずく、
つまり海に潜む「真珠」だともいわれている。
また宇宙の核をなすエネルギーの塊り、
「気の精髄」とも説かれています。』
(引用元:杉浦康平「宇宙を叩く」工作舎刊、以下同)
として、如意宝珠の世界を解き明かしてゆかれます。
神社仏閣や仏像仏画等で御覧になった方は御存知のように、
如意宝珠の典型的な図像は、
回転する水の宝珠が炎に包まれているというもので、
如意宝珠は、またの名を “ 火焔宝珠 ” 。
こちらは「国宝 阿弥陀如来聖衆来迎図」
(“ 空海と高野山 ” 展・ポストカードを撮影)
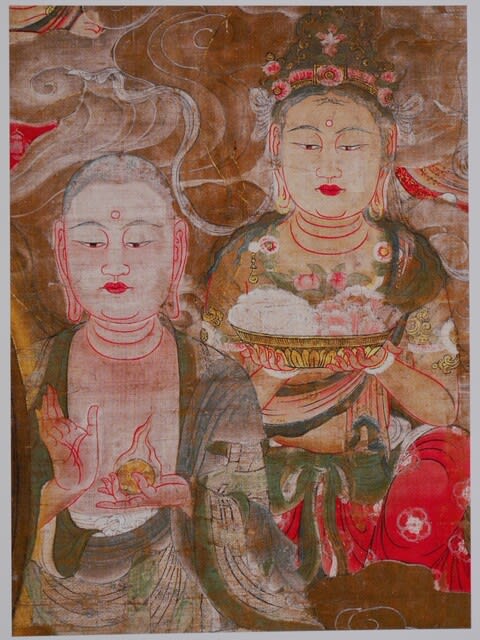
向かって左から、火焔宝珠菩薩と華籠(けろう・けこ)菩薩。
火焔宝珠菩薩の左手には、

火焔宝珠が載っています。
杉浦先生は、こうした火焔宝珠の図像について
『水中に潜む宝珠。雨を降らせる宝珠。
これは「水」の働きです。その宝珠が火焔に包まれている。
火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』
つまり如意宝珠の本質は、
『「火」と「水」の出会い』
であると説かれます。
本来的には打ち消し合うはずの「火」と「水」が、
一体となって回転しながら豊穣の気を湧き立たせているのが、
“ マニ宝珠 ” ということであり、このことから派生して、
陰陽一対、双極一体、二而不二(ににふに)の曼荼羅世界、
といったことが博覧強記に語られてゆきます。



須田道輝師(1929~2008)は、長崎県・天佑寺の住職にして、
仏教の奥深さを分かりやすく著された文筆家でもありました。
「虚空の神力」(柏樹社)は、虚空蔵菩薩について記された一冊。
この書籍の副題「マニと剣の秘儀」の「マニ」とは、
先に記した “ マニ宝珠 ” のことであります。
「虚空の神力」では、
この “ マニ宝珠 ” の持つ意味や意義が説かれています。
『マニ宝珠については、古来「最極の秘」として、
一般の人には公開されなかったものです。
しかしマニ宝珠の意味は、
結局「和合」という教えに他なりません。
つまり、宇宙法界の万物現象は、
すべて「和合」のはたらきにつきるということです。
この「和合」の徳をもって、
すべての願いを成就せしめるということです。』
(引用元:「虚空の神力」柏樹社刊、以下同)
或いは又、
『“ マニ宝珠 ” は、汚れたものを清浄にします。』
『“ マニ宝珠 ” は、生命の気力を充実せしめる力があります。』
『“ マニ宝珠 ” は、乱れたものに和合を与えます。』
とも書かれています。
この辺りは、先の「宇宙を叩く」の中で説かれていたように、
「水」と「火」という、本来ならば相容れない要素が出会い、
打ち消し合うはずの働きが、働きのままに結ばれ、
一つに融けて「和合」するというところに重なります。
また須田師が繰り返し記しておられるのは、
『マニ宝珠は、菩薩の功徳を象徴化したもの』
ということ。
“ マニ宝珠 ” というものは、
あくまでも神仏の功徳や徳力をシンボライズしたものであって、
「これが “ マニ宝珠 ” です」というような現物ではありません。
須田師も、その辺りを懸念されていて、
“ マニ宝珠 ” が、さも現実のモノであるかのように捉えるのは、
邪道・邪法と断じておられます。
哀しい哉、江戸~明治期には、
ガラス片や瓦礫で “ マニ宝珠 ” 状のモノを造っては、
これを “ マニ宝珠の現物 ” と銘打って、
「あなたの不運が改善される」とか、
「あなたの病気が治ります」といった文言を弄して宣伝し、
粗悪な丸玉を売りつける “ マニ売り ” なる輩が多くいたそうです。
今で言う「霊感商法」であります。
嘆かわしいのは、西暦も2000年代に入った現代にあって尚、
こうした「霊感商法」が “ アトを断たない ” こと。
“ アトを断たない ” どころか、昨今のネット社会化に伴って、
より巧妙化・悪質化しているように見受けられます。
いつの時代にも、どこの国にも、
「◯◯を身につければ “ 浄化 ” されます」
「◯◯を身近に置けば “ 除霊 ” できます」等々の言葉を騙り、
思わしくない現状を生きる人々の
“ 弱みにつけこむ ”
ことで法外な金銭を要求する組織・集団・勢力が存在します。
それら組織・集団・勢力は、時として “ 宗教 ” の名の下に、
表向きは極めてクリーンな装いを見せているもの。
くれぐれも気をつけたいところであります。



つい話が逸れましたが、
“ マニ宝珠 ” なるものは実際の現物や、何らかの商品ではない、
ということでありました。
では、事象としての “ マニ宝珠 ” はどうでしょうか?
例えば東大寺の修二会では、
通称 “ お松明 ” の行において、大火焔が振り回され、
通称 “ お水取り ” の行では、聖なる水が本尊に捧げられます。
考えようによっては、修二会という仏事全体が、水と火の結び、
事象としての “ マニ宝珠 ” と観ることも出来ようかと思います。
或いは又、密教寺院で日々厳修される “ 護摩行 ” というものも、
水と火の「和合」という視点で観想してみますと、
一種の「“ マニ宝珠 ” 事象」のようにも感じられます。
また古来、稲を実らせるものは雷であると信じられ、
雷を「稲」の「妻」、「稲妻(イナズマ)」と称したことは、
よく知られているところ。
水田という「水」の場に植えられたものに、
稲妻という「火」の力が天からくだり、稲は黄金の実を結ぶ。
もしかしたら太古の人々は、稲作の春夏秋冬に、
現象としての “ マニ宝珠 ” を観ていたのかも知れません。
相対するもの、双極に在るもの、本来相容れないもの、
そうした要素や事象が、ある瞬間、
或いは瞬間の連続としての一定期間、ひとつになり、
ダイナミックな働きを示す事で、1+1=2以上の何かを生み出す、
というのが “ マニ宝珠 ” の側面でもあろうかと思います。



先の「宇宙を叩く」では、
『火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』
と記され、
『「火」と「水」の出会い』
その『出会い』が、“ マニ宝珠 ” であり、
その『出会い』が、豊かさをもたらすとされていました。
思い浮かぶのは、“ 地球 ” でありましょうか。
地球は、その約70%が「水」であることを思えば「水の珠」。
地球を取り巻く大気圏の外層を構成する “ 熱圏 ” は、
文字通り、およそ2000度という高温であり、言わば「大火焔」。
回転する「水の珠」が「大火焔」に包まれているというのは、
紛れもなく “ マニ宝珠 ” と申せましょう。
地球は、宇宙の中で、かけがえのない “ マニ宝珠 ” 。

皆様、良き日々でありますように!







今朝8時半頃の様子ですが、参道には簡易店舗が設営され始め、
「弘法市」ならではの賑わいを予感させていました。
日泰寺門前・千躰地蔵堂に祀られる地蔵菩薩。

その左手に載っているのは “ マニ宝珠 ” であります。

“ マニ宝珠 ” の “ マニ ” 自体が、サンスクリット語で「宝珠」。
元々の語形は “ cinta mani(チンター・マニ)” で、
“ チンター ” が「意思」や「願い」を意味したところから、
後世において「如意(にょい)」と訳され、“ マニ宝珠 ” は、
一般的に “ 如意宝珠 ” と呼ばれるようになったと伝わります。
杉浦康平氏の著書「宇宙を叩く」(工作舎)は、
副題が「火炎太鼓・曼荼羅・アジアの響き」。
杉浦先生は、火炎太鼓の外形や仏像の光背等々は、
“ 如意宝珠 ” を模している・・・とされたうえで、
『如意宝珠は、たとえようもない霊力を秘めた不思議珠です。
いずことも見きわめぬところから不意に現れる。
ゆらめく炎を発しています。
宝珠は日・月の光の精だとされ、あるいは月のしずく、
つまり海に潜む「真珠」だともいわれている。
また宇宙の核をなすエネルギーの塊り、
「気の精髄」とも説かれています。』
(引用元:杉浦康平「宇宙を叩く」工作舎刊、以下同)
として、如意宝珠の世界を解き明かしてゆかれます。
神社仏閣や仏像仏画等で御覧になった方は御存知のように、
如意宝珠の典型的な図像は、
回転する水の宝珠が炎に包まれているというもので、
如意宝珠は、またの名を “ 火焔宝珠 ” 。
こちらは「国宝 阿弥陀如来聖衆来迎図」
(“ 空海と高野山 ” 展・ポストカードを撮影)
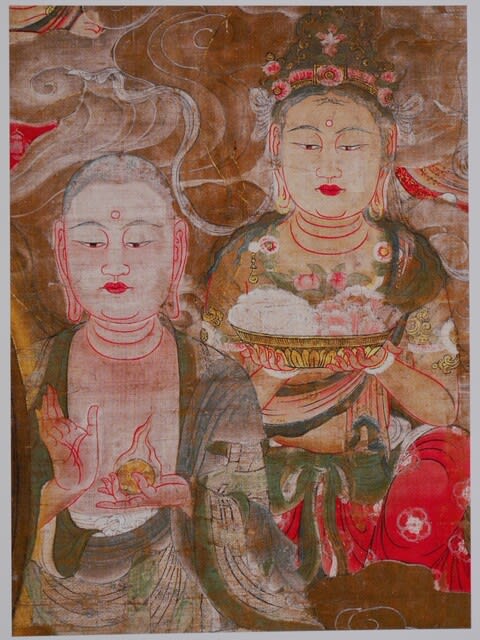
向かって左から、火焔宝珠菩薩と華籠(けろう・けこ)菩薩。
火焔宝珠菩薩の左手には、

火焔宝珠が載っています。
杉浦先生は、こうした火焔宝珠の図像について
『水中に潜む宝珠。雨を降らせる宝珠。
これは「水」の働きです。その宝珠が火焔に包まれている。
火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』
つまり如意宝珠の本質は、
『「火」と「水」の出会い』
であると説かれます。
本来的には打ち消し合うはずの「火」と「水」が、
一体となって回転しながら豊穣の気を湧き立たせているのが、
“ マニ宝珠 ” ということであり、このことから派生して、
陰陽一対、双極一体、二而不二(ににふに)の曼荼羅世界、
といったことが博覧強記に語られてゆきます。



須田道輝師(1929~2008)は、長崎県・天佑寺の住職にして、
仏教の奥深さを分かりやすく著された文筆家でもありました。
「虚空の神力」(柏樹社)は、虚空蔵菩薩について記された一冊。
この書籍の副題「マニと剣の秘儀」の「マニ」とは、
先に記した “ マニ宝珠 ” のことであります。
「虚空の神力」では、
この “ マニ宝珠 ” の持つ意味や意義が説かれています。
『マニ宝珠については、古来「最極の秘」として、
一般の人には公開されなかったものです。
しかしマニ宝珠の意味は、
結局「和合」という教えに他なりません。
つまり、宇宙法界の万物現象は、
すべて「和合」のはたらきにつきるということです。
この「和合」の徳をもって、
すべての願いを成就せしめるということです。』
(引用元:「虚空の神力」柏樹社刊、以下同)
或いは又、
『“ マニ宝珠 ” は、汚れたものを清浄にします。』
『“ マニ宝珠 ” は、生命の気力を充実せしめる力があります。』
『“ マニ宝珠 ” は、乱れたものに和合を与えます。』
とも書かれています。
この辺りは、先の「宇宙を叩く」の中で説かれていたように、
「水」と「火」という、本来ならば相容れない要素が出会い、
打ち消し合うはずの働きが、働きのままに結ばれ、
一つに融けて「和合」するというところに重なります。
また須田師が繰り返し記しておられるのは、
『マニ宝珠は、菩薩の功徳を象徴化したもの』
ということ。
“ マニ宝珠 ” というものは、
あくまでも神仏の功徳や徳力をシンボライズしたものであって、
「これが “ マニ宝珠 ” です」というような現物ではありません。
須田師も、その辺りを懸念されていて、
“ マニ宝珠 ” が、さも現実のモノであるかのように捉えるのは、
邪道・邪法と断じておられます。
哀しい哉、江戸~明治期には、
ガラス片や瓦礫で “ マニ宝珠 ” 状のモノを造っては、
これを “ マニ宝珠の現物 ” と銘打って、
「あなたの不運が改善される」とか、
「あなたの病気が治ります」といった文言を弄して宣伝し、
粗悪な丸玉を売りつける “ マニ売り ” なる輩が多くいたそうです。
今で言う「霊感商法」であります。
嘆かわしいのは、西暦も2000年代に入った現代にあって尚、
こうした「霊感商法」が “ アトを断たない ” こと。
“ アトを断たない ” どころか、昨今のネット社会化に伴って、
より巧妙化・悪質化しているように見受けられます。
いつの時代にも、どこの国にも、
「◯◯を身につければ “ 浄化 ” されます」
「◯◯を身近に置けば “ 除霊 ” できます」等々の言葉を騙り、
思わしくない現状を生きる人々の
“ 弱みにつけこむ ”
ことで法外な金銭を要求する組織・集団・勢力が存在します。
それら組織・集団・勢力は、時として “ 宗教 ” の名の下に、
表向きは極めてクリーンな装いを見せているもの。
くれぐれも気をつけたいところであります。



つい話が逸れましたが、
“ マニ宝珠 ” なるものは実際の現物や、何らかの商品ではない、
ということでありました。
では、事象としての “ マニ宝珠 ” はどうでしょうか?
例えば東大寺の修二会では、
通称 “ お松明 ” の行において、大火焔が振り回され、
通称 “ お水取り ” の行では、聖なる水が本尊に捧げられます。
考えようによっては、修二会という仏事全体が、水と火の結び、
事象としての “ マニ宝珠 ” と観ることも出来ようかと思います。
或いは又、密教寺院で日々厳修される “ 護摩行 ” というものも、
水と火の「和合」という視点で観想してみますと、
一種の「“ マニ宝珠 ” 事象」のようにも感じられます。
また古来、稲を実らせるものは雷であると信じられ、
雷を「稲」の「妻」、「稲妻(イナズマ)」と称したことは、
よく知られているところ。
水田という「水」の場に植えられたものに、
稲妻という「火」の力が天からくだり、稲は黄金の実を結ぶ。
もしかしたら太古の人々は、稲作の春夏秋冬に、
現象としての “ マニ宝珠 ” を観ていたのかも知れません。
相対するもの、双極に在るもの、本来相容れないもの、
そうした要素や事象が、ある瞬間、
或いは瞬間の連続としての一定期間、ひとつになり、
ダイナミックな働きを示す事で、1+1=2以上の何かを生み出す、
というのが “ マニ宝珠 ” の側面でもあろうかと思います。



先の「宇宙を叩く」では、
『火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』
と記され、
『「火」と「水」の出会い』
その『出会い』が、“ マニ宝珠 ” であり、
その『出会い』が、豊かさをもたらすとされていました。
思い浮かぶのは、“ 地球 ” でありましょうか。
地球は、その約70%が「水」であることを思えば「水の珠」。
地球を取り巻く大気圏の外層を構成する “ 熱圏 ” は、
文字通り、およそ2000度という高温であり、言わば「大火焔」。
回転する「水の珠」が「大火焔」に包まれているというのは、
紛れもなく “ マニ宝珠 ” と申せましょう。
地球は、宇宙の中で、かけがえのない “ マニ宝珠 ” 。

皆様、良き日々でありますように!

































