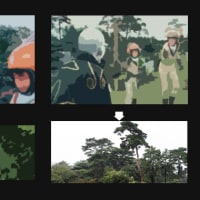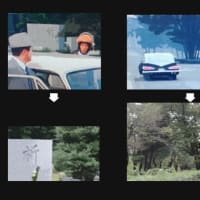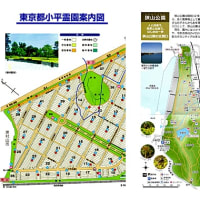神田川から日本橋川に入ったクルーズ船。
日本橋川は神田川の分流だが、自然河川ではなく
徳川家康が1590年頃造らせた道三堀が元になっているという。

現在では川に蓋をするように首都高速が上部を覆っている為、
うす暗く、半暗渠化した状態だ。
ここから日本橋までは、通過する橋が見所となる。


鎌倉橋付近には、その昔は材木問屋が軒をつらね、
鎌倉から来た材木商たちが築城に使う建築部材を取り仕切っていた。
そのため荷揚げ場が「鎌倉河岸」と呼ばれたそうだ。
今でも神田明神内に「神田の家」と呼ばれる材木商の家屋が移築され、
見学する事もできるそうだ。

雉子橋(地下鉄東西線竹橋駅)付近には江戸時代に築かれた外堀の石垣(上段右)が残っており、
歴史好きには萌えポイントだろう。
新常盤橋付近のJR鉄橋には1919年(大正8年)竣工時の鉄道省シンボルマーク(機関車の動輪/上段左)も
目にする事ができる。こちらは鉄道マニア萌えポイントだ。
さらに小さい水門(下段右)も発見。
現在は暗渠となっているが、日本橋川の支流だという。

常磐橋は江戸時代、日光街道に向かう主要ルートで将軍も利用した。
江戸五口の一つで常磐橋御門があり、家康入府直後から橋が架けられていた。

常磐橋御門は、桝形門遺構が残り、現在公園になっている。
1873年(明治6年)に常磐橋御門が廃止されると、その石を使って
1877年(明治10年)石橋にかけなおされ、東京最古の洋式石橋として
史跡に指定されている。

川岸からは竹坊達が見守ってくれた。
・・・そして、いよいよ日本橋に到着。


この橋は、1603年に架橋された。五街道の起点とされ、陸路の中心でもあり、水運の中心となったので、
問屋や商店が集中し、江戸随一の盛り場となった。
江戸期の橋には京橋、新橋、江戸城内の橋にしか許されなかった擬宝珠があった。
現在の橋は1911年(明治44年)に建設され、震災も戦災も無事に乗り越え、
国の重要文化財に指定されている。

青銅製の麒麟は東京の繁栄を、獅子は守護を示すという。
今回のクルーズで初めて見つけた橋の中央部にある獅子のレリーフ。
ピンボケ写真しか撮れなかった!
天候にめぐまれなかったのが残念だったが、
見所十分で説明も詳しく、充実したクルーズだった。
日本橋川は神田川の分流だが、自然河川ではなく
徳川家康が1590年頃造らせた道三堀が元になっているという。

現在では川に蓋をするように首都高速が上部を覆っている為、
うす暗く、半暗渠化した状態だ。
ここから日本橋までは、通過する橋が見所となる。


鎌倉橋付近には、その昔は材木問屋が軒をつらね、
鎌倉から来た材木商たちが築城に使う建築部材を取り仕切っていた。
そのため荷揚げ場が「鎌倉河岸」と呼ばれたそうだ。
今でも神田明神内に「神田の家」と呼ばれる材木商の家屋が移築され、
見学する事もできるそうだ。

雉子橋(地下鉄東西線竹橋駅)付近には江戸時代に築かれた外堀の石垣(上段右)が残っており、
歴史好きには萌えポイントだろう。
新常盤橋付近のJR鉄橋には1919年(大正8年)竣工時の鉄道省シンボルマーク(機関車の動輪/上段左)も
目にする事ができる。こちらは鉄道マニア萌えポイントだ。
さらに小さい水門(下段右)も発見。
現在は暗渠となっているが、日本橋川の支流だという。

常磐橋は江戸時代、日光街道に向かう主要ルートで将軍も利用した。
江戸五口の一つで常磐橋御門があり、家康入府直後から橋が架けられていた。

常磐橋御門は、桝形門遺構が残り、現在公園になっている。
1873年(明治6年)に常磐橋御門が廃止されると、その石を使って
1877年(明治10年)石橋にかけなおされ、東京最古の洋式石橋として
史跡に指定されている。

川岸からは竹坊達が見守ってくれた。
・・・そして、いよいよ日本橋に到着。


この橋は、1603年に架橋された。五街道の起点とされ、陸路の中心でもあり、水運の中心となったので、
問屋や商店が集中し、江戸随一の盛り場となった。
江戸期の橋には京橋、新橋、江戸城内の橋にしか許されなかった擬宝珠があった。
現在の橋は1911年(明治44年)に建設され、震災も戦災も無事に乗り越え、
国の重要文化財に指定されている。

青銅製の麒麟は東京の繁栄を、獅子は守護を示すという。
今回のクルーズで初めて見つけた橋の中央部にある獅子のレリーフ。
ピンボケ写真しか撮れなかった!
天候にめぐまれなかったのが残念だったが、
見所十分で説明も詳しく、充実したクルーズだった。