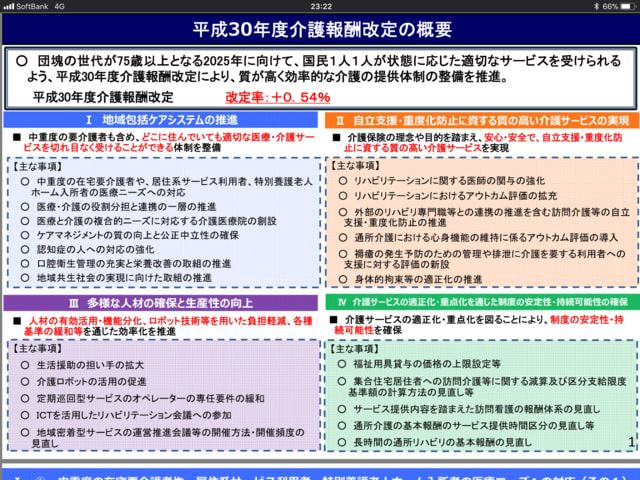前回の記事が平成最後の投稿にはなりませんでしたね(笑)
年度末までの繁忙期が終わり、ホッとした矢先、2019年度業務がどっと押し寄せ、10連休どころではない状況になってきました。
世間は新天皇即位にあやかって、海外旅行やレジャーを楽しむ方が多いと思いますが、福祉施設や医療機関、サービス業などにおいては、それどころじゃないことをお察しします。
さて平成最後の記事は、「アップデート」について取り上げます。
意味としては、「ソフトウェアやデータベースを最新の状態に更新すること」として用いられており、自己研鑽の意味合いとして用いることもあります。
iPhoneやスマホ、その中に入っている様々なアプリも、定期的なアップデートが行われ、サービス内容が充実したり、バグの解消といったアップデートもあります。
このようなデジタルに関するソフトウェアにはアップデートとう概念があることで、アジャイル的な迅速なサービス開発・提供とサービス内容の改善・高次化に常に取り組むことが出来ます(逆にここを怠ると、誰からも見向きもされないソフトウェアやアプリになってしまうでしょう)。
以前、介護ロボットのアップデートで出来ることが増えていくという話をしましたが、インターネットに接続されているIoT機器は常に進化を遂げることができる強みを持っています(先日の「名探偵コナン」の映画では、IoTテロという脅威も映像化されていましたが)。
「組織の弱体化を打ち破るためには古い慣習を捨てる」でもお伝えしましたが、古い慣習は捨てましょう。
特に福祉業界では、これまで培ってきた歴史を重んじながら、「〜しなければならない」「〜あるべきだ」という思考回路に陥りがちですが、それでは時代遅れになってしまいます。
そういう習慣は平成に置いて、令和の時代には持ち越さないようにしましょう。
車の自動運転支援システムやスマホによる電子決済という新しいサービスが生まれ、痛ましい高齢者による交通事故ゼロやお財布を持たない社会が現実味を帯びつつあります。
そうした新しいサービスが生まれるというのは、「もっとこうなったらいいなぁ(向上力)」の賜物といえます。
では、皆さんの施設・事業所はこれからの社会や地域住民から求められる役割を全うできるような機能強化や役割を担う準備が出来ていますか?
社会福祉法人のあり方検討会の流れを受けた社会福祉法の改正に伴う、ガバナンス強化や情報開示による透明性の確保、地域公益的取組の推進など社会福祉法人に求められる責務が明確化されましたが、はっきり言って、こんなのは序の口です。
これから本格的な少子高齢社会を迎える中、制度の持続可能性を鑑みれば、介護保険制度は聖域なきさらなる変革が断行されるでしょう。
ケアプランの有料化や軽度要介護者の介護保険からの切り離し(総合事業:介護予防・日常生活支援総合事業への移行)は避けて通れません。
地域住民同士の支え合い(互助、共助)の促進、予防介護による医療・福祉サービスは本当に必要な利用者への重点化が進められ、我々国民の意識も「病院・介護事業所から地域(いわゆるサードプレイス)へ」に変わっていくでしょう(デイのプログラムも団塊の世代用にアップデートが必須です)。
また、現場におけるデジタル化や介護ロボット・福祉機器の導入は加速するので、パソコンが使えない職員でも、スマホやタブレットで記録を残したり、会議はペーパレス化が推進されるでしょう(国会でもタブレットを導入しているのですから)。
また、機能や役割という点については、救護施設では、一足早く、自らの施設の社会的役割強化を明確化し、全国的に救護施設の認知度アップや情報開示の強化に向けた福祉サービス第三者評価受審を進めています。
特養においても、看取り介護に注力した終の住処としての専門性を、地域住民向けの勉強会などを通して、発信している施設もあります。
小規模法人の大規模化・協働化については、国も推進する姿勢を示しており、地域公益的取組の推進を含め、協働購買や法人横断で本部機能をBPOするなど、社会福祉法人のあり方の多様化が現在進行形で進んでいます。
すでに、危機感を感じている法人では、これまでの「〜しなければならない」「〜あるべきだ」から脱却し、自分たちの生き残りをかけてアップデートするための「戦略」を描き始め、それを実行しています。
2000年以前の措置の時代(福祉1.0)、2000年以降の介護保険制度導入:市場原理の導入(福祉2.0)、2017年社会福祉法改正:社会福祉法人のあり方の再考(福祉3.0)、2025年団塊の世代が後期高齢者となる:少子高齢社会に突入(福祉4.0)という、段階を経てきています。
そして、2040年問題(福祉5.0)にどう対処していくか、どう適応していくかという脅威が目前まで来ています。
介護保険制度の持続可能性を担保する前に、社会福祉法人や施設、事業所の経営を担保しなければ、社会インフラとして福祉や介護サービスは途切れてしまう最悪なシナリオも容易に想像ができてしまうような時代が来ようとしています。
と、平成最後の記事がなんだか暗くなってしまうのもアレなので、だからこそ、アップデートし続ける必要性を最後に伝えたいと思います。
施設を長期的な視点でクローズすると決めている施設長もいらっしゃいます。
それはそれで一つの役割を果たしたと判断できれば、納得ができるのではないでしょうか。
しかし、経営理念を実現するという社会福祉法人の使命を果たし続けるために、その時代時代にあった機能や役割を担い続けていく必要性があると、生意気ですが私は思っています。
戦略を描く、職員を育てる(マネジメント感覚の醸成)、経営成果や組織変革といった結果を残す、そのために組織を作るということに取り組んでいます。
お客様から評価していただいたり、フィードバックをいただくことは、私自身のアップデートがお客様に貢献できた証です。
令和の時代も、さらに厳しい事業環境となることが予想されます。
皆さんの法人や施設もぜひ利用者、家族、地域住民、関係者の方から「あってよかった」「お願いしてよかった」と言ってもらえるよう、アップデートをし続けてください。
一緒に良い時代を迎えましょう。
管理人
年度末までの繁忙期が終わり、ホッとした矢先、2019年度業務がどっと押し寄せ、10連休どころではない状況になってきました。
世間は新天皇即位にあやかって、海外旅行やレジャーを楽しむ方が多いと思いますが、福祉施設や医療機関、サービス業などにおいては、それどころじゃないことをお察しします。
さて平成最後の記事は、「アップデート」について取り上げます。
意味としては、「ソフトウェアやデータベースを最新の状態に更新すること」として用いられており、自己研鑽の意味合いとして用いることもあります。
iPhoneやスマホ、その中に入っている様々なアプリも、定期的なアップデートが行われ、サービス内容が充実したり、バグの解消といったアップデートもあります。
このようなデジタルに関するソフトウェアにはアップデートとう概念があることで、アジャイル的な迅速なサービス開発・提供とサービス内容の改善・高次化に常に取り組むことが出来ます(逆にここを怠ると、誰からも見向きもされないソフトウェアやアプリになってしまうでしょう)。
以前、介護ロボットのアップデートで出来ることが増えていくという話をしましたが、インターネットに接続されているIoT機器は常に進化を遂げることができる強みを持っています(先日の「名探偵コナン」の映画では、IoTテロという脅威も映像化されていましたが)。
「組織の弱体化を打ち破るためには古い慣習を捨てる」でもお伝えしましたが、古い慣習は捨てましょう。
特に福祉業界では、これまで培ってきた歴史を重んじながら、「〜しなければならない」「〜あるべきだ」という思考回路に陥りがちですが、それでは時代遅れになってしまいます。
そういう習慣は平成に置いて、令和の時代には持ち越さないようにしましょう。
車の自動運転支援システムやスマホによる電子決済という新しいサービスが生まれ、痛ましい高齢者による交通事故ゼロやお財布を持たない社会が現実味を帯びつつあります。
そうした新しいサービスが生まれるというのは、「もっとこうなったらいいなぁ(向上力)」の賜物といえます。
では、皆さんの施設・事業所はこれからの社会や地域住民から求められる役割を全うできるような機能強化や役割を担う準備が出来ていますか?
社会福祉法人のあり方検討会の流れを受けた社会福祉法の改正に伴う、ガバナンス強化や情報開示による透明性の確保、地域公益的取組の推進など社会福祉法人に求められる責務が明確化されましたが、はっきり言って、こんなのは序の口です。
これから本格的な少子高齢社会を迎える中、制度の持続可能性を鑑みれば、介護保険制度は聖域なきさらなる変革が断行されるでしょう。
ケアプランの有料化や軽度要介護者の介護保険からの切り離し(総合事業:介護予防・日常生活支援総合事業への移行)は避けて通れません。
地域住民同士の支え合い(互助、共助)の促進、予防介護による医療・福祉サービスは本当に必要な利用者への重点化が進められ、我々国民の意識も「病院・介護事業所から地域(いわゆるサードプレイス)へ」に変わっていくでしょう(デイのプログラムも団塊の世代用にアップデートが必須です)。
また、現場におけるデジタル化や介護ロボット・福祉機器の導入は加速するので、パソコンが使えない職員でも、スマホやタブレットで記録を残したり、会議はペーパレス化が推進されるでしょう(国会でもタブレットを導入しているのですから)。
また、機能や役割という点については、救護施設では、一足早く、自らの施設の社会的役割強化を明確化し、全国的に救護施設の認知度アップや情報開示の強化に向けた福祉サービス第三者評価受審を進めています。
特養においても、看取り介護に注力した終の住処としての専門性を、地域住民向けの勉強会などを通して、発信している施設もあります。
小規模法人の大規模化・協働化については、国も推進する姿勢を示しており、地域公益的取組の推進を含め、協働購買や法人横断で本部機能をBPOするなど、社会福祉法人のあり方の多様化が現在進行形で進んでいます。
すでに、危機感を感じている法人では、これまでの「〜しなければならない」「〜あるべきだ」から脱却し、自分たちの生き残りをかけてアップデートするための「戦略」を描き始め、それを実行しています。
2000年以前の措置の時代(福祉1.0)、2000年以降の介護保険制度導入:市場原理の導入(福祉2.0)、2017年社会福祉法改正:社会福祉法人のあり方の再考(福祉3.0)、2025年団塊の世代が後期高齢者となる:少子高齢社会に突入(福祉4.0)という、段階を経てきています。
そして、2040年問題(福祉5.0)にどう対処していくか、どう適応していくかという脅威が目前まで来ています。
介護保険制度の持続可能性を担保する前に、社会福祉法人や施設、事業所の経営を担保しなければ、社会インフラとして福祉や介護サービスは途切れてしまう最悪なシナリオも容易に想像ができてしまうような時代が来ようとしています。
と、平成最後の記事がなんだか暗くなってしまうのもアレなので、だからこそ、アップデートし続ける必要性を最後に伝えたいと思います。
施設を長期的な視点でクローズすると決めている施設長もいらっしゃいます。
それはそれで一つの役割を果たしたと判断できれば、納得ができるのではないでしょうか。
しかし、経営理念を実現するという社会福祉法人の使命を果たし続けるために、その時代時代にあった機能や役割を担い続けていく必要性があると、生意気ですが私は思っています。
戦略を描く、職員を育てる(マネジメント感覚の醸成)、経営成果や組織変革といった結果を残す、そのために組織を作るということに取り組んでいます。
お客様から評価していただいたり、フィードバックをいただくことは、私自身のアップデートがお客様に貢献できた証です。
令和の時代も、さらに厳しい事業環境となることが予想されます。
皆さんの法人や施設もぜひ利用者、家族、地域住民、関係者の方から「あってよかった」「お願いしてよかった」と言ってもらえるよう、アップデートをし続けてください。
一緒に良い時代を迎えましょう。
管理人