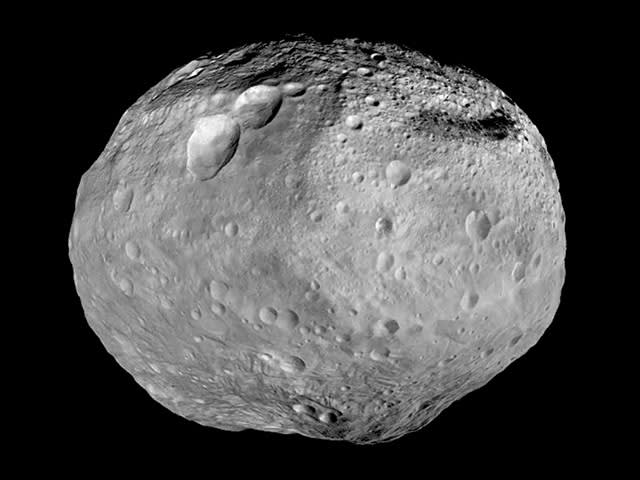月と水星のクレーターの観測データを新たに解析した結果、この2つの天体の極域に大量の氷が存在する可能性が示された。
【2019年8月13日 NASA】
月と水星の極域は、太陽系の中で最も温度が低い場所の一つだ。月の自転軸の傾きは5.1度、水星は7度で、地球(23.4度)よりもずっと小さい。このため、月や水星の極域では太陽は高く上ることがなく、クレーターの内部には太陽光が全く当たらない「永久影」もある。永久影は極めて低温のため、何らかの原因でここに溜まった水の氷は数十億年にわたって残ると考えられている。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース
【2019年8月13日 NASA】
月と水星の極域は、太陽系の中で最も温度が低い場所の一つだ。月の自転軸の傾きは5.1度、水星は7度で、地球(23.4度)よりもずっと小さい。このため、月や水星の極域では太陽は高く上ることがなく、クレーターの内部には太陽光が全く当たらない「永久影」もある。永久影は極めて低温のため、何らかの原因でここに溜まった水の氷は数十億年にわたって残ると考えられている。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース