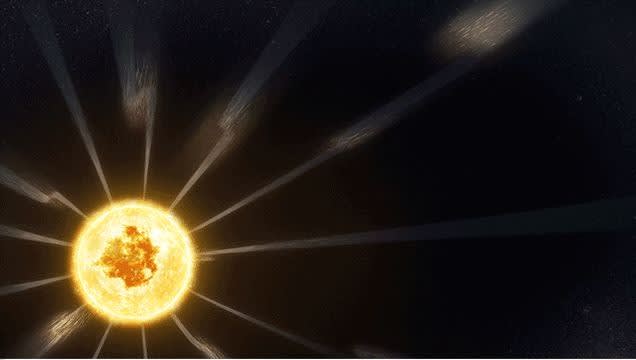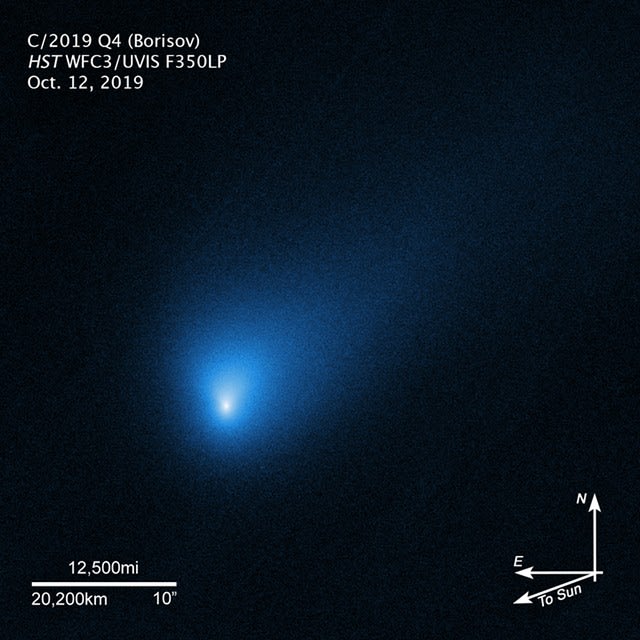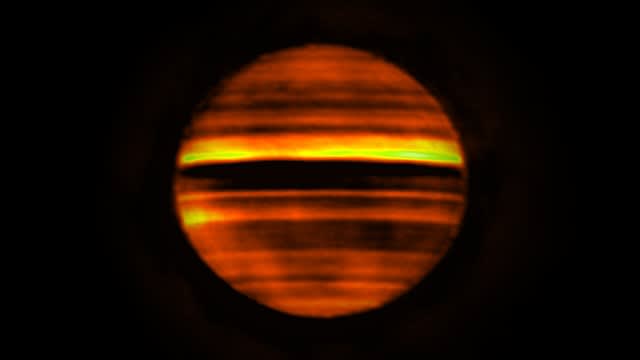火星への小天体衝突で衛星「フォボス」に物質が運ばれる現象のシミュレーション研究から、フォボスには従来の見積もりの10倍以上の火星表層物質が混ざっていることが示された。
【2020年1月17日 東京工業大学】
日本は「はやぶさ2」に続く次世代サンプルリターン計画として、火星の衛星「フォボス」と「ダイモス」を対象とした火星衛星探査計画「Martian Moons eXploration; MMX」を進めている。2024年に探査機を打ち上げ、2029年に衛星のサンプルが地球に帰還する計画だ。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース
【2020年1月17日 東京工業大学】
日本は「はやぶさ2」に続く次世代サンプルリターン計画として、火星の衛星「フォボス」と「ダイモス」を対象とした火星衛星探査計画「Martian Moons eXploration; MMX」を進めている。2024年に探査機を打ち上げ、2029年に衛星のサンプルが地球に帰還する計画だ。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース