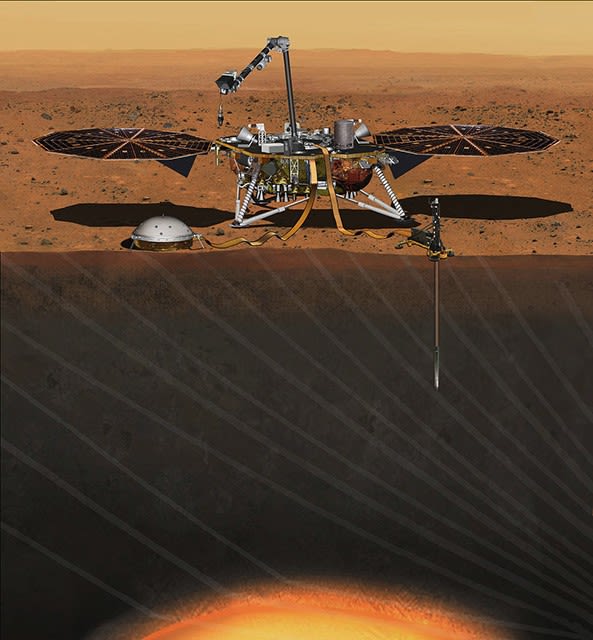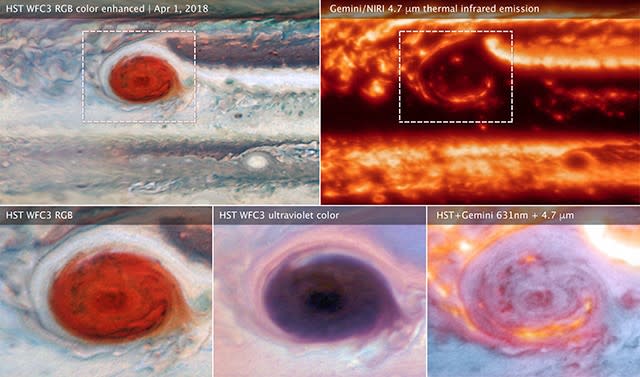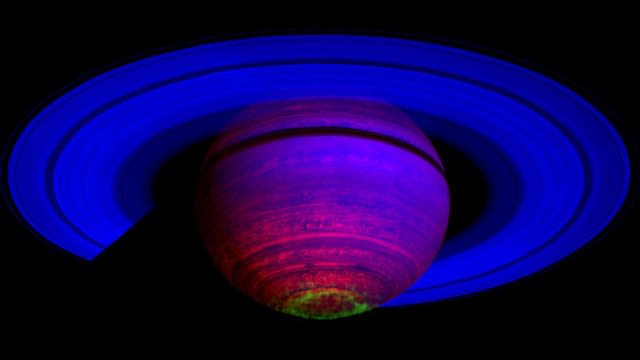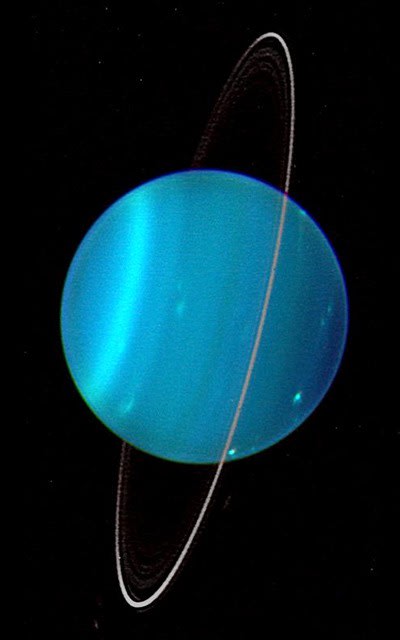「はやぶさ2」によるリュウグウ表面の温度データとモデル計算から、リュウグウの岩石は全球的にきわめてスカスカで凹凸が激しいことが裏付けられた。
【2020年7月3日 JAXAはやぶさ2プロジェクト】
「はやぶさ2」が小惑星リュウグウに到着して約1か月が経った2018年8月1日、「はやぶさ2」は高度5kmまで降下して、リュウグウの表面を中間赤外カメラで自転1周分、つまりリュウグウの丸1日(約7.6時間)にわたって連続観測した。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース
【2020年7月3日 JAXAはやぶさ2プロジェクト】
「はやぶさ2」が小惑星リュウグウに到着して約1か月が経った2018年8月1日、「はやぶさ2」は高度5kmまで降下して、リュウグウの表面を中間赤外カメラで自転1周分、つまりリュウグウの丸1日(約7.6時間)にわたって連続観測した。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース