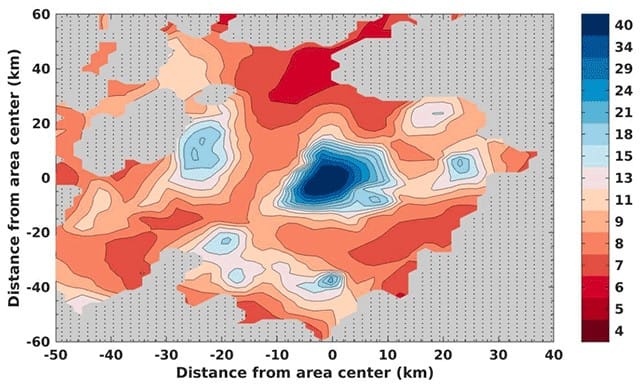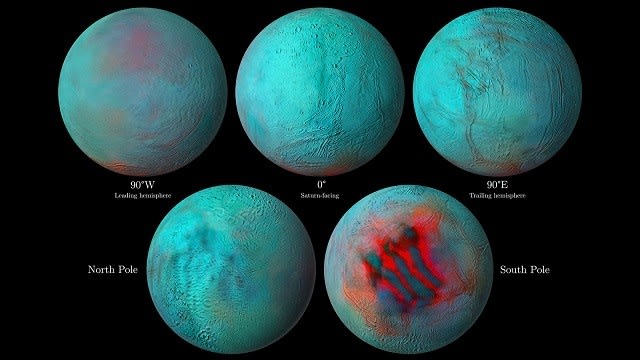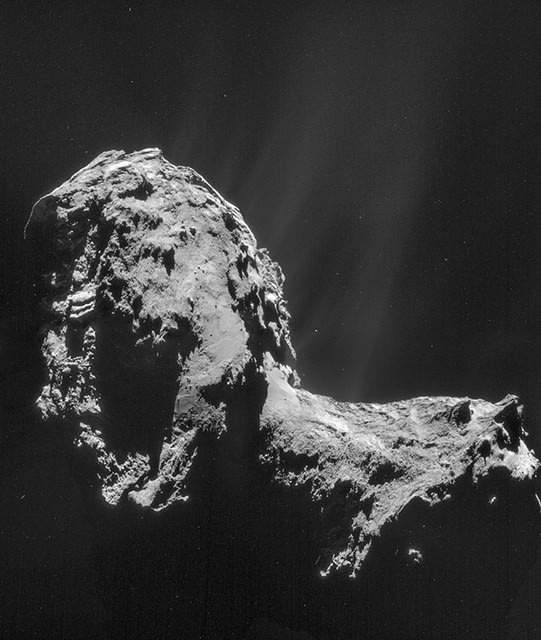太陽系の惑星が形成される最終段階において、水星には表面全体を削るほど小天体が降り注ぎ、揮発性元素を含む物質を供給した、と結論づける計算結果が発表された。
【2020年10月13日 東京工業大学地球生命研究所】
太陽系の惑星は、小さな塵が時間をかけて成長・集積を繰り返すことで形成されたと考えられている。約45億年前には惑星はすでに現在の大きさまで成長していたが、この時点では周囲にまだ小さな天体が多数残っていた。小天体は数億年かけて水星、金星、地球、火星に降り注いだとみられ、この過程は「後期集積」と呼ばれる。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース
【2020年10月13日 東京工業大学地球生命研究所】
太陽系の惑星は、小さな塵が時間をかけて成長・集積を繰り返すことで形成されたと考えられている。約45億年前には惑星はすでに現在の大きさまで成長していたが、この時点では周囲にまだ小さな天体が多数残っていた。小天体は数億年かけて水星、金星、地球、火星に降り注いだとみられ、この過程は「後期集積」と呼ばれる。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース