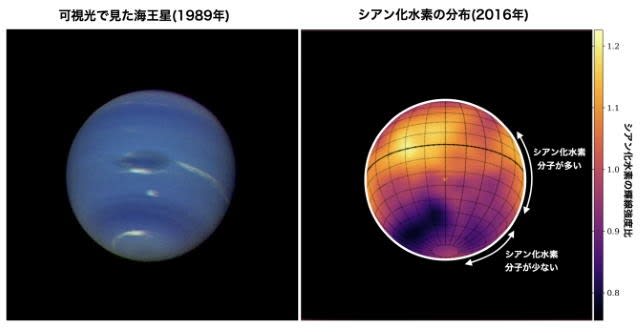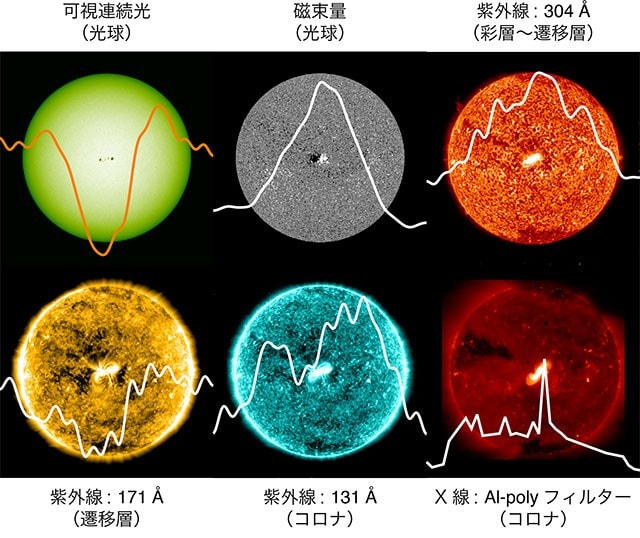太陽系形成に関する数値実験から、太陽系内の惑星が2つの異なるタイミングで形成されたとする新しい理論が提唱された。
【2021年1月27日 オックスフォード大学/バイロイト大学】
太陽系の惑星のうち地球や火星などは主に固形成分でできていて、木星や土星にガスや水などの蒸発しやすい物質が多く集まっている。従来、この差は単にどれだけ太陽に近い所で形成されたかの違いであると解釈されてきた。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース
【2021年1月27日 オックスフォード大学/バイロイト大学】
太陽系の惑星のうち地球や火星などは主に固形成分でできていて、木星や土星にガスや水などの蒸発しやすい物質が多く集まっている。従来、この差は単にどれだけ太陽に近い所で形成されたかの違いであると解釈されてきた。
----------------------------------------
アストロ天文ニュース