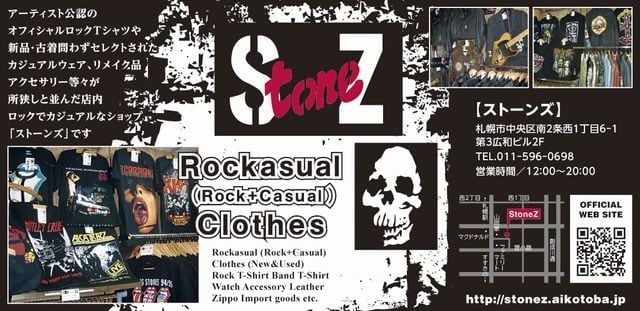↑ 「おすすめ ばん ばん!」 と 読みまして 私が ご推薦 する
CD や DVD を ご紹介 する コーナー です
さて 今回も 前 置き 無し で いきなり いっちゃいます(笑)
そんな 第七百一回目の 「お薦め 盤 Bang!」 は
「EURYTHMICS (ユーリズミックス)」 の
「Live 1983 ー 1989
(ライヴ 1983 ー 1989)」 です

リリースは 1993年 ...31年前 です ...(笑)
新しい ジャンル が チャート を 塗り替えて ブーム と なり
ロック は 死んだ ...と 思って しまった 私は
ブルース に はまり込んでいた 時代 でも ありました
ので ...ある お方が 絡んで おります(笑)
さて この 「ユーリズミックス」 と いう バンド
御存知の 方も いらっしゃる でしょうが
御存知 ない 方の 為に 簡単に ご説明 いたしますと
1980年に 結成 1981年に デビュー した
ヴォーカル : アニー・レノックス (左) と
ギター : デイヴ・スチュワート (右) に よる
イギリス の ロック ユニット です

スタジオ 盤の レコーディング 時の 打ち込み 等は
デイヴ・スチュワート が ほとんど 行い
ライヴ 含め 必要に 応じて サポート メンバー が
参加 する と いった 体制を 組まれて おりました
1981年の デビュー から 1989年 までの 間に
7枚の スタジオ 盤を 残し 1990年に 活動 停止
それぞれ ソロ で 活動 されました
(下段の 一番 右は 1991年 リリース の ベスト 盤)
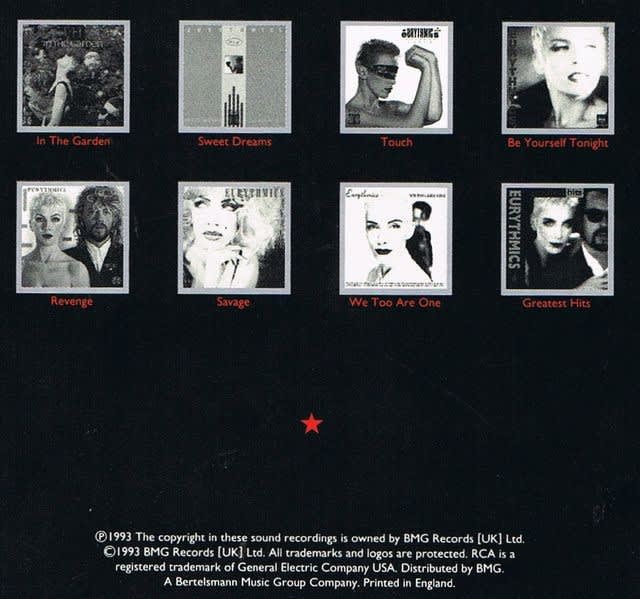
上手い
の 一言 では 片付けられない ヴォーカル
カッティング が やたら カッコ いい ギター
随所に 渡り アレンジ も いかしてる
イギリス 人 なのに かなり アメリカ っぽい
実は 好きな バンド (ユニット) でして
自分 らしい タイプ では ないので
こっそり 結構 聴いて おりました(笑)
そんな 私の 話は さておき(笑)
今回 ご紹介 させて いただいている アルバム は
その 活動 停止 (ソロ で 活動) 期間に
リリース された 公式 では ユニット 史上 初
且つ 唯一の ライヴ 盤 でして
1983年 から 1989年 までの 間に
イギリス や アメリカ で 開催 された 公演の
様子を 収録 されて おります

サウンド 的 には ブリティッシュ ポップ ロック
ニュー ウェイヴ の 流れ では ありましたが
パンク ロック 等 とは 真逆に 位置 する ような
ブルー アイド ソウル (白人に よる 黒人 音楽) や
エレクトロ ポップ の 要素が 強く
加えて ディスコ / クラブ 等の ダンス フロア で 踊れる
更に 加えて 邦楽で 例えると シティ ポップ みたいな
都会 的で 洗練 された 楽曲が 多く
ドラム の ビート や ベース ライン や キーボード の 旋律や
ギター の フレーズ の センス が 際立っており
リズム アンド ブルース や ソウル の 影響を 感じる
ヴォーカル が 見事に 調和 した ナンバー が 続きます

上の 写真の 12曲目 ディスク 2 の 1曲目
私の 中 では ” ♪ チョメ チョメ エンジェル ♪ ” (笑)
特に 好きな 曲 でしたが
スタジオ 盤 では フェイド アウト でしたので
へぇ~ ライヴ では こう 終わるんだ?
と ちょっと 感動 しました(笑)
先程の 写真の 22曲に 加え
冒頭の 表 ジャケット の 写真に
小さく 記載 されて おりましたが
6曲 (アコースティック ナンバー 集) 入り の
3枚組を 今回 聴かせて いただきまして
ユニット (バンド) の 素晴らしさ に 浸れました
「ユーリズミックス」 は ライヴ でも すごかったんですね
そして やっぱり 1980年代の ロック が
私は 好き なんですね と 思えた 音源 集
そんな この アルバム は 私の お薦め 盤 です

とは 言い つつ
私は この アルバム を 聴いた 事が 無かったのですが
(1980年代の スタジオ 盤は 所有 していて
引っ張り出して 聴き 直しました・笑)
こう いった アーティスト や アルバム に お詳しい 方が
いらっしゃいまして ...(笑)
「二階堂 一族」 ...ついに 4人目の 登場と なった(笑)
” よっちゃん ” の お蔭で 聴く 機会に 恵まれました
(一番 左に お持ち です)

” よっちゃん ” も 今回 更に 5枚 お持ち に なられまして
ネタ の ご提供と 言い つつ この 67枚目も
” ロック を 語る うえ では 聴いておけ ”
な アルバム でした ありがとう ございます
(ご本人は とても 謙遜 されて おりますが・笑)
この 機会を 逃すと 一生 聴けなかった かも しれないのですが
この コーナー や 私の 発言 から 的確な チョイス ...
さすが 「二階堂 一族」 恐るべし ...です(笑)。
「StoneZ」 インスタグラム は こちら
「StoneZ」 オフィシャル ウェブ サイト は 下の バナー から
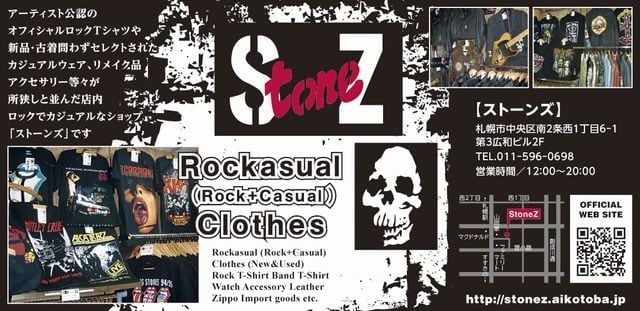
CD や DVD を ご紹介 する コーナー です
さて 今回も 前 置き 無し で いきなり いっちゃいます(笑)
そんな 第七百一回目の 「お薦め 盤 Bang!」 は
「EURYTHMICS (ユーリズミックス)」 の
「Live 1983 ー 1989
(ライヴ 1983 ー 1989)」 です

リリースは 1993年 ...31年前 です ...(笑)
新しい ジャンル が チャート を 塗り替えて ブーム と なり
ロック は 死んだ ...と 思って しまった 私は
ブルース に はまり込んでいた 時代 でも ありました
ので ...ある お方が 絡んで おります(笑)
さて この 「ユーリズミックス」 と いう バンド
御存知の 方も いらっしゃる でしょうが
御存知 ない 方の 為に 簡単に ご説明 いたしますと
1980年に 結成 1981年に デビュー した
ヴォーカル : アニー・レノックス (左) と
ギター : デイヴ・スチュワート (右) に よる
イギリス の ロック ユニット です

スタジオ 盤の レコーディング 時の 打ち込み 等は
デイヴ・スチュワート が ほとんど 行い
ライヴ 含め 必要に 応じて サポート メンバー が
参加 する と いった 体制を 組まれて おりました
1981年の デビュー から 1989年 までの 間に
7枚の スタジオ 盤を 残し 1990年に 活動 停止
それぞれ ソロ で 活動 されました
(下段の 一番 右は 1991年 リリース の ベスト 盤)
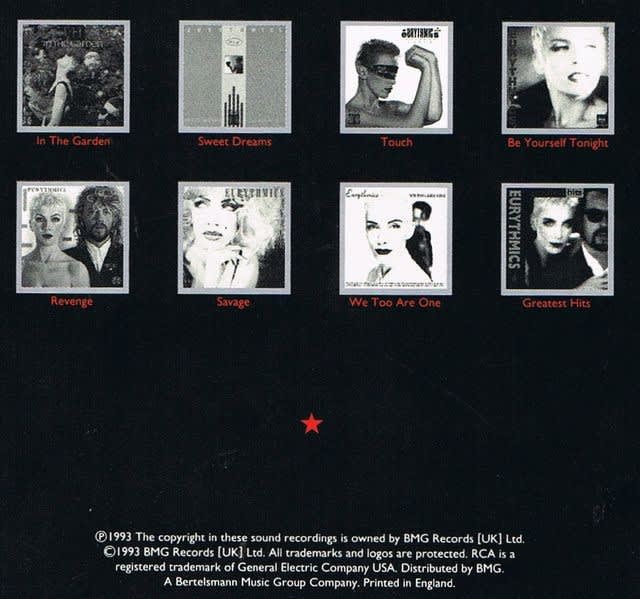
上手い
の 一言 では 片付けられない ヴォーカル
カッティング が やたら カッコ いい ギター
随所に 渡り アレンジ も いかしてる
イギリス 人 なのに かなり アメリカ っぽい
実は 好きな バンド (ユニット) でして
自分 らしい タイプ では ないので
こっそり 結構 聴いて おりました(笑)
そんな 私の 話は さておき(笑)
今回 ご紹介 させて いただいている アルバム は
その 活動 停止 (ソロ で 活動) 期間に
リリース された 公式 では ユニット 史上 初
且つ 唯一の ライヴ 盤 でして
1983年 から 1989年 までの 間に
イギリス や アメリカ で 開催 された 公演の
様子を 収録 されて おります

サウンド 的 には ブリティッシュ ポップ ロック
ニュー ウェイヴ の 流れ では ありましたが
パンク ロック 等 とは 真逆に 位置 する ような
ブルー アイド ソウル (白人に よる 黒人 音楽) や
エレクトロ ポップ の 要素が 強く
加えて ディスコ / クラブ 等の ダンス フロア で 踊れる
更に 加えて 邦楽で 例えると シティ ポップ みたいな
都会 的で 洗練 された 楽曲が 多く
ドラム の ビート や ベース ライン や キーボード の 旋律や
ギター の フレーズ の センス が 際立っており
リズム アンド ブルース や ソウル の 影響を 感じる
ヴォーカル が 見事に 調和 した ナンバー が 続きます

上の 写真の 12曲目 ディスク 2 の 1曲目
私の 中 では ” ♪ チョメ チョメ エンジェル ♪ ” (笑)
特に 好きな 曲 でしたが
スタジオ 盤 では フェイド アウト でしたので
へぇ~ ライヴ では こう 終わるんだ?
と ちょっと 感動 しました(笑)
先程の 写真の 22曲に 加え
冒頭の 表 ジャケット の 写真に
小さく 記載 されて おりましたが
6曲 (アコースティック ナンバー 集) 入り の
3枚組を 今回 聴かせて いただきまして
ユニット (バンド) の 素晴らしさ に 浸れました
「ユーリズミックス」 は ライヴ でも すごかったんですね
そして やっぱり 1980年代の ロック が
私は 好き なんですね と 思えた 音源 集
そんな この アルバム は 私の お薦め 盤 です

とは 言い つつ
私は この アルバム を 聴いた 事が 無かったのですが
(1980年代の スタジオ 盤は 所有 していて
引っ張り出して 聴き 直しました・笑)
こう いった アーティスト や アルバム に お詳しい 方が
いらっしゃいまして ...(笑)
「二階堂 一族」 ...ついに 4人目の 登場と なった(笑)
” よっちゃん ” の お蔭で 聴く 機会に 恵まれました
(一番 左に お持ち です)

” よっちゃん ” も 今回 更に 5枚 お持ち に なられまして
ネタ の ご提供と 言い つつ この 67枚目も
” ロック を 語る うえ では 聴いておけ ”
な アルバム でした ありがとう ございます
(ご本人は とても 謙遜 されて おりますが・笑)
この 機会を 逃すと 一生 聴けなかった かも しれないのですが
この コーナー や 私の 発言 から 的確な チョイス ...
さすが 「二階堂 一族」 恐るべし ...です(笑)。
「StoneZ」 インスタグラム は こちら
「StoneZ」 オフィシャル ウェブ サイト は 下の バナー から