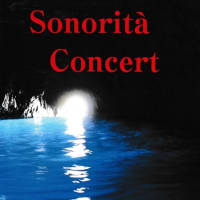こんにちは。
〜ピアノで心を育て、豊かな人生を〜
千葉県野田市の「せとピアノ教室」
講師の瀬戸喜美子です。
ご訪問ありがとうございます。
当教室は、千葉県庁認定【チーパス】協賛店舗のピアノ教室です。
千葉県野田市の「せとピアノ教室」
講師の瀬戸喜美子です。
ご訪問ありがとうございます。
当教室は、千葉県庁認定【チーパス】協賛店舗のピアノ教室です。
********************
今回は、タンバリンの持ち方・たたき方についてです。
タンバリンは
ヘッド(皮の貼ってある部分)
と呼ばれる部分と
ジングル(鈴の部分)
と呼ばれる部分からできています。
太鼓と鈴の両方の音を同時に出すことができます。
よく見ていただくと、木枠のところにひとつ穴があいています。
下の写真のように持つの、間違っていますよ!!

一昨年、リトミックの打楽器講習会を受講した時に、間違いだと知り、衝撃を受けました!!
先日のタンバリンのレッスンを受けた時にも(マリンバのレッスンの時に、ほかの小物楽器のたたき方も教えてもらっています)同じように教えていただきました。
じゃあこの穴は何のためなの?
はい!この穴は、手で持つことができない時にスタンドに取り付けるための穴なんですって!
手で持つときは、この部分にはジングルがありませんからここを写真のように持ちます。

親指は皮の端っこに乗せて、あとの4本の指で木枠をつかんでいます。
ヘッドをたたくと太鼓の音に。
手を広げて手のひらでたたくのではなく、指を立てて、ピアノを弾くような手にし、5本の指の腹でたたきます。
ヘッドに指を押し付けてしまっては音は止まってしまうので、たたいた瞬間に指を離します。
その時、タンバリンのヘッドは、床と平行になるように持っています。(上の写真参照)
小さな音がほしい時は、ヘッドを触っている持ち手の反対側の端っこを、たたきます。その時、たたく指は4本くっついてその裏側を親指が支えてる形です。

鈴の音がほしいときは、タンバリンを垂直に持ち、持ち手の手首のみを振る、あるいは、肘を揺らす、などのやり方があるそうです。
シンプルな楽器ですが、奥が深いです!
幼稚園・保育園の先生
小学校の先生
音楽教室の先生