
赤井羽根共同募金でビデオ化されたアニメーションの原作です。赤い羽根のタイトルは「ふしぎな電信柱」。原作では「古い電信柱のある町」でした。原作はアニメーションと違い、いわゆる教育的・合目的の色は薄くなっています。
古い電信柱のある町
作:佐賀由彦
1 霧の朝
静かで白い、夏の朝だった。ぼんやりとした灯りがキーコキーコとすれ違う。自転車なのだろう。朝の色に溶け込むような白い箱の中で「ミャー」と、か細い声がふるえた。その箱を運ぶ細い腕に、ポタリとしずくが落ちた。裕司の眼からあふれ出た涙だった。
「やっぱり家では飼えないわ」
昨日の夜のお母さんの声はやさしかったが、きっぱりとした響きに満ちていた。
一晩だけ、裕司は拾ってきたまっ白な子猫と一緒に過ごし、別れの朝がやってきた。子猫は、ペチャペチャとおいしそうにミルクをなめた後、白い箱のベッドにクルリと丸まった。裕司は半分だけ食パンを食べ、ベッドにふたをして靴をはいた。いつもなら、「きちんと食べなさい」と言うお母さんだったが、この日の朝は、「とても濃い霧ですよ。一人で大丈夫?」と控えめに声をかけただけだった。
「うん」
それ以上、言葉を続けることはできなかった。「いってきます」と元気よく言うつもりだったけど、世の中、そんなにかっこよく振るまえるわけはないのだった。
いつもなら五分もかからない道のりも、なぜだか二十分もかかってしまったのは、濃い霧のせいだけとは思えなかった。たどり着いたのは、昨日の夕方に子猫を拾った場所。そこには、木でできた古い電信柱が立っていた。
家々に電気を運ぶ電線は、もはやかかっていない。てっぺん近くにある街灯から薄白い光がもれている。そのための電線が一本だけかかっているはずだけど、霧が電線を消し込んでいた。電信柱にはツタがからみつきながら伸びている。寂しそうな電信柱の立ち姿、弱々しい街灯の光。それにくらべてツタだけは元気一杯で、もうすぐ街灯に届きそうな勢いだ。
裕司はツタの根をかきわけながら、電信柱の足元に白い箱をそっと置いた。箱の中から、「ミャー、ミャー」と声がする。でも、ふたを開けることなんて、とてもできなかった。
胸のポケットから折りたたんだ紙を取り出し、ていねいに広げた。背伸びをしながら、ツタの葉っぱを傷つけないように、用意してきた画びょうで電信柱に紙を留めた。紙は、昨日電信柱に貼りつけられていたものだった。
「とてもかわいい子猫です。お願いです。もらってください、育ててください」
紙にはそう書かれていた。昨日の夜、裕司は新しい言葉を探したけれど、何度もなんども紙に書いてみたけれど、昨日の紙よりもマシな言葉は見つからなかった。「コンクリートの電信柱だったら、画びょうで留めることなんてできないだろうな」なんて考えていたら、とても悲しそうな、年を取った男の人の声が聞こえてきた。
「ダメだったんだね」
裕司は、五十センチも垂直跳びをしたほど驚いた。あわてて振り向いたけれど、だれもいなかった。おそるおそる電信柱の後ろを見たけれど、やっぱりだれもいるはずがなかった。声は、電信柱の上のほうからしたようだった。口をあんぐり開けながら見上げてみても、霧の向こうに弱々しい街灯の光が見えるだけだった。足元の小さな箱をあわてて開けた。「こういうのをパニックというんだよな」と裕司は、何日か後で自分の行動を振り返ってみることができたが、その時は、白い箱を開けるぐらいしか思いつかなかったのだ。もちろん箱の中には子猫がいて、訴えるような眼で、「ミャー」と鳴いた。その声は震えているような心細げな響きだった。震えたいのは自分のほうだと裕司は思った。
「ここだよ、ここ」
声は、箱をのぞく頭の後ろから聞こえてきた。泣き出したいくらいに怖かった。
「ほら、上を向いてごらん」
怖いけど温かなその声は、「私は、電信柱だよ」と続けた。
「な~んだ、電信柱さんか」
腰を伸ばしながら声の主を見上げた後、今度は、自分の言った言葉のとんでもなさに、垂直跳び六十センチの驚きがおそってきた。
「ウソでしょう」
腰がくだけてへたり込む裕司のひざに、子猫がぴょこりと飛び乗った。
「ハハハ、驚かせたようだね」
「………」
「子猫君も、お目覚めだね」
「ニャー、ミャー」
「そうか、君は赤ちゃんだから、まだ言葉がしゃべれないんだね」
「ミャー、ニャー」
電信柱が話すたびに街灯がパカパカとまたたく。それだけでも驚きなのに、何と子猫と話が通じているようなのだ。気絶なんてテレビの世界だけのことだとも思っていた裕司だったが、気絶をするのはきっとこんな時なのだろうなと感じたのでもあった。しかし、小学校5年になるまで一度も気絶をしたことのなかった裕司は、やっぱり気絶はしなかった。
「裕司君、しっかりしなさい。男の子だろう」
「は、はい」
おもわず応える裕司は、このおかしな世界にしばらく身をまかせることにした。
「あの~」
どこを向いてしゃべればいいのか、本当はわからなかったが、子猫がそうしているように、とりあえず街灯に視線を向けてみようと思った。すると、木の節目や傷が目や鼻や口にも見えてくる。裕司はごくりと唾を飲み込み切り出した。
「どういうことなんでしょうか?」
「どういうことって、こういうことさ」
「こういうことって?」
「電信柱の私が話をして、その話が君にも、子猫君にもわかるってことだよ」
「はい、それはわかります。でも、それって……」
「ありえないとでも言うのかな?」
「常識的にはそうですけど……」
「では、いまここで起こっていることは?」
霧が薄くなってきた。鳥のさえずりがチュンと聞こえる。
「……うむ。ありえています」
「大切なのは、現実にどう向かい合っていくかということ」
裕司は電信柱に圧倒されていた。
「君にとって、今解決しなければならない問題はなんだろうね」
「う~ん」
「このおかしな世界から逃げ出すこと?」
「はっ、はい」
「それもいいけど、子猫君はどうする」
子猫が、ゴロゴロと喉を鳴らして、裕司の手を舐める。「そうだ、この小さな生命を自分が握っているのだ」と思った。
「だけど、自分の家では飼うことができないんです」
「だから、ここに置いていくのかい?」
「えぇ、拾う前と同じように」
「では、聞こう。君はどんな気持ちで子猫を家に連れていったんだい?」
「……かわいそうだから」
「そうだよね。君はとても心のやさしい子だからね」
電信柱は、そう言うと突然6年前のできごとを話し始めた。それは裕司が幼稚園に通っていたころの夏の日に起こった事件だった。
2 六年前
もうすぐ夏休み。裕司たちは毎日、幼稚園からいろいろなものを持ち帰っていた。その日はクレヨンを持って帰る日で、何かにラクガキしたくて、みんなウズウズしていたものだった。
裕司は、アキラとヒデキと一緒だった。アキラが「アレ!」と指さし言った。指の先には電信柱。ヒデキが「ウン」とうなずいた。裕司は最初、二人のアイコンタクトの意味がわからなかったが、アキラとヒデキが同時にクレヨンの箱を通園バックから抜き出したとたんに、二人が今からとても悪いことをしようとしているのだとわかった。でも、「ダメだよ」と裕司は言えなかった。そのころの電信柱は、今のようにツタに包まれてなかったと思うが、二人がラクガキを始めるのをだまって見ているだけだった。
暑い日だった。セミがジャージャー鳴いていた。アキラもヒデキもモクモクとラクガキをする。もし呼ばれたらどうしただろう。止めようとしたけど、やっぱり「やめなよ」の一言が言えず、「用があるから先に帰る」と言い残して、裕司はその場を離れた。もちろん、二人のイタズラを親や先生に言いつけたりはしなかったし、それからも三人は仲よしでいつづけた。
「思い出したかい?」
「ウン、あのときは、二人を止められなくてごめんなさい」と裕司は頭を下げた。
あの日、裕司は家に帰ると荷物を置いて、すぐに電信柱のところに引き返した。「やっぱりラクガキはいけないことだ」と思ったからだ。でも二人はもういなかった。電信柱のお腹のあたりには、サメやタコやサカナたちの絵が描かれていた。下手くそな絵だった。
裕司は走り寄って、電信柱に「ごめんなさい」とあやまった。ポケットからハンカチを出して、クレヨンを落とそうとしたけど、電信柱の肌は思いのほかデコボコで、ほとんど落ちなかった。
「あの時トゲがささらなかったかい?」
「忘れました。でもごめんなさい」
「あやまるのは、一度だけでいいんだよ。それに、君はあのとき、自分ができる精いっぱいのことをやったんじゃないかな」
「そうかなあ」
「そうさ。先生にしかられるからラクガキをしなかったのかな?」
「………」
「じゃあ、先生がしからなかったら、ラクガキをしたかな?」
裕司は首を大きく振った。
「それでいいんだよ」
3 霧の終わり
霧は一段と薄くなってきた。空も明るくなっていきた。まもなく晴れそうだ。
「じゃあ、子猫の話に戻ろうか」
裕司が子猫に目をやると、腕の中ですやすやと眠っていた。
「君はさっき、かわいそうだからと言ったね」
「だれからも拾われなければ、きっと死んじゃうと思ったから」
「では、聞こう。君のお母さんは、なぜ猫を飼えないといったのかな?」
「お父さんが猫アレルギーだから。でも、でも今はたんしんふにんというやつで、家にいないんです」
「つまり、お父さんが帰って来るまでは飼えるかもしれないと思ったわけだね」
コクリと裕司はうなずいた。
「でも、お母さんはダメだと言った」
「じょうがうつるからだって……」
「どんな意味かわかるかい?」
「はい何となく。一緒にいると子猫のことがますます好きになって、別れるのがとてもつらくなるのだと思います」
「そのとおり。やさしいお母さんだね」
風がピューと吹いてきた。
「お、おっといけない」
電信柱があわてた声を出す。
「君と話ができるのは、霧に包まれたときだけなんだ。子猫のことは何とかしよう。最後に一つ質問。もし、かわいそうな猫が子猫じゃなくて、よれよれの老いぼれ猫なら、君は拾っていっただろうか。よ~く考えていつか教えてください」
「あの、子猫は……」
「何とかすると言ったよ」
そう言うか言わないうちに、街灯が電信柱を支点にしてグルンと一回転した。するとどこからか大きな三毛猫が現れて、電信柱を忍者のように登っていく。てっぺんまでたどり着くと、背伸びするようにして「ニャオーン」と鳴いた。
「木の電信柱だから登れるんだ」
などと感心していると、三毛猫が飛ぶように降りてきて、裕司の前にピタリと座った。三毛猫とは言葉を交わすことができなかったが、「その子猫を私によこしなさい」と言っているのだと感じた。裕司は、ためらわずに子猫を差し出すと、三毛猫は立ち上がって、パクリと首を加え、電信柱の奧の草むらへと入っていった。さよならも言えなかったと裕司は思ったが、それでいいような気もした。
一匹、二匹、三匹……五匹。猫たちが次々に現れて、三毛猫と子猫が向かった草むらに吸い込まれていった。
「ははん、ネコ会議だな」
裕司も一緒に参加したかったが、「何とかすると言ったよ」の電信柱の言葉を信頼することにした。
「お願いします」
裕司は見えない猫たちに深くお辞儀をした。
「お願いします」
今は口をきかなくなった電信柱にも深くお辞儀をした。霧はすっかり晴れ、街灯の光は消えていた。
4 ネコ会議
電信柱が見下ろす草むらのなかの小さな広場でネコ会議は始まった。議長は三毛猫。出席者は議長と子猫を含めて七匹の猫。電信柱は猫ではないので、見ているだけの参加となった。議題は、「子猫の幸せを考える」である。
会議に先立ち、議長から今までのできごとついての次のような説明があった。
・子猫は、昨日の朝、電信柱の足元に人間により捨てられたこと。
・それは、親猫の意思を無視した身勝手な行いであること。
・目撃した電信柱の話によると、元の飼い主はこの町の住人ではないということ。
・昨日の夕方、一時的な避難先として期待ができる少年に引き取られたが、家庭の事情により本日の朝、元の捨て場所に戻されたこと。
・少年に好意を抱く電信柱の願いでこの会議を開くことになったこと。
・子猫は、会議の出席者を招き集めた議長(三毛猫)が緊急保護を行ったこと。
この説明を受けて、自由に意見を出し合うことにした。
最初に発言したのは、飼い猫のポン太だ。ポン太はタヌキのようなお腹をノッシノッシとさせながら言った。
「やはり、やさしい飼い主を探すのが、一番でしょうな。お腹を空かせて餌を探す苦労もなく、厳しい冬も寒さに震えることなく、雨の日も濡れることない。猫の幸せは飼い主しだいともいえます。もちろん私は幸せですよ」
やせ猫のガリ平は野良猫だ。ポン太を「飼い猫はいいねえ」とうらやましがる。
これに反発したのは、野良猫のゴン助だ。
「野良猫ほこりはどうしたんだ」
ゴン助は、今度はポン太をにらみをきかせ、みんなにむかって演説を始めた。
「ブクブクと肥ることが猫の幸せなのでしょうか」
ポン太の顔が真っ赤になった。といっても猫の顔色は毛で見えないのだが、眼が三角につり上がったから、きっと毛並みの下は真っ赤になったはずだ。だが、ゴン助はそんなことはおかまいなく続けた。
「猫の運命を、猫の幸せや不幸せを、いや、時には猫の命までを人間たちに握られていていいのでしょうか」
この演説に、飼い猫のタマ子が拍手をおくる。
「そうだわ、飼い主の顔色をうかがう毎日にはウンザリだわ」
ガリ平が、「そうだ。野良猫のほこりは大切だ」とコロリと意見を変えた。
その時、ガリ平のお腹がグウとなる。今度はポン太の反撃だ。
「でも、お腹を空かしては、考え方も貧しくなってしまいます。人間の眼を盗んで魚をドロボウする生き方が、果たして上等なのでしょうか」
カラスが電信柱のてっぺんにとまり、「カァ」と鳴いた。ポン太がお腹を突き出しながら電柱を見上げる。
「ゴミをあさり、人間たちの弁当をかすめ取り、結局は人間たちに嫌われるようになった、あの鳥のようになりたいのですか?」
ゴン助が反論する。
「でも、カラスは自由です。私たちは、自由なこころを捨ててまで、楽な生き方を選び取っていいのでしょうか」
「そうよ、自由は大切よ」とタマ子が言えば、「でも、ぼくたちにカラスのような羽はないし、それにお腹が減るのもつらいし」とガリ平が悩む。
ネコ会議は、「子猫の幸せを考える」はずだったのだが、その前に、「猫の幸せ」「人間とのつき合い方」「自由なこころとは何か」など、とても難しい議論へと進んでいった。
会議が進む。先ほどまで会議を見ていたカラスもいつの間にかいなくなった。参加者たちも疲れてきた。でも、こんな時が危ない。つまり、疲れてくると、何でもよくなって、かんたんな話やいせいのいい話に人気が集まるのだ。この会議でも、「人間との対決もやむなし」という危険な意見が大きな声となってくる。対決は、ケンカや戦争にもつながって、勝っても負けてもとても嫌なものなのだ。そして、お互いの滅びの道へとつながっていく。
さて、多くの場合、こうした危ない場面を救うのはお年寄りの意見だ。だって、お年寄りたちは、長く生きてきていろいろなことを知っているからだ。会議に参加していた長老猫のトラ爺(じい)がポツリといった。
「共に生きる道を探したいものじゃのう」
共に生きる道、つまり、猫と人間が仲よく手を取り合って生きる道である。
「猫には羽がないとだれかが言ったが、猫にはまだまだ自由がある。他のペットや家畜ようにクサリにつながれてもいないしオリにも入れられていない。自由に外出できる飼い猫だって多い。ヘイを飛び越え、カベをよじ登り、私たちは自由にどこにでも出かけられる」
他の猫たちも、電信柱も、トラ爺の話を熱心に聞いている。
「だがのう、今ある私たちの自由は、猫の先輩たちが築き上げてきたものだということを忘れてはならぬ」
「私たちは、人間たちが嫌がるネズミをとりつづけて来たわ」
口をはさんだのは、タマ子だった。
「寒いときはコタツの代わりにもなった」
飼い猫のポン太がそう続ける。
「でも、ゴロゴロと喉を鳴らしてまつわりつく姿はとても見ていられない」
とゴン助が言えば、「だって、とてもうれしそうな顔をして喜んでくれるんだもの」とタマ子が返す。
トラ爺が、「そう、互いに喜び合うことが大切なんじゃ」と言う。
「魚をちょっとだけくすねたこともはあっても、爪で少しだけひっかき傷をつけることはあっても、少なくとも私たちは人間にそれ以上の大きな害を与えなかった。そればかりか、ネズミをとり、温かさを届け、アイキョウを振りまいて人間たちのこころにやすらぎを与えてきた。それは人間たちの喜びとなり、その引きかえに私たちは自由を約束されてきたのじゃ」
トラ爺の重みある言葉に、参加者たちはみな、「なるほど」とうなずいた。
「俺は、これから先も飼い猫にはならないけど、飼い猫にも自由の道は残されていそうだな。何と言っても自由こそが猫のほこりだからな」
ゴン助の言葉に、「そう、どんな生き方をしたって自由はある」とトラ爺は応える。
「飼い猫になっても、野良猫になっても、自分で自由に考え、自由に行動ができるようにすることが大切なのね」
とタマ子は続ける。
「ぼくも、なんだか飼い猫になりたくなったけど、まあ、そんなことより、この子猫がそんな大人になるまで、守ってやろうよ」
ガリ平の発言に、ポン太が付け加える。
「そのために、自分たちになにができるか、知恵を出し合おうよ」
それからの会議は、とてもスムーズに進んだ。
議長の三毛猫は、子猫を毛づくろいしながら、他の猫たちの発言を楽しそうに聞いている。
飼い猫で太っちょのポン太は、「子猫の飼い主が見つかるまで、自分の食事の一部を子猫に分ける」と約束した。
同じく飼い猫のタマ子は、「それはダイエットにとてもいいわ」と感想を述べた後、「私は、人間に愛されるつき合い方を教えてあげる」と提案した。
野良猫のゴン助は、「子猫の安全をおびやかす悪者をやっつけるとともに、自分の冒険談を話して聞かせたい」と言った。
ガリ平は、「野良猫だからこそ気づくこの町の危険な場所を教えていきたい」と語り、「危ないことを知ってこそ、本当に自由でのびのびとした行動ができるのだ」と付け加えた。
ドラ爺は、「困った時は、いつでも相談においで」と子猫にやさしく語りかけた。三毛猫の議長は、参加者に「ありがとう」とお礼を言った後、「この子猫にできるだけステキな飼い主が見つかるように努力し、もし、飼い主が見つからなくても、ほこりを失わない自由猫になるように育てたい」とホウフを述べた。
何も言わない電信柱であったが、とても満足そうな表情のように見えた。
子猫が「ミャー」と鳴き、ポン太が「これ、ぼくのオヤツだけど」と首に下げていた袋からクッキーをさしだし、会議は終わった。
5 悲しい知らせ
ネコ会議がたけなわのころ、裕司は家に帰ってきた。白い子猫を白い箱に入れて電信柱の足元に戻しに行ったときの悲しい気持ちは、すっかり晴れた霧のようになくなっていた。
お母さんは、庭の花壇の手入れをしていた。手を止めて裕司の顔を見たお母さんは、裕司の気持ちに起こった変化がわかったのに違いない。にっこりと微笑むと、「おかえり」とこころを込めて言った。
「霧、晴れたわね」
裕司は、お母さんに霧の中で起こった不思議なできごとを話したいと思った。
「町はずれにある電信柱知ってる?」
「ええ、木でできた電信柱でしょう」
「そ、その電信柱とね、ぼく、いろいろなお話をしたんだ」
「あら、それはすごいわね。どんなお話をしたか聞かせてちょうだい」
でもお母さんは、「お話だけじゃなくて、ほら、そこの土を持ってきてくれない」とか、「この花を植え替えるから、根っこの土をやさしくほぐしてちょうだい」とか、いろいろとお手伝いをさせようとする。こんなすごい話を、お手伝いをしながらするのはちょっとイヤだったけど、裕司は、がまんすることにした。
霧の中で見た電信柱にツタが巻きついていたこと、ツタの葉っぱを傷つけないように「とてもかわいい子猫です」と書かれた紙を貼ったこと、木の電信柱だから紙が画びょうで留められたこと、その時に、「ダメだったんだね」ととても年を取った男の人の声が聞こえてきて、それが電信柱の声だったこと……。
裕司は、今朝のできごとを一つ残らず話していった。でも、6年前のクレヨン事件をお母さん教えていいかどうかはちょっと迷った。だって、アキラとヒデキのイタズラは親にも先生にもヒミツにしていたことだったからだ。だけど、そこを飛ばすと電信柱と自分の関係がうまくお母さんに伝わらないと思った。裕司は、二人のラクガキに加わらなかったこと、ラクガキのことはだれにも言わなかったこと、後で二人のラクガキを止められなかったことを電信柱にあやまったことなどをお母さんに思い切って打ち明けた。
「電信柱さんがね、君は精いっぱいのことをやったんじゃないかなと言ってくれたよ」と話したとき、お母さんは、スコップを動かす手を止めて、「よかったね」と言ってくれた。裕司は、とてもうれしかった。
つづいて、猫が飼えない理由を電信柱から聞かれて、その理由を応えると、「やさしいお母さんだね」と電信柱が言ってくれたことも報告した。お母さんは、その時は、「そう」と言っただけで、モクモクとスコップを動かしていた。
「それでね、霧が晴れてきたんだ。電信柱さんがお話できるのは、霧があるときだけでね、電信柱さんは少しだけあわてた感じで、子猫のことは何とかしようと言っていれたんだ」
お母さんは、もう一度スコップの手を止めて、「よかったね」と言った。
「でも、宿題があるんだ」
「何かしら?」
「子猫がよれよれの老いぼれ猫なら拾っていったかなって聞かれたんだ。お母さんはどう思うかしら」
「それは、裕司君への質問でしょう?」
「うん」
「とてもすばらしい質問だから、ゆっくり考えるといいわ。でも……」
お母さんの「でも」と言って黙ってしまった。
「でも、どうしたの?」
「………」
裕司の目をまっすぐに見つめて、お母さんは言った。
「町はずれの電信柱さんだけど、もうすぐてっきょされるかもしれないの」
「てっきょ? えっ? どういうこと?」
お母さんの言葉の意味が、裕司にはわからなかった。でも、あまり嬉しくないような気もした。
「てっきょって、取り去ること。つまり、電信柱さんがなくなるってこと」
「そんなのだめだ」
「電信柱さんは、とても古くなって、それと、あの土地は公園に生まれ変わるらしいのよ」
「うそでしょう。せっかく仲よくなれたのに」
裕司は、ネコ会議のために猫たちが集まったことをお母さんに話すことはもうできなかった。子猫ばかりか、電信柱さんともお別れしなくてはならないなんて……。霧の晴れたまぶしい太陽の下で、裕司はとても悲しい気持ちになったのだった。
6 電信柱とおばあさん
電信柱にぶっつかった経験のない人なんているんだろうか。友だちと話していてガーン、よそ見をしていてドシーン、自転車の乗っていてぶっつかった人もいるだろう。時々だけど、車が突っ込んでいることもある。そんな電信柱だけど、電信柱があるから電気が使えて、電話で話すことができる。暗い夜の道を電信柱の街灯が明るく照らしてくれる。電信柱の間に張られた電線がたこ揚げにじゃまだったり、お祭りのダシと呼ばれる大きな車を動かすのに電線を持ち上げたりしなくてはならないけど、電信柱のおかげで、テレビを見ることができて、冷蔵庫でジュースを冷やすことができて、冬はコタツ、夏はエアコンを使うことができるんだ。もちろん、夜、勉強をしなくてはならないのも、電気を電信柱と電線が運んでくるからなんだけど……。
そんな電信柱も時代が進むに連れ、木製からコンクリート製にかわり、都会や観光地などでは、町の景観をだいなしにするじゃまものとして、電信柱をなくし、電線や電話線を地下に埋めようとする動きも広まってきた。
裕司の町では、電線を地下に埋めるのはまだまだ先のことのようだけど、さすがに木の電信柱は、町はずれのあの電信柱だけになっていた。ふつう木の電信柱は、十五年くらいで新しいものと取り替えられるらしい。だけど、あの電信柱だけは、六十年以上もあの場所に立っているのだという。なんでも、とっくの昔に電気を運ぶ電線をかける役目を終えたのと、付近では、あの電信柱だけに電灯がついていたため、街灯として残されたのだ。でも最後まで残ったその役目も、まもなく終わろうとしている。
「三毛猫が忍者のように駆け上がり、ネコ会議の開催を告げることはもうできない」
裕司は、そんなことを考えているうちにいつしか電信柱の立っている場所に来ていた。霧はかかっていなかった。
光の消えた街灯、物言わぬ電信柱、その足元に一人のおばあさんが立っている。おばあさんは、白い子猫を大事そうに抱え、小さな頭をヨシヨシとなでている。その横のほうに目をやると、大人の猫たちがおばあさんと子猫のようすを眺めている。猫たちの中に、あの三毛猫もいた。少し前の経験だったけど、とてもなつかしことのような気がした。一歩進み出た裕司に、おばあさんが気づいた。
「ほら、かわいい子猫でしょう」
おばあさんが、子猫を裕司に見せた。
「うん、知ってるよ」
「そうかい。あの猫たちがね……」
おばあさんは、三毛猫たちのほうを指さした。
「あの猫たちが、子猫を守っていたんだよ」
今度は、三毛猫たちに向かって語りかける。
「猫さんたちや、私がこの子猫ちゃんを育ててもいいかしら?」
三毛猫たちは、互いに顔を見合わせ、電信柱とも合図を交わし(裕司にはそう見えた)、「ニャー」と言った。それは、オーケーの返事だと、裕司は思った。
「ありがとうよ」
おばあさんは、猫たちにちょこんと頭を下げ、裕司に向き直った。
「坊やも猫の気持ちがわかるようだね」
小学校五年生の裕司は、「坊や」と呼ばれるのはちょっとイヤだったけど、「うん、何となくわかるような気がします」と返した。
「霧が晴れちゃったね」
その言葉の意味も裕司にはわかった。
「朝、ぼくここに来たんです」
「そうかい。霧が出ていたんだね。電信柱さんは、あのことを悲しんでいたかい」
「いいえ、てっきょの話はしませんでした。母に聞きました」
「おや、坊やはむつかしい言葉を知ってるんだね」
やっぱり「坊や」という呼び方はやめてもらいたい。裕司は、勇気を出して、「あの、ぼく小学校の高学年なので、坊やじゃなくて……」
「あら、そうだったね、お名前は?」
「裕司です」
「じゃあ、裕司君でいいわね。で、裕司君も悲しくなるとここに来るのかしら?」
確かに、今朝は悲しかったけど、ここに来たのは違う理由からだった。
「いいえ違います。おばあさんは、そうなんですか?」
手提げから風呂敷のようなものを出したおばあさんは、電信柱の足元にヒラリと広げ、「ヨッコイショ」と正座すると、裕司にも座るようにうながした。
「私はね、悲しいことがあるとここに来るのさ」
おばあさんはひとり暮らしだそうだ。毎年、夏休みになると孫たちが遊びにくるのだけど、今年の夏は海外旅行ににいくので遊びに来られないのだという。それが昨日わかったらしい。
「なぜ、悲しいと電信柱さんに会いに来るのですか?」
遠くを見るような目つきになりながら、おばあさんは亡くなったおじいさんのことを話し始めた。おじいさんは、十年前まで漁師をしていて、漁師の仕事の最後の日に、嵐にあってそのまま帰らなくなったらしい。そのおじいさんがまだ若いとき、若いころのおばあさんに向かって、「お嫁さんになってほしい」と打ち明けたのがこの電信柱の下だったのだという。
「ずっとずっと昔のことだけど、昨日のことのようにも思えるのさ。その後で、おじいさんは戦争に行くことになってね。おじいさんからの手紙が来るたびにここに来て、何度もなんども手紙を読んだものなのよ。だって、家にはおおぜい人がいて、とても一人きりになれるところがなかったもの」
そのころの街灯は、はだか電球だったという。
「手紙を広げるとね、なぜだか、電球がパッと明るくなってね。おじいさんが戦場でこころを込めて書いた文字がハッキリと浮かび上がったの」
おじいさんは、戦争が終わってもすぐに帰って来られず、シベリアというところに連れて行かれたらしい。三年たっておじいさんが帰ってくることが決まり、おばあさんはうれしくなって、電信柱の下に駆けつけ、「ありがとうございました」と深々と頭を下げたのだという。
「霧のかかった朝だったわね。そうしたらね、『よかったね』って、とてもやさしい声が聞こえるのさ」
「電信柱さんの声だったんだよね」
「そうさ坊や、いや、裕司君。人が生きていくには、うれしいことだけじゃなく、悲しいことだってある。そのときに、悲しい気持ちを受け止めてくれる人、私の場合は電信柱だったけど、そんなものがあると、何とか生きていくことができるんだよ。おじいさんが亡くなったときに、ひとりぼっちになった私をなぐさめてくれたのはこの電信柱なのさ」
おばあさんは、そう言いながら、そっと電信柱の木肌をなでた。
まだ小学生の裕司だったけど、おばあさんの言うことがわかるような気がした。でも、その電信柱はまもなくてっきょされてしまう。おばあさんには、そんな裕司の不安な気持ちをさっしたのか、ハッキリといった。
「この電信柱は、とてもおじいさんなのさ。だからもうすぐいなくなる。それはとても自然なことなんだよ」
裕司の悲しい気持ちはまだそのままだったけど、自分には話のわかるお母さんがいて、遠くに住んでいるけどお父さんがいるということを改めて思った。そして、いろんなヒミツを一緒に知っているおばあさんが新しい知り合いになったことで、なんとかこの悲しい気持ちを乗り越えられるような気もしてきた。
「あの~」
「なんだい」
「子猫に会いに、時々いってもいいですか?」
おばあさんはニッコリとうなずいてくれた。裕司は、おじいさんのこと、おばあさんのこと、電信柱のこと、そしてこの町のことを、もっともっと聞きたいと思った。それが、自分のためにも、おばあさんのためにも、とてもいいような気がした。もちろん、子猫のお世話も手伝うけれど……。
7 再び霧の朝
裕司は、霧の日を待った。電信柱にお別れが言いたかった。それと、電信柱からもらった宿題の答えも電信柱に教えなければならなかった。
一日が過ぎ、二日が過ぎ、一週間が過ぎ、やっと霧の朝がやってきた。霧が晴れないうちに、まだ薄暗い道を裕司は急いだ。
霧のかなたに、電信柱の街灯がうるんで見えた。
駆けつけた裕司は、「電信柱さん」と呼びかけた。
「霧の日を待っていてくれたようだね。子猫はおばあさんのもとで元気に暮らしているらしいよ」
電信柱はなんでも知っていた。裕司は、宿題の答えを切り出した。
「あの、この間の質問の答えなんですけど。一週間前だったらよれよれの老いぼれ猫はやっぱり拾わなかったような気がします。だけど……」
裕司は、大きく深呼吸して言った。
「今なら、老いぼれ猫を拾えるかもしれません」
「拾えると言い切らないところが、君らしいね。とてもいい答えだ」
それから裕司は、霧が晴れるまでいろいろなことを語り合った。その話の中身は、電信柱と裕司のヒミツだ。
そして、霧が晴れるとき、裕司は、「お別れですね」とちょっと気取って電信柱に言った。だって、涙を見せたくなかったから。
「ありがとう」
「こちらこそありがとう」
その言葉を最後に、風が霧を吹き飛ばした。
夏が終わるころ、電信柱がてっきょされると聞いたけど、裕司はそのようすを見にいかなかった。だって、お別れは済ませてきたのだから。その代わりに、おばあさんには時々会っている。
おばあさんの家には、猫たちも子猫の世話に入れ替わりやってくる。教育係、給食係、相談係、ボディーガード……、どうやら猫それぞれに役目があるらしい。裕司は、子猫の世話はもっぱら猫たちにまかせて、おばあさんの話にゆっくりと耳をかたむけることにした。
子猫や猫たちと散歩にもいく。お気に入りの場所は、かつて電信柱があったところ。秋が深まったころ、小さいけれど、とてもステキな公園ができ上がったのだ。
裕司は、公園のベンチに座り、おばあさんの話を聞くのが好きだった。ベンチには猫たち駆け上った爪のあとや、「とてもかわいい子猫です」と書かれた紙を貼りつけた画びょうのあとが残っていた。
古い電信柱のある町
作:佐賀由彦
1 霧の朝
静かで白い、夏の朝だった。ぼんやりとした灯りがキーコキーコとすれ違う。自転車なのだろう。朝の色に溶け込むような白い箱の中で「ミャー」と、か細い声がふるえた。その箱を運ぶ細い腕に、ポタリとしずくが落ちた。裕司の眼からあふれ出た涙だった。
「やっぱり家では飼えないわ」
昨日の夜のお母さんの声はやさしかったが、きっぱりとした響きに満ちていた。
一晩だけ、裕司は拾ってきたまっ白な子猫と一緒に過ごし、別れの朝がやってきた。子猫は、ペチャペチャとおいしそうにミルクをなめた後、白い箱のベッドにクルリと丸まった。裕司は半分だけ食パンを食べ、ベッドにふたをして靴をはいた。いつもなら、「きちんと食べなさい」と言うお母さんだったが、この日の朝は、「とても濃い霧ですよ。一人で大丈夫?」と控えめに声をかけただけだった。
「うん」
それ以上、言葉を続けることはできなかった。「いってきます」と元気よく言うつもりだったけど、世の中、そんなにかっこよく振るまえるわけはないのだった。
いつもなら五分もかからない道のりも、なぜだか二十分もかかってしまったのは、濃い霧のせいだけとは思えなかった。たどり着いたのは、昨日の夕方に子猫を拾った場所。そこには、木でできた古い電信柱が立っていた。
家々に電気を運ぶ電線は、もはやかかっていない。てっぺん近くにある街灯から薄白い光がもれている。そのための電線が一本だけかかっているはずだけど、霧が電線を消し込んでいた。電信柱にはツタがからみつきながら伸びている。寂しそうな電信柱の立ち姿、弱々しい街灯の光。それにくらべてツタだけは元気一杯で、もうすぐ街灯に届きそうな勢いだ。
裕司はツタの根をかきわけながら、電信柱の足元に白い箱をそっと置いた。箱の中から、「ミャー、ミャー」と声がする。でも、ふたを開けることなんて、とてもできなかった。
胸のポケットから折りたたんだ紙を取り出し、ていねいに広げた。背伸びをしながら、ツタの葉っぱを傷つけないように、用意してきた画びょうで電信柱に紙を留めた。紙は、昨日電信柱に貼りつけられていたものだった。
「とてもかわいい子猫です。お願いです。もらってください、育ててください」
紙にはそう書かれていた。昨日の夜、裕司は新しい言葉を探したけれど、何度もなんども紙に書いてみたけれど、昨日の紙よりもマシな言葉は見つからなかった。「コンクリートの電信柱だったら、画びょうで留めることなんてできないだろうな」なんて考えていたら、とても悲しそうな、年を取った男の人の声が聞こえてきた。
「ダメだったんだね」
裕司は、五十センチも垂直跳びをしたほど驚いた。あわてて振り向いたけれど、だれもいなかった。おそるおそる電信柱の後ろを見たけれど、やっぱりだれもいるはずがなかった。声は、電信柱の上のほうからしたようだった。口をあんぐり開けながら見上げてみても、霧の向こうに弱々しい街灯の光が見えるだけだった。足元の小さな箱をあわてて開けた。「こういうのをパニックというんだよな」と裕司は、何日か後で自分の行動を振り返ってみることができたが、その時は、白い箱を開けるぐらいしか思いつかなかったのだ。もちろん箱の中には子猫がいて、訴えるような眼で、「ミャー」と鳴いた。その声は震えているような心細げな響きだった。震えたいのは自分のほうだと裕司は思った。
「ここだよ、ここ」
声は、箱をのぞく頭の後ろから聞こえてきた。泣き出したいくらいに怖かった。
「ほら、上を向いてごらん」
怖いけど温かなその声は、「私は、電信柱だよ」と続けた。
「な~んだ、電信柱さんか」
腰を伸ばしながら声の主を見上げた後、今度は、自分の言った言葉のとんでもなさに、垂直跳び六十センチの驚きがおそってきた。
「ウソでしょう」
腰がくだけてへたり込む裕司のひざに、子猫がぴょこりと飛び乗った。
「ハハハ、驚かせたようだね」
「………」
「子猫君も、お目覚めだね」
「ニャー、ミャー」
「そうか、君は赤ちゃんだから、まだ言葉がしゃべれないんだね」
「ミャー、ニャー」
電信柱が話すたびに街灯がパカパカとまたたく。それだけでも驚きなのに、何と子猫と話が通じているようなのだ。気絶なんてテレビの世界だけのことだとも思っていた裕司だったが、気絶をするのはきっとこんな時なのだろうなと感じたのでもあった。しかし、小学校5年になるまで一度も気絶をしたことのなかった裕司は、やっぱり気絶はしなかった。
「裕司君、しっかりしなさい。男の子だろう」
「は、はい」
おもわず応える裕司は、このおかしな世界にしばらく身をまかせることにした。
「あの~」
どこを向いてしゃべればいいのか、本当はわからなかったが、子猫がそうしているように、とりあえず街灯に視線を向けてみようと思った。すると、木の節目や傷が目や鼻や口にも見えてくる。裕司はごくりと唾を飲み込み切り出した。
「どういうことなんでしょうか?」
「どういうことって、こういうことさ」
「こういうことって?」
「電信柱の私が話をして、その話が君にも、子猫君にもわかるってことだよ」
「はい、それはわかります。でも、それって……」
「ありえないとでも言うのかな?」
「常識的にはそうですけど……」
「では、いまここで起こっていることは?」
霧が薄くなってきた。鳥のさえずりがチュンと聞こえる。
「……うむ。ありえています」
「大切なのは、現実にどう向かい合っていくかということ」
裕司は電信柱に圧倒されていた。
「君にとって、今解決しなければならない問題はなんだろうね」
「う~ん」
「このおかしな世界から逃げ出すこと?」
「はっ、はい」
「それもいいけど、子猫君はどうする」
子猫が、ゴロゴロと喉を鳴らして、裕司の手を舐める。「そうだ、この小さな生命を自分が握っているのだ」と思った。
「だけど、自分の家では飼うことができないんです」
「だから、ここに置いていくのかい?」
「えぇ、拾う前と同じように」
「では、聞こう。君はどんな気持ちで子猫を家に連れていったんだい?」
「……かわいそうだから」
「そうだよね。君はとても心のやさしい子だからね」
電信柱は、そう言うと突然6年前のできごとを話し始めた。それは裕司が幼稚園に通っていたころの夏の日に起こった事件だった。
2 六年前
もうすぐ夏休み。裕司たちは毎日、幼稚園からいろいろなものを持ち帰っていた。その日はクレヨンを持って帰る日で、何かにラクガキしたくて、みんなウズウズしていたものだった。
裕司は、アキラとヒデキと一緒だった。アキラが「アレ!」と指さし言った。指の先には電信柱。ヒデキが「ウン」とうなずいた。裕司は最初、二人のアイコンタクトの意味がわからなかったが、アキラとヒデキが同時にクレヨンの箱を通園バックから抜き出したとたんに、二人が今からとても悪いことをしようとしているのだとわかった。でも、「ダメだよ」と裕司は言えなかった。そのころの電信柱は、今のようにツタに包まれてなかったと思うが、二人がラクガキを始めるのをだまって見ているだけだった。
暑い日だった。セミがジャージャー鳴いていた。アキラもヒデキもモクモクとラクガキをする。もし呼ばれたらどうしただろう。止めようとしたけど、やっぱり「やめなよ」の一言が言えず、「用があるから先に帰る」と言い残して、裕司はその場を離れた。もちろん、二人のイタズラを親や先生に言いつけたりはしなかったし、それからも三人は仲よしでいつづけた。
「思い出したかい?」
「ウン、あのときは、二人を止められなくてごめんなさい」と裕司は頭を下げた。
あの日、裕司は家に帰ると荷物を置いて、すぐに電信柱のところに引き返した。「やっぱりラクガキはいけないことだ」と思ったからだ。でも二人はもういなかった。電信柱のお腹のあたりには、サメやタコやサカナたちの絵が描かれていた。下手くそな絵だった。
裕司は走り寄って、電信柱に「ごめんなさい」とあやまった。ポケットからハンカチを出して、クレヨンを落とそうとしたけど、電信柱の肌は思いのほかデコボコで、ほとんど落ちなかった。
「あの時トゲがささらなかったかい?」
「忘れました。でもごめんなさい」
「あやまるのは、一度だけでいいんだよ。それに、君はあのとき、自分ができる精いっぱいのことをやったんじゃないかな」
「そうかなあ」
「そうさ。先生にしかられるからラクガキをしなかったのかな?」
「………」
「じゃあ、先生がしからなかったら、ラクガキをしたかな?」
裕司は首を大きく振った。
「それでいいんだよ」
3 霧の終わり
霧は一段と薄くなってきた。空も明るくなっていきた。まもなく晴れそうだ。
「じゃあ、子猫の話に戻ろうか」
裕司が子猫に目をやると、腕の中ですやすやと眠っていた。
「君はさっき、かわいそうだからと言ったね」
「だれからも拾われなければ、きっと死んじゃうと思ったから」
「では、聞こう。君のお母さんは、なぜ猫を飼えないといったのかな?」
「お父さんが猫アレルギーだから。でも、でも今はたんしんふにんというやつで、家にいないんです」
「つまり、お父さんが帰って来るまでは飼えるかもしれないと思ったわけだね」
コクリと裕司はうなずいた。
「でも、お母さんはダメだと言った」
「じょうがうつるからだって……」
「どんな意味かわかるかい?」
「はい何となく。一緒にいると子猫のことがますます好きになって、別れるのがとてもつらくなるのだと思います」
「そのとおり。やさしいお母さんだね」
風がピューと吹いてきた。
「お、おっといけない」
電信柱があわてた声を出す。
「君と話ができるのは、霧に包まれたときだけなんだ。子猫のことは何とかしよう。最後に一つ質問。もし、かわいそうな猫が子猫じゃなくて、よれよれの老いぼれ猫なら、君は拾っていっただろうか。よ~く考えていつか教えてください」
「あの、子猫は……」
「何とかすると言ったよ」
そう言うか言わないうちに、街灯が電信柱を支点にしてグルンと一回転した。するとどこからか大きな三毛猫が現れて、電信柱を忍者のように登っていく。てっぺんまでたどり着くと、背伸びするようにして「ニャオーン」と鳴いた。
「木の電信柱だから登れるんだ」
などと感心していると、三毛猫が飛ぶように降りてきて、裕司の前にピタリと座った。三毛猫とは言葉を交わすことができなかったが、「その子猫を私によこしなさい」と言っているのだと感じた。裕司は、ためらわずに子猫を差し出すと、三毛猫は立ち上がって、パクリと首を加え、電信柱の奧の草むらへと入っていった。さよならも言えなかったと裕司は思ったが、それでいいような気もした。
一匹、二匹、三匹……五匹。猫たちが次々に現れて、三毛猫と子猫が向かった草むらに吸い込まれていった。
「ははん、ネコ会議だな」
裕司も一緒に参加したかったが、「何とかすると言ったよ」の電信柱の言葉を信頼することにした。
「お願いします」
裕司は見えない猫たちに深くお辞儀をした。
「お願いします」
今は口をきかなくなった電信柱にも深くお辞儀をした。霧はすっかり晴れ、街灯の光は消えていた。
4 ネコ会議
電信柱が見下ろす草むらのなかの小さな広場でネコ会議は始まった。議長は三毛猫。出席者は議長と子猫を含めて七匹の猫。電信柱は猫ではないので、見ているだけの参加となった。議題は、「子猫の幸せを考える」である。
会議に先立ち、議長から今までのできごとついての次のような説明があった。
・子猫は、昨日の朝、電信柱の足元に人間により捨てられたこと。
・それは、親猫の意思を無視した身勝手な行いであること。
・目撃した電信柱の話によると、元の飼い主はこの町の住人ではないということ。
・昨日の夕方、一時的な避難先として期待ができる少年に引き取られたが、家庭の事情により本日の朝、元の捨て場所に戻されたこと。
・少年に好意を抱く電信柱の願いでこの会議を開くことになったこと。
・子猫は、会議の出席者を招き集めた議長(三毛猫)が緊急保護を行ったこと。
この説明を受けて、自由に意見を出し合うことにした。
最初に発言したのは、飼い猫のポン太だ。ポン太はタヌキのようなお腹をノッシノッシとさせながら言った。
「やはり、やさしい飼い主を探すのが、一番でしょうな。お腹を空かせて餌を探す苦労もなく、厳しい冬も寒さに震えることなく、雨の日も濡れることない。猫の幸せは飼い主しだいともいえます。もちろん私は幸せですよ」
やせ猫のガリ平は野良猫だ。ポン太を「飼い猫はいいねえ」とうらやましがる。
これに反発したのは、野良猫のゴン助だ。
「野良猫ほこりはどうしたんだ」
ゴン助は、今度はポン太をにらみをきかせ、みんなにむかって演説を始めた。
「ブクブクと肥ることが猫の幸せなのでしょうか」
ポン太の顔が真っ赤になった。といっても猫の顔色は毛で見えないのだが、眼が三角につり上がったから、きっと毛並みの下は真っ赤になったはずだ。だが、ゴン助はそんなことはおかまいなく続けた。
「猫の運命を、猫の幸せや不幸せを、いや、時には猫の命までを人間たちに握られていていいのでしょうか」
この演説に、飼い猫のタマ子が拍手をおくる。
「そうだわ、飼い主の顔色をうかがう毎日にはウンザリだわ」
ガリ平が、「そうだ。野良猫のほこりは大切だ」とコロリと意見を変えた。
その時、ガリ平のお腹がグウとなる。今度はポン太の反撃だ。
「でも、お腹を空かしては、考え方も貧しくなってしまいます。人間の眼を盗んで魚をドロボウする生き方が、果たして上等なのでしょうか」
カラスが電信柱のてっぺんにとまり、「カァ」と鳴いた。ポン太がお腹を突き出しながら電柱を見上げる。
「ゴミをあさり、人間たちの弁当をかすめ取り、結局は人間たちに嫌われるようになった、あの鳥のようになりたいのですか?」
ゴン助が反論する。
「でも、カラスは自由です。私たちは、自由なこころを捨ててまで、楽な生き方を選び取っていいのでしょうか」
「そうよ、自由は大切よ」とタマ子が言えば、「でも、ぼくたちにカラスのような羽はないし、それにお腹が減るのもつらいし」とガリ平が悩む。
ネコ会議は、「子猫の幸せを考える」はずだったのだが、その前に、「猫の幸せ」「人間とのつき合い方」「自由なこころとは何か」など、とても難しい議論へと進んでいった。
会議が進む。先ほどまで会議を見ていたカラスもいつの間にかいなくなった。参加者たちも疲れてきた。でも、こんな時が危ない。つまり、疲れてくると、何でもよくなって、かんたんな話やいせいのいい話に人気が集まるのだ。この会議でも、「人間との対決もやむなし」という危険な意見が大きな声となってくる。対決は、ケンカや戦争にもつながって、勝っても負けてもとても嫌なものなのだ。そして、お互いの滅びの道へとつながっていく。
さて、多くの場合、こうした危ない場面を救うのはお年寄りの意見だ。だって、お年寄りたちは、長く生きてきていろいろなことを知っているからだ。会議に参加していた長老猫のトラ爺(じい)がポツリといった。
「共に生きる道を探したいものじゃのう」
共に生きる道、つまり、猫と人間が仲よく手を取り合って生きる道である。
「猫には羽がないとだれかが言ったが、猫にはまだまだ自由がある。他のペットや家畜ようにクサリにつながれてもいないしオリにも入れられていない。自由に外出できる飼い猫だって多い。ヘイを飛び越え、カベをよじ登り、私たちは自由にどこにでも出かけられる」
他の猫たちも、電信柱も、トラ爺の話を熱心に聞いている。
「だがのう、今ある私たちの自由は、猫の先輩たちが築き上げてきたものだということを忘れてはならぬ」
「私たちは、人間たちが嫌がるネズミをとりつづけて来たわ」
口をはさんだのは、タマ子だった。
「寒いときはコタツの代わりにもなった」
飼い猫のポン太がそう続ける。
「でも、ゴロゴロと喉を鳴らしてまつわりつく姿はとても見ていられない」
とゴン助が言えば、「だって、とてもうれしそうな顔をして喜んでくれるんだもの」とタマ子が返す。
トラ爺が、「そう、互いに喜び合うことが大切なんじゃ」と言う。
「魚をちょっとだけくすねたこともはあっても、爪で少しだけひっかき傷をつけることはあっても、少なくとも私たちは人間にそれ以上の大きな害を与えなかった。そればかりか、ネズミをとり、温かさを届け、アイキョウを振りまいて人間たちのこころにやすらぎを与えてきた。それは人間たちの喜びとなり、その引きかえに私たちは自由を約束されてきたのじゃ」
トラ爺の重みある言葉に、参加者たちはみな、「なるほど」とうなずいた。
「俺は、これから先も飼い猫にはならないけど、飼い猫にも自由の道は残されていそうだな。何と言っても自由こそが猫のほこりだからな」
ゴン助の言葉に、「そう、どんな生き方をしたって自由はある」とトラ爺は応える。
「飼い猫になっても、野良猫になっても、自分で自由に考え、自由に行動ができるようにすることが大切なのね」
とタマ子は続ける。
「ぼくも、なんだか飼い猫になりたくなったけど、まあ、そんなことより、この子猫がそんな大人になるまで、守ってやろうよ」
ガリ平の発言に、ポン太が付け加える。
「そのために、自分たちになにができるか、知恵を出し合おうよ」
それからの会議は、とてもスムーズに進んだ。
議長の三毛猫は、子猫を毛づくろいしながら、他の猫たちの発言を楽しそうに聞いている。
飼い猫で太っちょのポン太は、「子猫の飼い主が見つかるまで、自分の食事の一部を子猫に分ける」と約束した。
同じく飼い猫のタマ子は、「それはダイエットにとてもいいわ」と感想を述べた後、「私は、人間に愛されるつき合い方を教えてあげる」と提案した。
野良猫のゴン助は、「子猫の安全をおびやかす悪者をやっつけるとともに、自分の冒険談を話して聞かせたい」と言った。
ガリ平は、「野良猫だからこそ気づくこの町の危険な場所を教えていきたい」と語り、「危ないことを知ってこそ、本当に自由でのびのびとした行動ができるのだ」と付け加えた。
ドラ爺は、「困った時は、いつでも相談においで」と子猫にやさしく語りかけた。三毛猫の議長は、参加者に「ありがとう」とお礼を言った後、「この子猫にできるだけステキな飼い主が見つかるように努力し、もし、飼い主が見つからなくても、ほこりを失わない自由猫になるように育てたい」とホウフを述べた。
何も言わない電信柱であったが、とても満足そうな表情のように見えた。
子猫が「ミャー」と鳴き、ポン太が「これ、ぼくのオヤツだけど」と首に下げていた袋からクッキーをさしだし、会議は終わった。
5 悲しい知らせ
ネコ会議がたけなわのころ、裕司は家に帰ってきた。白い子猫を白い箱に入れて電信柱の足元に戻しに行ったときの悲しい気持ちは、すっかり晴れた霧のようになくなっていた。
お母さんは、庭の花壇の手入れをしていた。手を止めて裕司の顔を見たお母さんは、裕司の気持ちに起こった変化がわかったのに違いない。にっこりと微笑むと、「おかえり」とこころを込めて言った。
「霧、晴れたわね」
裕司は、お母さんに霧の中で起こった不思議なできごとを話したいと思った。
「町はずれにある電信柱知ってる?」
「ええ、木でできた電信柱でしょう」
「そ、その電信柱とね、ぼく、いろいろなお話をしたんだ」
「あら、それはすごいわね。どんなお話をしたか聞かせてちょうだい」
でもお母さんは、「お話だけじゃなくて、ほら、そこの土を持ってきてくれない」とか、「この花を植え替えるから、根っこの土をやさしくほぐしてちょうだい」とか、いろいろとお手伝いをさせようとする。こんなすごい話を、お手伝いをしながらするのはちょっとイヤだったけど、裕司は、がまんすることにした。
霧の中で見た電信柱にツタが巻きついていたこと、ツタの葉っぱを傷つけないように「とてもかわいい子猫です」と書かれた紙を貼ったこと、木の電信柱だから紙が画びょうで留められたこと、その時に、「ダメだったんだね」ととても年を取った男の人の声が聞こえてきて、それが電信柱の声だったこと……。
裕司は、今朝のできごとを一つ残らず話していった。でも、6年前のクレヨン事件をお母さん教えていいかどうかはちょっと迷った。だって、アキラとヒデキのイタズラは親にも先生にもヒミツにしていたことだったからだ。だけど、そこを飛ばすと電信柱と自分の関係がうまくお母さんに伝わらないと思った。裕司は、二人のラクガキに加わらなかったこと、ラクガキのことはだれにも言わなかったこと、後で二人のラクガキを止められなかったことを電信柱にあやまったことなどをお母さんに思い切って打ち明けた。
「電信柱さんがね、君は精いっぱいのことをやったんじゃないかなと言ってくれたよ」と話したとき、お母さんは、スコップを動かす手を止めて、「よかったね」と言ってくれた。裕司は、とてもうれしかった。
つづいて、猫が飼えない理由を電信柱から聞かれて、その理由を応えると、「やさしいお母さんだね」と電信柱が言ってくれたことも報告した。お母さんは、その時は、「そう」と言っただけで、モクモクとスコップを動かしていた。
「それでね、霧が晴れてきたんだ。電信柱さんがお話できるのは、霧があるときだけでね、電信柱さんは少しだけあわてた感じで、子猫のことは何とかしようと言っていれたんだ」
お母さんは、もう一度スコップの手を止めて、「よかったね」と言った。
「でも、宿題があるんだ」
「何かしら?」
「子猫がよれよれの老いぼれ猫なら拾っていったかなって聞かれたんだ。お母さんはどう思うかしら」
「それは、裕司君への質問でしょう?」
「うん」
「とてもすばらしい質問だから、ゆっくり考えるといいわ。でも……」
お母さんの「でも」と言って黙ってしまった。
「でも、どうしたの?」
「………」
裕司の目をまっすぐに見つめて、お母さんは言った。
「町はずれの電信柱さんだけど、もうすぐてっきょされるかもしれないの」
「てっきょ? えっ? どういうこと?」
お母さんの言葉の意味が、裕司にはわからなかった。でも、あまり嬉しくないような気もした。
「てっきょって、取り去ること。つまり、電信柱さんがなくなるってこと」
「そんなのだめだ」
「電信柱さんは、とても古くなって、それと、あの土地は公園に生まれ変わるらしいのよ」
「うそでしょう。せっかく仲よくなれたのに」
裕司は、ネコ会議のために猫たちが集まったことをお母さんに話すことはもうできなかった。子猫ばかりか、電信柱さんともお別れしなくてはならないなんて……。霧の晴れたまぶしい太陽の下で、裕司はとても悲しい気持ちになったのだった。
6 電信柱とおばあさん
電信柱にぶっつかった経験のない人なんているんだろうか。友だちと話していてガーン、よそ見をしていてドシーン、自転車の乗っていてぶっつかった人もいるだろう。時々だけど、車が突っ込んでいることもある。そんな電信柱だけど、電信柱があるから電気が使えて、電話で話すことができる。暗い夜の道を電信柱の街灯が明るく照らしてくれる。電信柱の間に張られた電線がたこ揚げにじゃまだったり、お祭りのダシと呼ばれる大きな車を動かすのに電線を持ち上げたりしなくてはならないけど、電信柱のおかげで、テレビを見ることができて、冷蔵庫でジュースを冷やすことができて、冬はコタツ、夏はエアコンを使うことができるんだ。もちろん、夜、勉強をしなくてはならないのも、電気を電信柱と電線が運んでくるからなんだけど……。
そんな電信柱も時代が進むに連れ、木製からコンクリート製にかわり、都会や観光地などでは、町の景観をだいなしにするじゃまものとして、電信柱をなくし、電線や電話線を地下に埋めようとする動きも広まってきた。
裕司の町では、電線を地下に埋めるのはまだまだ先のことのようだけど、さすがに木の電信柱は、町はずれのあの電信柱だけになっていた。ふつう木の電信柱は、十五年くらいで新しいものと取り替えられるらしい。だけど、あの電信柱だけは、六十年以上もあの場所に立っているのだという。なんでも、とっくの昔に電気を運ぶ電線をかける役目を終えたのと、付近では、あの電信柱だけに電灯がついていたため、街灯として残されたのだ。でも最後まで残ったその役目も、まもなく終わろうとしている。
「三毛猫が忍者のように駆け上がり、ネコ会議の開催を告げることはもうできない」
裕司は、そんなことを考えているうちにいつしか電信柱の立っている場所に来ていた。霧はかかっていなかった。
光の消えた街灯、物言わぬ電信柱、その足元に一人のおばあさんが立っている。おばあさんは、白い子猫を大事そうに抱え、小さな頭をヨシヨシとなでている。その横のほうに目をやると、大人の猫たちがおばあさんと子猫のようすを眺めている。猫たちの中に、あの三毛猫もいた。少し前の経験だったけど、とてもなつかしことのような気がした。一歩進み出た裕司に、おばあさんが気づいた。
「ほら、かわいい子猫でしょう」
おばあさんが、子猫を裕司に見せた。
「うん、知ってるよ」
「そうかい。あの猫たちがね……」
おばあさんは、三毛猫たちのほうを指さした。
「あの猫たちが、子猫を守っていたんだよ」
今度は、三毛猫たちに向かって語りかける。
「猫さんたちや、私がこの子猫ちゃんを育ててもいいかしら?」
三毛猫たちは、互いに顔を見合わせ、電信柱とも合図を交わし(裕司にはそう見えた)、「ニャー」と言った。それは、オーケーの返事だと、裕司は思った。
「ありがとうよ」
おばあさんは、猫たちにちょこんと頭を下げ、裕司に向き直った。
「坊やも猫の気持ちがわかるようだね」
小学校五年生の裕司は、「坊や」と呼ばれるのはちょっとイヤだったけど、「うん、何となくわかるような気がします」と返した。
「霧が晴れちゃったね」
その言葉の意味も裕司にはわかった。
「朝、ぼくここに来たんです」
「そうかい。霧が出ていたんだね。電信柱さんは、あのことを悲しんでいたかい」
「いいえ、てっきょの話はしませんでした。母に聞きました」
「おや、坊やはむつかしい言葉を知ってるんだね」
やっぱり「坊や」という呼び方はやめてもらいたい。裕司は、勇気を出して、「あの、ぼく小学校の高学年なので、坊やじゃなくて……」
「あら、そうだったね、お名前は?」
「裕司です」
「じゃあ、裕司君でいいわね。で、裕司君も悲しくなるとここに来るのかしら?」
確かに、今朝は悲しかったけど、ここに来たのは違う理由からだった。
「いいえ違います。おばあさんは、そうなんですか?」
手提げから風呂敷のようなものを出したおばあさんは、電信柱の足元にヒラリと広げ、「ヨッコイショ」と正座すると、裕司にも座るようにうながした。
「私はね、悲しいことがあるとここに来るのさ」
おばあさんはひとり暮らしだそうだ。毎年、夏休みになると孫たちが遊びにくるのだけど、今年の夏は海外旅行ににいくので遊びに来られないのだという。それが昨日わかったらしい。
「なぜ、悲しいと電信柱さんに会いに来るのですか?」
遠くを見るような目つきになりながら、おばあさんは亡くなったおじいさんのことを話し始めた。おじいさんは、十年前まで漁師をしていて、漁師の仕事の最後の日に、嵐にあってそのまま帰らなくなったらしい。そのおじいさんがまだ若いとき、若いころのおばあさんに向かって、「お嫁さんになってほしい」と打ち明けたのがこの電信柱の下だったのだという。
「ずっとずっと昔のことだけど、昨日のことのようにも思えるのさ。その後で、おじいさんは戦争に行くことになってね。おじいさんからの手紙が来るたびにここに来て、何度もなんども手紙を読んだものなのよ。だって、家にはおおぜい人がいて、とても一人きりになれるところがなかったもの」
そのころの街灯は、はだか電球だったという。
「手紙を広げるとね、なぜだか、電球がパッと明るくなってね。おじいさんが戦場でこころを込めて書いた文字がハッキリと浮かび上がったの」
おじいさんは、戦争が終わってもすぐに帰って来られず、シベリアというところに連れて行かれたらしい。三年たっておじいさんが帰ってくることが決まり、おばあさんはうれしくなって、電信柱の下に駆けつけ、「ありがとうございました」と深々と頭を下げたのだという。
「霧のかかった朝だったわね。そうしたらね、『よかったね』って、とてもやさしい声が聞こえるのさ」
「電信柱さんの声だったんだよね」
「そうさ坊や、いや、裕司君。人が生きていくには、うれしいことだけじゃなく、悲しいことだってある。そのときに、悲しい気持ちを受け止めてくれる人、私の場合は電信柱だったけど、そんなものがあると、何とか生きていくことができるんだよ。おじいさんが亡くなったときに、ひとりぼっちになった私をなぐさめてくれたのはこの電信柱なのさ」
おばあさんは、そう言いながら、そっと電信柱の木肌をなでた。
まだ小学生の裕司だったけど、おばあさんの言うことがわかるような気がした。でも、その電信柱はまもなくてっきょされてしまう。おばあさんには、そんな裕司の不安な気持ちをさっしたのか、ハッキリといった。
「この電信柱は、とてもおじいさんなのさ。だからもうすぐいなくなる。それはとても自然なことなんだよ」
裕司の悲しい気持ちはまだそのままだったけど、自分には話のわかるお母さんがいて、遠くに住んでいるけどお父さんがいるということを改めて思った。そして、いろんなヒミツを一緒に知っているおばあさんが新しい知り合いになったことで、なんとかこの悲しい気持ちを乗り越えられるような気もしてきた。
「あの~」
「なんだい」
「子猫に会いに、時々いってもいいですか?」
おばあさんはニッコリとうなずいてくれた。裕司は、おじいさんのこと、おばあさんのこと、電信柱のこと、そしてこの町のことを、もっともっと聞きたいと思った。それが、自分のためにも、おばあさんのためにも、とてもいいような気がした。もちろん、子猫のお世話も手伝うけれど……。
7 再び霧の朝
裕司は、霧の日を待った。電信柱にお別れが言いたかった。それと、電信柱からもらった宿題の答えも電信柱に教えなければならなかった。
一日が過ぎ、二日が過ぎ、一週間が過ぎ、やっと霧の朝がやってきた。霧が晴れないうちに、まだ薄暗い道を裕司は急いだ。
霧のかなたに、電信柱の街灯がうるんで見えた。
駆けつけた裕司は、「電信柱さん」と呼びかけた。
「霧の日を待っていてくれたようだね。子猫はおばあさんのもとで元気に暮らしているらしいよ」
電信柱はなんでも知っていた。裕司は、宿題の答えを切り出した。
「あの、この間の質問の答えなんですけど。一週間前だったらよれよれの老いぼれ猫はやっぱり拾わなかったような気がします。だけど……」
裕司は、大きく深呼吸して言った。
「今なら、老いぼれ猫を拾えるかもしれません」
「拾えると言い切らないところが、君らしいね。とてもいい答えだ」
それから裕司は、霧が晴れるまでいろいろなことを語り合った。その話の中身は、電信柱と裕司のヒミツだ。
そして、霧が晴れるとき、裕司は、「お別れですね」とちょっと気取って電信柱に言った。だって、涙を見せたくなかったから。
「ありがとう」
「こちらこそありがとう」
その言葉を最後に、風が霧を吹き飛ばした。
夏が終わるころ、電信柱がてっきょされると聞いたけど、裕司はそのようすを見にいかなかった。だって、お別れは済ませてきたのだから。その代わりに、おばあさんには時々会っている。
おばあさんの家には、猫たちも子猫の世話に入れ替わりやってくる。教育係、給食係、相談係、ボディーガード……、どうやら猫それぞれに役目があるらしい。裕司は、子猫の世話はもっぱら猫たちにまかせて、おばあさんの話にゆっくりと耳をかたむけることにした。
子猫や猫たちと散歩にもいく。お気に入りの場所は、かつて電信柱があったところ。秋が深まったころ、小さいけれど、とてもステキな公園ができ上がったのだ。
裕司は、公園のベンチに座り、おばあさんの話を聞くのが好きだった。ベンチには猫たち駆け上った爪のあとや、「とてもかわいい子猫です」と書かれた紙を貼りつけた画びょうのあとが残っていた。
















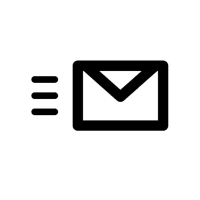

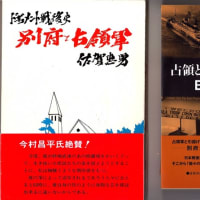

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます