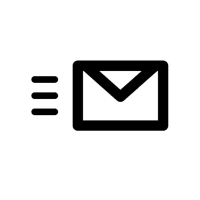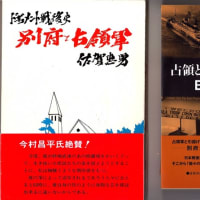真紀の故郷、鹿児島県枕崎市の夕陽。
枕崎は真紀の故郷だ。でも、真紀が生まれた場所ではない。真紀は昭和10年に福岡で生まれたらしい。フジテレビの「ザ・ノンフィクション」という番組(本ブログBAR真紀─1「出会い編」参照)によると、両親共に早逝し、枕崎の叔父の養子になったようだ。数十年後、叔父の妻、つまり真紀の養母と感動のご対面となるのだが、生まれは福岡、育ちは枕崎というのが真紀の生い立ちだ。17歳の時「美容師になりたい」と家を出たという。番組の副題は「女になって47年目の帰郷」。帰郷したのは、2012年だったから47年を引くと、東京オリンピックの翌年である1965年となる。真紀はその頃に性転換手術をしている。ということは、男性最後の年あたりに帰郷したということになるのだろう。
鹿児島と枕崎
鹿児島には、薩摩藩独自の士族意識があり、薩摩藩以来、男尊女卑の価値観が息づいてきた。MBC南日本放送「郷中教育51」(2018年5月28日/郷中教育(ごじゅうる)とは薩摩藩の武士階級の青少年教育法のこと)によると、「女の子を産んだら床の下に寝かせよ」という言葉が伝わるぐらい、男子と女子では扱いに差があっという。さらに、二才(にせ:若衆)が世帯を構えたときに新妻と双方の親の4人で登城すると、藩主は「女子(おなご)は、幼くして父母に仕え、長(ちょうじ)ては夫に従い、老いては子に養わるる習わしである。穏やかな心で、貞操を守ることが慣用である」などと諭したともいう。現代ならまだしも、真紀が育った戦中や終戦直後であれば、その風潮は色濃く残っていたのではあるまいか。また、枕崎は、かつおとかつお節の漁師町だ。総じて保守的。そんな故郷に「女になった自分が帰ることはできない」と真紀が思い続けたとしても無理はない。
取材先
話は変わるが、BAR真紀に通っていた頃、僕は「ケアマネジャー」という中央法規出版発行の月刊誌の編集をしていた。同雑誌の巻頭カラー「View Finder」は、僕の担当コーナーの一つだった。僕が記者となりカメラマンと一緒にケアマネジャー最前線を取材する。15年間担当を続け、全都道府県を3巡以上した。詳しい話は別の機会に譲るが、利用者や家族が顔出し・実名で登場し続けたのが僕のこだわりだった。
さて、当雑誌の2009年の6月号で鹿児島市のとある地域包括支援センターのHさんという主任ケアマネジャーを取材することになった。Hさんの趣味はスキューバダイビング。今の仕事に就く前に3年間、スキューバダイビングの店で働いたという本格派だ。
「潜りませんか」と僕は誘ってみた。フロントページの写真は、それでいきたかったからだ。HさんはOKしてくれた。次は場所探し、いつも潜る場所は……。その候補の一つに枕崎があったのか、枕崎がズバリとHさんの口から出たのか、僕から枕崎を持ち出したのかは忘れたが、そう、真紀の故郷である枕崎の近く海で潜ることになったのだ。ついでに宿泊も枕崎になった。6月号は5月20日発行なので、取材は4月。少し寒いけど「ウエットスーツだからどうってことありませんよ」と快諾をもらうことができた。
真紀の反応
取材が決まってすぐ、僕はBAR真紀のドアを開け、いつものようにカウンターに座っていた真紀に、「真紀、枕崎に行くことになったぞ」と告げた。少しは驚くかと思ったが、反応は鈍かった。「ふ〜ん、余計なことを」と言われたような記憶もある。でもその言葉の奥には、なにがしかの思いの数々が去来していたはずだ。真紀は極めて事務的な口調で「実家に挨拶してきな」と言いながら、弟さんの連絡先のメモを差し出した。営業用の真紀の言葉遣いなら「挨拶してきて〜」か「挨拶して、ちょうだい」であろう。その瞬間、真紀は営業モードから離れていた。そのときの模様などを僕は雑誌の編集後記に書いた。
編集後記より
新宿のスナックに元男性の70代のママがいる。故郷は九州の某所としておく。「取材で近くに行く」と告げたら「実家に挨拶してきな」とメモを渡された。今でさえ性同一障害への視線は厳しい。「どんな挨拶を…」と悩みつつも勢いで連絡。何と弟さんと飲むことになった。「50年以上出たきりだ。一度帰るように伝えてくれ」。重いメッセージを託された。
半世紀
弟さんの言葉である「50年以上出たきりだ」は、フジテレビの「47年目の帰郷」とは合わない。実際に真紀が帰郷したのは2012年であるから、取材した2009年は最後の帰郷から44年目となるからだ。弟さんの記憶違いか、44年前に帰郷したときに弟さんとは合っていないかのどちらかなのだろう。いずれにせよ、半世紀近く真紀は故郷の地を踏まなかった、いや踏めなかったのである。
枕崎の夜
僕が弟さんと会うことができた顛末を話そう。海から上がって来るHさんのウエットスーツ姿の撮影を終え、カメラマンを交えて枕崎市の居酒屋で一杯やった。これがあるから地方取材は楽しい。それはさておき、枕崎訪問の目的がすべて果たされたわけではなかった。真紀の実家にいる弟さんに挨拶しなればならないのだ。でも、事ここに至ってまだ逡巡していた。「挨拶してきな」って、何をどう挨拶するんだよ! とぐずぐずと思っていたのだ。真紀の本名を書いたメモも渡されていた。寺本文雄(仮名)が真紀の本名、または戸籍を女性にしていたら旧氏名だ。それはさておき、「いつも文雄さんにお世話になっています」では、やっぱり何か変だ。だって、僕は文雄氏の店の客の一人にすぎないのだから……。
そんなことを考えるうちに酒が回ってきた。酔いは気分を大胆にする。その居酒屋で、実家の住所と連絡先を見せ、「ここ近いですか?」と尋ねてしまったのだ。
「ああ、ここ、うちのすぐ近くですよ」
もう、観念するしかない。僕は、メモにあった電話番号をプッシュした。電話に出たのは、真紀が言っていた弟さんだった。弟といっても、叔父さんの子どもだから従兄弟に当たるのか。でも、養子に入ったから弟なのだ。
「東京の新宿でお店を出している文雄さんにお世話になっている者です。文雄さんが枕崎に行ったら挨拶をしてきてほしいというので、電話をしました。本当に夜分すみません」
その挨拶の後、弟さんは、居酒屋に来てくれたのだ。その速さといったらなかった。電話を切って数分後の到着だった。
それから、真紀こと文雄氏の思い出話を長い時間聞いた。真紀は帰郷こそしていないものの、真紀と実家の間には、小包のやりとりが続いているらしい。枕崎の旬の品々を真紀に届け、真紀も東京のハイカラな品々を送ってくるということだった。
「兄もつらかったんだろうと思います。元気なのに故郷に帰れなかったんですから」
弟さんはそう言った後で続けた。
「でも今はもう、兄のことを知る人も、兄を悪く言う人も、いなくなりました。家族みんなが文雄兄さんの帰りを待っています。ぜひ、帰ってくるように伝えてくれますか」
それは、編集後記に記したように、重いメッセージだった。
真紀の反応再び
東京に帰った僕は、その足でBAR真紀に向かった。そこには、「どうだった?」とも聞かない真紀がいた。
「枕崎、行ってきたぞ」
「そう」
「弟さんに会えた」
「そう」
「ぜひ、帰って来てほしいと言ってたぞ。家族のみんなが待っているって」
「余計なことを」
真紀は、焼酎の水割りをグイと飲み干し、そう言った。