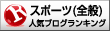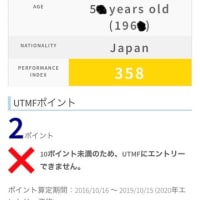■ 最近の悠太は手を抜かない
日本記録更新、あるいは日本人初の1時間切りはできなかったけど、ハーフ日本記録保持者としてさすがの走りだった。設楽悠太最大の魅力は、日本人では珍しい攻めの走りにある。久方ぶりの中山竹通の系譜に連なるランナーじゃなかろうか。後先あんまり考えず1番を目指す、行けるとこまでいく。といっても馬鹿みたいに勝算もなく序盤だけ頑張って失速を繰り返すというわけじゃない。いや、以前はそういうところもあったけど、今は違う。何が悠太を変えたのか? 是非聴いてみたいものだ。
今や大迫と並んで、押しも押されもしない日本マラソン界のエースといってもいい。
そして今年の丸亀ハーフでもその片鱗はしっかりと見せた。出だしから中盤までの村山謙太も悪くなかったけど、失速するだろうと予想できてしまったところが残念。それでもゴールテープ直前に、ハーフ世界記録保持者のタデッセをかわしたあたりここしばらくの低迷から復活しつつあることを予感させた。
■ 競技による体型の違いは何に支配されるのか
そのテレビを見ながら「悠太ってそんなにちいさかったのか!?」と家人が聞く。170cmと紹介されたからだ。私は多少の知識を動員して「小さくて軽い方が長距離ランニングには有利だからね。だからマラソン選手にそんな大きな選手はいない」「ふーん。そうなんだ」
たわいもない会話。
でも、そのあとこの会話が頭の中を駆け巡った。
つまり、こういうことだ。長距離走のトップ選手に170を越えるような選手があまりいないのは、この競技に有利なように、どこかの時期から身長が伸びなくなる、ということなのか? 身長もそうだが、体重の増加は致命的にタイムに影響するので、また、当然だけど、走ることで代謝が上がり体脂肪が減り体重は減るわけで、結果的に「軽い」というのはランナーにとって当たり前のことである。
たとえば、体操選手なんかも、大きいと身体のコントロールが難しくなるに決まってるので、そう大きな選手はいない。こうしたことが、競技で有利なように「競技が体型を制限する」ということなのだろうな、と漠然と考えていた。
でも今回違うんじゃないかと思ったのだ。そういう側面がゼロではないが、支配しているのは、自然界における進化の理論と同じなのではないか、ということである。
トップレベルでは、体型においてもその競技に有利な者が良い成績を収めていく確率が高いだろう。陸上の長距離なら、風などの自然の影響を受けにくい、小さくて軽い選手が有利で、途中から大きくなった選手は成績を落として上位から脱落してゆく。結果小さくて軽い選手が残っていく。もちろん例外もある。大きくても練習量を増やしたり、走り方の工夫をしたりして小さい選手に伍していい成績を収める者もいるだろう。でもその数は少ないということになる。より困難な道だからだ。
そういうことが1000万年単位で繰り返され、遺伝子を書き換え、進化というものが行われるのだろうと、なんだか腑に落ちたという話。
デカくちゃダメ、ちっちゃくちゃダメというわけではない。特に市民ランナーレベルなら、そんなの誤差に過ぎないだろうから。もっと別の要素でいくらでも挽回できる。
すべてのランナーにエールを。もちろん自分にも。
日本記録更新、あるいは日本人初の1時間切りはできなかったけど、ハーフ日本記録保持者としてさすがの走りだった。設楽悠太最大の魅力は、日本人では珍しい攻めの走りにある。久方ぶりの中山竹通の系譜に連なるランナーじゃなかろうか。後先あんまり考えず1番を目指す、行けるとこまでいく。といっても馬鹿みたいに勝算もなく序盤だけ頑張って失速を繰り返すというわけじゃない。いや、以前はそういうところもあったけど、今は違う。何が悠太を変えたのか? 是非聴いてみたいものだ。
今や大迫と並んで、押しも押されもしない日本マラソン界のエースといってもいい。
そして今年の丸亀ハーフでもその片鱗はしっかりと見せた。出だしから中盤までの村山謙太も悪くなかったけど、失速するだろうと予想できてしまったところが残念。それでもゴールテープ直前に、ハーフ世界記録保持者のタデッセをかわしたあたりここしばらくの低迷から復活しつつあることを予感させた。
■ 競技による体型の違いは何に支配されるのか
そのテレビを見ながら「悠太ってそんなにちいさかったのか!?」と家人が聞く。170cmと紹介されたからだ。私は多少の知識を動員して「小さくて軽い方が長距離ランニングには有利だからね。だからマラソン選手にそんな大きな選手はいない」「ふーん。そうなんだ」
たわいもない会話。
でも、そのあとこの会話が頭の中を駆け巡った。
つまり、こういうことだ。長距離走のトップ選手に170を越えるような選手があまりいないのは、この競技に有利なように、どこかの時期から身長が伸びなくなる、ということなのか? 身長もそうだが、体重の増加は致命的にタイムに影響するので、また、当然だけど、走ることで代謝が上がり体脂肪が減り体重は減るわけで、結果的に「軽い」というのはランナーにとって当たり前のことである。
たとえば、体操選手なんかも、大きいと身体のコントロールが難しくなるに決まってるので、そう大きな選手はいない。こうしたことが、競技で有利なように「競技が体型を制限する」ということなのだろうな、と漠然と考えていた。
でも今回違うんじゃないかと思ったのだ。そういう側面がゼロではないが、支配しているのは、自然界における進化の理論と同じなのではないか、ということである。
トップレベルでは、体型においてもその競技に有利な者が良い成績を収めていく確率が高いだろう。陸上の長距離なら、風などの自然の影響を受けにくい、小さくて軽い選手が有利で、途中から大きくなった選手は成績を落として上位から脱落してゆく。結果小さくて軽い選手が残っていく。もちろん例外もある。大きくても練習量を増やしたり、走り方の工夫をしたりして小さい選手に伍していい成績を収める者もいるだろう。でもその数は少ないということになる。より困難な道だからだ。
そういうことが1000万年単位で繰り返され、遺伝子を書き換え、進化というものが行われるのだろうと、なんだか腑に落ちたという話。
デカくちゃダメ、ちっちゃくちゃダメというわけではない。特に市民ランナーレベルなら、そんなの誤差に過ぎないだろうから。もっと別の要素でいくらでも挽回できる。
すべてのランナーにエールを。もちろん自分にも。