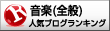「トレランと環境負荷」について考えてみるきっかけになったのが、実はこの「トレイルランニングの未来を考える全国会議」についての記事を読んだことだった。
2014年4月28日。ということは3日間にわたって行われたUTMF終了の翌日である。会議でのプレゼンテーションがYouTubeにアップされていたので、いくつかピックアップした。
全部を観てはいないが、松本大さんの説明された「スカイランニング」のコンセプトは興味深かった。日本のトレイルランナーは「ラン」のほうにあまりにも重きを置きすぎているのではないか、という話。登山やハイキングの延長、ファスト・トレッキングという感覚が大事。というのも、やはり日本ではトレイルランニング専用コースが(ほぼ)なくてハイカーや登山者と同じフィールドを利用しているから。
まずはここにアップしておいて、時間を見つけてわたし自身もじっくりあとから見ようと思う。こういう会議を鏑木さんが呼びかけたのは、トレランの将来を見据えた時、現状を手放しで良しとしていてはまずいという危機感があるからだとろう。裏返せばトレランをする方も見る方も、主催者も地域住民も、十分に議論してお互いに理解を深めた中で、広く愛されるスポーツに育ってほしいというトレランへの「愛」ゆえだということは切実に伝わってくる。
鏑木毅-開会あいさつと問題提起
石川弘樹-日本のトレイルランナーおよびレースが心がけるべき大切なこと
松本大-ランニンク?形式の登山という考え方
鏑木毅-日本のトレイルランニンク?の未来に向けた行動
2014年4月28日。ということは3日間にわたって行われたUTMF終了の翌日である。会議でのプレゼンテーションがYouTubeにアップされていたので、いくつかピックアップした。
全部を観てはいないが、松本大さんの説明された「スカイランニング」のコンセプトは興味深かった。日本のトレイルランナーは「ラン」のほうにあまりにも重きを置きすぎているのではないか、という話。登山やハイキングの延長、ファスト・トレッキングという感覚が大事。というのも、やはり日本ではトレイルランニング専用コースが(ほぼ)なくてハイカーや登山者と同じフィールドを利用しているから。
まずはここにアップしておいて、時間を見つけてわたし自身もじっくりあとから見ようと思う。こういう会議を鏑木さんが呼びかけたのは、トレランの将来を見据えた時、現状を手放しで良しとしていてはまずいという危機感があるからだとろう。裏返せばトレランをする方も見る方も、主催者も地域住民も、十分に議論してお互いに理解を深めた中で、広く愛されるスポーツに育ってほしいというトレランへの「愛」ゆえだということは切実に伝わってくる。
鏑木毅-開会あいさつと問題提起
石川弘樹-日本のトレイルランナーおよびレースが心がけるべき大切なこと
松本大-ランニンク?形式の登山という考え方
鏑木毅-日本のトレイルランニンク?の未来に向けた行動