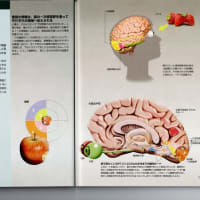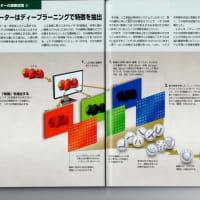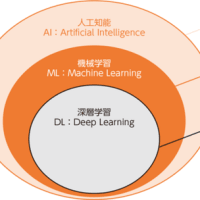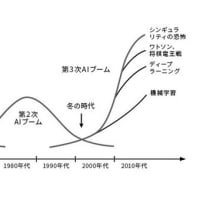団塊世代はQOLや死に方へのこだわりがそれ以前の世代より強いという=ゲッティ共同
かねて政府は2025年を社会保障にとって最大の制度危機の年と位置づけ、医療・介護サービスの提供体制と財源調達を滞らせぬよう警戒してきた。
1947〜49年の戦後第1次ベビーブーム期に生を受けた「団塊の世代」すべてが75歳以上の後期高齢者になり、医療・介護需要が爆増するとにらんでいるためだ。2025年問題である。
団塊世代のラストランナー、49年生まれはおよそ270万人だった。2024年の出生数はこのままだと70万人を切る可能性が出てきた。
20年国勢調査によると、団塊世代(当時71〜73歳)は総人口の4.7%にあたる600万人弱。この世代の存在感がいかに大きいかが実感できよう。

一般に、人は後期高齢者になるのにともなって病気やけがをするリスクが格段に高まる。
25年問題に警戒が怠れないのも、むべなるかなだ。ところが団塊世代の3分の2あまりが後期高齢者になった現時点で医療・介護サービスの提供が大きく逼迫しているという話はあまり聞こえてこない。
コロナ後に一段と進んだ人材不足によって、介護サービスに支障が生じる例はある。
地域によっては介護専門職の採用が思うにまかせず、空室があっても要介護者の入居を断る高齢者施設がある。もっともそれは供給側の問題に起因しており、団塊世代の後期高齢化という需要側の問題は、目立っては顕在化していない。何が起こっているのか。
考えられるのは、団塊世代に特有の行動変容や価値観が、彼ら彼女らの健康状態におよぼすプラスの影響である。
この世代の死生観が変わりつつあることに着目するのが国際医療福祉大の高橋泰教授だ。団塊世代からほぼ12年刻みでさかのぼった各世代の特徴についてこんな仮説を立てた。
①1926年(昭和元年)生まれ 2025年に99歳。敗戦を20歳弱で迎え、生き延びようとする意志が強い
②1937年(昭和12年)生まれ 25年に88歳。敗戦時7〜8歳。要介護状態では生き続けたくないと思う人が多い
③1949年(昭和24年)生まれ 25年に76歳。戦後生まれの団塊世代。病気や要介護になったときの暮らしの質(QOL)や死に方にこだわりをもつ
食べ物をかんだり飲み込んだりする力の衰えや肺炎によるせき込みで、ものが口から食べられなくなった人への治療法に、胃ろうがある。
手術でおなかに小さな穴を開け、カテーテルを通し、栄養剤を胃に送り込む栄養補給法だ。かつては食事をとれなくなった人への代表的な治療の一つだった。
だが東日本大震災が起こった11年ごろを境に、胃ろう手術を受ける人は急速に減っている。これは、団塊世代の父親世代が90歳を超えて死期に近づく時期と一致する。
11年以前は、胃ろう手術をするかを医師に問われた家族(子供)は「おまかせします」と、ゴーサインを出すことがふつうだった。団塊世代の多くは「父は寿命を迎えつつある」と感じ、延命治療を求めない例が増えていると考えられる。

北欧諸国などでは、要介護の高齢者に早い段階から食べ物を飲み込む機能を回復させる訓練をするのが一般的だが、自ら食べようとしない人への無理な食事介助は虐待にあたるという考え方が浸透している。
日本も団塊世代の後期高齢化とともに、高齢者介護の考え方が徐々に北欧型になってゆく、というのが高橋氏の見立てだ。
高齢者の身体・精神機能の急速な若返りも2025年問題の緩和につながる。しばしば引き合いに出されるのが、戦後しばらくして新聞連載が始まった4コマ漫画「サザエさん」一家の家族像とライフスタイルだ。
サザエさんの父、明治生まれの磯野波平は作中、54歳という設定である。当時の男性の平均寿命は60歳に満たない。
一方、団塊世代を活写した漫画作品が「課長島耕作」だ。54歳のときに初芝電器産業から関連会社に出向して社長になった耕作は、1947年生まれという設定である。社長になったころの男性の平均寿命は78歳。
サザエさんの時代から半世紀あまりを経て、54歳の男性像に大きな差が出たように、50年前の75歳にくらべた団塊世代の若返りは劇的だ。
認知症研究者による患者数の将来推計も低下傾向にある。
これら高齢者像のさまざまな変容を前提に医療・介護サービスの需要予測をしなければ、将来の病床数や高齢者施設のベッド数が過剰になるおそれが強くなろう。
厚生労働省は3月、コロナ後の新しい地域医療構想をつくるために検討会を組織し、議論を始めた。
検討会メンバーの高橋氏は5月22日の第3回会合で、医療・介護サービスの需要について従来の静態的予測を脱し、団塊世代の身体・精神機能の大幅な若返りを映した動態的予測に転換するよう促す。
「2025年問題、恐るるに足らず」となるか。団塊世代は文字どおり人口の巨大な塊だ。
需要予測が下方修正される可能性が大きいとはいえ、医療・介護サービスを必要とする人がある程度、増えるのは避けられまい。
サービスを過不足なく提供する体制を整えるのは、全国の医療圏を構成する関連業界と地元首長だ。
その創意工夫と手腕によって医療圏ごとのサービスの良しあしには一段と差がつく時代になろう。
需要予測が下方修正されても社会保障給付費の増大を圧縮する制度改革は不可欠である。
厚労省は高橋説に乗り気という。仮説を裏づけるエビデンス(根拠)を集めて丁寧に精査し、多数が納得できる制度・政策の立案に生かすのが同省の責務だ。

日経記事2024.05.22より引用