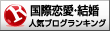ある人が花屋に立ち寄り、200マイル離れたところに住む母親に花を配達するように注文した。
車に向かうところで、縁石に座って小さな少女がすすり泣いているのに気づいた。
その人は少女にどうしたのか尋ねると、彼女は言った:「母のために赤いバラを買いたかったんです。薔薇は、一本2ドルかかると知り、私はたった75セントしか持っていなくて。」
その人は微笑んで言った、「私と一緒にいらっしゃい。あなたに薔薇を買いましょう」。
花屋で少女のために薔薇を買った。
車のところへ戻ると、その人は少女に車で家まで送りましょうかと申し出た。
少女は、「まあ、本当ですか? はい、お願いします! 一緒に母のもとへ行きましょう。」と言った。
「ここです。」と少女はその人を墓地に案内し、そこで彼女はバラを黒々と土の盛られた新しい墓の上に置いた。
その後その人は花屋に戻り、配達の注文をキャンセルし、花束を手に取り、200マイルを母親の家まで運転した。

今年の母の日も、Covidー19のせいで、母親と対面して会うのが難しい日本やヨーロッパであるのが残念だ。
私の母はもう亡い。今になって思うのは、なんと多くのことを母に教わったことか。勿論母は完璧完全な人間ではなかったが、身を投げるように姉や弟や私を育ててくれた。書が好きで、絵心もあり、その上お裁縫や編み物も一通りこなせた。小さかった私は、何か問題があっても、母に聞けば解決すると思っていた。
幼少時にある合唱団のメンバーだったくらい音楽が好きで、よくオルガンを弾きながら歌ったり、「人魚の歌」を弾いてくれたものだった。好きな歌手はパッツィ・クラインとジム・リーブスで「国境の南」や「スカーレット・リボン」を機嫌がよければ口ずさむ母だった。
よく世間で聞く娘と母との確執は、私にはなかったが、それでも亡くなってから、ああしていたら、こうしていたら、と胸が詰まるような気持ちになる。特に後悔するのは、もっと母と時間を過ごせていたら、である。
病に倒れたのは、私と一緒に旅行していたオーストラリアでだった。そしてその一月後母は逝った。母の入院中、一旦こちらへ帰国した私は、下の子がまだ小さく、その子や他の子供達の世話を夫や友人の好意と親切に甘えて託し、慌ただしく再び日本へ戻った。すると病床の母はうっすらと目を開け、私を見るや否や「あなたはすぐ帰りなさい。子供達はもっと大切よ。」とはっきりとした口調で言ったのだった。
その時日本へはただ二週間しかいられず、もう2度と生きては会えないだろう母の手を握る私に、母は「大事な末娘に会えたのだから、私は満足よ。」と一言、また眠りに入ってしまった。 私は泣く泣く離日し、母はそれからしばらくして逝った。
つい2、3年前にこの歌をふとしたきっかけで聞き、その言葉に涙が溢れた。それは、吾亦紅である。この曲が流行ったのはだいぶ前のようで、歌う方も私はよく知らないが、耳にするたびに心に染み入る。
参考:theholidayspot.com