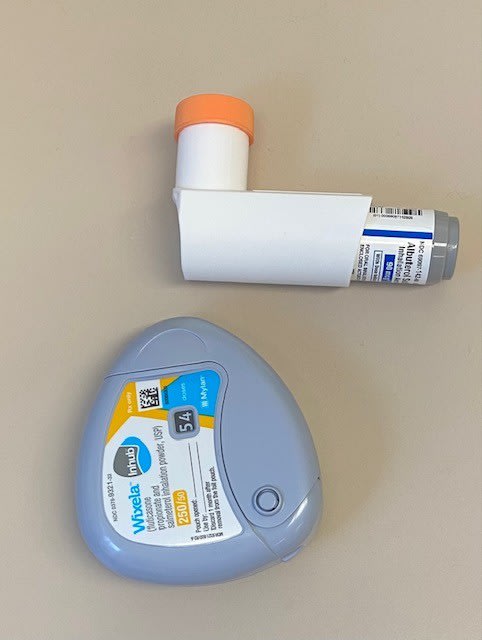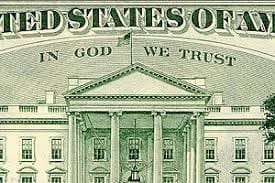Associated Press/Efrem Lukatsky
イースターの日曜の朝、教会へ行く支度をしている間、時計代わりにつけているテレビのニュース番組では、相変わらずロシア軍の残酷さを報じている。 三男夫婦の住むスエーデンとフィンランドがNATO(北大西洋条約機構)に加入する希望を述べてから、あの独裁者は核兵器があることをちらつかせて反対している。 呆れを通り越して、この独裁者が落ちるところまで落ちていく将来を自ら急がせているのを絵に描いたように目に浮かべた。
このイースターの朝、私にできることは一体なんだろうと再び思う。 すると今から24年ほど前に夫と観劇したあるブロードウェイの舞台俳優・歌手の歌った歌を思い出した。 あれは、ヴィクトル・ユーゴーのLes Misérables レ・ミゼラブル(ああ、無情、あるいは悲惨な人々)で、ジャン・ヴァルジャンが歌った祈りの歌である。
それはジャン・ヴァルジャンが、かつて彼のガラス宝石工場で働いていた女工の娘をコゼットを我子のように慈しみ世話をしてきて、そんな彼女を愛するマリウスという青年の無事な帰還を祈り求める歌だ。
マリウスは、「ABCの友人」と称する革命的なフランスの共和党学生の(物語上の架空の)協会に入り、民主主義の擁護、支援など、さまざまな政治的視点から活動をしていた。 この架空の団体はユーゴーの小説では、1832年6月5日に実際に起こった、六月暴動あるいはパリ蜂起として知られるパリ市民による王政打倒活動にマリウスが加わったことになっている。 物語後半の山場において、マリウスが無事に帰還できることを神に祈るジャン・ヴァルジャンの懇願のこの歌が歌われる。
舞台を観た時にこの歌にとても感動したが、それからだいぶ経って、タバナクル合唱団のコンサートでゲストとして招かれた舞台俳優アルフィ・ボーが、ジャン・ヴァルジャン役としてこの曲を歌ったのを観た。 その時2万2千人を収容していたカンファレンスハウスは満員で、それにも関わらず、彼が歌い始めると、水を打ったように会場はなんの物音も聞こえなくなった。 ボーの熱唱が終わると、3,4分間のスタンディング・オベイションが続いた。 それほどアルフィ・ボーの歌唱は心を動かす懇願の祈りの歌だった。
今この世界の嵐において、この歌は、ひとりひとりが聴いて心にかけたなら、それは祈りに近く、祈りに近ければ、それは祈りとなり、どの名前でも呼ばれている神に届くのではないだろうか、ウクライナの国と人々に安寧が戻るように、と私はふと思った。 イースターの朝、窓から上を見上げると、カリフォルニア・クラシックと言われる青い空が光っていた。
Bring Him Home
Hear my prayer
In my need
You have always been there
He is young
He's afraid
Let him rest
Heaven blessed.
Bring him home
Bring him home
Bring him home.
He's like the son I might have known
If God had granted me a son.
The summers die
One by one
How soon they fly
On and on
And will be gone.
Bring him peace
Bring him joy
He is young
He is only a boy
You can take
You can give
Let him be
Let him live
If I die
Let me die
Let him live
Bring him home
Bring him home
Bring him home.
日本語訳
家に戻して
高きにまします神よ
私の祈りを聞き給え
若い彼を救い給え
彼を家に帰らせ給え
御心は存じております
彼はまるでわが子なのです
歳の波が寄せて
やがて私は死ぬでしょう
まだ若い彼に平和を与え給え
全能の神よ彼に命を与え給え
死ねばならぬならば私を死なせてください
彼を家に帰らせ給え
彼を家に帰らせ給え