
中華街のお土産で、“花咲くお茶”を頂いた。
少し奇妙な色形だが、とても良い香りがする。
もったいないので、出がらしになるまで何杯も入れる。
昨今、“もったいない”という日本語が世界から注目されている。
2004年ノーベル平和賞受賞者のワンガリ・マータイさんが、
“もったいない”という日本語を知り、感銘を受けたとのこと。
彼女は環境保護の合言葉を「MOTTAINAI」として、世界に広めようとしている。
私が子供の頃は、お茶碗に残る一粒のお米も「もったいない」と躾けられた。
給食の時の子供たちを見ていると、そんな精神は残念ながら伝わってこない。
今一度、「モッタイナイ」という日本の精神を、再発見・再獲得していきたい。
このブログを応援してくださる方はお手数ですがクリックをお願いします。
ランキングサイトが開きます。(1日1クリック有効です)
↓↓↓

現在、ランキング3位です。
自分には“もったいない”位置だと感謝しています。
ランキング上位に入ることが目的ではありませんが、純粋に嬉しいです。
拙い文章ですが、宜しければ今後もお付き合いくださいませ。










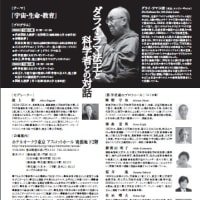
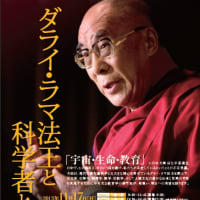






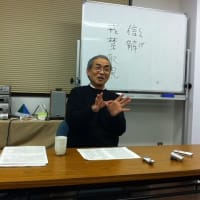

でも「もったいないばあさん」と言う絵本を読んだら、少しですが「もったいない」と言う意味が解りだし、水が出しっぱなしになっていたら「もったいなぁ~い」と、絵本の真似をして言うようになりました。
これからも「もったいない」を広めようと思うサーコ先生です
イイ話、ありがとうございました
当の日本人が忘れ、外国からの逆輸入という感じですね。
Mottainaiの精神で、環境にやさしい生活をしていきたいです。
お茶、おいしそう!
もったいないお話を有り難うございました(笑)
お茶の花、とても不思議な形ですね・・・
さすがに花は食べれませんよね・・・たぶん。
生活のなかで、断片的にはこういった「もったいない」気持ちをもちろん持ちますが、子どもに教えるほど、できていないと思います。
子どもや私達をとり巻く環境が、大きく影響してはいないでしょうか。
資本主義の社会と「もったいない」精神をどう調和させていくか、その辺をよく考えていくことも、大事なことかな、と思います。。。
自分はもったいないがりやというより、ケチなのかっ?!
でも、物はとっても大切にします。
「もったいないばあさん」の話、子供いは入りやすいかもしれませんね。
私は大人になってからも、「もったいないお化けがでるぞ~」なんて友人と良く言っていた気がします。
子供に響く教育に励んでいきましょう。
>ことさん
ほんと、逆輸入という感じですね。
環境に優しい生活を心掛けていきましょうね。
>りょうさん
もったいないお言葉を有り難うございます(笑)
花を食べるという発想はあしませんでした!
やってみればよかった。
もったいなかった・・・♪
>ときどきファンタ+さん
私も、もったいないことをたくさんしています。
資本主義社会で、できることから。
そして、ちょっと視野を広げて資本主義体制の是非も、ぜひ問うていきたいですね♪
>しのしのさん
もったないと、けち。紙一重ですね。
僕も後者かも・・・
ではでは、もったいないコメント、たくさん有り難うございます。
器物霊とか物に宿る魂とか、先人はうまいこと子供たちに「もったいない」精神を教えていたんだな、としみじみ思います。
世界にこの日本語を広めようとしてくれる方がいる一方で日本の子供たちに通じなくなっている・・・なにかおかしくありませんか?
以前、冷夏で米不足になったとき、青森の農家の親戚宅へ行ったのですが、畳にお米粒ひとつ落ちていても「もったいない!」と言ってすぐさま口に運んでいました。
作る側の気持ちなら、なおさらですよね。
子供には、呪術的に教えていくのも効果がありますよね。
作る側の気持ち「米という字は八十八の人・行程で・・・」なんて言う風にも教わった気がします。
実践できるかは別として、教育ってとても重要だと思います。
お互い、もったいない精神を大事にしていきたいですね。