
Michael Collins(1996)
「アイルランド独立の英雄」として一般的には知られる、激動の時代を生きた青年の伝記映画。アイルランドの状況についてご存知ない方でも、この映画を見れば彼が母国アイルランドの為に命を捧げた「愛国者」であった事は、理解していただけると思います。この映画を見ようという人は知っているはずのIRAというテロ組織、現在は理念を口実にした人殺しの集まりですが、アイルランドの独立戦争時は、英国からの独立を勝ち取る為に戦うレジスタンスの集団でした。簡単に言えば、コリンズは当時のIRAを先導し、結果的にアイルランドを独立に導いた人物です。
この映画の背景には、アイルランドの700年に及ぶ英国による抑圧と、独立、その後の混乱・・・現在まで続くIRA/UFFの抗争、カソリックかプロテスタントかの宗教の違いや、出身地、主義の違いによる差別や憎悪がいまだ存在する悲しい事実があります。パブやカフェといった公共の場所で、本心を語れない現実がいまだアイルランドには存在します。ダブリンのパブで、近代国家アイルランド共和国のダークサイドについて知りたがる私に、「そんなことを公共の場で口にしないほうがいい」と真剣な表情で忠告されたこともありました。
映画にも描かれる、罪のないアイルランドの人々を惨殺した英国支配からの独立、そしてその後の内戦による、英国人に殺された人数よりもっと多くの死者。私達はこの映画を見る時、描かれている出来事を遠い国の遠い出来事でしか、捉えることが出来ません。。しかし現在も、地球上では主義や種族、宗教の違いで殺しあいは続いています。それが戦争という正式なものなのか、テロとよばれる非公式なものなのかの違いはあっても。また、映画の中で描写される英国側の残忍さ(ほとんど事実です)に、ショックを受ける人もいるでしょう。どうして今だアイリッシュがあれほどまでに英国を嫌うのか、その理由はこの映画を見れば明白になるでしょう。そして、どうしてアジアの国々が日本を嫌うのか、私達日本人は彼等に何をしたのか、可能ならそちらにも思いを馳せて頂きたいと思います。
かつて、1993年北アイルランドとアイルランド共和国のボーダーで、バスの中に自動小銃を持った英国軍兵士達が爆弾を調べに乗り込んで来た時、私は今戦場にいるのだ、と悟りました。彼等が探していたのは北のIRAサイドへアイルランド共和国側から運び込まれる、荷物としての爆発物だったと推測します。殺さなければ殺される、死と隣り合わせの感覚からくる兵士達の空気が切れるような緊張感と、飛び交う軍用ヘリの爆音、声1つ立てず身じろぎもせず凍り付く乗客。私の五感は極限まで研ぎすまされ、乗客の心臓の鼓動まで聞こえるような気がしました。この時の経験は、かつてジャーナリストを目指したことのある私に、多くのジャーナリストたちが自ら戦場を目指す理由を教えてくれました。その場で、状況を共有しなければ決して真実の報道は出来ないのです。伝え聞きや推測では、人々の置かれた状況を理解することは不可能といっても良いかもしれません。
そのような現状のために、アイリッシュであるジョーダン監督はコリンズの映画を撮りたくても撮れなかったといいます。コリンズの映画化には、肯定的に描こうと批判的に描こうと、一歩間違えれば監督生命に関わるかもしれなかったのですから。90年代半ばに、IRAは武装解除に応じ、(その後協定は破られます)その時ジョーダンは映画制作にかかった、と記憶しています。ジョーダンによるコリンズ像は、本人なりに国の為に尽し、貢献したのに、信頼していた上司デヴァレラの策略で、不本意ではあるが現実的な最善策である独立条約(北アイルランドは英国に属すという、アイルランド島を2分割する条約のことです)を締結した当事者とされ、その結果を快く思わない完全独立派に暗殺されてしまう、頭はきれるが直球しか投げられない、朴訥な田舎の青年。アイリッシュのリアム・ニーソンがむっちゃコーク訛りで情熱的に演じます。史実を交え、同僚のハリー(エイダン・クイン)との友情、その後の悲劇、歴史的事実の再現を、アイリッシュ・ミュージックに乗せて見せてくれます。各建造物も見事に再現。ダブリンのロケで、本当にカスタムハウスが燃え上がっているようです。花を添える一応アイリッシュ女性役のジュリア・ロバーツは、正直いりません。映画として少しは色恋があったほうがいいのかもしれませんが、アクセントはまるっきりへただし、ベッドの上のバラの花のシーンなんか臭すぎです。
アラン・リックマンが演じたエイモン・デヴァレラは、当時のアイルランド大統領。目的を遂げる為には命を捧げる覚悟の愛国者であったことは、コリンズと同じだったのですが、この映画では、彼は洗練され、冷静沈着、冷徹な策略家として描かれ、コリンズと対比を生んでいます。ジョーダンのデヴァレラ像はしかし、彼の行為に完全に肯定的では有りません。自分の信念に合わない条約を締結せざるを得ない状況を察したデヴは、理由をつけてコリンズを代表としてイングランドへ送り込んでおきながら!その条約とコリンズを責めます。少なくともそう受け取れる演出です。デヴの不在時に有名になっていくコリンズを、彼が快く感じていないことを明確にもしています。その自分勝手な部分や冷酷さの表現が、最後のコリンズのデヴへの伝言を活かしています。「あなたは何時でも私のチーフなのですから。あなたとなら地獄だろうと一緒に行く覚悟だった。いや、もうすでに地獄にいるのかもしれない。」この辺りは当然創作なのですが、見るたびに涙腺が弛んで困ります。ちなみに、地獄へ行くというのはカソリックの人にとって死ぬより恐いことらしいです。
アランは父親がアイリッシュだとのこと。(言われてみればミドルネームもパトリックだったね)アランは、鉄のような意志を持つこの策略家を、実は神経質で繊細な人物として演じています。アドリブだと思うのですが、会議発言中に手を気にする仕種や、議会からの離脱を宣言する時の顔のぴくつきや微妙に体が揺れる所等、上手いなと感心してしまいます。映画の最初の方で、デヴァレラが本当に書いた獄中からの手紙を彼は朗読します。戦った仲間たちが、次々と処刑されていく中で、「彼等が我々を1人、1人殺すたびに、さらの多くの人々が我々の側に就くだろう」と。感情を押さえた朗読ですが、心に響きます。
デヴの喋りかた、姿勢を、彼は忠実に研究し演じています。「彼等は同胞の血にまみれるだろう」の演説シーン、本物のデヴとそっくりで恐いくらいです。アラン演じるデヴはしかし、本物より魅力的なのは否定出来ません。出番は多く無いのですが、この映画を見るたびアランの見せる表情に引き付けられます。静かな口調と押さえた表情の裏に、激しさと情熱を隠した演技。毅然と振舞い、それでいて最後に見せる感情の起伏。アランは、英雄デヴァレラ像に人間としての魅力を加えました。アランは同時期に「ある晴れた日に」に出演し、同じように静かな口調と感情を押さえたブランドン大佐を演じて賞も取っていたと思いますが、大佐にはこの映画のデヴァレラほどの迫力がないと感じるのは、私だけでしょうか。
映画では、コリンズを暗殺したのはデヴァレラではない、との解釈です。彼であって欲しく無いとの思いもあるのでしょうが、コリンズの暗殺については実際は分かっていない部分も多く、私も彼がそこまで冷酷ではないと信じたいのです。
「アイルランド独立の英雄」として一般的には知られる、激動の時代を生きた青年の伝記映画。アイルランドの状況についてご存知ない方でも、この映画を見れば彼が母国アイルランドの為に命を捧げた「愛国者」であった事は、理解していただけると思います。この映画を見ようという人は知っているはずのIRAというテロ組織、現在は理念を口実にした人殺しの集まりですが、アイルランドの独立戦争時は、英国からの独立を勝ち取る為に戦うレジスタンスの集団でした。簡単に言えば、コリンズは当時のIRAを先導し、結果的にアイルランドを独立に導いた人物です。
この映画の背景には、アイルランドの700年に及ぶ英国による抑圧と、独立、その後の混乱・・・現在まで続くIRA/UFFの抗争、カソリックかプロテスタントかの宗教の違いや、出身地、主義の違いによる差別や憎悪がいまだ存在する悲しい事実があります。パブやカフェといった公共の場所で、本心を語れない現実がいまだアイルランドには存在します。ダブリンのパブで、近代国家アイルランド共和国のダークサイドについて知りたがる私に、「そんなことを公共の場で口にしないほうがいい」と真剣な表情で忠告されたこともありました。
映画にも描かれる、罪のないアイルランドの人々を惨殺した英国支配からの独立、そしてその後の内戦による、英国人に殺された人数よりもっと多くの死者。私達はこの映画を見る時、描かれている出来事を遠い国の遠い出来事でしか、捉えることが出来ません。。しかし現在も、地球上では主義や種族、宗教の違いで殺しあいは続いています。それが戦争という正式なものなのか、テロとよばれる非公式なものなのかの違いはあっても。また、映画の中で描写される英国側の残忍さ(ほとんど事実です)に、ショックを受ける人もいるでしょう。どうして今だアイリッシュがあれほどまでに英国を嫌うのか、その理由はこの映画を見れば明白になるでしょう。そして、どうしてアジアの国々が日本を嫌うのか、私達日本人は彼等に何をしたのか、可能ならそちらにも思いを馳せて頂きたいと思います。
かつて、1993年北アイルランドとアイルランド共和国のボーダーで、バスの中に自動小銃を持った英国軍兵士達が爆弾を調べに乗り込んで来た時、私は今戦場にいるのだ、と悟りました。彼等が探していたのは北のIRAサイドへアイルランド共和国側から運び込まれる、荷物としての爆発物だったと推測します。殺さなければ殺される、死と隣り合わせの感覚からくる兵士達の空気が切れるような緊張感と、飛び交う軍用ヘリの爆音、声1つ立てず身じろぎもせず凍り付く乗客。私の五感は極限まで研ぎすまされ、乗客の心臓の鼓動まで聞こえるような気がしました。この時の経験は、かつてジャーナリストを目指したことのある私に、多くのジャーナリストたちが自ら戦場を目指す理由を教えてくれました。その場で、状況を共有しなければ決して真実の報道は出来ないのです。伝え聞きや推測では、人々の置かれた状況を理解することは不可能といっても良いかもしれません。
そのような現状のために、アイリッシュであるジョーダン監督はコリンズの映画を撮りたくても撮れなかったといいます。コリンズの映画化には、肯定的に描こうと批判的に描こうと、一歩間違えれば監督生命に関わるかもしれなかったのですから。90年代半ばに、IRAは武装解除に応じ、(その後協定は破られます)その時ジョーダンは映画制作にかかった、と記憶しています。ジョーダンによるコリンズ像は、本人なりに国の為に尽し、貢献したのに、信頼していた上司デヴァレラの策略で、不本意ではあるが現実的な最善策である独立条約(北アイルランドは英国に属すという、アイルランド島を2分割する条約のことです)を締結した当事者とされ、その結果を快く思わない完全独立派に暗殺されてしまう、頭はきれるが直球しか投げられない、朴訥な田舎の青年。アイリッシュのリアム・ニーソンがむっちゃコーク訛りで情熱的に演じます。史実を交え、同僚のハリー(エイダン・クイン)との友情、その後の悲劇、歴史的事実の再現を、アイリッシュ・ミュージックに乗せて見せてくれます。各建造物も見事に再現。ダブリンのロケで、本当にカスタムハウスが燃え上がっているようです。花を添える一応アイリッシュ女性役のジュリア・ロバーツは、正直いりません。映画として少しは色恋があったほうがいいのかもしれませんが、アクセントはまるっきりへただし、ベッドの上のバラの花のシーンなんか臭すぎです。
アラン・リックマンが演じたエイモン・デヴァレラは、当時のアイルランド大統領。目的を遂げる為には命を捧げる覚悟の愛国者であったことは、コリンズと同じだったのですが、この映画では、彼は洗練され、冷静沈着、冷徹な策略家として描かれ、コリンズと対比を生んでいます。ジョーダンのデヴァレラ像はしかし、彼の行為に完全に肯定的では有りません。自分の信念に合わない条約を締結せざるを得ない状況を察したデヴは、理由をつけてコリンズを代表としてイングランドへ送り込んでおきながら!その条約とコリンズを責めます。少なくともそう受け取れる演出です。デヴの不在時に有名になっていくコリンズを、彼が快く感じていないことを明確にもしています。その自分勝手な部分や冷酷さの表現が、最後のコリンズのデヴへの伝言を活かしています。「あなたは何時でも私のチーフなのですから。あなたとなら地獄だろうと一緒に行く覚悟だった。いや、もうすでに地獄にいるのかもしれない。」この辺りは当然創作なのですが、見るたびに涙腺が弛んで困ります。ちなみに、地獄へ行くというのはカソリックの人にとって死ぬより恐いことらしいです。
アランは父親がアイリッシュだとのこと。(言われてみればミドルネームもパトリックだったね)アランは、鉄のような意志を持つこの策略家を、実は神経質で繊細な人物として演じています。アドリブだと思うのですが、会議発言中に手を気にする仕種や、議会からの離脱を宣言する時の顔のぴくつきや微妙に体が揺れる所等、上手いなと感心してしまいます。映画の最初の方で、デヴァレラが本当に書いた獄中からの手紙を彼は朗読します。戦った仲間たちが、次々と処刑されていく中で、「彼等が我々を1人、1人殺すたびに、さらの多くの人々が我々の側に就くだろう」と。感情を押さえた朗読ですが、心に響きます。
デヴの喋りかた、姿勢を、彼は忠実に研究し演じています。「彼等は同胞の血にまみれるだろう」の演説シーン、本物のデヴとそっくりで恐いくらいです。アラン演じるデヴはしかし、本物より魅力的なのは否定出来ません。出番は多く無いのですが、この映画を見るたびアランの見せる表情に引き付けられます。静かな口調と押さえた表情の裏に、激しさと情熱を隠した演技。毅然と振舞い、それでいて最後に見せる感情の起伏。アランは、英雄デヴァレラ像に人間としての魅力を加えました。アランは同時期に「ある晴れた日に」に出演し、同じように静かな口調と感情を押さえたブランドン大佐を演じて賞も取っていたと思いますが、大佐にはこの映画のデヴァレラほどの迫力がないと感じるのは、私だけでしょうか。
映画では、コリンズを暗殺したのはデヴァレラではない、との解釈です。彼であって欲しく無いとの思いもあるのでしょうが、コリンズの暗殺については実際は分かっていない部分も多く、私も彼がそこまで冷酷ではないと信じたいのです。












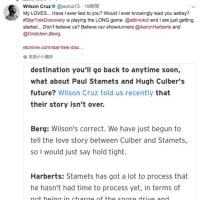


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます