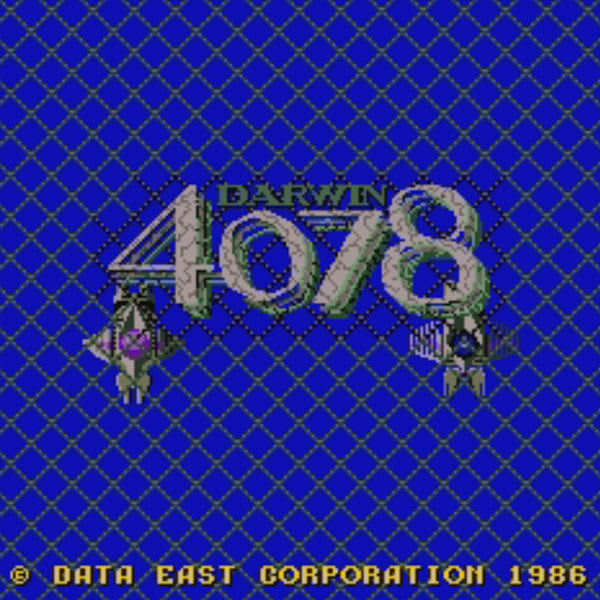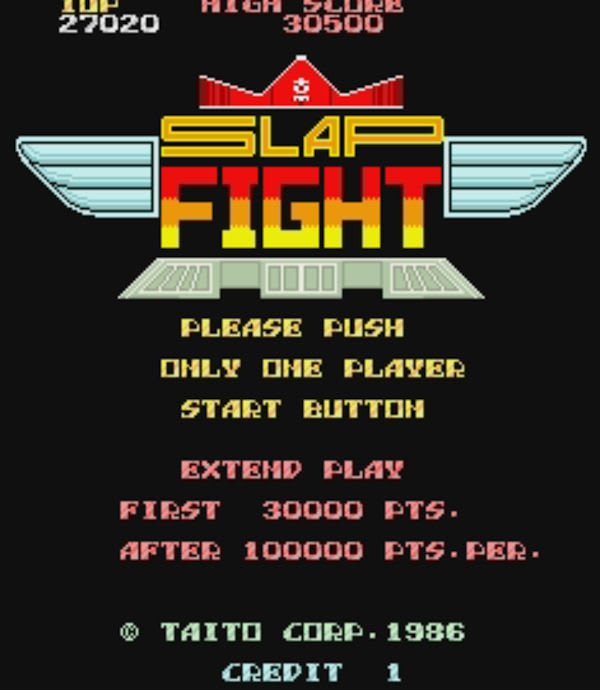3DSが突然1万円も値下げした。よほど任天堂も苦しい立場にあるのだろうが、「3Dモノは当面
メインフレームにならない法則」というのがある気がする。人間の目は正面に2つあり、位置の
差分から自然に立体視が可能となっている。つまり最初から立体視できる目を持っているわけだ。
現在のモニタで3D表示する場合、錯視させて無理矢理立体に見せる。見るという行為に余計な
行程をひとつ追加しているのだ。立体視に無理があるのは、この余分な行程が違和感を感じる
からであり、人間工学に基づいていないのが原因と考えられる。
元々立体視できる目を持っているのに、なぜ無理をして更に立体視しなければならないのかという
事で、それがウザったいわけだ。余程立体で見たくてたまらない映像でもない限り、その根気は
続かないだろう。例を上げればアダルトビデオくらいか。
「飛び出す絵本」というのがあるが、世の中の全ての絵本が飛び出すのは少々ウザい。また全ての
本がいちいち飛び出していたら物凄くウザい。「飛び出す週刊誌」「飛び出す文庫本」「飛び出す
辞書」など、飛び出さなくてもいいどころか、飛び出すなと叫びたくなるだろう。人間はごく
たまにしか飛び出すのを望んでいないのだ。
それでも立体モニタの時代は必ず来るだろう。しかしそれは平面のモニタが目に負担をかけて
立体視するタイプのものではなく、立体のモニタに立体像が浮かび上がるスタイルに限定される
と考えられる。立方体の透明な箱の中の映像を360度から眺められるような物だ。これなら
人間の目は通常の物を眺めるように立体映像を見る事ができる。
だがそのようなモニタの開発には、もう少々時間が必要だろう。
さて、pcfxは「バーチャルボーイ」を発売日に買ったクチだ。実は立体視が好きで好きで
たまらない種類の人間であり、じゃあ今までの前置きは何だったのかと問われれば、そんなのは
一般論だと開き直る。だが、立体視が好きだからこそ、その欠点も細かく指摘できるつもり
になっている。バーチャルボーイは「失敗作」だった。そんな事はわかってた上で購入
した。「今後のゲームはバーチャルボーイだけで発売されることになるぜ!」などとは
毛程も思っていなかった。何しろ赤一色のモニタで、双眼鏡を覗き込むようにゲームをする
というスタイルなのだ。流行るわけがない。
しかし他人に流行るかどうかなど問題ではない。「自分がやりたいかどうか」だけが問題で
あり、pcfxは「立体で見たい人」だ。買うしかあるまい。やるしかあるまい。他に選択肢など
ないのだ。そしてバーチャルボーイのゴルフやシューティングやピンボールを楽しんだ。
買ったことを全く後悔などしていない。お値段以上を遊んだ。満足した。
で、3DSのスペックが発表された時、ガッカリした。モニターがカラーになった事と、ハード
のスペックが上がった事以外は、完全にバーチャルボーイに負けている。迫力も臨場感も
ない、小さなモニターに奥行きをちょびっと感じるだけだ。あんなのを作るぐらいだったら、
まだバーチャルボーイ2として作ったほうがマシだったと思える。現在のハードの性能と
モニタでバーチャルボーイを作れば、売れたかどうかはともかくとして、立体視マシンと
しての完成度は抜きん出ていただろう。売れるのが重要だというのなら、現状の3DSが売れて
いるのかと言われたらお終いだ。つまり結果として、またコンセプトとして、3DSの評価は
「全然駄目」の一言に尽きる。そりゃ売れないわな。
さて、ゲームのコンシューマー機はどうあるべきなのかという事だが、結論を先に言えば、
もうゲーム専用機など必要ないということだ。携帯電話が通話専用機だったのは初期の頃
だけだった。ゲーム機はいつまで専用機を作るつもりなのかは知らないが、そんな単一の
目的にしか使えないものよりも、任天堂スマートフォンを作ったほうがよく、また据え置き
なら任天堂テレビを作ったほうがよいのは当たり前の話だ。もうゲーム機単体という発想から
ダメであり、ゲーム会社のライバルは業界内だけではないという現実に向きあう必要がある。
当然こんなことは言われなくても当事者が一番良く理解していると思うが、結局踏みきれずに
まだゲーム専用機を出しているのだから、立体がどうこうじゃなくてそこが問題なのだといえる。
現在、コンシューマ機の国内メーカーといえば、任天堂とソニーだけという構図になっている。
昔あれだけ乱立していたゲーム機メーカーはもう参戦していない。ライバル会社を駆逐した
結果、二極化の冷戦構造になって立ち往生している。任天堂が今回の失敗で倒産し、また
専用機の需要がなくなった事でソニーが撤退したら、コンシューマ機という概念自体が
終焉する。まるでソ連が崩壊して冷戦構造が終了した事によってあちこちで小競り合いが
勃発したように、スマホ市場やPCゲーム市場で弱小ソフトメーカーがチマチマゲームを
作る事になるだろう。
ここまでは「どうなるか」という話だったが、果たしてそれでいいのか。誰がそれを望んで
いるのか。そんなつまらない未来で楽しいのか。答えは否だろう。誰得未来像を邁進するのは
そろそろやめにしてはどうなのか。
ソフトのプラットホームはスマホとパソコンで十分だ。専用機を作る必要はない。スマホなら
割と簡単に作れるだろうが、1つ重要なものを忘れている。
いいかげん、日本の企業はパソコンOSを作ったらどうなのか。いつまで米国製OSを放置して
いるのか。国産パソコンはどうしたのか。どうして作ろうとしなくなった。マイクロソフトと
IBMに弱みでも握られているのか。ネットの規格さえ共通していれば、ハードやOSなど
好きなように作れる筈だ。ゲーム屋がゲーム専用機を作れないのなら、次のターゲットは
任天堂OSに任天堂パソコンだろう。この際ソニーでもいい。今からでも遅くない。というか、
もうそれを作るしかない。一社で不安というのなら、国内電機メーカーで共通規格とか
作ればいい。いつまで足の引っ張り合いを続けるのか。MSXの時代を忘れたのか。
どっちみちこのままだとコンシューマ機などなくなるのだから、運を天に任せて、最後に
デカイ花火を上げて散ってみてはどうだろう。思い切ってセガを巻き込むという手もある。
こういう思い切った事はセガが得意だ。京都の狭い商習慣など全部切り捨てる時だ。企業など
いつかは消えてなくなるものだ。株主など寄生虫だと思えば良い。
最後にもう一つ。ビデオゲームのブームは「戦いへの飢え」に支えられてきた。日本は戦争
できない国なので、若者はゲームで戦っていたわけだ。その条件は変わっていない。また
日本は「愛への飢え」も顕著だ。若者はゲームで愛を満たしている。現実には手に入らない
「飢えを満たす」のがゲームという仮想行為ならば、「飢え」を徹底的に満たす物を作れば
いいのだ。若者が今何に飢えているのか、見てればわかりそうなものだ。ハードの性能はそれを
満たすために使えばいいだけの話である。
3DSの結論としては、「3DSの本当の性能を引き出したのはラブプラス3Dだけ」という結果が
待っており、それを最後に3DSは役目を終了するだろうという事だ。最初に出せばよかったのに。
メインフレームにならない法則」というのがある気がする。人間の目は正面に2つあり、位置の
差分から自然に立体視が可能となっている。つまり最初から立体視できる目を持っているわけだ。
現在のモニタで3D表示する場合、錯視させて無理矢理立体に見せる。見るという行為に余計な
行程をひとつ追加しているのだ。立体視に無理があるのは、この余分な行程が違和感を感じる
からであり、人間工学に基づいていないのが原因と考えられる。
元々立体視できる目を持っているのに、なぜ無理をして更に立体視しなければならないのかという
事で、それがウザったいわけだ。余程立体で見たくてたまらない映像でもない限り、その根気は
続かないだろう。例を上げればアダルトビデオくらいか。
「飛び出す絵本」というのがあるが、世の中の全ての絵本が飛び出すのは少々ウザい。また全ての
本がいちいち飛び出していたら物凄くウザい。「飛び出す週刊誌」「飛び出す文庫本」「飛び出す
辞書」など、飛び出さなくてもいいどころか、飛び出すなと叫びたくなるだろう。人間はごく
たまにしか飛び出すのを望んでいないのだ。
それでも立体モニタの時代は必ず来るだろう。しかしそれは平面のモニタが目に負担をかけて
立体視するタイプのものではなく、立体のモニタに立体像が浮かび上がるスタイルに限定される
と考えられる。立方体の透明な箱の中の映像を360度から眺められるような物だ。これなら
人間の目は通常の物を眺めるように立体映像を見る事ができる。
だがそのようなモニタの開発には、もう少々時間が必要だろう。
さて、pcfxは「バーチャルボーイ」を発売日に買ったクチだ。実は立体視が好きで好きで
たまらない種類の人間であり、じゃあ今までの前置きは何だったのかと問われれば、そんなのは
一般論だと開き直る。だが、立体視が好きだからこそ、その欠点も細かく指摘できるつもり
になっている。バーチャルボーイは「失敗作」だった。そんな事はわかってた上で購入
した。「今後のゲームはバーチャルボーイだけで発売されることになるぜ!」などとは
毛程も思っていなかった。何しろ赤一色のモニタで、双眼鏡を覗き込むようにゲームをする
というスタイルなのだ。流行るわけがない。
しかし他人に流行るかどうかなど問題ではない。「自分がやりたいかどうか」だけが問題で
あり、pcfxは「立体で見たい人」だ。買うしかあるまい。やるしかあるまい。他に選択肢など
ないのだ。そしてバーチャルボーイのゴルフやシューティングやピンボールを楽しんだ。
買ったことを全く後悔などしていない。お値段以上を遊んだ。満足した。
で、3DSのスペックが発表された時、ガッカリした。モニターがカラーになった事と、ハード
のスペックが上がった事以外は、完全にバーチャルボーイに負けている。迫力も臨場感も
ない、小さなモニターに奥行きをちょびっと感じるだけだ。あんなのを作るぐらいだったら、
まだバーチャルボーイ2として作ったほうがマシだったと思える。現在のハードの性能と
モニタでバーチャルボーイを作れば、売れたかどうかはともかくとして、立体視マシンと
しての完成度は抜きん出ていただろう。売れるのが重要だというのなら、現状の3DSが売れて
いるのかと言われたらお終いだ。つまり結果として、またコンセプトとして、3DSの評価は
「全然駄目」の一言に尽きる。そりゃ売れないわな。
さて、ゲームのコンシューマー機はどうあるべきなのかという事だが、結論を先に言えば、
もうゲーム専用機など必要ないということだ。携帯電話が通話専用機だったのは初期の頃
だけだった。ゲーム機はいつまで専用機を作るつもりなのかは知らないが、そんな単一の
目的にしか使えないものよりも、任天堂スマートフォンを作ったほうがよく、また据え置き
なら任天堂テレビを作ったほうがよいのは当たり前の話だ。もうゲーム機単体という発想から
ダメであり、ゲーム会社のライバルは業界内だけではないという現実に向きあう必要がある。
当然こんなことは言われなくても当事者が一番良く理解していると思うが、結局踏みきれずに
まだゲーム専用機を出しているのだから、立体がどうこうじゃなくてそこが問題なのだといえる。
現在、コンシューマ機の国内メーカーといえば、任天堂とソニーだけという構図になっている。
昔あれだけ乱立していたゲーム機メーカーはもう参戦していない。ライバル会社を駆逐した
結果、二極化の冷戦構造になって立ち往生している。任天堂が今回の失敗で倒産し、また
専用機の需要がなくなった事でソニーが撤退したら、コンシューマ機という概念自体が
終焉する。まるでソ連が崩壊して冷戦構造が終了した事によってあちこちで小競り合いが
勃発したように、スマホ市場やPCゲーム市場で弱小ソフトメーカーがチマチマゲームを
作る事になるだろう。
ここまでは「どうなるか」という話だったが、果たしてそれでいいのか。誰がそれを望んで
いるのか。そんなつまらない未来で楽しいのか。答えは否だろう。誰得未来像を邁進するのは
そろそろやめにしてはどうなのか。
ソフトのプラットホームはスマホとパソコンで十分だ。専用機を作る必要はない。スマホなら
割と簡単に作れるだろうが、1つ重要なものを忘れている。
いいかげん、日本の企業はパソコンOSを作ったらどうなのか。いつまで米国製OSを放置して
いるのか。国産パソコンはどうしたのか。どうして作ろうとしなくなった。マイクロソフトと
IBMに弱みでも握られているのか。ネットの規格さえ共通していれば、ハードやOSなど
好きなように作れる筈だ。ゲーム屋がゲーム専用機を作れないのなら、次のターゲットは
任天堂OSに任天堂パソコンだろう。この際ソニーでもいい。今からでも遅くない。というか、
もうそれを作るしかない。一社で不安というのなら、国内電機メーカーで共通規格とか
作ればいい。いつまで足の引っ張り合いを続けるのか。MSXの時代を忘れたのか。
どっちみちこのままだとコンシューマ機などなくなるのだから、運を天に任せて、最後に
デカイ花火を上げて散ってみてはどうだろう。思い切ってセガを巻き込むという手もある。
こういう思い切った事はセガが得意だ。京都の狭い商習慣など全部切り捨てる時だ。企業など
いつかは消えてなくなるものだ。株主など寄生虫だと思えば良い。
最後にもう一つ。ビデオゲームのブームは「戦いへの飢え」に支えられてきた。日本は戦争
できない国なので、若者はゲームで戦っていたわけだ。その条件は変わっていない。また
日本は「愛への飢え」も顕著だ。若者はゲームで愛を満たしている。現実には手に入らない
「飢えを満たす」のがゲームという仮想行為ならば、「飢え」を徹底的に満たす物を作れば
いいのだ。若者が今何に飢えているのか、見てればわかりそうなものだ。ハードの性能はそれを
満たすために使えばいいだけの話である。
3DSの結論としては、「3DSの本当の性能を引き出したのはラブプラス3Dだけ」という結果が
待っており、それを最後に3DSは役目を終了するだろうという事だ。最初に出せばよかったのに。