昨日、文末にカレンダーに使った桜の花から入学式へと連想したのでした。
その夜、朝日新聞「ひととき」欄に47歳の女性がランドセルの思い出を書いていらっしゃいました。義父の介護をしていて心が沈みがちだった。夕方、河原の土手が夕日を浴びて輝く景色の荘厳さにうたれて勇気を掻き立てていた。
子どもにランドセルを買う頃になった。色も自由に選べる豊かな時代に、娘は土色の地味な色を選んだ。何故?と聞くと、「お日様に当たると金色に輝くから」と答えた。二人同じ美しさを感じていたのだ。娘が使わなくなったランドセルは途上国へ送ることにした。
家族のいい思い出になりますね。
私は、昭和20年、終戦の年の4月に小学校でなく、国民学校一年生に入学しました。その頃のことを語る最後の世代でしょうか。
山口県のごく田舎の村の国民学校でした。貧しい時代でした。物のない、お金のない時代でした。ランドセルを新しく買うといった時代ではありませんでした。大抵のこどもが古布の風呂敷に包んで教科書を運んだのだったと思います。包むべき教科書も墨で真っ黒に塗りつぶした 兄姉のお古を使っていたのでした。4年生になって、やっと新しい教科書が配布されたのでしたかしら。それも現在っ子には思いもつかないものでしょう、紙質も、活字もおんぼろの今でいう新聞紙様のものが配られたのです。それを折って切って糸でとじたのでした。その教材の一つに「校門の樫の木」という長文がありました。もう覚えていませんが、これを全文暗唱して朗読したのでした。声を揃えて真面目にやっているのですが、まず出だしは必ず笑いになるのでした。「校門」=「肛門」、センセイの困ったような顔も思い出せます。
元に帰って、ランドセルのない時代、私は背負っていたのです。5兄が3歳年上で、私が新入生の時は4年生になったところだったのです。母が私に譲るように勧めたのか、自発的に妹に下げてくれたのか、私はランドセルを背負ったのです。
色は黒でした。あれはいったいどういう材質だったのでしょうか、今思い出しながら書くと、厚いボール紙をカチカチに固まらせた板状のものを、ランドセルの形にしたものでした。プラスチックなどはまだなかったと思います。戦争の最後の頃は、戦闘機さえいろんな材料を工夫したらしいのですから、なにかの液をしみこませて乾かしたものだったのでしょうか。兄たちが順繰りに下げていったにしてはきちんと形状を保った立派なものでした。立派すぎて・・・
ところがこの硬さが・・・ランドセルの厚みそのままに変わらないのです。その頃各自の椅子の背に布製の袋などを下げていたのですが、・・・私もそうしていましたが・・・「起立!」の号令がかかった時、ランドセルの厚み分,机と机の距離がランドセルでふさがるのです。立てないのです。困ったことでした。
さて孫の時代のランドセル話。時々ブログに登場するH君が1年生に入学することになった時です。(今はもう20代最後くらいかな)。山口市の繁華街のかばん屋さんに買いに行ったのだそうです。選んでいると、おばさんが
「かるうてみいさん。こっちも、こっちも」と勧めてくれたのだそうです。この「かるう」が分からなかったと、東京から越していった家族は困ったのだそうです。
4月、入学式。クラス分けが発表になり、担任の先生とご対面。終わりのホームルームの最後に先生。
「まだ、明日はランドセルはかるうてこんでもええからね」。
「かるう」は「背負う」でした!!
カルチャーショックなどと言ってはおれません。しっかり山口弁を学ばなくっちゃと思ったのだそうです。


















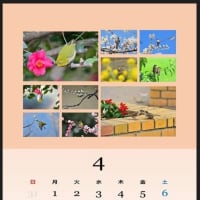

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます