
池澤夏樹 『カデナ』
新潮社:2009年 新潮文庫:2012年
あの夏、私たちは四人だけの分隊で闘った――。![]()
ベトナム戦争末期、沖縄カデナ基地の中と外を結んで、巨大な米軍への抵抗を試みた四人だけの小さな「スパイ組織」があった。戦争という個人には抗いがたい現実と、それでも抗おうとするごくふつうの人たちの果敢な姿を、沖縄戦後史のなかに描きだす。著者の沖縄在住十余年の思索と経験のすべてが注ぎ込まれた傑作長篇小説。
新潮社
<例会レポート>
9月27日の例会は、男性会員7名、女性会員15名の参加で行われました。課題本は池澤夏樹『カデナ』。珍しく参加メンバーからの否定的な意見、感想はまったくと言ってよいほど聞かれず、推薦者としてはちょっとびっくりしました。こういうテーマの本に対しては拒否反応を示す人がいると思っていたからです。
以下に感想を列記します。
・世界主義(コスモポリタン)で描かれている。
・やらされている戦争と、自分の意思で止めることも可能な反戦活動。その対比が面白かった。
・二度目だが読み直してみて初読のときより心に迫るものがあった。3.11以降の自分の受け止め方が変わってきたのだろうか。朝栄さんの、境界をさまよう人たちに対する共感、あたたかいまなざしに心を打たれた。
・悲劇が起こる予感を持ちながら読んだ。世の中に危機感がある今、この本を読めてよかった。
・戦争ものかと思いなかなか手をつけなかったが、読み始めたら面白かった。軽すぎず、重すぎずのフリーダの口調がいい。
・ザラザラとした現実を突きつけられた感じ。
・池澤夏樹は始めて読んだ。自分史と重ねて読むことができた。
・池澤夏樹は勇敢で安住しない作家。尊敬している。
・すごくいい小説だった。戦争のキズを持つ4人が個人の生活の中で続けているささやかな抵抗と反戦の意思。
・過不足なく人の気持ちが描かれていた。沖縄戦の情景が浮かんでくる洞窟のシーンにはしみじみした。
・世代的にベトナム戦争には現実感がなかったが、登場人物像や背景がわかってきてから面白くなった。
・戦争は遠いところで行われているものだと思っていた自分だが、この本からは、ちょうどイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」を聴いたときのような、何かが終わったという喪失感を感じた。
・知花先生の組織論は今のものを持ってきている(←モデルは鶴見俊輔との講師からの指摘あり)。
・食べ物や模型や車などモノの描写がリアル。
・60年代末期の話だが、今読んでみても違和感を感じない。書き方によっては重苦しくなるテーマを淡々と書いている。
・読みやすくすらすらと最後まで読めた。
・登場人物4人それぞれの気持ちはよく理解できた。それに比べてパトリックには魅力がない。フリーダとパトリックのエピソードは、アメリカ映画を見ているようだった。
このように参加メンバーからは熱い思いが語られ、その結果、今回も菊池先生の持ち時間が少なくなってしまいました。当日の講評は以下にまとめますが、話し足りなかったこと、これだけは言っておきたいことなどは、先生、ぜひともブログ(会員限定サイト)に書き込んでください。
・本書では、その時代、その国、その言語など、作者の世界観がまとめて表現されている。あえてカタカナで表記した「カデナ」というタイトルは、沖縄の一つの土地が完全にアメリカの基地になっていることを表している。作者は、処女作以来、ずっとアメリカと対峙する姿勢を鮮明にしている。それは、「侵略者」と「静かな生活をおくる人々」との対峙でもあると思う。
推薦者が驚いたことは、参加メンバーの多くがもうベトナム戦争を知らない世代だったということでした。「初めて意識した戦争がフォークランド戦争だった」という発言を聞いて、ずいぶんと時が流れたのだなぁ、と思いました。
ベトナム戦争当時、推薦者が住んでいた町の近くにはアメリカ軍の大きな基地や補給廠があり、よくヘリコプターが飛来していました。「ヘリでベトナムから負傷者や死体を運んで来るんだよ」と、周囲の大人は教えてくれました。ヘリが多く飛来した次の日の新聞やニュースは、決まってベトナムで大規模な戦闘があったことを報じていました。
まだ子どもだった推薦者ですが、主に深夜放送を通してベトナムで何が起こっているかを知るようになり、反戦フォークを聞いたり、同時代作家の小説を読むことで、何となく日本とアメリカの関係、日本とベトナム戦争の関係などを理解していったと思っています。当時は、森山良子も「愛する人に歌わせないで」という反戦歌を歌っていましたし、少年・少女マンガにも日常的に反戦マンガが掲載されていました。都会では、鶴見俊輔や小田実のベトナムに平和を!市民連合(いわゆる「ベ平連」)がデモをしたり、脱走兵を助ける活動を行っていました。
もし興味がある人は以下にあげる小説やマンガを読んでみてください。ほとんどは絶版や品切れで手に入りにくいものですが、言ってくれればお貸ししますよ。
同時代の作家の中でもっとも積極的に作品を発表していたのが、五木寛之。『海を見ていたジョニー』(人を殺した帰還兵はジャズを演奏できるのか。傑作中の傑作)、『天使の墓場』(墜落したB52に積まれていたものは。非核三原則って知ってる?)、『GIブルース』(岩国基地からの脱走兵の悲劇)など。マンガでは、真崎守や宮谷一彦ら若手劇画マンガ家が大人向けの先鋭的な作品を発表していましたし、手塚治虫・石森章太郎らベテランも子ども向けの作品で反戦を主張していました。前者には、『0次元の丘』(ソンミ村虐殺事件と輪廻転生)、『イエローダスト』(沖縄の基地に秘匿されていた厭戦対策薬の悲劇)、『ジョーを訪ねた男』(ベトナム戦争と人種問題を描く)。後者には、『サイボーグ009』のエピソードをはじめ、『おかしなおかしなおかしなあの子(さるとびエッちゃん)』の一作などに叙情的な作品が残っています。
もっと手に入れやすいものならば、集英社から刊行中のシリーズ『戦争×文学』の2巻と20巻が、それぞれベトナム戦争と沖縄戦をテーマにしたアンソロジーになっています。
長くなりまして失礼いたしました。










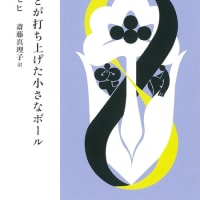
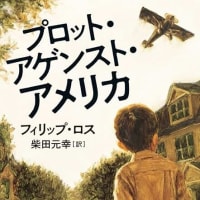













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます