
高井有一『この国の空』
新潮文庫 2015年 (初出は1983年)
戦争末期の東京――空襲に怯え、明日をもしれぬ不安な日々を生きる十九歳の里子。母と伯母と女三人、杉並の家に暮らす彼女の前に、妻子を疎開させた隣人・市毛が現れる。切迫する時代の空の下、身の回りの世話をするうち、里子と市毛はやがて密やかに結ばれるが……。戦争の時代を生きる市井の人々の日常と一人の女性の成長を、端正な筆致で描き上げた長編文学作品。谷崎潤一郎賞受賞作。(Amazon内容紹介より)
=例会レポ=
「わたしが一番きれいだったとき
街々はがらがら崩れていって
とんでもないところから
青空なんかが見えたりした
わたしが一番きれいだったとき
まわりの人達がたくさん死んだ
工場で 海で 名もない島で
わたしはおしゃれのきっかけを落としてしまった」
講師が本書のモチーフとして紹介してくれた茨木のり子の詩「わたしが一番きれいだったとき」の冒頭です。映画版『この国の空』のラストでも使われたこの詩が、本書の主人公・里子の生活、思い、哀しみのすべてを言い尽くしているようです。
さて、戦争体験者(と言っても幼いころ)や、親や祖父母から伝え聞いただけの世代の男女11名(男性2名・女性9名、講師は除く)の例会参加者からは、先ず本書が描く〈戦争のリアル〉についての賛否両論が挙がりました。
「戦時中の閉塞感を感じた」
「舞台となった場所を知っていたり、旅行したことのある場所だったり、住んだことのある場所だった」
「空襲で焼け出されたりするなど、ヒリヒリ感がある」
「体験した作者ではないと書けない。見聞きしたことに他者からの聞き書きで肉付けしている」
「リアルさは感じられなかった」
ところで、物語に描かれる〈リアル〉って何でしょうね。
ジャンルによっても異なるでしょうが、時代設定も風俗描写も関係なく、何でも頭に浮かんだことを筆の勢いで思ったままに書き連ねるフィクションに徹した小説もあるでしょう。それに対して、当事者への取材、綿密な考証を経て、言葉の一つ一つ、立ち居振る舞いの一挙一動にまでこだわって書き上げられた小説もあるでしょう。ただ、後者にばかり比重がかかると、いきおい物語としてのエンタテインメント性に欠けるきらいもあるように思われます。そういうのは、ドキュメンタリーやルポルタージュといったジャンルにまかせておけばいいのです。少なくとも本書のような「物語」=フィクションを読む際には、登場人物の行動や考え方の背後に横たわっている背景、つまりその時代の歴史や文化を学習し、そこから作品に込めた作者の意図を類推する努力も必要なのではないでしょうか。作者が書かなかった、あるいは書けなかった〈リアル〉は、読者の想像力に寄って立ち上がってくるものかもしれませんね。
講師は、本書の設定に注目し、
「自由のない非常時にあって、事務員として働くことで町内の人々の動静を自然に知っていく里子。普段ならそんなこともないだろう老人たちとも触れ合う。こうやって、普通では見えなかったものが見えてくる」
と解説してくれました。
もう一つ、話題になったのは、「なぜ里子と市毛は結ばれたのか」という疑問。ある種、「お約束」的なこのシーンに対しても、
「最後の結ばれるシーンは受け入れられない」
「男性目線。そこに市毛がいたから何となくつきあっちゃったのかな」
「誰かに頼らなければ生きていけない女性の姿。でも、母はなぜ里子を市毛のもとに送り出したのか」
という感想がありました。
「わたしが一番きれいだったとき
だれもやさしい贈り物を捧げてはくれなかった
男たちは挙手の礼しか知らなくて
きれいな眼差しだけを残し皆発っていった」
死が偏在する銃後の生活、平和だったら異性との恋愛を楽しんでいるだろう里子が、老人ばかりしか周囲に残っていない中、身近の男性の市毛に惹かれていくのは当然のことかも知れません。思い出したのが、ジョージ・スティーブンス監督の『アンネの日記』(1959年)のラスト、隠れ家に踏み込んでくるゲシュタポの軍靴が響く中、それまでの思いが堰を切ったようにあふれ抱き合うアンネ(ミリー・パーキンス♡)とペーター。いずれにも、切羽詰まった極限状態での愛の姿を見る思いがします。「里子にとっての記念碑」とは、講師の言葉です。
さて、感想にもあるように、終盤までは里子が市毛に弄ばれているのではと危惧する母・蔦枝の姿が何度か描かれていますが、ラストでは(おそらく二人がすでに結ばれたことを知っているうえで)、「里子、お送りしたら」と、二人だけになること、つまりまた市毛に抱かれることを肯定するような発言をしています。
ここで注目したいのは、その夜、里子と蔦枝の家を訪ねた市毛の口から終戦が近いことを教えられた事実。戦争が終われば市毛の妻子が疎開先から帰ってきて家族水入らずの生活が始まり、里子への思いは消えてしまう。また、戦争に負ければ占領軍に男は去勢され、女は強姦されるという噂が信じられていた当時の日本。せめて短い間でも愛した男性との限られた日々を過ごさせてやりたという、伝えの不憫な娘へ寄せたせめてもの親心と考えるのはうがった見方でしょうか。
本書全体に漂う雰囲気を、
「全体を覆うやるせなさ」
「当時の生活を淡々と描いている」
「戦争な悲惨な描写がなかった」
「里子と市毛の恋はあるけれど、灰色一色のイメージ」
と評した感想がありました。しかし、市毛との別れを実感しながらも、戦争の終わったあとの新しい生活に希望を見出そうとする里子の姿を、茨木のり子は予言するようにこう詠っています。女性って、強いですよねぇ~。
「わたしが一番きれいだったとき
わたしの国は戦争で負けた
そんな馬鹿なことってあるものか
ブラウスの腕をまくり
卑屈な町をのし歩いた」
(追記)なお、参加者や講師から以下のような書籍の名前が挙がりました。興味を持たれた方は、是非。
グードルン・バウゼヴァング『片手の郵便配達人』みすず書房
大江健三郎『芽むしり仔撃ち』新潮文庫
瀧井孝作『無限抱擁』岩波文庫ほか
(以上)










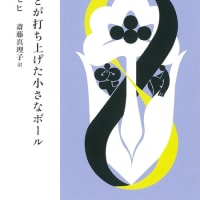
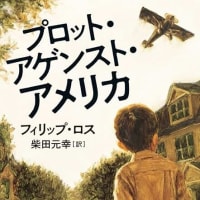













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます