
価格:¥ 2,625 (税込)
単行本 ; 203 p ; サイズ : 26(cm)
出版社 : ウルトラヴァイヴ
現実はつまらない。仕事は忙しいけれど、給料はさっぱり上がらない。家に帰れば、何年もセックスレスの妻と、言うことを聞かない子どもたちが文句ばかりを言う。年金支給の開始は延期されるというし、定年まで延びるそうだ。目の前ににんじんをぶら下げられて、それを目標に走り続けてきた馬だって、そのにんじんがなくなればへたり込んでしまう。現実にも未来にも夢も希望が無い、そんなときは……そう、バック・トゥ・ザ・パスト、過去への逃避である。「あのころはよかった」と、ノスタルジーにひたるのだ。
と、いうわけで、今回の『和モノ事典1970’s人名編』。一種のキワモノ企画かもしれないけれど、70年代にこだわりを持つ世代にとっては、お涙モノの一冊だ。全体は、映画編と音楽編の二部構成で、それぞれの分野で70年代に活躍した約690人のデータが、50音順に記されている。特記すべきは、選択ならびに記載の基準が「70年代」に限られていることだ。だから、それ以降現代も当時と同じスタンスで活動を続けている人物にとっては、彼・彼女のその後にとって70年代がどのような意味を持っていたのか、が理解できる仕組みになっているし、逆に時代とともに消えていった人物、時代に迎合して変節を遂げた人物などの履歴もよくわかると思う。
人物紹介自体は、スペースの都合からか簡潔すぎて物足りなさも感じられるけれど、編集者がおそらくは個人の思い入れでピックアップした、見開き掲載の50人については圧巻である。映画編の秋吉久美子に始まり、音楽編の吉田拓郎で終わる50人の生き様は、ぼく自身がまがりなりにも彼らと同じ時代を併走した(正確に言えば、後をよたよたと追い続けた)ことを思い出させてくれる。
70年4月に高校に入学し、78年4月に社会人になったぼく。このほぼ10年間を世の中の流れに当てはめてみると、奇しくも70年3月の日本万国博覧会開幕と、78年4月4日のキャンディーズさよならコンサートが符合する。70年代という戦後最大の祭りの始まりと、その終焉に、ぼくの「青春」と呼ばれる人生の一時期が重なり合って見える。無条件に、日本の、そして自分自身のばら色の未来を信じた70年初頭の自分と、届かぬ思いや見果てぬ夢を抱いたまま70年代を不完全燃焼にしか終わらせられなかった自分自身。70年代に思いをはせるとき、ぼくはいつも自己嫌悪と懐かしさが入り混じった、ひどくアンビヴァレンツな感情に我とわが身を引き裂かれる。
ぼくは、どこから来て、どこへ行くのか……かつて、「帰りたい、帰れない。帰れないなら、進むだけです」という嘆息をよく口にしていたぼくだけれど、「進む」ことと「流される」こととは、根本的に違うものなのだろうと最近良く考える。
こうした感想は今だからの評論家的なものであり、当時のぼくはそれなりにいい思いもしたし、本も読んだし、映画も見たし、恋だってした。その事実に対しては、堂々と胸を張ることができる。ケータイでメールを打つことだけが自慢のいまどきの兄ちゃん、姉ちゃんたちよ。ぼくはあんたらが伝説でしか知らないような、この本に載っている素晴らしい人たちと同じ時代を生きたんだぞ。
とりとめのない文章になってしまったが、最後に、本事典に先立つ企画として、同じスタッフの編集による『歌謡曲名曲名盤ガイドJAPANESE POPS1970’s』があり、こちらも甲乙付けがたい名著であることを付記しておく。
(T.I.)










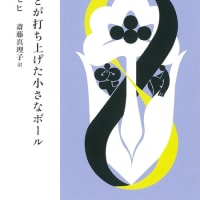
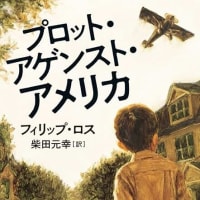













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます