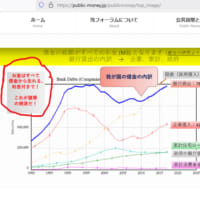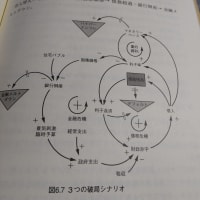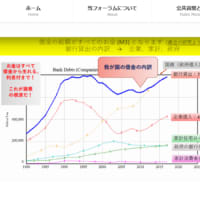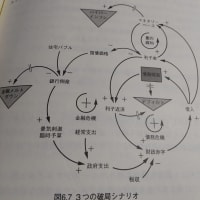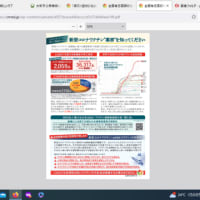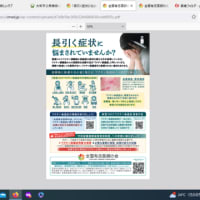とあるスナックで
コー
ではまたまた読んでいこう。
p-243
これだけ進歩した世の中に生きている聡明な人々がどうして、「通貨供給を増やせば富が増える」などと信じてしまうのだろうか。中央銀行と紙切れ通貨の旗振り人たちは、健全な経済理論よりも強欲と権力への誘惑にかられて不健全な政策を支持しているのである。この問題について深く考えたことがなく、疑問を抱くこともなく信じている人もいるだろう。(コー注:たしかに日本にも沢山いるようだ)ーーーー
若者たちは、自分たちが受け入れなければならない経済的な混乱は巨大で、それが連銀と紙切れ通貨に関連していることに気がついている。連銀の政策は何十年にわたって悲劇的な結果を招いてきた。これから人々は必要に迫られて、堅実なお金について学び始めることになるだろう。(コー注:残念だが、日本の若者も中国の若者もバブルとバブル崩壊が起こり、悲惨な経済状況になり、日本は30年、40年と所得が伸びず、経済成長しないという状況が、原因は「お金の問題」そのものにあるという事を考える若者は、おそらくいないんだろうと思う。お金のしくみ「信用創造」さへ、理解していないのだから。)
p-253
関税というものを最も単純に説明すると次のようになる。自由経済の国では、国民は自分のお金を自分が使いたいように使う権利を持っている。貧しい若者が中国製のスニーカーを手ごろな値段で買いたいならだれにもそれを妨げる権利はない。ただ、関税は憲法で合法的に認めれれている。もし連邦政府が福祉や戦争になど浪費せず、憲法で定められている規模の国家予算ならば、輸入品に均一な関税をかけるだけで充分にやっていけるのである。これは所得税や付加価値税などよりずっとまともだ(訳注:実際にアメリカ連邦政府は1913年に所得税が導入されるまで関税だけで予算を賄っていた)。
p-254
経済不況や恐慌が起きれば、だれもがその経済の落ち込みを認める。だが大部分のアメリカ人は偽りの経済学ですっかり洗脳されている。何が経済の落ち込みの真の原因なのか、少しもわかっていない。だから経済を復活ささせるために政策を正すことが出来ないのである。しばしば国民、政治家、中央銀行家がそれまでとまったく同じ政策を、経済を復活させるために必要だと要求するのである。すなわち財政支出の拡大、国債の増発、さらなる規制、そして通貨膨張である。これらは何一つとして問題の解決には役にたたない。それどころか問題をさらに悪化させるのである。(コー注:いやー、耳がいたいね。)
p-271
理想的な世界では連銀はただちに廃止される。新たな通貨供給は停止され、通貨供給量は一定になる。これは信用がなくなるという事ではない。もともと信用というのは預金から生まれるもので、中央銀行がお金を刷るから生まれるものではない。議会は連銀から免許を取り上げ、大統領は新しい連銀議長を任命するのをやめる。連銀の豪奢な建物は、他の目的のために使われるだろう。(普通の銀行が買い取ってもいいだろう)。同時にドルは、もう一度金と兌換できるようになる。連邦政府が所有している金準備は、国内外でのこの兌換を保証するのに使われる。お金に関連したその他のすべての権限は財務省に移管される。もちろん、この政府の権限を監視する、チェックの仕組みが設けられる。
連銀を持たない金本位制は政府に規律を与える。ワシントンでも新しい堅実な財政風土が生まれることになる。戦争や政府の政策のコストが、はっきりと明確にわかるようになる。一般の家庭と同じで、経済的に困難の時は何でもすべて好きなことをやるわけにはいかないと、議員はかがつくことになる。議会は選択を迫られる。歳入が充分でなければ、予算を削減しなくてはならなくなる。現実世界と同じように、この家計の法則が議会の野心を制御するようになる。そうなれば正直に自分が約束したことだけをやる、新世代の指導者が生まれてくるかもしれない。
だが、この優れた金本位制を再導入するためには、連銀の廃止をまず先にしなければいけない。ドルは世界で傑出した役割を担っている。それは堅実な通貨としての長い歴史があったからで、アメリカはその恩恵を受けているのだ。
p-279
連銀はズルをしている
連銀=税金である
連銀は偽金を作っている
連銀は一般大衆の費用で、ごく一部の人間だけを富ましている。
連銀は契約の原則を破っている。
連銀は罪のない人間を罰し、苦しめている。
連銀は戦争を可能にして権力者に莫大な利益を捧げている。
ーーー 終わり ーーー
小林
コーサン、読み終えてどうですか、感想は。
コー
そうだな、どうも金本位制は、ピンとこないな。
俺としては、「100%準備率での融資と、1%準備率での融資では何が、そしてどこが違うのかという事を先に知りたいな。そしてそれぞれ、返済不能となったときに、どう違うかという事だ。
いっぺんに金本位制に持っていくことは難しいけれど、準備率をだんだん上げていくことは出来るんじゃないだろうか。もちろん銀行は大反対だろうけど。
小林
この本の92ページあたりに、オーストリア経済学者というのが出てきて、マレー・ロスバートという人が紹介されていましたね。
ロスバードの本で、「アメリカの大恐慌」と「政府はお金に何をしたのか」という2冊ですね。こちらも出来たら読んでみたいですね。
コー
実は、アマゾンのKindle版で読み始めているんだ。いやー専門的でちんぷんかんぷんだな。ただ著者は、アメリカのあの大恐慌の原因は何だったのかを徹底的に追及したかったんだろうと思う。
小林
お願いしますね、また感想を聞かせてください。
コー
そうだね、ちょっと時間が掛かるけど、出来たらそうしたいと思う。