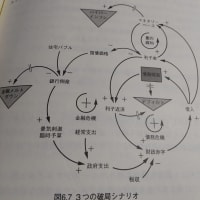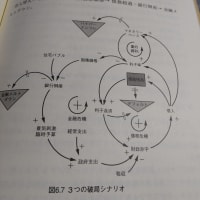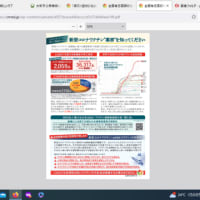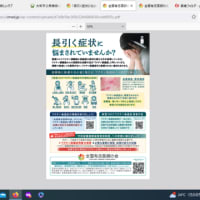とあるスナックで
小林
コー
小林
コー
小林
コー
小林
小林
しかし以前見た12歳のカナダ人の彼女は、まだあどけない感じの子でしたね。
コー
そうだね、12歳の子が、ここまでわかって言うのかな。
本当に彼女がこの<債務貨幣システム>を理解し、この言葉を言ったとしたら大したもんだな。
俺らは、<債務貨幣システム>を理解するのに1年以上かかり、それでもまだ完全に理解できていないんだから。
結論
結論として、私達は銀行制度と共謀した政府によって、横領され、略奪され続けていることは12歳カナダ人の私ですら、痛ましいほど明らかなことです。
この犯罪を止めるには私たちは何をすべきでしょうか?次の世代が銀行家により奴隷にされる借金ベースの経済から自由で解放されるために何をすべきでしょうか?
本当に彼女がこの<債務貨幣システム>を理解し、この言葉を言ったとしたら大したもんだな。
俺らは、<債務貨幣システム>を理解するのに1年以上かかり、それでもまだ完全に理解できていないんだから。
結論
結論として、私達は銀行制度と共謀した政府によって、横領され、略奪され続けていることは12歳カナダ人の私ですら、痛ましいほど明らかなことです。
この犯罪を止めるには私たちは何をすべきでしょうか?次の世代が銀行家により奴隷にされる借金ベースの経済から自由で解放されるために何をすべきでしょうか?
小林
ここで彼女も問題にしている、なぜ政府が金融機関から利息のついたお金を借りなければいけないのかということなんですが、これは<通貨発行権>の問題なんですか。
コー
政府が歳入の範囲で支出をしていれば、そもそも政府の借金の問題はないんだろうが、世の中が不況になればそうもいかなくなるわけだ。政府が借金をして公共事業、財政出動をしなければ、景気は回復しないんだろうと思う、今の<債務貨幣システム>では。
そうなんだな、今の<債務貨幣システム>のもとでは、政府はお金を作れないんだな。そこが重要な点だと思う。
そうなんだな、今の<債務貨幣システム>のもとでは、政府はお金を作れないんだな。そこが重要な点だと思う。
小林
この政府は(お金)を作れない、ということに関して山口薫は<公共貨幣>という本でこう書いていますね。 P-57
それでは日本のお金、貨幣、法貨とはなにか。どの法律で法貨を制定し、誰が発行しているのか。現在国内で流通しているお金は(1)政府貨幣(百円玉等の鋳貨、コイン、)(2)日本銀行券(千円札等)及び(3)預金(銀行の預金口座にある信用のデジタル数字)の3種類である。この3種類のお金で財やサービスの交換や支払決算が行われている。その中で、政府貨幣及び日銀券のみが手で触ることができる、いわゆる現金(Cash)と呼ばれるお金である。それ以外にも、交換手段、支払手段として用いられているものに、銀行預金がある。それではこれらの3種類の交換、支払手段は、全て法律で規定されている法貨なのであろうか。
2・3・1 政府貨幣=>制限付き法貨
まずは政府貨幣から考察していく。政府貨幣の製造及び発行であるが、それは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年6月1日法律第42号)で以下のように定められている。
第四条
貨幣の製造及び発行の機能は、政府に属する。
次に、貨幣の種類として、以下のように定めている。
第五条
貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円、及び一円の六種類とする。
私たちは金属で鋳造される小額の百円玉等のコイン(硬貨)のみが政府が発行できる貨幣であると思い込まされているが、それは間違いで、政府は「記念貨幣」として政令で定めれば、一万円等の政府貨幣も無制限に発行できるのである。それでは、現行の日本銀行券のような「政府紙幣」は発行できないのであるかといえば、そうではない。貨幣の素材等として次の規定がある。
第六条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
よって、貨幣の素材を、金属か、紙か、デジタル数字等のいずれにするかについては、政府が自由に決定できるのである。このように現行法でも貨幣は、コイン、紙幣を問わず、政府が無制限に発行できる。但し、ここに落とし穴を用意した。政府は貨幣を無制限に発行できるが、政府貨幣が無制限に取引に通用(流通)できないように、以下のように制約した。
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
すなわち、最大額面の1万円貨幣を用いたとしても、政府貨幣では最大20万円までしか、通用させられないのである。これでは、企業等の大口支払いに貨幣は使えないということになる。すなわち、政府貨幣は「制限付き法貨」なのである。
2・3・2 日本銀行券=>無制限法貨
そして、この制限付き法貨という欠陥を補うために日本銀行に日本銀行券という紙幣発行権を付与した。そのために、「貨幣(Money)」とは別に「通貨(Currency)」という概念を「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で以下のように新たに定義した。
ここがキーポイントである。
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
すなわち、いかのように定義した。
* 通貨 Currenncy = 貨幣 Money + 銀行券 Bank Notes
そこでこの第二条三で定める、「日本銀行法第四十六条」(平成九年六月十八日に法律第八十九号として改正)を覗いてみよう。
第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
ここで初めて、「法貨」という用語が出て来る。すなわちこの法律で、紙切れにすぎない日本銀行券を法貨(Legal Tender)として無制限に強制的に流通させるとした。元来は、政府が発行する貨幣のみが法貨となるべきなのであるが、この日銀法によって新たに日本銀行券にも法貨なる地位が与えられ、「通貨=政府貨幣+日本銀行券」という本来の貨幣とは異なる拡大・変質概念が創り出されたのである。そして、日本銀行券の種類及び様式については、貨幣の種類及び素材と整合性になるように、以下のように規定した。
第四十七条 日本銀行券の種類は、政令で定める。
このようにして日銀券という紙切れが新たに法貨とされ、誰もその受け取りを無制限に拒否できなくした。政府は貨幣(紙幣を含む)を無制限に発行できるのに、その通用範囲を自ら制約し、日本銀行という独立の別組織に、政府貨幣とは別の銀行券の発行を許可し、それを法貨として無制限に通用させる権限を与えた。
2・3・3 マネタリーベース=法貨
こうして、日本のお金(法貨)とは何かと問えば、上述した二つの貨幣に関する法律により、「 通貨=政府貨幣(実際には硬貨、コイン)+日本銀行券 」であるということになる。そしてそのことが、現在の貨幣システムを混乱に陥れ、今日の不況、政府債務危機、所得格差等の経済混乱をもたらす根本原因を作った。(従って、この混乱の根本原因である2つの貨幣法を除去すれば、今日の経済的混乱が回避できる)。
それでは日本のお金、貨幣、法貨とはなにか。どの法律で法貨を制定し、誰が発行しているのか。現在国内で流通しているお金は(1)政府貨幣(百円玉等の鋳貨、コイン、)(2)日本銀行券(千円札等)及び(3)預金(銀行の預金口座にある信用のデジタル数字)の3種類である。この3種類のお金で財やサービスの交換や支払決算が行われている。その中で、政府貨幣及び日銀券のみが手で触ることができる、いわゆる現金(Cash)と呼ばれるお金である。それ以外にも、交換手段、支払手段として用いられているものに、銀行預金がある。それではこれらの3種類の交換、支払手段は、全て法律で規定されている法貨なのであろうか。
2・3・1 政府貨幣=>制限付き法貨
まずは政府貨幣から考察していく。政府貨幣の製造及び発行であるが、それは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年6月1日法律第42号)で以下のように定められている。
第四条
貨幣の製造及び発行の機能は、政府に属する。
二 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下、「造幣局」という)に行わせる。
三 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済みの貨幣を交付することにより行う。
四 財務大臣が造幣局に対して支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
三 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済みの貨幣を交付することにより行う。
四 財務大臣が造幣局に対して支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
次に、貨幣の種類として、以下のように定めている。
第五条
貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円、及び一円の六種類とする。
二 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円、及び千円の三種類とする。
三 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下「記念貨幣」という)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
三 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下「記念貨幣」という)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
私たちは金属で鋳造される小額の百円玉等のコイン(硬貨)のみが政府が発行できる貨幣であると思い込まされているが、それは間違いで、政府は「記念貨幣」として政令で定めれば、一万円等の政府貨幣も無制限に発行できるのである。それでは、現行の日本銀行券のような「政府紙幣」は発行できないのであるかといえば、そうではない。貨幣の素材等として次の規定がある。
第六条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
よって、貨幣の素材を、金属か、紙か、デジタル数字等のいずれにするかについては、政府が自由に決定できるのである。このように現行法でも貨幣は、コイン、紙幣を問わず、政府が無制限に発行できる。但し、ここに落とし穴を用意した。政府は貨幣を無制限に発行できるが、政府貨幣が無制限に取引に通用(流通)できないように、以下のように制約した。
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
すなわち、最大額面の1万円貨幣を用いたとしても、政府貨幣では最大20万円までしか、通用させられないのである。これでは、企業等の大口支払いに貨幣は使えないということになる。すなわち、政府貨幣は「制限付き法貨」なのである。
2・3・2 日本銀行券=>無制限法貨
そして、この制限付き法貨という欠陥を補うために日本銀行に日本銀行券という紙幣発行権を付与した。そのために、「貨幣(Money)」とは別に「通貨(Currency)」という概念を「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で以下のように新たに定義した。
ここがキーポイントである。
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
三 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
すなわち、いかのように定義した。
* 通貨 Currenncy = 貨幣 Money + 銀行券 Bank Notes
そこでこの第二条三で定める、「日本銀行法第四十六条」(平成九年六月十八日に法律第八十九号として改正)を覗いてみよう。
第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
二 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
ここで初めて、「法貨」という用語が出て来る。すなわちこの法律で、紙切れにすぎない日本銀行券を法貨(Legal Tender)として無制限に強制的に流通させるとした。元来は、政府が発行する貨幣のみが法貨となるべきなのであるが、この日銀法によって新たに日本銀行券にも法貨なる地位が与えられ、「通貨=政府貨幣+日本銀行券」という本来の貨幣とは異なる拡大・変質概念が創り出されたのである。そして、日本銀行券の種類及び様式については、貨幣の種類及び素材と整合性になるように、以下のように規定した。
第四十七条 日本銀行券の種類は、政令で定める。
二 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。
このようにして日銀券という紙切れが新たに法貨とされ、誰もその受け取りを無制限に拒否できなくした。政府は貨幣(紙幣を含む)を無制限に発行できるのに、その通用範囲を自ら制約し、日本銀行という独立の別組織に、政府貨幣とは別の銀行券の発行を許可し、それを法貨として無制限に通用させる権限を与えた。
2・3・3 マネタリーベース=法貨
こうして、日本のお金(法貨)とは何かと問えば、上述した二つの貨幣に関する法律により、「 通貨=政府貨幣(実際には硬貨、コイン)+日本銀行券 」であるということになる。そしてそのことが、現在の貨幣システムを混乱に陥れ、今日の不況、政府債務危機、所得格差等の経済混乱をもたらす根本原因を作った。(従って、この混乱の根本原因である2つの貨幣法を除去すれば、今日の経済的混乱が回避できる)。
コー
だから俺は、政府はお金を作れないと言ったんだよ。制限付きのお金って一体何なんだよ、そんなの日本の政府が作るべきお金なんかよ。なんでこんなややこしい制度ができたんだよ。
小林
やっぱり、中央銀行がイギリスで作られたところを、考えざるを得なくなるわけですね。