皆さんこんにちは~

昨日、実家に電話をしたところ…
母「もしもし~?」
私「あっ!お母さん?私だけど~」
母「……………。」
私「もしもしっ?」
「ツーツー…」
電話を切られてしまいました

数秒後、母の携帯から折り返しがかかってきまして…
私「もしもし…何で切っ」
母「ちょっと!!今、あんたのふりしてオレオレ詐欺の電話きたわよ~!!
でも、声がぜーんぜん違ったから、すぐ分かった!危なかったわ~」
と、食い気味に言われました

私「いや!!風邪引いて性別不明な声になっているけど、さっき電話したのはあなたの娘ですから~

」(○○侍みたいw)
これで、母はオレオレ詐欺に引っかからないと確信いたしました

さて!
今日は少しコアな吹奏楽のお話をします

吹奏楽の演奏体系(並び方)は団体によってさまざまです

でも、好き勝手に並んでいるのではなく、ちゃんとした理由があります

理由は大まかにいうと
「奏者がお互い合わせやすいか?」
「客席で聴いたときに演奏効果があるか?」
という2点が挙げられます

前者は同じ動きを演奏する者同士が、お互いの音を聴こえるように並ぶ考えかたで
チューバ、コントラバスが近くで演奏するのも、この理由ですね

しかしながら、必ずしも同じ動きのパート同士がかたまって演奏することが良いこととは言えません

たとえば
クラリネットとサックスが、対比して語り合っているような曲では
両者は離れた位置で演奏したほうが効果的な場合があります

合わせやすさと演奏効果…
相反する要素になりますが、うまくバランスを取りながら
よりよい並び方をするのが良いと思います

今回は、オーケストラでいうヴァイオリンのパートを演奏している
クラリネットの位置をご紹介します

クラリネットは吹奏楽の中で一番人数が多く、このセクションがうまくまとまって演奏が出来るかが
バンド全体の評価を左右すると言っても過言ではありません

!
1、クラリネット全体が最前列に座る並び方。
クラリネットアンサンブルのように、お互いの目を見ながらアンサンブルできるのが特徴!

2、クラリネットが下手側にまとまって座る並び方。
セクションの音が、かたまりになって響かせることができるが、パート間のバランスを取るのが難しくなってしまう

3、フルートが前列に出て、クラリネットが2列目に座る並び方。
フルートの音が良く聞こえるため、アンサンブルしやすくなるが、クラリネットは合わせにくくなってしまう

一般的には2番の並び方が多いです

座る位置えを変えるだけで、客席に届く演奏がガラッと変化します

演奏する曲に合わせて、位置を変えてみてはいかがでしょうか??
では、次回の記事もお楽しみに~


ぽちっと!!
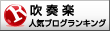 吹奏楽 ブログランキングへ
吹奏楽 ブログランキングへ
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ














 」(○○侍みたいw)
」(○○侍みたいw)





 !
!

























