皆さんこんにちは~

最近、夜の涼しさにやられておりまして

昨日はとうとう毛布を掛けて就寝しました

このままですと、真冬はどうなってしまうのでしょうか…

さて!
本日はパッド(タンポ)の接着剤のご紹介をします

パッドの接着剤に、何が使用されているかご存知ですか?
トーンホールをふさぐためのパッド、その接着剤には細かなタンポ調整を可能にする、少し特殊な接着剤が使われています


それがこちら!!
ラックと呼ばれる、パッドの接着剤です

このラック、東南アジアなどに生息するラックカイガラムシの分泌液を精製して作られているんです

(画像を載せようと思いましたが…寒気がするのでやめました

ご覧になりたいかたは検索してください

)
スティック状をして固まっていますが、これは熱で溶け、冷めると固まるのです

また、種類によって融点が異なるため、楽器やメーカーで使い分けています

バーナーでラックを温めて溶かしていきます


ドロっとして溶けたら、パッドにラックを乗せます


溶けたラックは高温のため、扱いは十分に注意しなければなりません

(未だに油断すると火傷をします

笑)
キィにはめます


ここから楽器に組み立て、パッドの調整をしていきます

木管楽器のパッドを調整する時は、タンポにつけたラックをキィごと温めて溶かし、パッドがトーンホールを上手く塞ぐように調整します!
きちんと塞げる位置で冷まして固定するのですが、これがとても集中力を要する作業なのです


キィを熱する温度が低いとパッドは動いてくれません

逆に高いと、キィのラッカーが焦げる、ラックが柔らかくなりすぎて溢れる、タンポが痛むなどのアクシデントが起こってしまいます

常に、火の加減に細心の注意を払い、その上でコンマ数ミリのズレを調整しています


大変な作業ですが、数ミリのズレで楽器の響きに大きな影響を及ぼしてしまいます

良くパッドが取れてしまい、ボンドや瞬間接着剤でつけたパッドを目にしますが、絶対にやめてくださいね

取れてしまたっら速やかに楽器店に持ち込みましょう

では、次回の記事もお楽しみに~


ポチっと!!!
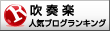 吹奏楽 ブログランキングへ
吹奏楽 ブログランキングへ























































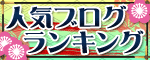


 ご覧になりたいかたは検索してください
ご覧になりたいかたは検索してください





