いよいよ最終日。午後2時の特急八雲で帰るので、どうしても参拝しておきたい神社は二社と松江まで来て参観しないのも失礼なので松江城を見ることとする。
その前に、その5の最後にアップするつもりだった、前日の宍道湖の沈みゆく夕陽を見てください。

それでは、最初に神魂神社(かもす)へ。
なんでかもすと読むのか案内板見ても不明。検索もしてみたが、これといった確かな説はないようだ。
しかし、神社本殿は国宝。摂社にも重文建物がある。
こんもりとした森の中に、参道から荘厳さをもった神社。

祭神はい伊弉冉大神(いざなみのおおかみ)、伊弉諾大神(いざなぎのおおかみ)。(案内板のいざなみのなみとういう字はIMEパッドにないので普通いざなみと書くときに使われる漢字利用した。)
鳥居には、何か神祭りの儀式機関だったのか地の輪のような竹笹で作った大きなわが鳥居にくくられている。
たまたま地元の方が三人ほど参拝を済ませて降りてこられたので、鳥居のくぐり方を教えてもらう。

風習は輪越祭(わこしさい)というらしいが、まず輪をくぐり左の曲がって、輪と鳥居の間を通る。また正面から輪をくぐり今度は右の鳥居と輪の間をくぐる。もう一度正面から入って左に曲がりもう一度輪と鳥居の間を抜けて正式に正面から境内に入るそうだ。
地元の人たちのお祭りらしく、案内板にも書かれていない。
参道を進む。石段で森に囲まれて気持ちのいい空間。

右に曲がると、本殿へ通じる石段。まっすぐ行くと女坂で緩やかな坂になっている。

本殿は大社造りの立派な国宝建築。


ここの神紋は二重亀甲に有。これは字を分解すると十と月になる。出雲では十月は神在月なのでありを神紋にしたようだ。
その5までは分からなかったので、屋根の紋と書いてきたが、正式には神紋というようだ。ひとつ利口になった。
境内には、二重流造の摂社があり、貴布禰神社と稲荷神社が祀られ、社は重要文化財だそうだ。
境内には他に伊勢社などいくつかの祠が見られた。

また、氏子の人以外触るなと書いた札をつけた一角があり、囲われている。この囲いの左奥に洞窟が見えるが、関係は不明。

社務所によりご朱印を頼むと、朱印帳以外書かないとすげなくはねつけられる。愛想もなく、朱印帳も売っていない。なんだかなぁ。
さあ次に行こう。
出雲国一宮 熊野大社へ。
ウワー大きな神社だ。出雲大社と並び大社を名乗る。出雲国風土記はじめ多くの文献に記載されているそうで、平安中期に出雲国で最も神格の高い一宮とされたとのこと。


祭神は 神祖熊野大神櫛気野命(かぶろぎくまのおおかみくしみけぬのみこと)この神名は、素盞鳴尊の御尊称、右手に御后神 奇稲田姫を祀りしている稲田神社、左手に御母神 伊弉冉尊をお祭りしている。


朱印も書いたものをいただくと袋に入れてくださるが、出雲大社と同じ 上 の字一字のみ。
まず、隋身(神)門を通って境内へ。先ず本殿に参拝。主祭神は素盞鳴尊。


左手の伊弉冉尊を祀る神社。神社名称は 伊邪那美神社(いざなみじんじゃ)となっている。

右手の神社奇稲田姫(くしいなだひめ)を祀る神社。神社名稲田神社(いなたじんじゃ)。相殿はあしなづち・てなづちで稲田姫の親神二神。合祀は少彦名命。

境内の左奥に茅葺の古い建屋がある。見ると何か曰くあり気。立ち寄る。

建屋の前に建屋の説明札がありこの屋を鑚火殿(さんかでん)としてある。説明札をそのまま書き写す。
「御祭神スサノオノ大神は檜の臼、卯木(うつぎ)の杵」で火を鑚(き)りだす法を教えられたので、日本火出初社(ひのもとひでぞめのやしろ)とも讃えます。出雲国造(いずもこくぞう=出雲大社宮司)は、古来しきたりにより、襲職(しゅうしょく=代を継ぐ)には必ず大神の霊幸[よめない]い給う神器の燧臼(ひきうす)・燧杵(ひきりぎね)を拝載し鑚火して「火継=霊継」の式を仕え、大神より霊慮を戴き神性国造となります。この鑚火殿はその古伝由緒を伝える建物であり、神器が奉安してあります。毎年10月15日の鑚火祭は出雲国造が出雲大社で用いられる神器を拝載するために参向し斎行されるまつりで、特殊な亀太夫神事として奉仕され、また神歌・琴板のもと神慮一体の祈念の百番の榊舞を納める。」
少々消化しにくいが、出雲国造とは出雲大社宮司の苗字で熊野大社の社務所にいた巫女さんに聞いたところ千家国造家という言い方だった。
この建屋の中のは白布で仕切られその奥には、火おこしの神器が置かれているそうだ。火は手で神器を使って起こす。
現在の国造家はしなかったが、それまでは襲職のとき先代の遺体の傍に一晩中付き添ってきたそうだ。
ここの神紋は一重亀甲の中に大の字1字。
神社巡りの纏めをするのが、こんなに大変とは思ってもみなかった。
祭神の名前一つとっても、神社ごとに表記が異なったり、祭神の名前に使われる漢字も簡単ではない。
できる限り正確に書くよう努めてみた。
神社の説明は、初めて参拝したところばかりだし、神社側もあまり説明できない場合があった。
しかし、初めてながら、出雲という土地の古代からのありようや、位置づけがおぼろげながら見えてきたような気がする。これは大きな収穫だ。
さあ最後の松江城へ。
驚いた。石垣は野面積みだ。


城の敷地内に入ると、説明人が所ところに拝されている。石積みについて聞くと、野面積みだが、あちこち手入れしてきている。色の違うところはほとんど修理痕とか。

城内には巨樹もある。
左:樹齢350年のクスノキ。木の直径160㎝。 右:バクチノキ。(なかなか見られない木)


もうひとつ、洋館あり。案内文では、明治天皇の行幸を仰ぐためにご座所を作ろうと建てたが、結局行幸成らずだったとある。

さてそろそろ天守閣へ。

天守閣内部はどこのお城でもそう突飛なつくりはない。

しかしこの城の天守閣は太い柱が間隔狭く、しっかりと囲んでいるので、耐震性もありそうな感じ。
天守閣から宍道湖方面をみる。宍道湖の向こうにある白い平たい屋根が美術館。

これで全部終了。あとは、昼食と土産物を買って、午後2時の八雲に乗るだけ。
城のそばの観光会館で済ませることにして、ゆっくり休む。
午後1時30分松江駅に到着。

駅前はバスターミナルになっているが、一番暑い時間帯のためか、人はまばら。駅構内に売店あるが休憩所で休んでいる人ばかり。
駅前には商店らしきもの見られず。
時間になり、改札に入り松江とお別れ。
今回の旅行で、多くの神社参拝をしてきたが、いざ写真の整理をすると200枚以上で整理に時間がかかった。また神様の名前が同じでも神社により漢字が異なったり、改めて調べないとわからない年代とかまとめるのに、大変四苦八苦。
結局6回に分けてブログアップしてが、8月に入って得た話がまとめられずになっている。
一段落したので、たまった分をなるべく早くブログに書き込むつもり。
















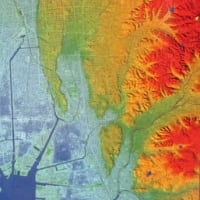
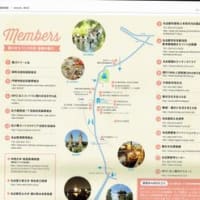
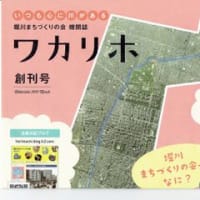
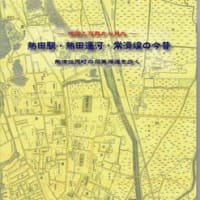

体調のこともあり、島根でのんびり過ごすのかと思いきやハードスケジュールでしたね。
名古屋より暑い島根でへとへとになることもあったけど、これだけのブログを書き上げるとは、満足な旅ができたということですね。本当によかったです。島根に来てくれてありがとう。
今こちらは、神楽の情報を集めています。毎週土曜の夜はそこここで神楽が行われているので、繰り出そうと計画中。温泉や、棚田の風景なども堪能したいです。
最近「うん、何?」という島根の雲南地方が舞台の映画に感動しました。自宅から近く、だんな様も仕事でよくロケ地付近を通るそうです。映画の世界をまるごと紹介したいな。ヤマタノ大蛇伝説の神社など興味深いですよ。
お薬のことなどブログを読んでいて私も気になりますが、美しいものに感動する心、新しいものに出会い、発見を喜ぶ体験を増やしてお互いに健全、健康になっていくことを心から願い、次回の来松を楽しみにしています!