昨日は義母の3回忌法要でお寺へ。
本堂を温かくして貰っていて助かる。
今年一番の寒い日になったが、今日10日は昨日より一層冷え、今日でなくて幸いだった。
法事が終了してお墓へ向かうとき、和尚がぽつりと、この寒さで亡くなる方が増えて、今日だけで葬儀の依頼が2件入ってきたと言っていた。
外に出ると風も出てきて、体感温度は0度かと思うばかり。さもありなん。
無事法事も済み帰ってきたところで、今まで 千種生涯学習センター千種史跡ガイドの会主催の「日泰寺をもっと知ろう」に当選し、知っているようで知らない日泰寺を教えてもらう良い機会を得たと思い参加、しかし、折角教えていただいた日泰寺についてブログをアップできずグズグズしていたが、法事も住んでなんとなくアップしようという気分になった。
遅ればせながら纏めてみた。
当日のコースは以下の通り。

山門に集合した後2班に分かれてガイドを受けた。
先ず山門の彫刻について説明受ける。


多くの人が知っている通り、仁王様ではなく、人物像。山門に説明板が貼られているので迦葉(かしょう)、阿難(あなん)像とわかるが、何故迦葉・阿難像なのか?
答えは、お釈迦様の真骨が納められている寺院の山門だから仏弟子で第2祖迦葉、第3祖阿難を置いたもの。
迦葉 阿難


私がたまたま日泰寺へ参拝に出かけたところ、山門に2体の像が納まり、その日が落慶法要の当日で、運よく立ち会うことができた思い出がある。25年以上前だ。
落慶当日はその年の当番宗派である華厳宗東大寺が開眼法要を行っていたことを思い出す。
山門を通って本堂へ。寺務所との間に本遷記念と掲げられた玄関から入場。

入って左へ本堂、我々は右へ。


大書院に出る。鳳凰台と額が掲げられている。写真撮影OK。

広い。

作りも贅沢。

広間の一隅で寺院僧侶から日泰寺の由緒説明。殆ど案内パンフに書かれた略記と同じ。

概略はインドが英国領時代イギリスの駐在官ウイリアム・ペッペが仏陀の遺骨を発見。
釈尊死後火葬に付され、遺骨を八つに分けてお祀り、そのうちの一つが発見されたようだ。
その後インド政庁は御遺骨を仏教国であるタイ国(当時シャム)の王室に寄贈した。
時の国王チュラロンコン陛下は大変喜ばれ、ワットサケットにお祀りされ一部をセイロン、ビルマに分与された。
このとき、日本のタイ国弁理公使稲垣満次郎は日本にも頒与せられんことをタイ国王に懇願した結果下賜するとのお言葉が頂けた。
当時の外相が日本仏教各宗管長に受け入れの態勢の要請がなされたものの、紆余曲折の末名古屋に新寺院を建立するとの結論になる。(この辺りの事情は長くなるので省略する)
釈尊を表す「覚王」を山号とし、日タイの友好を象徴する「日泰寺」の寺号持った「覚王山日泰寺」が誕生と記されている。
この日泰寺はいずれの宗派にも属さないことから、運営は各宗は三年交代で住職を務める。
説明が終わる。しばらく書院見学。


この書院は名古屋市指定有形文化財。

使われている木材・建具なども凝っている。柱は5寸くらいあり、面取りしている。



次に茶室草結庵へ。腰掛け待合(茶室に入る前に腰掛けて待つ場所)

にじり口

室内

敷地の一番奥にある。垣根をコスト裏の通りと接している。
この茶室は愛知県指定有形文化財。

庭にかけられた石橋。高そうな石。

紅葉もきれいだ。

時間一杯で外へ。
本堂正面から改めて参拝。
本尊は完成時タイ国王から本尊にと頂いた、タイ国々宝の一千年を経た釈尊金銅仏。


本堂左壁面に2枚の額。左は”きくきりをうく”右”らんけむりにそまる” ええとあってるかな?

本堂前の散策。チュラロンコン殿下の銅像。

銅像前の植栽。海紅豆(カイコウズ)、アメリカデイゴとも呼ばれているそうだ。


開花時期は7~8月。真夏に南国を思わせる真っ赤な花をつける。寒さに比較的弱く、南関東以南での栽培のみ可能だそうだ。
次に、奉安塔へ。
釈尊の真骨を奉安している塔。


普段は門内には入れないが、今回特別に参拝許可出る。
門をはいると、釈迦入滅に阿難が泣き伏す姿。


この先にも門。潜ると奉安塔。

真骨の位置は?と聞くも、分からないとの回答。
僧侶が付ききりで我々の行動チェック。少し脇にそれて歩いてもだめだ!と大声で叱責される。
一言。もう2度と入れてやらないぞだって。恐ろしや恐ろしや。釈尊笑っておられるのでは?
次は日清戦役第1軍戦死者記念碑へ。

日清戦争で戦死した726人の霊を慰めるtあめ、明治34年に名古屋中心部(栄)に建てられたが、市電の延伸に邪魔だと、現在地に移設。
現在では誰が管理しているのか、全く清掃されていない様子だ。何なんだろうな・・・(ため息)
日泰寺山門前に戻る。
山門の南に八十八ケ所霊場一番札所。


日泰寺創建時、寂しいところで人が寄りつかなかった。そこで有志の人達が参詣者を増やそうと考えだしたのが霊場巡りだったそうだ。碑には明治42年と彫られている。
伊藤満蔵という方が世話人の筆頭者で、第一番札所の開拓者だそうだ。本堂前の大きな灯篭の1基も伊藤満蔵氏の寄進。この方は多くの神社仏閣に灯篭等を寄進しておられることで有名。
隣は千体地蔵堂。


千体の地蔵完成は大正3年ころ。1体ごとに寄進者の名前が入っている。毎月21日開扉。
参道を駅に向かい途中屋根神。現在は閉じられているが、毎月1日・15日月並祭。
ここで解散。
改めて日泰寺について勉強できた。
















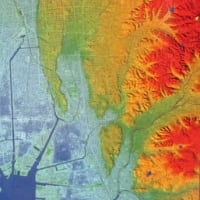
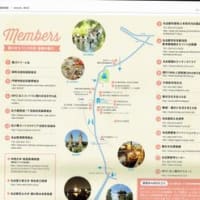
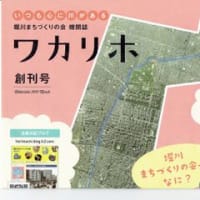
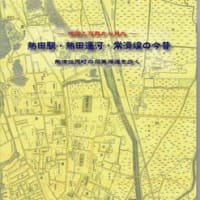

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます