
監督:アニエスカ・ホランド
脚本:クリストファー・ウィルキンソン&スティーブン・リヴェル
出演:エド・ハリス
ダイアン・クルーガー
(他)
音楽:マーク・アイシャム
<物語前半の粗筋>
“ 第9 ” の初演を4日後に控えた1824年のウィーン。楽譜が完成しない中、ベートーヴェンのもとに写譜師としてアンナが派遣されてくる。ベートーヴェンはアンナを冷たくあしらうが、彼女の才能を知り、仕事を任せる事に。尊大で傲慢なベートーヴェンだが、ただ1人の肉親である甥のカールだけは溺愛していた。しかしカールがその一方的な愛を疎ましく感じている事に気付かない。やがて初演の日が来た。難聴から指揮を怖れるベートーヴェンを助けたのはアンナだった…。
現在公開中の映画、“ 敬愛なるベートーヴェン ” を観てきた。クラシック音楽にまつわる映画だと、どうしても観たくなってしまう。
注)ネタバレの感想なので、これから鑑賞したいと思っている方は、この先を読まないで下さい。
エド・ハリスがベートーヴェンの狂人じみた傲慢不遜な性格と、彼の音楽に対する姿勢・情念といったものをなかなか上手く演じていたと思う。またその風貌は、現存する肖像画等からスタッフが緻密に練り上げた成果だろう、画面上に登場しても特別な違和感はなかった(実際のベートーヴェンはもっと汚らしい姿だったのだろうが)。

アンナ・ホルツを演じたダイアン・クルーガーは美しく、どこかのレビューにフェルメールの絵画を想わせるとあったが正にそんな感じで、衣装の効果もあるだろうが、陰影に富んだ映像の中でよく映えていた。

初めにこの作品の難点から言ってしまうと、全編が英語で通されるという事である。やはりベートーヴェンにはドイツ語で話してほしい。制作国がイギリスとハンガリーだから英語になったのだと短絡的には思えないが、ともあれこの点を気にしなければ、それなりに楽しめる映画ではないだろうか。
物語はフィクションだが、着想が女性監督から湧いたのか、アンナのベートーヴェンに対する敬意がメインであり、それは原題の “ Copying Beethoven ” からも窺える。故に、ベートーヴェンの耳の疾病にまつわる苦悩と対人への在り方、自身の楽曲に取り組む姿勢や音楽そのものに対する考えが劇中で描かれてはいるものの、それ等を重点として受け手が捉えてしまうと鑑賞後は消化不良になりかねない。
さて、この映画には他では見られないような手法がある。
ベートーヴェン自身の指揮による “ 第9 ” 演奏を物語の最後に置くのではなく、中盤に据える事によってその後のベートーヴェンとアンナの、ある意味落ち着いた関係が築かれた事を静かに物語っているという点である。一等盛り上がる “ 第9 ” 演奏のシーンをクライマックスに持ってくるのが常套手段であるはずなのに、この映画ではそれをしていない。これに不満や違和感を覚える人もあろうが、これはこれで巧みな演出であると思う。だからこそ、それまで人間的に心を通い合わせられなかった彼等がようやく互いに尊敬し、信じ合えるようになったその後をじっくりと丹念に描いてほしかっという想いで一杯である。
“ 大フーガ ” に着手したベートーヴェンの意図と作品そのものの世界が分からないアンナは、時を経た物語冒頭の、死の床に伏したベートーヴェンの元でようやく自分の内に “ 大フーガ ” を聴く事ができるようになるのだが、それまでの時間経過における彼等2人の様々な遣り取り、その心模様を観たかったと強く感じたのは僕だけだろうか。冒頭でアンナが馬車に揺られながら田園風景を目に流してゆく様が、“ 大フーガ ” の旋律と相俟って視聴側に強い緊張感と、一体これから何が始まるのだという期待感を持たせるのが実に印象的で良かっただけに(このシーンは青ないし青緑色を基調とした画像になっているが、次第に大きく揺れ動いてゆくアンナの顔や風光と “ 大フーガ ” の絡み合いを、この色彩が上手く取りまとめていると感じた)、長年孤独に苛まれてきた楽聖ベートーヴェンが “ 第9 ” 初演後にアンナを真の意味で身近に感じた時、また、恋人を捨ててまで作曲の道に身を投じたアンナの覚悟・決意が以前にも増して高じた時、そこからが本当のドラマとして花開いていくのではないだろうか。さすれば、死するベートーヴェンとそこに駆け付けたアンナの描写を序盤に据えた意義が出てくると思う。だから3時間並みの大作になっても良かったのでは、と思えて仕方ない。
また “ 第9 ” の場面そのものについてだが、耳の聴こえ具合がいよいよ劣悪になったベートーヴェンを助けるべくアンナが弦楽セクションの後方に座して、彼に曲の入りとテンポを指示するのがこの作品の最大の見所である。

アンナが実在しなかった人物で、且つこの様なシチュエーションが実際にはなかったと分かってはいても、2人の “ 第9 ” を成功させたいという想いが次第にこちらにも乗り移ってくる。殊にベートーヴェンが指揮する両の手の中にアンナの指揮する姿が入ってくるカットは、いささか演出的に過ぎている感もあるが、それだけに作り手側のメッセージが匂い立ってくる。
曲が終わりに近付く箇所で、彼等の顔をカメラが意図的に揺らしているが、これもまた2人の高揚感を醸し出すための演出として好感が持てなくもない。ただし、甥のカールが舞台袖で演奏に接し涙を流すのは蛇足に感じた。そこまで彼を物語の引き合いに出すのなら、後半にもう1シーンか2シーン、彼のエピソードを加えるべきである。
劇中流れる曲は、晩年のベートーヴェンを描いた作品だけあって後期の楽曲がメインである。“ 第9 ” をはじめ、“ 弦楽四重奏曲第14番 ” や “ 同第15番 ”、“ ピアノ・ソナタ第32番 ”、“ ピアノ協奏曲第4番 ”、“ 交響曲第7番 ”、そして “ 大フーガ ” 等、名曲が目白押しである。この作品に興味を持った方がいたら、是非とも臨場感ある劇場で観る事をお勧めする。
アンナという1人の女性写譜師を起用し、彼女を物語の軸に据えた事で、今までになかったベートーヴェン映画が登場したと断言できる。とはいえ、好みは様々に分かれるだろう。クラシック音楽やベートーヴェン自身に想い入れの強い人ならば全くの捏造だと批判するかもしれないが、新しい視点でのベートーヴェン像を作り上げたという(フィクションとしての)点においては画期的だったと思う。
以下、余談。
本編中指揮をするシーンはクリストファー・ホグウッドが監修を努めたそうだ。日本で公開される字幕スーパー版では、指揮者の佐渡裕とベートーヴェン研究の第一人者である平野昭が監修を行っている。
アンナ・ホルツは架空の女性だが、ベートーヴェン晩年の作品を写譜した人物の中にはカール・ホルツという似た名前の男性が実在したそうで、ベートーヴェンのお気に入りだった写譜師のヴェンツェル・シュレンマー(1823年没)には妻がいて、やはり写譜を手伝っていた。もう1人、“ 第9 ” の写譜を行ったヴェンツェル・ランプルもアンナのモデルになったとの事。
脚本:クリストファー・ウィルキンソン&スティーブン・リヴェル
出演:エド・ハリス
ダイアン・クルーガー
(他)
音楽:マーク・アイシャム
<物語前半の粗筋>
“ 第9 ” の初演を4日後に控えた1824年のウィーン。楽譜が完成しない中、ベートーヴェンのもとに写譜師としてアンナが派遣されてくる。ベートーヴェンはアンナを冷たくあしらうが、彼女の才能を知り、仕事を任せる事に。尊大で傲慢なベートーヴェンだが、ただ1人の肉親である甥のカールだけは溺愛していた。しかしカールがその一方的な愛を疎ましく感じている事に気付かない。やがて初演の日が来た。難聴から指揮を怖れるベートーヴェンを助けたのはアンナだった…。
現在公開中の映画、“ 敬愛なるベートーヴェン ” を観てきた。クラシック音楽にまつわる映画だと、どうしても観たくなってしまう。
注)ネタバレの感想なので、これから鑑賞したいと思っている方は、この先を読まないで下さい。
エド・ハリスがベートーヴェンの狂人じみた傲慢不遜な性格と、彼の音楽に対する姿勢・情念といったものをなかなか上手く演じていたと思う。またその風貌は、現存する肖像画等からスタッフが緻密に練り上げた成果だろう、画面上に登場しても特別な違和感はなかった(実際のベートーヴェンはもっと汚らしい姿だったのだろうが)。

アンナ・ホルツを演じたダイアン・クルーガーは美しく、どこかのレビューにフェルメールの絵画を想わせるとあったが正にそんな感じで、衣装の効果もあるだろうが、陰影に富んだ映像の中でよく映えていた。

初めにこの作品の難点から言ってしまうと、全編が英語で通されるという事である。やはりベートーヴェンにはドイツ語で話してほしい。制作国がイギリスとハンガリーだから英語になったのだと短絡的には思えないが、ともあれこの点を気にしなければ、それなりに楽しめる映画ではないだろうか。
物語はフィクションだが、着想が女性監督から湧いたのか、アンナのベートーヴェンに対する敬意がメインであり、それは原題の “ Copying Beethoven ” からも窺える。故に、ベートーヴェンの耳の疾病にまつわる苦悩と対人への在り方、自身の楽曲に取り組む姿勢や音楽そのものに対する考えが劇中で描かれてはいるものの、それ等を重点として受け手が捉えてしまうと鑑賞後は消化不良になりかねない。
さて、この映画には他では見られないような手法がある。
ベートーヴェン自身の指揮による “ 第9 ” 演奏を物語の最後に置くのではなく、中盤に据える事によってその後のベートーヴェンとアンナの、ある意味落ち着いた関係が築かれた事を静かに物語っているという点である。一等盛り上がる “ 第9 ” 演奏のシーンをクライマックスに持ってくるのが常套手段であるはずなのに、この映画ではそれをしていない。これに不満や違和感を覚える人もあろうが、これはこれで巧みな演出であると思う。だからこそ、それまで人間的に心を通い合わせられなかった彼等がようやく互いに尊敬し、信じ合えるようになったその後をじっくりと丹念に描いてほしかっという想いで一杯である。
“ 大フーガ ” に着手したベートーヴェンの意図と作品そのものの世界が分からないアンナは、時を経た物語冒頭の、死の床に伏したベートーヴェンの元でようやく自分の内に “ 大フーガ ” を聴く事ができるようになるのだが、それまでの時間経過における彼等2人の様々な遣り取り、その心模様を観たかったと強く感じたのは僕だけだろうか。冒頭でアンナが馬車に揺られながら田園風景を目に流してゆく様が、“ 大フーガ ” の旋律と相俟って視聴側に強い緊張感と、一体これから何が始まるのだという期待感を持たせるのが実に印象的で良かっただけに(このシーンは青ないし青緑色を基調とした画像になっているが、次第に大きく揺れ動いてゆくアンナの顔や風光と “ 大フーガ ” の絡み合いを、この色彩が上手く取りまとめていると感じた)、長年孤独に苛まれてきた楽聖ベートーヴェンが “ 第9 ” 初演後にアンナを真の意味で身近に感じた時、また、恋人を捨ててまで作曲の道に身を投じたアンナの覚悟・決意が以前にも増して高じた時、そこからが本当のドラマとして花開いていくのではないだろうか。さすれば、死するベートーヴェンとそこに駆け付けたアンナの描写を序盤に据えた意義が出てくると思う。だから3時間並みの大作になっても良かったのでは、と思えて仕方ない。
また “ 第9 ” の場面そのものについてだが、耳の聴こえ具合がいよいよ劣悪になったベートーヴェンを助けるべくアンナが弦楽セクションの後方に座して、彼に曲の入りとテンポを指示するのがこの作品の最大の見所である。

アンナが実在しなかった人物で、且つこの様なシチュエーションが実際にはなかったと分かってはいても、2人の “ 第9 ” を成功させたいという想いが次第にこちらにも乗り移ってくる。殊にベートーヴェンが指揮する両の手の中にアンナの指揮する姿が入ってくるカットは、いささか演出的に過ぎている感もあるが、それだけに作り手側のメッセージが匂い立ってくる。
曲が終わりに近付く箇所で、彼等の顔をカメラが意図的に揺らしているが、これもまた2人の高揚感を醸し出すための演出として好感が持てなくもない。ただし、甥のカールが舞台袖で演奏に接し涙を流すのは蛇足に感じた。そこまで彼を物語の引き合いに出すのなら、後半にもう1シーンか2シーン、彼のエピソードを加えるべきである。
劇中流れる曲は、晩年のベートーヴェンを描いた作品だけあって後期の楽曲がメインである。“ 第9 ” をはじめ、“ 弦楽四重奏曲第14番 ” や “ 同第15番 ”、“ ピアノ・ソナタ第32番 ”、“ ピアノ協奏曲第4番 ”、“ 交響曲第7番 ”、そして “ 大フーガ ” 等、名曲が目白押しである。この作品に興味を持った方がいたら、是非とも臨場感ある劇場で観る事をお勧めする。
アンナという1人の女性写譜師を起用し、彼女を物語の軸に据えた事で、今までになかったベートーヴェン映画が登場したと断言できる。とはいえ、好みは様々に分かれるだろう。クラシック音楽やベートーヴェン自身に想い入れの強い人ならば全くの捏造だと批判するかもしれないが、新しい視点でのベートーヴェン像を作り上げたという(フィクションとしての)点においては画期的だったと思う。
以下、余談。
本編中指揮をするシーンはクリストファー・ホグウッドが監修を努めたそうだ。日本で公開される字幕スーパー版では、指揮者の佐渡裕とベートーヴェン研究の第一人者である平野昭が監修を行っている。
アンナ・ホルツは架空の女性だが、ベートーヴェン晩年の作品を写譜した人物の中にはカール・ホルツという似た名前の男性が実在したそうで、ベートーヴェンのお気に入りだった写譜師のヴェンツェル・シュレンマー(1823年没)には妻がいて、やはり写譜を手伝っていた。もう1人、“ 第9 ” の写譜を行ったヴェンツェル・ランプルもアンナのモデルになったとの事。










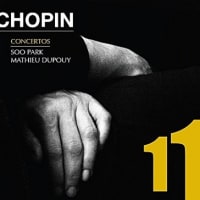
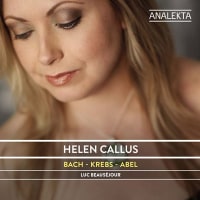
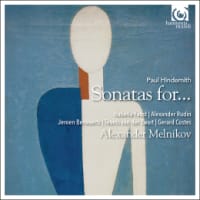


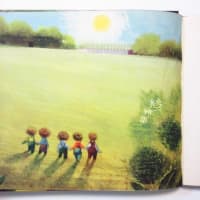


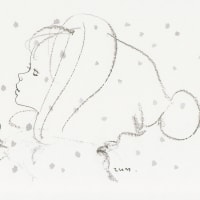
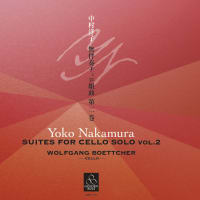

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます