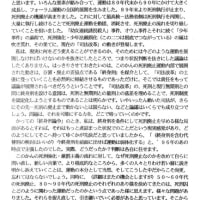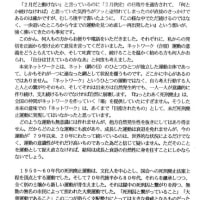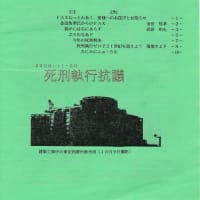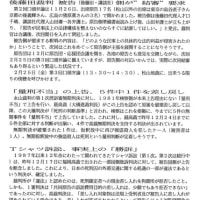『ねっとわあく死刑廃止42号』 1997年10月20日発行
また、1997年10月20日とは、永山則夫が死刑になって、2ヶ月後ですね。
永山則夫はこの年の8月1日に処刑されました。
※一部の人の氏名は、ボカシました。出してもOKだろう、という方の名前は出してます。
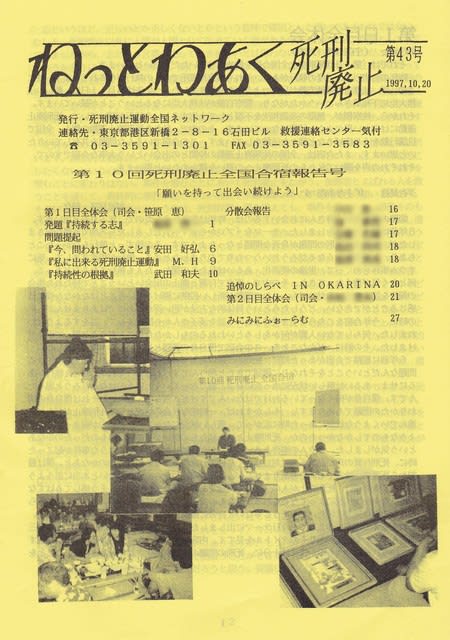
第10回死刑廃止合宿にて、この会報に収録されていた、
武田和夫氏がスピーチされた内容を以下に貼ります。(武田氏は終身刑導入反対派)
問題提起3『持続性の根拠』
武田和夫
全国合宿は、毎回その時の死刑廃止運動の状況を忠実に反映して来たと思います。今回もそういう議論があるわけですが、こういう機会ですのでもう少し基本的なことについて話します。
私たちの死刑廃止運動は、二つの要素を含んでいると思います。ひとつは大前提といっていいと思うんですが、1948年に国連で人権宣言が採択され、その中の生命権、そして残虐な刑罰の禁止ということの第一の課題が死刑廃止だということで、それが世界的な流れを作ってきた。その中に私たちも立っているわけで、この生命の尊厳そして人権は、死刑廃止に不可欠な基礎であると思います。そしてその中で私たちの死刑廃止運動は、死刑囚と直接関わり、支援し、判決そして執行という死刑の具体的な運用の局面で、死刑と切り結んで来ました。これは、この運動の特徴だという言い方を私はして来たんですが、最近の「デッドマン・ウォーキング」の特に原作を読みますと、あのシスター・プレジャンという方も、まず死刑囚と出会って、死刑廃止の問題を考え始め、さらに被害者に出会っていくという、非常に私たちに近い経過をたどっている。
こういう形は意外と、死刑廃止のひとつの普遍的な形としてあるんじゃないかと最近思い始めています。この二つの要素が渾然一体となって、この運動の粘り強い大きな流れを形作って来たのではないかと思うんです。
この観点、から今の状況を見ると、ひとつの事実が分かります。つまり、法務省によるこの間の執拗な、大量死刑執行が、運動の中のとりわけ「死刑囚と共に」という傾向に大きな打撃を与え、「個々に死刑を阻止しても限界があるんだ」というあきらめを生じさせ、路線転換をせまり、今まで死刑囚に関わって来た部分を分断解体させていく、ということです。
死刑囚に直接関わらなくてもいろんな形で多くの人が死刑囚の問題を共有してきたわけですから、そういうものに対する攻撃として、あったんじゃないか。これは法務省が、この運動が直接死刑囚につながっていることに対して、いかに恐れをなしているかということの端的な現れであろうと思います。
しかし同時に私たち自身も、「死刑囚と共に」と言ってきたことがどういうことだったのか、あらためて試されていると思います。何のために、私たちは死刑囚にかかわって来たのか。私たちの死刑廃止の姿勢の基本にかかわることとして、あらためて問われていると思っています。
私自身、死刑囚との関わりということを通じて死刑廃止に入ってきた一人です。死刑囚との関わりについては後半で述べます。今まで、死刑廃止運動のなかでいろんなことがありましたが、そのつど実は、このままやれるのだろうかと絶えず揺れてきたわけです。そういう中で私自身は、何か何でもやり続けるのだという発想からは自由であろうとしてきたつもりです。何が何でもやるんだと考えると状況が見えなくなります。どんな状況でもやり続けるのはプロフェッショナルです。
以前の姫路の合宿でプロからアマヘという問題提起がありましたが、アマチュアは自分の内的必然性がなくなるあるいは見えなくなった時は立ち止まって考えてみる必要がある。そういう時に私にとっては二つの柱が存在しました。ひとつは先程から言っております「死刑囚とのかかわり」ということです。もうひとつは、「死刑とは、そもそも何なのか」ということなんです。この問題についてはめったに話す機会がないと思うので、少しお話ししたいと思います。
「死刑とは何か」これは「死刑廃止論」とは違い、そもそも「死刑」とは歴史的事実として何だったのかという、事実に対する認識です。たとえばこのかん、「存置論と廃止論との対話」ということで、いろんな方が発言されています。学ぶべきことの多い優れた論陣を張られるかたが、存置の側にも廃止の側にもおられます。その反面、これはどうかと思うことを言われる人も両方におられるわけで、要は私たちが取捨選択していくことなんですが、その中で、「死刑制度が、長い歴史を持っていたということを事実として認めなければいけない。」という発言があります。
確かに古代国家から死刑制度はありますが、ややもすると私たちは、死刑制度が今と同じ姿で一貫して長い歴史を存在して来たと思いがちです。実はどうであったか。
たとえば古代ギリシヤでは、殺人罪は、死刑でしたが「親告罪」だったことが分かっています。
つまり被害者側の親族が告訴しなければ、国家はこれを裁判にかけることができなかった。これはなぜか。
国家成立以前の氏族制社会では、殺人が起これば加害者側の氏族と被害者側の氏族がまず話し合いを行った(*1)といわれています。
考えてみれば国家がなければ当然そうなるわけですが、当時の社会には、良く知られている「血の復讐」というものがありました。でもそれをやる前に話し合いをしていたんです。それで解決すると、それでよかった。
それでも折り合いがつかないと、被害者側から何人かが選び出されて犯人をどこまでも追いかけて行って殺さなければならなかった。権利ではなく義務だったんです。
それをしないと殺された人の魂が鎮まらなくて災いをもたらす。
だから死生観が今とは全然違っていた。今でも復讐というものの背景としては殺された人の魂という感情がありますね。
ただそれを個人的感情として持っているのと、国家が制度に組み入れるのとは別だと思うんですけれども。
そういう社会の伝統がまだ、古代国家の中に残っていて、「殺人」という問題に国家がまだ十分介入できなかったということなんですね。
(*I F.エングルス『家族・私有財産・国家の起源』岩波文庫p115)
この「死者の魂による災い」という意識は、「穢れ」という観念を生んでいった。古代に普遍的にある意識ですが、これは私たちの中も残ってますよね。罪の意識であるとかあるいは、犯罪者に対する一種独特の差別観に残っています。古代国家において殺人が問題になるのは、この「穢れ」で国家のテリトリーが汚されないということで、古代ギリシャでは、殺人者は、裁判の途中で国外退去することが許されていた。こうしたことをどう観るか。学者は、古代の人々は、人命を軽視したというわけですが、そういう問題ではないと思う。
古代ギリシャにも国家の制度としての死刑はあり、さまざまな罪(神殿を汚した罪、反逆罪など、「共同体に対する罪」が主)に対して適用されていましたが、国家の制度としての「死刑」と、殺人罪とがまだ完全には結びついていなかったということではないか。殺人は、まだ「当事者間の問題」という色彩が強かったんじゃないかと思うんです。つまり加害者と被害者の問題であると。これは非常に重要な問題だと思うんです。私たちは殺人イコール死刑と思いこんでいますが、必ずしもそうではなかった。国家以前の社会の「血の復讐」そのものが発展して死刑制度になったのではなく、国家成立後に、国家制度として生まれた死刑に吸収されていったのではないか。国家が殺人の問題に十分介入できない時代があったのです。
(古代ギリシアに関しては村川堅太郎『古代ギリシア市民』岩波講座世界歴史2古代2・6)
ついでに、中世の「死刑」は何だったのかというと、これは死刑というよりも、犯罪者の身体に、「力」を加える(八つ裂き、火あぶり)、「身体刑」である。結果として死ぬんですけれども、身体に対して支配者が、無制限の力を加えうる、それを人々に「見せつけ」て、支配権力の絶対性を示すためにやった。当時の封建社会は農民から実力で搾取する社会で、実力を見せつける必要があった。「見せしめ刑」とは、悪いことをしたらこういう目に遭うと見せしめるのではなく、お前たちの支配者はこんなに絶対的な力をふるうのだと見せしめることだった。(*2)
(*2 M.フーコー『監獄の誕牛』新潮社54p )
こうした中世の死刑は、権力が集中した後期、いわゆる絶対主義時代に大量に行われています。私の見るかぎりでは死刑は中世後期から近代初期にかけてがピークではないかと思います。
では近代の死刑というのは何かというと、近代は法治国家ですから、「法」による理性的な支配をたてまえとし、むき出しの暴力による支配はかえって不合理でマイナスであり、死刑は徐々に押さえられていく、とりわけ見えなくさせられていくんですね。けれどもなくなりはしなかった。なぜなら現実の搾取、差別、抑圧によってこぼれ落ちる人がどんどん出てくる。むしろ犯罪は、近代に入って爆発的に増えるわけです。そういう人々のなかで、支配に組み込めない人を抹殺するために、死刑が必要だった。近代の死刑こそが、文字通り「殺す=消す」ことを目的とした死刑です。だから中世の死刑と近代の死刑を比べて、中世のほうが残酷だから今の死刑はもっとましだという比較は意味がないわけです。むしろ近代という個人に基礎を置いた社会の中で、その個人を全面的に抹殺する、人格を全面的に否定するそういう刑罰があっていいのかという形で問題にしなければいけないと思うんです。
このように、同じ「死刑」でも、その時代の支配形態の必要性によってその性格は異なるものだったということができます。死刑制度は長い固定した歴史を持つのではなく、国家と共に生まれ、変化し、やがて必要がなければ消えていくものだということが良く分かるわけです。そこで「罪の償い」といったようなことが言われても、それは後から正当化のためにつけ加えられたものでしかない。なぜなら同じ罪の償いが時代によって何でそんなに違うのか。だから今の私たちの社会が、死刑を必要としている社会なのか、必要としない社会なのか。
必要としない理由が、もっとあるいは同等にひどい刑罰があるから必要としないのか、あるいはそもそも人を殺すような刑罰を必要としない社会なのか。あるいはまた本当は必要としないのに、一握りの勢力がそれに固執している社会なのか、ということを見極めてい
けばいいのだと思います。