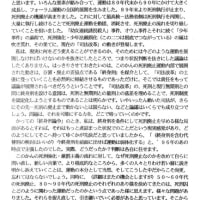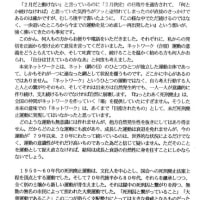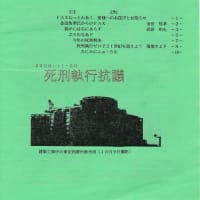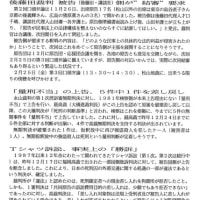ついでに、今の「死刑廃止の世界的趨勢」ということについても考えてみたいと思います。これは第2次大戦後、先に述べた国連の人権宣言を端緒として広まっていますが、これには戦争に対する反省、とりわけファシズムという、人間の尊厳を根底から崩すような殺りくを、自分たちの歴史が生み出したことへの痛切な反省が背景にあると思う、ということは2年前の新潟合宿でも述べたのですが、最近の神戸の少年による事件の関連で読んだのですが、ドイツの母親たちは戦後、兵器を扱った読み物や残酷なシーンのある映像などを、子供からガードする態勢を作ってきたというんです。日本とは違うと。
ファシズムを体験した、あるいは接した場合に感じるのは、人間がその本性にどうしようもなく残虐性を持っていることを自覚せざるをえないということだと思うのです。だから、価値観の定まらない子供の時期に、残虐性を引き出すようなものは見せない。あるいは子供に限らず大人であっても、その残虐性を発現してしまった人に対しても、ただ断罪するだけでは無意味であるということを自覚するに至ったのではないか。
私は人間は、ある状況に置かれたら(個人差はあるが)どんな人でも、人を殺す存在だと思います。「人を殺すな」とは絶対的真理だというが、その真理が現実に通用した時代はなかった。どの時代でも、人が人を殺して来た。私は、「殺すべきではない」といったようなことで死刑廃止と言っても、おそらく説得力はないだろうと思います。むしろ私たち自身が、場合によっては人を殺す存在なんだということを本当に自覚して、だからどんなことがあっても殺すまいと決断しなければいけない。どんな正しい理由があっても絶対に殺してはいけないんだということを私たちが決断し互いに約束し合わない限り、かならずまた殺しあいを始めてしまうのだという、それを痛切に自覚したのが、「死刑廃止の世界的趨勢」の背景としてあっただろうと思うし、またそれが、私たちの死刑廃止ということなんだろうと思います。
この日本を見ても、戦時中にあれだけ大陸で残酷なことをしてきながら、反省がない。あるいは、騙されたからやったんだ、本性は善なんだけどだまされて悪くなったんだという言い方をしている大が多い。騙されたんだったらそれにどう決着をつけているかというとたいして何もしていない。死刑廃止はそういうことも含めて、私たちの社会そのものを根底から問い直す、そういう内容を持たざるをえないんじゃないかという気がしています。次に、死刑囚との関わりという、私にとってのもうひとつの柱について述べたいと思います。
先日、1968年に19才で4人のピストル殺人事件を犯し死刑判決を受けていた、永山則夫さんが処刑されました。私は彼の裁判を、二審の無期減刑まで支援し、その後彼と決別しています。形の上では、彼から「追放」されたことになっているので、二審の減刑までに何があったのかということを、十分提起できないで来ました。しかし、二審の減刑をひっくり返した最高裁の判例が、いわゆる「死刑適用の基準」であるという形でひとり歩きしている。裁判所が判決で引用するだけではなく、最近は検察庁までそれを上告の理由として引用しているという事態があり、それに対して死刑廃止運動の側が、その最高裁判決以前のことについて何も語れないでいる。これはよくないんじないかと思って、前号『ねっとわあく死刑廃止』に永山裁判斗争の経緯を掲載させて頂きましたが、その直後に執行がありました。
前号『ねっとわあく』で、「なぜ減刑になったのか」は十分述べていません。当時法律専門家、マスコミ等が判決についてさまざまに論じていますが、なぜ減刑になったかを説明できたひとはいませんでした。
私たちは一審で、事件当時違法捜査があり、犯人と知りつつ捕まえないで犯行を重ねるのを待っていた疑いがあることを追及しました。これは事件当時の記事を国会図書館でコピーして捜査状況を丹念に分析した結果、追及する根拠があると判断したものです。しかしその裁判で永山さんと私たちが、根本的に主張しようとしたことは、「この裁判は永山則夫を裁けるのか」ということでした。社会から疎外され、死のうと思って米軍基地へ侵入してピストルを見つけた。友達に会った気がしたといいます。それを持ってさ迷ううちに4人の大を殺してしまった19才の少年の事件に、誰がどのように責任を負うべきなのか。本人にももちろん責任はある。しかし死刑というのは、すべてを本人個人の責任として葬り去ってしまう。それは間違っている…。しかしコトバだけでそれを主張しても、裁判所は一蹴するだけです。「違法捜査追及」は、永山さんと私たちの主張を、裁判の土俵に乗せるための手順でした。裁判所はいったん審理を約束したんですが、裁判長が交代して強引な訴訟指揮を始め、弁護団が抗議の辞任をし、一審は紛糾しました。
私たちは弁護士会に、国選弁護人を推薦するのは待ってほしいと要請しました。そうすると法務省が動き出し、「弁護人なしでも裁判をやれる」法案の国会提出を発表しました。これは弁護士会への大きな圧力となり、弁護士会は生命保険付きで国選弁護人を永山裁判に送り込んで、一審は全くの形式審理を経て死刑となりました。
法務省はたったひとつの刑事裁判になかなか判決が下せない時、そこまでやるのです。二審の裁判長は、裁判を始める前の弁護団との打ち合わせで、「静かに判決をおろさせてほしい」「静岡事件(違法捜査の追及)を争うなら結果は(死刑だ)。しかし被告は被害者に著作の印税を送って慰謝を行っている。それを尽くしなさい」と言っています。それを弁護団がしばらく私に知らせず、私たちを裁判から遠ざけ、私が状況を把握する前に、「獄中結婚」を前面に押し出した路線を敷いてしまった。この裁判長の言葉を「闘うな」と理解したのです。
結果としてマスコミは、「獄中結婚と永山の人変り」を強調しましたが、もしそうでなかったらあの時に、死刑の存廃ということがもっと正面から論じられたと思います。あの一審の裁判闘争の中で私たちは、ひとつの法廷に納まりきらない、裁判の前提を問う問題を、命がけで審理させようとしたのです。二審裁判長が「静かに判決を・・・」と言ったのは、「この法廷でそれをやってくれるな」という意味だったと思います。
裁判所も情状は十分に見るから、静かにしてくれと。
それが、「減刑判決」でした。
減刑になってからある作家が「永山は素直になった」と言って文学賞を与えて近づいてきました。彼があのときに素直になったのではないのは、私が良く知っています。彼は一貫して素直な人間でした。取りまく状況につねにストレートに反応してきた人です。「永山は素直になった」ということの真意は、「市民社会に素直になれ」ということだったと思います。彼は、そうなっていきました。それは彼と私が離れていく過程でした。結果として、「情状一本」でのぞんだ上告審(検察側上告による)は逆転判決になりました。そのとき私はもうそこにいませんでした。
「素直になれ」と言った人たちは、それをどうフォローしたのか。何もできませんでした。弁護団も、精神鑑定を出せば彼が弁護団を解任することが分かっている状況で、彼を「精神異常」とする精神鑑定申請を行ない、弁護から離れて行ったのです。
彼は小説を書き始めました。私はそれをほとんど読んでいません。それまでの彼の著作はすべて読んでいます。彼は「獄中作家」と言われることを極度に嫌っていたんです。小説のことを彼は「生きざまさらしだ」と言っているようですが、「生きざまさらし」というのは、自分が生きてきた過程のすべてを、ありのままに明らかにすることであって、それは商品にはなりません。小説とは違うんです。彼は過去に生き始めた、そうせざるをえなくなったんだと私は思っていました。
私と彼との時計は止まったままでした。処刑の報に接したときも、私は比較的冷静だったんです。早いか遅いかといった問題ではなく、来るものが来てしまったかという感じでした。しかし時間がたつにつれて、怒りが私の中にどんどんふくらんでくるんです。自分でも意外でした。そして思い出したんです。この怒りは、私が彼と共に命がけで闘っていた時の怒りと同じだと。止まっていた彼との間の時計が、回り始めました。これはもう決して止まることはないと思います。
私が彼に見ていたのは、著名な獄中作家、永山則夫ではありません。「連続射殺魔」=間という、社会が投げつけた呼び名を正面から受け止めて、必死になって人間になろうと努力をしていた一人の死刑囚です。それは、すべての死刑囚に共通する姿だと私は思っています。私が一緒に闘った永山則夫は、立派に今の死刑廃止運動の中で生きているんです。たとえば私たちが使う、「死刑囚と共に生きる」という言葉、まだまだ私たちにとって課題なのですけれども、この言葉を最初に提起してくれたのは永山則夫さんです。また彼は、個別裁判支援の大切さを示してくれたと思います。以降の死刑廃止運動の中で、個別裁判支援の輪が広がって行くきっかけを作ったのが永山裁判闘争でした。その一審の闘いの間、彼も私たちも、助かると思ってはいませんでした。
彼は「ただ生きれば勝ちというわけではない」と言っていました。さきざき死刑をまぬがれるかもしれないということではなく、今、事件の真実を追及して死刑と闘い、共に生きるのだということでした。そこにものすごい力が生まれていました。それが、不可能を可能にしたんだと思います。
今も私は、ある再審事件にかかわっています。弁護団はじめいろんな人の努力で、再審請求をしていますが、再審請求をしたからといって、甘い考えは持っていません。だから毎月の弁護団会議は、緊迫感がありますが、気力が充実しています。獄中の死刑囚と共に、今を悔いなく闘い抜こうとしているという実感があるからです。もちろん、判決の不当性を主張して再審をやっているのですから、死刑は回避されるべきだと思っています。けどそれだけではありません。死刑囚、とりわけ死刑確定者は、獄中にいて、死刑を執行されなければそれで生きているというのではないんです。毎日毎日殺され続けるんです。外から遮断され、生きる希望を奪われ、生きる感覚そのものを奪われていく。今、彼らを生かす必要があるのです。個々に死刑判決を阻止しても限界がある、という戦術主義的な発想は、そうした発想自体に限界があると思います。今共に闘いぬいて、彼らを生かす、そして自分たちも生かされる。そのこと自身が、死刑廃止運動の大きな力になっていくんだと思います。
これは、誰もが死刑囚と関わるべきだと言っているのではないわけで、仮に関わっているのが一部でも、それを全体が課題として共有して行くような、そういう運動のつながりが必要なんだと思います。
私たちの運動は、もうひと回り、量的にも質的にも広がりを持った運動を作っていかないといけない、国会で死刑廃止を実現するにも、大衆運動が背景にないと出来ません。そのためには、今各地の仲間が思いきって力を出して、自分たちにできることに取り組み、それらを互いに共有できるネットワークを作っていくことが必要です。その中で、運動全体として、死刑囚に向き合った運動、その中からたとえば、今回の「いのちの絵画展」のようなすばらしい企画もどんどん生まれてくると思うんです。そういう運動の輪をもっともっと広げていく必要があるんじゃないかと思います。今回の私の話が、そのための何かの参考になればいいと思います。
最後に、私は今年、水戸被害者援助センターのボランティア養成講座入門編を受けてきました。これは来年テストに合格すれば相談員としての訓練に参加できるのですが、被害者相談というのは、被害者の中でも、特に厳しい状況に置かれた人に接することなので、(仮に合格しても)私が死刑廃止運動をやりながらできるか今のところ分かりません。
しかし私たちの運動が、死刑囚と関わり、さらに被害者とも出会ってきている現在、まず被害者の問題をもっともっと学ぶ必要があると思うんです。だからこの養成講座にできればぜひ参加されるといいと思います。そして、私たちの究極の目標は国家の介入なしに加害者と被害者が向き合い、そこで和解しあい、共に生きることが可能な社会ではないが。それをめざす過程で当然死刑は廃止されなければならないのですが、そういう、死刑廃止よりも長い射程を持った取り組みが、私たちの運動の持続性、そしてむしろ死刑廃止をより早く実現できるインパクトを持ちうるのではないかと思っています。
以上