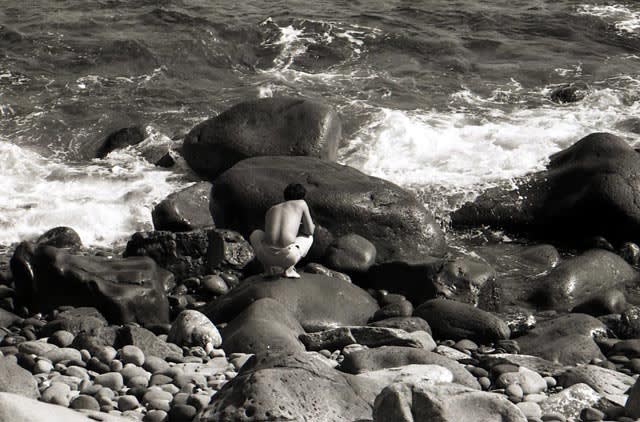昭和36年(1961)今上天皇のご成婚を記念して、皇居前の和田倉に噴水が作られ、周辺も公園として整備されたとの報道で、早速出かけました。10月でした。高さ8.5mに吹き上げる大噴水、皇居の和田倉門をバックに見事でした。話題になっていましたから、見物客も極めて大勢居ました。


現皇太子の成婚を記念して1995年に整備されたと聞きましたが、車で時々前を通りますが、しげしげと眺めた訳ではないので違いは分かりません。町並みの変化を見たくて探した写真ですが、絵柄としてビルをバックでは映えなかったのでしょう、皇居を背景にした写真ばかりでした。

バックのパレスホテルは全く変わっていないので、町の変遷の参考にはなりません。昼休みだったのでしょうか、ワイシャツ姿のビジネスマンや、制服姿のBG(当時はOLの呼び名の前でした)が大勢居ました。大手町や丸の内のこの姿は、今も昔も変わりません。

お堀の白鳥、当時も今も健在です。

余談ですが、バックのパレスホテルでのエピソード(宣伝?)を一つ。娘の結婚式で、娘夫婦が絶対にとしたのが、メインディッシュに“ロースト・ビーフ”でした。確かに「オイシ~モット~」と感じました。今まで数多くの結婚式に出席してきて、西洋料理で珍重される“ロースト・ビーフ”、どうしてこれが?と言うレベルしか経験していなかったのです。本当に美味しいと感じたのは、初めてでした。矢張り高価なメニューですから、日常的にとはいかないのですが・・・。
長年旅を続けてきて最近では、品数を競っている旅館の食事に辟易しています。もちろん、料理を自慢にする高級旅館は別格でしょうが、度々泊まれる身分でもありませんし、その一泊で何回も旅が出来るなら、そちらを選びます。旅館でも、ホテルのように食事が選べる所も出てきています。そのあたりに、低迷を続けている観光旅館の出口があると思われますが・・・。