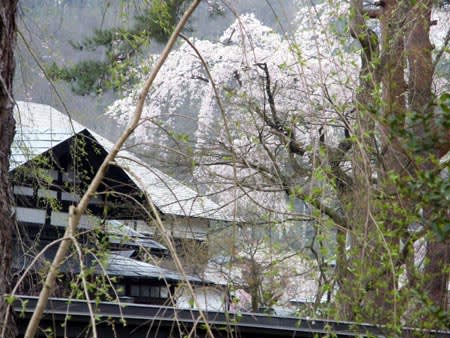ブルマをはいた女子中学生が見事に走り高跳びのバーをクリアーしている。かって学んだ頃の学校では遠足、学芸会、展覧会そして運動会が4大行事といえた。もちろんとっておきは修学旅行だが・・・。この画像で何を語ろうとしているのか??古い画像記録から“時の旅人”を気取ってみた。
昭和28年の秋(の筈。中学校では春の記録会、秋の総合運動会と2度開催されていた記憶があるから)まだ戦後の故かハイジャンプのバーはなんと竹竿そのまま、飛び方も前跳びであってロールオーバーは少なかった。この画像で語るのは背後の校舎である。木造瓦葺き平屋建て、中渡り廊下で串刺しされた並列型であった。同じ中学校の最近のホームページ表紙の写真を借りてきた。運動場の正面同じ場所に建つ立派な校舎であった。

念のためGoogleの3D画像で写真と同じ方向で眺めてみた。・・・便利な世の中だ!

校舎内の画像はそんなに保存していなかったが、その後3年間夢中になって打ち込んだ放送部の「送別会」(翌年度末であろうか)の模様があった。畳の部屋だから教室と同じ造りではあるが家庭科室のようだ。当時の教室内では特異な雰囲気だが、木質サッシや“黒板”が当時を物語っている。


運動会に戻るが、男子生徒おそらく3年生だった記憶があるが「組み立て体操」の画像である。多勢なのだが一学年400名全校で1200名、今ならさしずめマンモス校だが、当時は当たり前の人数だった。

この画像が語るのは背後の煙突の煙の右端の屋根にとんがり屋根が乗った建物についてである。4階ほどの高さのレンガ造りの建物は「カブトビール」の醸造工場として建設され、戦争中は中島飛行機の部品工場として使用されていたため壁に米軍機から放たれて機銃掃射の弾痕があった・・・(現在は市の文化財として保存されている)・・・朝晩通学時に眺めていた。当時は学校は田んぼに囲まれていたので見通せたが、現在は住宅が密集しているので、何処まで見えるかは確認していない。
もう一枚は女子生徒のダンスの画像だった。今だったらおそらく派手な色彩のミニスカートにボンボン持ってホップに踊るのであろうが、当時では紺のプリーツ入りのスカートにセーラー服が制服だったので、白いブラウスを組み合わせてそろいのスタイルで踊っている。曲目などは記録にない!

背後の学校周辺の模様が写っているが、階段上の田んぼの上段には画像でははっきりしないが名鉄電車の線路があり、2~30分に1本程度の電車が走っていた。(現在では倍以上の運行本数になっている)その線路の向こう側、写真では右端の連棟の建物は精神病院であったか伝染病隔離病院であったかどちらかの記憶は曖昧だが、そんな施設が置かれる程の郊外であった。現在では病院も移転し町中心部から移転してきた役所(裁判所などの公的な)や、住宅に埋め尽くされているようだ。田舎といえども田園風景は遠のいているようだ。
追記:保存状態の悪いアルバムのモノクロ写真、変色やシミ取り階調を整えるのに手間取っているが、デジタルでなければそんな作業も不可能だ。だが修正出来るのも程があり、しばらく“あれた”画像が続く・・・!