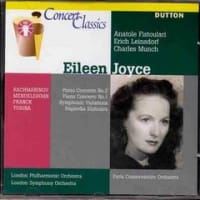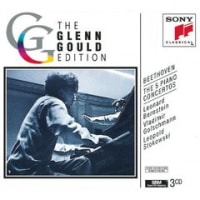NHK芸術劇場で、いま話題の、ドゥダメル/シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラの来日公演が放映された。
ベネズエラは、国家的情操教育プログラムの一貫で、貧民街などの子供たちにも楽器を持たせ、音楽する喜びを与えた。このオーケストラは、そうして生まれたのだそうで、映画「ミュージック・オブ・ハーツ」を思い出させる。
そんな事情もあり、また若手の精鋭指揮者ドゥダメルを迎えて、昨年から注目を集めて来たのであった。
けれども私は、持ち前のあまのじゃく精神というか、少なからず偏見を持ってこれを眺めていたことを、告白しなければならない。
今日の放送を、家人の妨害によって、途中から見ることを余儀なくされたのであったが、もう驚きと感動で、すっかり満たされてしまった。
曲目は、ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲 チャイコフスキー:交響曲第5番。私はチャイコフスキーの途中から見た。
まず、舞台上の人の多さに驚く。マーラーでも始まるのかしらという、巨大な編成である。顔ぶれは、確かに若いようだ。
指揮のドゥダメルは、彼らを煽りに煽って、けれども、統率してゆく。
というのも、彼らは実に自由で、演奏中に私語したり、演奏をやめたり、隣の奏者を気にしていたりするのが、ハッキリ画面に映されていた。だがしかし、実に一所懸命に、指揮者に食らいついてゆく。結果として音楽は、ただならぬ熱気を帯びて来るのであった。
チャイコフスキーの5番には些か食傷気味であったけれども、私はこれを聴いていて、抑え難い興奮を覚えた。とにかくスリリングとまで言えるほどの激しい音楽表現と、純粋に音楽を楽しむ精神とが、自然に併存しているのである。フィナーレでは、思わず笑みがこぼれて来るほど、彼らの演奏は、素直な、言葉通り、ムジツィーレンに満ち溢れていた。
それはアンコールのバーンスタインやヒナステラでいよいよ爆発し、吹奏楽部の学生のような盛り上がりを見せてくれた。あんまり彼らが楽しそうなので、余程の臍曲がりでなければ、一緒になって手拍子でもしたくなったろう。
「音楽」とはまさにこういうことだ、というのを彼らは体現していた。
もちろん指揮者もオーケストラも、かなり勢い任せに終始していて、この曲だから成功したという側面を、私は否定するつもりはない。けれども、チャイコフスキーはとても素晴らしかったので、いま、私は彼らを賞賛する。
ただ、彼らはあくまでもパフォーマンスではなくて、また特別な成立事情ではなくて、真剣な芸で勝負しているので、些か会場に異質な盛り上がり方もあったようだ。尤も、あのアンコールをして、何をか謂わんや、であろう。
ともかく、マンネリズムか、新奇さを狙ったような軽々しい演奏が増える今の音楽界に、非常に快い新風が吹いて来たことは疑い得ない。余り商業戦略に乗らずに、初心を忘れずいてもらいたいと、思う。
余談ながら、美人奏者の多さが目についた。聞けば、かの国は美人養成の国家プロジェクトもあるのだそう。ある種の独裁体制から生まれる利点を、考えさせられもしたことであった。
ベネズエラは、国家的情操教育プログラムの一貫で、貧民街などの子供たちにも楽器を持たせ、音楽する喜びを与えた。このオーケストラは、そうして生まれたのだそうで、映画「ミュージック・オブ・ハーツ」を思い出させる。
そんな事情もあり、また若手の精鋭指揮者ドゥダメルを迎えて、昨年から注目を集めて来たのであった。
けれども私は、持ち前のあまのじゃく精神というか、少なからず偏見を持ってこれを眺めていたことを、告白しなければならない。
今日の放送を、家人の妨害によって、途中から見ることを余儀なくされたのであったが、もう驚きと感動で、すっかり満たされてしまった。
曲目は、ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲 チャイコフスキー:交響曲第5番。私はチャイコフスキーの途中から見た。
まず、舞台上の人の多さに驚く。マーラーでも始まるのかしらという、巨大な編成である。顔ぶれは、確かに若いようだ。
指揮のドゥダメルは、彼らを煽りに煽って、けれども、統率してゆく。
というのも、彼らは実に自由で、演奏中に私語したり、演奏をやめたり、隣の奏者を気にしていたりするのが、ハッキリ画面に映されていた。だがしかし、実に一所懸命に、指揮者に食らいついてゆく。結果として音楽は、ただならぬ熱気を帯びて来るのであった。
チャイコフスキーの5番には些か食傷気味であったけれども、私はこれを聴いていて、抑え難い興奮を覚えた。とにかくスリリングとまで言えるほどの激しい音楽表現と、純粋に音楽を楽しむ精神とが、自然に併存しているのである。フィナーレでは、思わず笑みがこぼれて来るほど、彼らの演奏は、素直な、言葉通り、ムジツィーレンに満ち溢れていた。
それはアンコールのバーンスタインやヒナステラでいよいよ爆発し、吹奏楽部の学生のような盛り上がりを見せてくれた。あんまり彼らが楽しそうなので、余程の臍曲がりでなければ、一緒になって手拍子でもしたくなったろう。
「音楽」とはまさにこういうことだ、というのを彼らは体現していた。
もちろん指揮者もオーケストラも、かなり勢い任せに終始していて、この曲だから成功したという側面を、私は否定するつもりはない。けれども、チャイコフスキーはとても素晴らしかったので、いま、私は彼らを賞賛する。
ただ、彼らはあくまでもパフォーマンスではなくて、また特別な成立事情ではなくて、真剣な芸で勝負しているので、些か会場に異質な盛り上がり方もあったようだ。尤も、あのアンコールをして、何をか謂わんや、であろう。
ともかく、マンネリズムか、新奇さを狙ったような軽々しい演奏が増える今の音楽界に、非常に快い新風が吹いて来たことは疑い得ない。余り商業戦略に乗らずに、初心を忘れずいてもらいたいと、思う。
余談ながら、美人奏者の多さが目についた。聞けば、かの国は美人養成の国家プロジェクトもあるのだそう。ある種の独裁体制から生まれる利点を、考えさせられもしたことであった。