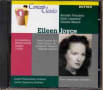響/都プロジェクト京芸ルネッサンス2008コンサートシリーズ
大学院第24回オペラ公演
日時:2009/2/21(土) 午後3時開演(午後2時開場)
曲目:G.プッチーニ/『ラ・ボエーム』より第3幕
V.ベッリーニ作曲『カプレーティ家とモンテッキ家』全3幕
場所:京都市立芸術大学 講堂
まず、プッチーニは前座ということになるのだろうけれど、そういう具合には済ませられないような天才の筆の冴えが、ボエームの第3幕には、ある。有名な、二組のアベックそれぞれに与えられた、全く別々の音楽。プッチーニという人は、とかく甘美なメロディーメーカーとのみされがちであるけれど、かかる巧妙な音楽をもまた、書き得た作曲家であった。
演奏は、手堅くまとめたという印象で、―悪く言うと―小さくまとまりすぎた。もっと、思い切って感情的にやってもいい音楽だろうと、思う。
後半のカプレーティ家とモンテッキ家は、私などは、なかなか最後まで同じ集中力を維持し難いベッリーニの(この時代の)オペラにあって、「ノルマ」「清教徒」など、カラスが得意にした有名なものより、ずっと面白く聴く作品だ。例えば、ロメオが自らの正体を明かした後、ベッリーニは、大方の予想に反して、実に静謐な音楽を書いた。このあたりに、私はこの作曲家の才気を感じずにはいられない。
ベッリーニは、管弦楽部分が脆弱だとしばしば言われるけれども、それでもその前後のオペラに比べて、かなり充実した音楽を、オーケストラに与えている。よって、名歌手を配して、圧倒的な声の魅力で押し切るというだけでは、不満が残る。
その点を考慮すれば、ボエーム同様、指揮者は些かコンパクトに仕上げ過ぎたと言える。もっと振幅を大きくとって、柄の大きい表現をした方が、私はいいように思う。どちらかというと、ロッシーニの軽快さで以って全体が貫かれていて、劇的な効果は上がっていなかった。
無論、オーケストラがそこまでの表現をするためには、歌い手の側にもそれに負けない力感が求められようが、こちらもどちらかと言えばリリコの声質が中心で、そもそも私の言ったような音楽を、志向していなかったのかもしれない。
―随分私は自分の好みを振りかざして、悪口を言い過ぎてしまった。
私には、演出が非常に好ましかった。様々な制約があったろうが、実に効果的に舞台を利用していた。昨今の、作品を隷属させるような傲慢な演出家とは、一線を画する。
キャストには、それぞれ言い得ることがあるだろうが、とにかく全員一所懸命なのである。それで、いい。私は、心地よい充実感を持って、会場を後にしたことであった。
敢えて言うなら、一幕のロメオ役は低音がいかにも辛そうだったし、ロレンツォ役は、声は立派だが、―ちょうど往年のジョージ・ロンドンのように―一本調子に過ぎる。ロメオ、ジュリエッタともニ幕の方が整っていた。
ただ、これは日本のオペラ界すべてに言えることだけれども、「芝居」の稽古は一層充実させられるべきであろう。
歌も芝居も、こういうオペラは、言うなれば歌舞伎に於ける「世話物」の世界であるから、もっと思い切って、あざといくらいにやった方がいい。
余談ながら、当日は立ち見や通路への座り見がひしめく大盛況であった。終了後、カンパの要請があって、私も微力ながら貧者の一灯を燈したような次第であるが、例えば1000円なり500円なりでもとって、京都会館あたりで公演した方がいいのではないか。毎年クオリティーが上がってきているようなので、こういった期待も持ちたいと思う。
最後に、両曲の私の推薦盤を記しておこう。
ボエームは、テバルディが若き日に残した、エレーデ指揮の古いデッカ録音を。セラフィンとの新盤にはない、瑞々しさがある。ただ、ビョルリンクとロス・アンヘレスが歌ったビーチャムのEMI盤、これとの兄弟が、私にはつけ難い。
カプレーティ家とモンテッキ家は、ベイカー・シルズ・ゲッダというキャスティングの面白さ、加うるに指揮のパターネのダイナミックな音楽作りを評価して、このEMI盤を。
大学院第24回オペラ公演
日時:2009/2/21(土) 午後3時開演(午後2時開場)
曲目:G.プッチーニ/『ラ・ボエーム』より第3幕
V.ベッリーニ作曲『カプレーティ家とモンテッキ家』全3幕
場所:京都市立芸術大学 講堂
まず、プッチーニは前座ということになるのだろうけれど、そういう具合には済ませられないような天才の筆の冴えが、ボエームの第3幕には、ある。有名な、二組のアベックそれぞれに与えられた、全く別々の音楽。プッチーニという人は、とかく甘美なメロディーメーカーとのみされがちであるけれど、かかる巧妙な音楽をもまた、書き得た作曲家であった。
演奏は、手堅くまとめたという印象で、―悪く言うと―小さくまとまりすぎた。もっと、思い切って感情的にやってもいい音楽だろうと、思う。
後半のカプレーティ家とモンテッキ家は、私などは、なかなか最後まで同じ集中力を維持し難いベッリーニの(この時代の)オペラにあって、「ノルマ」「清教徒」など、カラスが得意にした有名なものより、ずっと面白く聴く作品だ。例えば、ロメオが自らの正体を明かした後、ベッリーニは、大方の予想に反して、実に静謐な音楽を書いた。このあたりに、私はこの作曲家の才気を感じずにはいられない。
ベッリーニは、管弦楽部分が脆弱だとしばしば言われるけれども、それでもその前後のオペラに比べて、かなり充実した音楽を、オーケストラに与えている。よって、名歌手を配して、圧倒的な声の魅力で押し切るというだけでは、不満が残る。
その点を考慮すれば、ボエーム同様、指揮者は些かコンパクトに仕上げ過ぎたと言える。もっと振幅を大きくとって、柄の大きい表現をした方が、私はいいように思う。どちらかというと、ロッシーニの軽快さで以って全体が貫かれていて、劇的な効果は上がっていなかった。
無論、オーケストラがそこまでの表現をするためには、歌い手の側にもそれに負けない力感が求められようが、こちらもどちらかと言えばリリコの声質が中心で、そもそも私の言ったような音楽を、志向していなかったのかもしれない。
―随分私は自分の好みを振りかざして、悪口を言い過ぎてしまった。
私には、演出が非常に好ましかった。様々な制約があったろうが、実に効果的に舞台を利用していた。昨今の、作品を隷属させるような傲慢な演出家とは、一線を画する。
キャストには、それぞれ言い得ることがあるだろうが、とにかく全員一所懸命なのである。それで、いい。私は、心地よい充実感を持って、会場を後にしたことであった。
敢えて言うなら、一幕のロメオ役は低音がいかにも辛そうだったし、ロレンツォ役は、声は立派だが、―ちょうど往年のジョージ・ロンドンのように―一本調子に過ぎる。ロメオ、ジュリエッタともニ幕の方が整っていた。
ただ、これは日本のオペラ界すべてに言えることだけれども、「芝居」の稽古は一層充実させられるべきであろう。
歌も芝居も、こういうオペラは、言うなれば歌舞伎に於ける「世話物」の世界であるから、もっと思い切って、あざといくらいにやった方がいい。
余談ながら、当日は立ち見や通路への座り見がひしめく大盛況であった。終了後、カンパの要請があって、私も微力ながら貧者の一灯を燈したような次第であるが、例えば1000円なり500円なりでもとって、京都会館あたりで公演した方がいいのではないか。毎年クオリティーが上がってきているようなので、こういった期待も持ちたいと思う。
最後に、両曲の私の推薦盤を記しておこう。
ボエームは、テバルディが若き日に残した、エレーデ指揮の古いデッカ録音を。セラフィンとの新盤にはない、瑞々しさがある。ただ、ビョルリンクとロス・アンヘレスが歌ったビーチャムのEMI盤、これとの兄弟が、私にはつけ難い。
カプレーティ家とモンテッキ家は、ベイカー・シルズ・ゲッダというキャスティングの面白さ、加うるに指揮のパターネのダイナミックな音楽作りを評価して、このEMI盤を。